
散歩と雑学と読書ノート

読書ノート
1.「日経サイエンス」2023、12
「日経サイエンス,2023 ,12」に「ノーベル賞詳報」という記事が載っている。簡単な紹介と感想を述べておきたい。
また同誌の「量子もつれは何を語るか ベル不等式が問う人間の直感」という記事は興味深く考えさせられるものであった。
ノーベル賞詳報
● 今年のノーベル生理学・医学賞は、新型コロナウィルス感染症に対する効果的なmRNAワクチンの開発を可能にしたヌクレオシド塩基修飾の発見に対して、米ペンシルベニア大学の、カリコ(Katalin Kariko)氏と同大のワイスマン(Drew Weissman)の両氏に授与された。
ハンガリー生まれのカリコ氏に関しては、40年にわたる研究生活が苦難の連続であったことが伝えられている。また女性科学者にとって大切なことはよき夫を選ぶことだという談話も好感を持って受けとめられている。
新型コロナのmRNAワクチンはウィルスのスパイクを作る遺伝情報のみを取り出してヌクレシド塩基修飾(ウリジンをシュードウリジンに置換)をした後に脂質のカプセルに封入して注入される。それを取り込んだ樹状細胞で抗原となるスパイクを作成、さらに分解して細胞表面に提示し免疫システムを作動させる仕組みとなっている。
このようにワクチンを開発して癌や自己免疫疾患の治療にも結び付けたり、mRNAを投与して治療用のたんぱく質を直接つくらせたりするmRNA医薬の研究は、カリコ氏やワイスマン氏らの努力のおかげで、現在活発になされている。私はその過程で免疫と言う極めて巧妙な生体反応のメカニズムがより明確になることを期待したいと思う。たとえば自己と他者のmRNAがどのように区別されているのか、樹状細胞がどのような場合に過剰にサイトカインを放出してワクチンの副作用につながる炎症反応を起こしてしまうのか。また樹状細胞から免疫B細胞やヘルパーT細胞、キラーT細胞に抗原情報が的確に伝わり効果的な免疫機能が出現するにはどのような仕組みが必要なのかといった研究が少しずつ進んでいることは楽しみである。
● 物理学賞は、物質中の電子の挙動を捉える「アト秒レーザー」の生成に関する実験的手法に貢献した、米オハイオ州立大学のアゴスティーニ
(Pierre Agostini)氏、独マックス・プランク量子工学研究所のクラウス(Ferenc Krausz)氏、スウェーデン・ルンド大学のルイリエ(Anne L'Huillier)氏に贈られた。
「アト」という単位は10のマイナス18乗を意味する。文字通りほんの一瞬だ け輝く「アト秒レーザー」をカメラのフラッシュとして使用すると、原子核の周辺を猛スピードで動く電子も鮮明に撮影できる。この手法は生命現象の解明にも利用可能であるという。そうだとするといずれ、免疫細胞や神経細胞などの電子の動きを観察することでその細胞の働きの謎に迫ることも可能ではないかと私は勝手に想像してみた。研究の実態を知らない私のたんなる想像に過ぎないのだが。
● 化学賞は高精細なディスプレーなどに使われる半導体の微粒子「量子ドット」を発見した米コロンビア大学のブルース(Louis Brus)氏と米ナノクリスタルズ・テクノロジー社のエキモフ(Alexei Ekimov)氏、均一な量子ドットを安価に作成する方法を開発した米マサチューセッツ工科大学のバウェンディ(Moungi Bawendi)氏が受賞した。
「量子ドット」は直径が数nmから数十nmほどの半導体微粒子で、その粒径に応じて特定の波長の光をだすことが分かっている。そのことを応用して
量子ドットで色を作成してディスプレーの色彩を鮮やかにすることが可能となりすでに家電に使われて販売されている。
さらに生体の細胞や分子の多くはほとんど色がついていないが、量子ドットの利用で生体の複数の分子を別々の色で可視化できることがわかってきて応用されている。
先にふれた「アト秒レーザー」やこの「量子ドット」などによって、分子や電子のレベルで可視化しながら生体の観察ができるというとても面白い時代に我々は生きているのだ。
2 リベラリズムをめぐる読書ノート
(1)はじめに
戦後日本の政治体制上の対立は保守対革新と呼ばれていた。それがいつの間にか保守対リベラルと呼ばれるようになった。現在そのリベラルが右からも左からも強い批判にさらされて侮蔑に近い扱いを受けている。しかもリベラルに対する批判的、侮蔑的な視線や不人気は日本だけの問題でなく世界的なもののようだ。
リベラルあるいはリベラリズムにいったい何が起きたのだろうか。そもそもリベラリズムとは何だったのだろうか。これまで私は充分な知識を持たないままに、リベラリズムに親近感を持ってきた。
その親近感に関して少し補足をさせていただくと、私がまだ学生の頃、私の父(96歳で他界)は自民党嫌いで革新(当時の社会党)の支持者であった。同時に父は野球が好きで、巨人嫌いの熱烈な阪神フアンであった。私はあまり考えもせずに父の影響を受けて革新(リベラル)の支持者になり、阪神フアンになった。今は日ハムのフアンでもある。また今は当時よりはもう少し確信を持った革新(リベラル)支持者である。そのリベラルがかくも批判的に見られてしまうのはどうしてなのだろうか。
私にとってのリベラリズムは、自由や平等、フェアーな人権の擁護、民主主義、多様な価値観を受け入れること、福祉を充実させることなどを意味している。そこには、「自由主義」と言う「本来のリベラリズム?」からははみ出す意味も含まれているのだが、リベラリズムには自由という認識だけでは済まない関連する意味づけが離れがたく付加されてきたと思われる。リベラリズムという見方は確かに極めて多義的でどうかすると正反対と思われる立場もリベラルないしリベラリズムの言葉が使用されているようだ。
私はリベラリズムと分かちがたい意味づけとして自由のほかに平等と民主主義があることを特に強調しておきたいと思う。しかし我々の社会では、自由を追求すると平等が成り立たず、平等を追求すると自由は失われる、その矛盾を民主主義で調節しようとしても困難である。そうした点を含めて私なりに少しリベラリズムをめぐる問題点を捉え直してみたいと思う。
今回の検討には手元にある雑誌の幾つかの特集を参考にさせてもらった。その雑誌の特集に関して先に少し触れておくことにしたい。
岩波の「思想」の特集についてまず述べておく。この雑誌として始めてリベラリズムをとりあげたというのが2004年9月号の「リベラリズムの再定義」である。教えられることが多かった。この特集でリアリズムと言う言葉がいかに多義的な使用をされているかを端的に指摘しているのが、冒頭の記事(思想の言葉)を書いた川崎修の「リアリズムの多義性」である。その一部を引用しておくことにする。
「現代のアメリカ合衆国では、政治の用語としてのリベラリズムとは政府による再配分や福祉国家的政策を支持する立場をさすのが通例であるが(こうした含意は日本語の「リベラリズム」にも時としてみられるが「自由主義」にはない)、ヨーロッパでは同様の政治的立場は社会民主主義とされる。他方、「小さな政府」と市場経済の擁護としての「古典的」なリベラルは、アメリカでは「新保守主義」の経済政策とされるがアメリカ以外の文脈では「新自由主義(neo-liberalism)」と呼ばれる。つまり、、リベラリズム・自由主義なる言葉は、保守主義や社会民主主義とも交錯しつつその意味を散乱させており、文脈抜きには意味を全く確定できないのだ。」
その他の特集では、2006年8月号「丸山眞男を読み直す」のなかの柄谷行人の記事が面白かった。また2020年8月号「資本主義の未来」、2021年6月号「アイザイア・バーリン」、2023年11月号「アダム・スミスー生誕300年ー」などを興味を持って読ませてもらった。
アダム・スミスについては後ほど触れる予定である。ここではバーリンについて少し述べておきたい。私は彼のことは名前だけしか知らなかったが特集によって、彼が20世紀を代表するリベラリストであり、その価値多元論はこれも後に触れる予定のロールズに影響を与えた。さらに同じベラリズム陣営の丸山眞男とは友人同士であったということを初めて知った。またバーリンはユダヤ人でリベラルなシオニスト左派というやや矛盾した思想の持主であった。彼の価値多元論を私は充分わかっているわけではないが、今も進行中のウクライナ戦争やパレスチナ自治区ガザでの残忍な戦闘を思いうかべると、異質者同士の平和共存を目指す政治理論の構築において彼の価値多元論は今後ますます重要な意味を帯びてくるのではあるまいか。
次に「現代思想」の特集では、2018年2月号「保守とリベラルーねじれる対立軸」の記事がとても勉強になった。特にそのなかの二つの討議が面白かった。
もう一冊2007年の「大航海、No.61」の特集「ケインズ/ハイエク」をあげておきたい。そのなかの三浦雅士による岩井克人へのインタビュー「現代思想としての経済学」が特に参考になりいろいろと考えさせられた。
(2)経済的視点から見たリベラリズムーアダム・スミス
今年はアダム・スミス(1723~1790)の生誕300年にあたる、すでに触れたように「思想」の11月号でアダム・スミスの特集が組まれている。
アダム・スミスは経済学的にはリベラルな自由放任主義者で、「見えざる手」により、市場のメカニズムがうまく機能するので政府による介入は不要であると主張したというのが伝統的なスミス像である。
ところが、今回の「思想」の特集では多くの記事が上で述べたようなスミス像とは少し異なる像を提起している。つまりスミスは市場メカニズムの万能主義者ではなく政府の役割を否定もしていなかったというのである。また近年では経済学者のスミスとしてのみではなく、政治思想、道徳思想、哲学、倫理学の分野でのスミスに言及する研究者が多くなっているという。
スミスは「国富論」において自由のみでなく平等に関しても触れていて、自由放任と平等を念頭におく政府介入の二元論への思想転換がみられる。野村聡によると、スミスは公教育への政府支援や累進課税など現在のわが国でも議論されている課題を当時すでに取り上げていて、福祉国家思想の先駆者ともみなせる人物であるという。
スミスはまた過剰投資による市場の不安定化に関しても触れている。後に資本主義と呼ばれる資本の特有のロジックと市場の不安定化についての認識をスミスはすでに持っており、決して単純にリベラルな市場万能主義者ではなかったのである。さらにスミスは法的な議論やジェンダーにかかわる議論を展開し、「道徳感情論」では「正義と慎み」が社会の腐敗への処方となることを論じていた。
そうしたスミスに影響された後の経済学者にケインズ(1883 ~1946)とハイエク(1899~1992)がいる。二人はラオバル同士であり、その議論は実際の政策にも影響を与えてきた。ケインズはニューディール政策でよく知られているように、不況に対応するために公共事業により需要を喚起する政策を提案した。またハイエクはケインズとは違って自由放任と市場のメカニズムをより重視した。ハイエクは市場の不安定化に関する認識も持っていたが、彼の影響をうけたシカゴ学派のフリードマン(1921~2006)を中心とするネオリベラリズム(新自由主義)では市場の不安定化は重視されなかった。フリードマン等は、個人の自由の尊厳と市場原理にもとづいて、政府による介入は最低限に抑えることを主張し、市場原理が理想的には経済のすべてを解決すると考えていた。その考えはグローバルに展開され、イギリスのサッチャーやアメリカのレーガンそして日本の中曽根、小泉政権の政策に反映している。ネオリベラリズムの政策は成功したとみられる点もあるが、資本主義経済の矛盾や問題点を解決できたわけではない。むしろ格差を極端に拡大し社会的な不安定化を引き起こしてもいる。また自己責任論を唱えるその政策は弱者に過酷な一面を持つ。ネオリベラリズムはさらにネオコン(ネオコンサバティブ,新保守主義)と親和性が強くそのネオコンは武力の行使もいとわない。
ネオリベラリズムと似た表現だがほぼ反対と言ってもよい動きに20世紀前半のイギリスのニューリベラリズム(新自由主義)がある。それはこれまでのリベラルな市場経済がうまくいかなくなったイギリスで福祉国家への理論的な基礎を提供するもので、ケインズにも通じるものがある。
私はこれまで子供や老人や障碍者にやさしい社会を作るにはどうするべきかということに関心を持ってきた。だから弱者に厳しい政治・経済的な主張をするネオリベラリズムにはどうしてもなじめない。
私は日本の経済学者の宇沢弘文(1928 ~2014)が主張する社会的共通資本と言う考え方に興味を持っているが、その宇沢が、同僚でもあったフリードマンのネオリベラリズムを厳しく批判していたことを今回知って、宇沢の思想にさらに関心を深めている。宇沢は晩年に成長優先の政策に批判的な対場をとっていることにも私は共感する。
これまで私はスウェーデンなど北欧の社会民主主義的な福祉国家が行っている試みに関心を持ってきた。それは日本の障碍者福祉にも参考になるのではないかという思いからでもある。福祉政策論の専門家である宮本太郎がスウェーデンの福祉に関して積極的に議論を展開していることを私はテレビなどを通じて承知していたが、今回手元に置いたままで読まないでいた政治学者の山口二郎との共著「徹底討論 日本の政治を変える これまでとこれから」(岩波現代全書、2015)を読んでとても面白かった。内容に深入りする余裕はないが、福祉にかかわる生活保障のありかたやもつれた日本の政治のかたちをどう変えていけるのかということを考えてみる良い機会になった。政治を変えるというためには改めて沢山の難題があることを考える機会にもなった。蛇足ながら、宮本と山口は1958年の同じ日の生まれということである。さらに11年間、北海道大学法学部の同僚教授として様々な共同研究もした仲で、本書は息の合った良い対論になっている。
(3)政治哲学の視点から見たリベラリズムージョン・ロールズ
米国の政治哲学者ジョン・ロールズ(1921~2002)は1971 年刊行の「正義論」や「政治的リベラリズム」「公正としての正義 再説」などの著書で知られている。特に「正義論」はリベラリズムの理論的支柱とみなされていて大きな影響力を持つ大書である。私はこの「正義論」をほんの一部分を読んだだけで書棚に並べてままである。ここでは主に斎藤純一、田中将人著の「ジョン・ロールズ 社会正義の探究者」(中公新書、2021)を参考にしてロールズについて、少しふれさせていただきたい。
ロールズは「正義にかなった社会とは何か」と言う一貫した問いのもとに研究を展開した。「正義論」のなかで「公正な社会」の構築の重要性や、「平等な自由」を重視する思想が語られているのは、それらが正義にかなった社会にとって重要なことと考えてのことだろう。また最晩年のインタビューで語った「リベラルな立憲デモクラシーとは、すべての市民が自由かつ平等であり、基本的権利及び自由が保障されている状態を確実にするものを指します」という言葉も、ロールズがリベラルな憲法規範をそなえたデモクラシーを政治の起点にすえたことと同時に、それが正義にかなった社会の条件ともなると考えてのものだろう。
「正義論」でロールズが提示する正義の内容は「正義の二原理」として定式化されている。それは、「最大多数の最大幸福」を掲げる功利主義が少数者の権利を踏みにじる可能性があることへの対抗として出された原理であり、また公正な契約手続きこそが実質的内容を持つ正義原理を正当化するという「公正としての正義」のための原理である。その第一原理が「平等な自由の原理」第二原理の前段が「公平な機会平等の原理」、そして後段が「格差原理」である。その中では特に格差原理が重要であるとロールズが述べている。
格差原理とは社会の価値評価にマッチできない人々をも含めて様々な才能を持つ人々を「コモンアセット」(共同の資産)としてとらえて、様々な才能が相補性をもつような社会を組織しようとすることである。そのためには正義にかなった公正や寛容が必要となる。
「正義論」は称賛とともに批判的な考察も惹起した。たとえば、個人の自由と共同体の価値との関係性や優先性をめぐる論争の中で批判を受けることがあった。「正義論」は個人の自由により重きを置く理論とみなされている。
ロールズは70歳を超えた1993年に現実政治に目を向けて、「政治的リベラリズム」を出版して再び注目を集めた。同時に理想的、形而上学的な「正義論」以上に批判を受けることにもなった。
なかでもロールズとハーバーマスの論争が有名である。政治的リベラリズムでロールズが述べる価値多様な世界での「重なり合うコンセンサス」というみかただけでは、完全には正義にかなっていない実践や文化を温存してしまうのではないかというのがハーバーマスのもっともクリティカルな批判であった。
私はロールズが好きであるのと同様に、今回は触れることができなかったが,ロールズに近い一面を持つリチャード・ローティーが好きである。しかし、彼らの著書を十分読み込んでもいない、まったくの素人がこれ以上いささか抽象的で不十分な言葉を重ねるのは控えたほうがよさそうだ。
(4)「保守とリベラルーねじれる対立軸」(現代思想)をめぐって
現代思想の「保守とリベラルーねじれる対立軸」と言う特集では二つの討議が載せられている。そのなかの一つの討議についてここではすこし触れさせていただきたい。
それは「転倒する保守とリベラルーその空虚さをいかに超えるか」と言う題の、大澤真幸と宇野重規による討議である。
もう一つの討議に触れる余裕がないのが残念だが、萩上チキ、立岩真也、岸正彦の三人による「事実への信仰 ディティールで現実に介入する」と言う題の生命倫理とリベラリズムに関連している討議で、相模原障碍者殺傷事件が取り上げられている。(追記ー私の好きな立岩氏が今年亡くなったことをとても残念に思っている)
大澤と宇野による討議は「保守とは何か」という問題提起から始まる。特に現在の日本やアメリカでの保守対リベラルという対立をみてみると、そこで「保守」とか「リベラル」と言われているものは、かってそういわれていたものとは異なるものになっているのではないかと議論は展開する。
保守は歴史の連続性の中に何を保守するかを見定めているものだ。実際保守主義の元祖はイギリスのエドマンド・バークだが、彼には名誉革命以来のイギリスの自由な政治体制が守るべきものとして明確であった。
しかし日本の保守は明治と戦後という二つの断絶の中で何を保守するのかが見えなくなっている。現在の保守は戦後民主主義や自由平等というアメリカ的な価値に十分にコミットせずに親米、反共であることで保守という自己定義をしている。しかしもはや反共は保守すべき大きな意味づけを持たなくなっているのではあるまいか。にもかかわらず、そこから十分抜け出せないでいることが旧統一教会の問題で見せた今回の自民党の対応がはしなくも露呈していると私には思われる。いっぽうでリベラルは戦後のアメリカ的価値観にコミットしながら反米的な姿勢を示す。またリベラルは、真の意味で進歩的で変革志向的でなく不徹底になってしまっている。リベラルな価値を擁護するとむしろ現状肯定的に聞こえてしまう、つまり保守主義以上に保守的に見えてしまうのだ。そうしたリベラルの態度は、現状に不遇感を抱く人たちには強い反感と批判の対象になる。保守主義は自分が守ることがはっきりしていること、敵がしっかりしていることで成立するものだが現在はその両方が失われている。保守政権は代わりに藁人形のようなリベラルをこしらえて叩いている。あるいは政治的に弱い立場のリベラルの政策が保守政権に盗まれてしまう。保守はたくみにリベラルの政策と、リベラルに対する不信の感情を利用している。このように保守の思想の一部にリベラルが、リベラルの中に保守が見え隠れしてしまい空虚なかたちで保守とリベラルがねじれてしまっているのが現在の日本の政治状況である。従って現状に不満を覚える有権者はリベラルにも保守にも同調できず、選択肢を見失っている。討議はおおよそそのように現状を位置づけている。
それではリベラルはどうあるべきだろうか。討議での提言を見ておこう、
宇野 ……多様性を涵養することがどれだけ痛みを伴うとしても、それは私たちの社会として払うべきコストであるという価値観こそがリベラルの本質だと思います。その意味で、現代のいわゆるリベラルが、真の意味で自らと異なる存在に開かれているでしょうか。リベラル以上のリベラルであることを狙うなら……やせ我慢でも多様性と普遍主義を維持する。それが短期的に不利であっても長期的には社会をよくしていくという感覚を、徐々にであれ広めていくしかない。……
大澤 ……「保守」の勝利に一つだけ効用があるとすれば、リベラルがうまくいっていないことを教えてくれたことです。……宇野さんがおっしゃる通り、多様性や普遍性にこだわり続けることは確かに必要です。しかしそれを日本という文脈のなかでどのように展開すればよいのか。……そこで私が思うのは、やはり憲法九条をめぐる問題だろうということです。……私たちは九条の前提としてある普遍主義的な価値観をどのように展開させていくかを問わなければいけないのです。
ですから、柄谷行人氏が「憲法の無意識」(岩波新書、2016)で主張したことは、ある面の真実をついています。……
宇野 ……結局はリベラルにとどまるのではなく、その先の普遍主義を目指すべきだということです。普遍主義の下で寛容と平等を探るべきです。一方で、保守の側に立ってみても、それぞれが自らの価値や伝統を発見し明確化していくしか道はない。……
これまで憲法九条に関しては私なりに考えてきたが、以上の討議を受けて私は憲法九条の普遍主義をどう展開できのかを改めて考え直す必要性を感じている。
柄谷行人は「憲法の無意識」のなかで、憲法九条を日本人の集団的超自我であり、文化であるという。確かにそれは自発的な意志によってできたのではなく占領軍という外部の力によって押しつけられたものだ。しかし、フロイトが言うように、最初の欲動の断念は、外部の(倫理的な要求の)力によって強制されるものである。先ず占領軍と言う外部の力による戦争(攻撃性)の断念があり、それが良心(超自我)を生みだし、さらに、それが戦争の断念をいっそう求めることになった。柄谷はこのように日本人のこころに定着した憲法九条を説明している。
現在の世界は憲法九条の精神とは真逆と思われる情勢にある。そのなかで、いかにして普遍的な世界平和への道筋をつけることが可能だろうか。多くの日本人のこころに憲法九条が定着している間に何ができるのだろうか。「ただ日本は歴史的にみても世界でトップクラスに普遍が苦手な国ですよね」という大澤の言葉に私はつい笑ってしまったのだが、気を引き締めて、日本のリベラリズムの責務には重いものがあるのだと受けとめておきたいと思う。
***
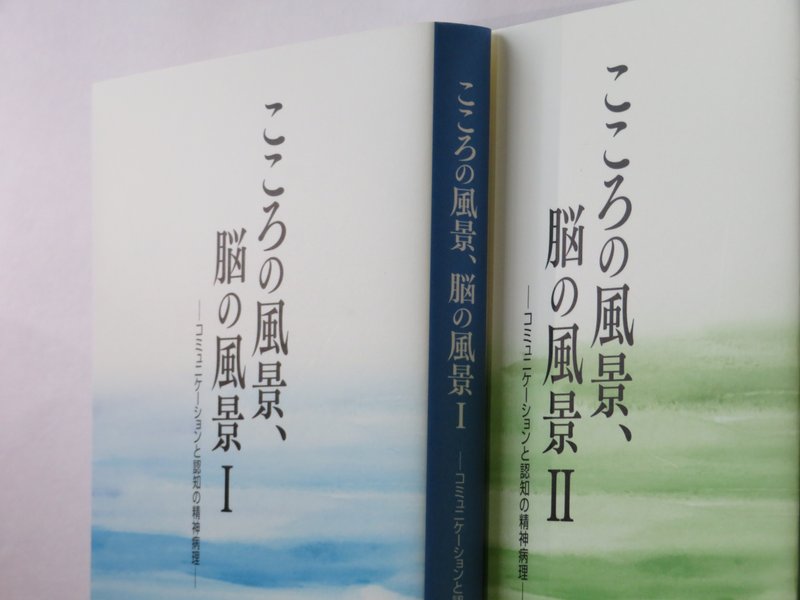
「こころの風景、脳の風景―コミュニケーションと認知の精神病理―Ⅰ、Ⅱ」より
★「札幌農学校 日本近代精神の源流」(蛯名賢造著、新評論、1991)
千歳市のほぼ中央にグリーンベルトと名付けられた広場があり、その一角に建てられた記念碑に、若き日の新渡戸稲造先生がこの地で内村鑑三先生と友情を深めたということが記されている。二人は1876年(明治10年)に開校された札幌農学校の2期生で彼らが入学した時には、クラークはもうアメリカに去った後だった。しかし彼が植えつけた、自由や独立のピューリタン精神はしっかりと一期生によって伝えられた。千歳を訪れたのはもちろん新渡戸や内村だけではない。二人の終生の友である宮部金吾も含めて、複数の学生が、よく千歳川で遊び、アイヌのサケ漁が禁止される法律が成立した時にはそこで怒りの声をあげたと記録に残されている。


記念碑建立趣意
千歳市は新渡戸稲造先生が札幌農学校に在籍中に古里と学校との往来に(この地に寄られ)
若き日の内村鑑三先生との友情を深められたところです このゆかりの地に先生の
偉業をたたえ又その(業績を)伝承すべく多くの市民のご厚意により記念碑を建立(致します)
(カッコ内は私が言葉を予想して補った)
本書、「札幌農学校 日本近代世代精神の源流」の事を私は、元朝日新聞の記者外岡秀俊氏(残念ながら2021年に亡くなられた)のエッセイによって知った。氏は新渡戸稲造と内村鑑三を戦前の自由思想の源流の一方に位置づけ、札幌発のリベラリズムとして評価したうえで、本書には特にこの二人の人脈の広がりが克明に記されていると紹介している。二人の教えを受けた人脈には、矢内原忠雄や南原繁その弟子の丸山眞男などがいる。さらに、クラークの弟子と言ってはばからない石橋湛山も含めておきたい。彼らは、戦時体制による言論統制が深まる空気の中で次第に孤立させられていった。新渡戸と内村は戦争の始まる前に亡くなっているが、本書の著者は戦後の日本国憲法には内村の非戦論や平和論が、教育基本法には新渡戸の教育理念が結実していると述べている。しかし現在の政権はそのどちらにも変更を加えて、まるで戦前に回帰しようとしているかのようである。気をつけないと言論もその自由の幅を狭められかねないとすら思える昨今である。そんな中で、私は札幌発のリベラリズムについて、その脆弱性や批判すべき点も含めてだが、今一度思いをめぐらしてみるのも意味のあることではないかと思う。(2021年、読書ノートより)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
