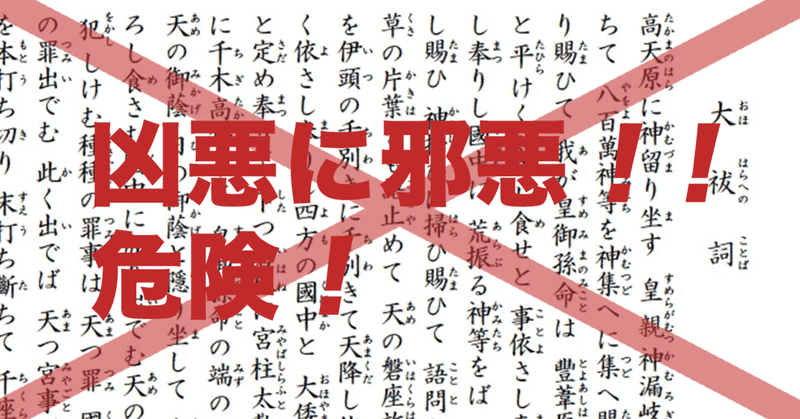
77.古文・祝詞・日神示の読み方(大祝詞説明のnoteの前書き)
3770文字
大祝詞・延喜式の説明の前に作られた時代背景
醍醐天皇は「延喜の治」と呼ばれる天皇親政を行ったが、晩年には清涼殿に落雷が直撃し、沢山の公暁が亡くなるという天罰に見舞われている。
朱雀天皇の代には「承平・天慶の乱」が起こり、さらに富士山の噴火や地震・洪水などが頻発。
そして村上天皇から円融天皇の時代には内裏が何度も焼亡している。の時代、このような災害が起きるのは天皇の不徳のせいと見做す向きがあった。仏教伝来以前の日本では、穢れと罪と天災は因果論によって不可分の関係にあり、厳密には区別されていなかった。
御写真はYouTubeの天皇芸人の方々
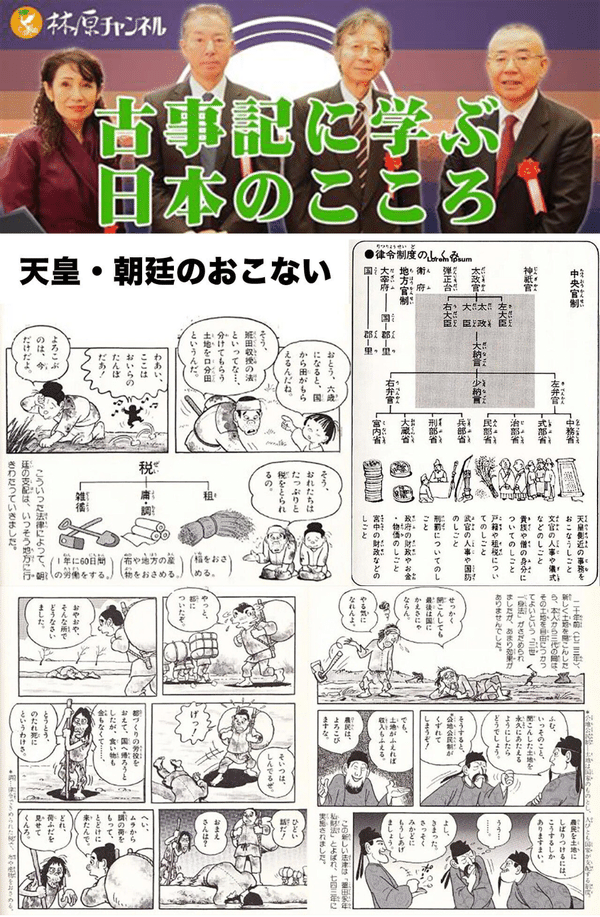
こんなフザケタ事が何もなく上手くいくはずもなく、天の本当の神の怒りによる天罰につぐ天罰が、朝廷、天皇に落ちに落ちまくった時代に延喜式は作られた。延喜式は天罰対策の祝詞。
大祝詞が載っているのは延喜式
成立
905年(延喜5年)、醍醐天皇の命により藤原時平らが編纂を始め、時平の死後は藤原忠平が編纂に当たった。『弘仁式』『貞観式』とその後の式を取捨編集し、927年(延長5年)に完成した。その後改訂を重ね、967年(康保4年)より施行された。
大祓詞
大祓詞は、神道の祭祀に用いられる祝詞の一つである。中臣祓詞ともいう。典型は延喜式巻八に六月晦大祓という題名で載る。中臣氏は朝廷の役人の仕事のする時は藤原氏を名のり、神官をする時は元の中臣氏を名乗る、中身同じ。
大祓詞を読み推測できることは、一般的に大祓詞を中臣祓という場合は、朝廷の役人たちに暗唱さえるための文で、大祓詞という場合は愚かな大衆に広め宣り聞かせるために、天皇の邪悪なルーツがバレる危険があるところをカットしたものを言う。
古文が読めない人のためにひらながのルビ付きの文で広めているが、これもバレないようにするためで、このひらながでより意味が分からなくなるのだ。このテクニックは、日本の聖書で生かされている。だから、日本で聖書を翻訳した輩は、このテクニックを知っている者。この手の文は、サービスのように見えるが実は罠なの。ひらなが、カタカナのルビを手作業で消して、自身で一から読むことが大事だ。
天皇の教育勅語など、そうんな風に読むわけがないだろう!というカタカナで、誰も意味が分からず、今でも騙されている!
大祓詞≒中臣祓詞=六月”晦”大祓
ここから先は
¥ 250
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
