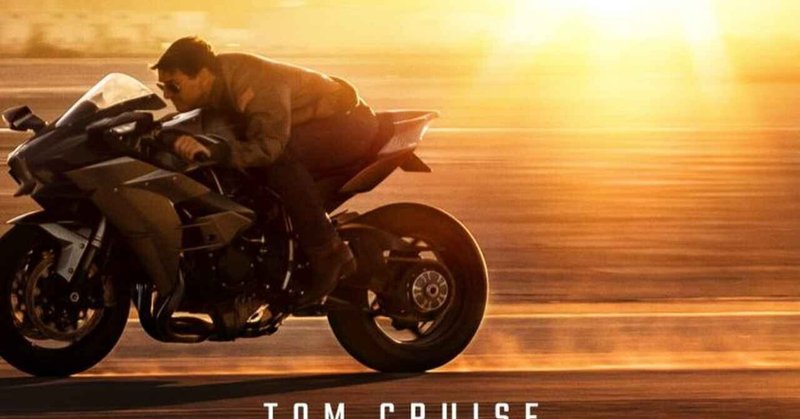
『トップガン マーヴェリック』の狂騒が覆い隠す違和感と背徳〜ニンテンドー・ウォー・ムービーの完成〜
ドルビーシネマで観られて、何にも変え難い体験になった。
心臓を直接鷲掴みにして揺さぶられる体験。
やはり映画館で観る映画は、「音」が肝だ。
役者本人たちが生命の危険を背負って体を張って魅せるエンタメを果たして「劇映画」「物語」のカテゴリに入れていいのか、という一抹の疑問はよぎる。
本当の戦地を描いた戦争映画はエンタメにはならない。
ドキュメンタリーだ。
これが行き過ぎればその先に待っているのはスナッフフィルムだ。
この「誰もがスカッとできるエンタメ映画」への狂騒が、数十年前に各国で(もちろん我が国でも)創られた『戦意高揚映画』の側面を背負っていながら、ほとんどのライトな観客には当然気づかれていないことにも危うさがある。(この側面を無視してか、気づかずか、手放しで絶賛している映画評価者はプロとして認めてはいけない、絶対に。)そしてその点を註釈的にでも指摘しようものならかえって「危ない人だなあ」「面倒な人だなあ」と言われる時代である。逆だ。プロパガンダをプロパガンダと見抜けず手放しで絶賛してしまう声の大きい人の方が、ずっと危険だ。
「これは戦争映画ではなくスポーツ映画だ」と創り手は言う。しかし、明らかに前作よりも先制攻撃的な作戦が描かれる。国際法的にアウトな作戦をわざわざ描く意図はなんだろう。多くの観客がそこに一抹の疑問さえ抱かないのはなぜだろう。
『トップガン マーヴェリック』の劇中では、「極悪な枢軸国」たる敵は疑問の余地のない絶対悪として描かれる。徹底的に思考停止させてくれる観客へのホスピタリティとして評価すべきか。
敵地に「人間」の温度はほとんどない。気持ち程度に人間も映りはするが、人工物と戦っているような錯覚に陥るくらい、敵の人間としての存在感は希薄だ。
湾岸戦争は「ニンテンドー・ウォー=ゲームのような戦争」と形容されたが、まさに『トップガン マーヴェリック』は「ニンテンドー・ウォー」的感覚の極地たる戦争映画だ。多くの観客がロシアのウクライナ侵攻の中でもこの映画を「戦争映画」とすら捉えていない事実がまた、この映画の「ニンテンドー・ウォー・ムービー」っぷりを補強する。
そして興味深いのは、敵軍の人間らしさは極限まで漂白されている一方で、主人公らアメリカ軍人の主観に没入する体験価値が本作の一番のセールスポイントになっている逆説だ。味方の五感に没入させる努力を200%する。敵の存在感は200%希釈する。これは当然、湾岸戦争以降30年かけて、ゲームが主観への没入を進化させてきた歴史と連動する。
前作から36年かかって完成した超大作はそのまま、私たちの戦争への価値観がゲーム化していく歴史の写鏡であったと言えよう。『トップガン マーヴェリック』は「ニンテンドー・ウォー・ムービー」の完成形だ。
では、本作が危険なプロパガンダ映画か、と問われると悩ましい。率直に言えば、受け手のリテラシーの低下が問題ではないかと現在の私は思っている。「大興奮の映画体験!」と満足して映画館を出た後に、喫茶店で友と語り合いながら、10分くらいは「でも戦争映画としてはだいぶあざといよね…」と苦笑いで嘆息する。そんな時間と多層的な感想をシェアする余裕を、一体どれほどの日本人観客が持ち合わせているだろうか。
「映画」という芸術が存在意義を悩まねばならないパンデミック禍と過剰供給情報社会の中で、「遊園地」「見世物小屋」としての体験価値を有無を言わせず屹立させた功績。
戦争の陶酔の危険性に、僅差で功績が勝つ。
喜びたい。何度でも観たい。
そして毎回喫茶店で「でも、危険だよね」と溜息を吐きたい。
文章を書くと肩が凝る。肩が凝ると血流が遅れる。血流が遅れると脳が遅れる。脳が遅れると文字も遅れる。そんな時に、整体かサウナに行ければ、全てが加速する。
