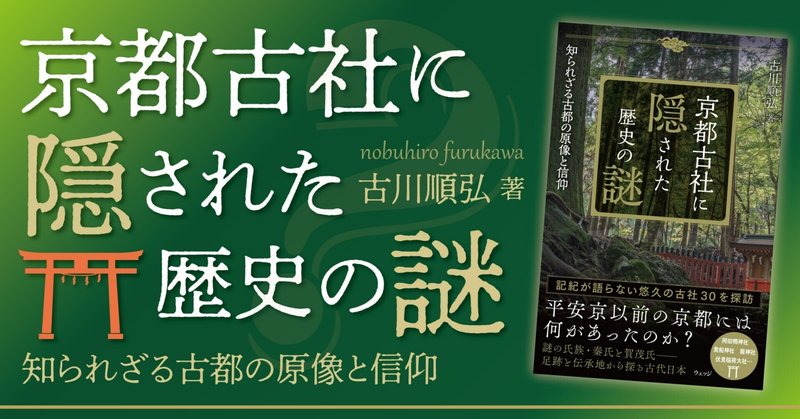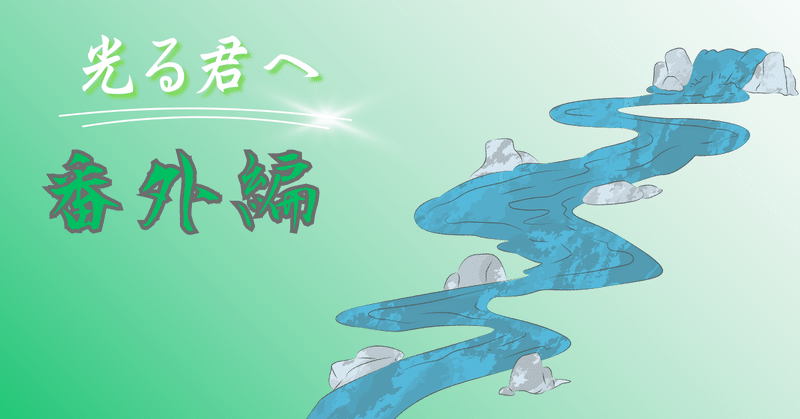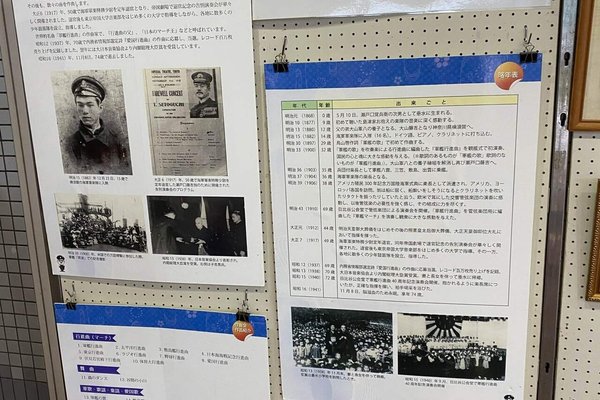人気の記事一覧

【奈良国立博物館】特別展「空海 KŪKAI─密教のルーツとマンダラ世界」の見どころを、仏像イラストレーターの田中ひろみさんが現地レポート!
奈良国立博物館 生誕1250年記念特別展「空海 KŪKAI―密教のルーツとマンダラ世界」の内覧会に行ってきました。 空海の生誕1250年を記念して、「かつてない空海展になる!」と井上洋一館長が力説される奈良国立博物館の総力を挙げた展覧会は、国宝28点、重要文化財約59点*とお宝だらけ。わたしのスーパーヒーロー・空海や密教のことがよくわかる展示内容でした。 5体が揃う最古の五智如来像会場に入るとすぐに、京都・安祥寺の国宝「五智如来坐像」が、大日如来像を中心に並んでいます。5
スキ
167