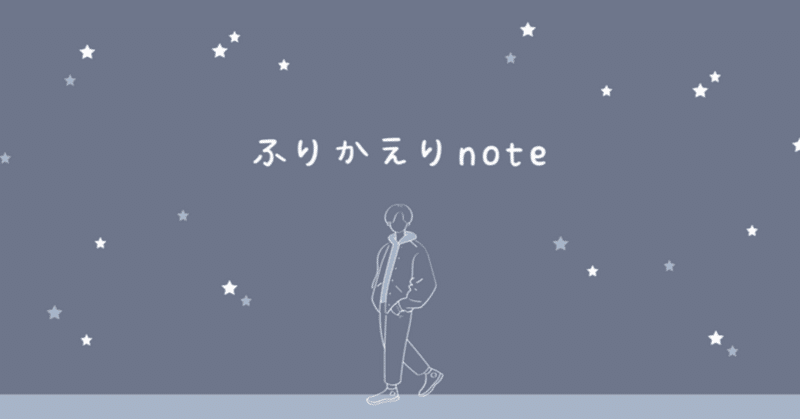
目指すのは指導者?教育者?
専門学校の教員として長く働いています。
もともと専門学校は実践力・即戦力を養うための職業訓練校の側面を持って生まれたこともあり、簿記経理や理美容、自動車整備、幼保、情報処理など様々な種類の学校の中から身につけたい技術を基準に選んで学び、実践力を習得することができるわけです。
その専門学校で教えるわたしたちは果たしてどんな存在なのでしょう?
技術を習得させるための指導者?
学問として学び教えるための教育者?
これは長らく論じられてきました。そしていまでも、どちらの立場で関わるかが問われていると、現場にいるわたしは感じています。
そこには専門学校の役割の変化も影響しています。
昭和の後半までは、専門学校は職業直結の学びであり、資格取得と合わせて『専門的な技術を習得する学校』として社会から求められてきました。
かたや大学は『学問を修める学校』として学術的な研究を中心とした学びを追求し、高度な知識を修得することを求められてきました。
しかしバブルがはじけて以来、大学は専門学校化の道を、専門学校は大学化の道を進むことになります。いまでは専門職大学や高度専門士など、4年間で専門的な知識と技術を身につけることができる学校が数多く誕生しています。
だとすれば、専門学校の教員はどこを目指せばよいのでしょう?
わたしは、「これからの時代の専門学校教員は教育者を目指すべき」と考えています。放送大学で心理学を学ぶと同時に教育科目を選択した大きな理由がこの考えです。
教育基本法や学習指導要領を知らずに、専門学校の「教員」を名乗ってよいのかと……技術を伝承するだけなら「指導者」や「講師」でよいのではないかと……そんな迷いを抱いたからこそ、放送大学の『 教養学部 教養学科 心理と教育コース』に惹かれたのでしょう。
実際に学んだこの3年間で、わたし自身が「教育者」として成長できたと感じる場面は幾度もありました。特に変わったのは「この科目は何を学び、どのような力をつけることができるのか」「そのために今日の授業は何をゴールとするのか」を、意識せずに語れるほどになったことです。
毎回、授業の冒頭にセットアップのために短時間で伝えています。これがあるとないとでは大きく違う・・・と思っています。
実はこのセットアップ、JCDAのピアファシリテーターとしてピアトレーニングを行う際に毎回行っていることなんですよね。タイミングよく大学での学びとピアファシリテーターの活動が重なったため、少しずつ学びの場づくりに「教育」の要素を取り入れて伝えるようになっていきました。
教育は教えることも大切ですが、それと同じくらい育むことが重要です。キャリアカウンセラーとしてどんな自分でありたいか、自分で自分を育むための学びがピアトレーニングにはあります。そこに気づいて強調し、アプローチしてきたというのがわたしのピアトレの特徴なのかもしれません。
授業もピアトレも、誰が担当しても同じ内容を教えることはできます。ですが育むことについては、その人のあり方が如実に表れます。どんな人に育ってほしいかと考え抜くことで、関わり方も伝え方も変わります。そのために自己研鑽を行いますし、自身のあり方を自問自答することが続きます。
ある種ストイックな生き方かもしれませんが、それをよしとし、厳しさと愛情を持って自らを鍛えることでしか教育者としての成長はないと、わたしは感じています。近道なんてないんですよね。真摯に生きていくだけです。
改めてわたしは胸を張ってこう言います。
「専門学校“教員”のオカベヤスユキです」
#明日も佳き日でありますように
#教育者
#指導者
#教育基本法
#学習指導要領
#専門学校
#専修学校
#ピアトレーニング
#ピアファシリテーター
#生き方
#あり方
#毎日note
#おかちんnote
#キャリアカウンセラー
#キャリアコンサルタント
#キャリアカウンセリング
#キャリアコンサルティング
#キャリア
#キャリコン
#CDA
#コミュニケーション
#コミュニケーションファシリテーター
#コミュファシ
#アートマインドコーチング
#AMC
#対話型アート鑑賞
#JEARA
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
