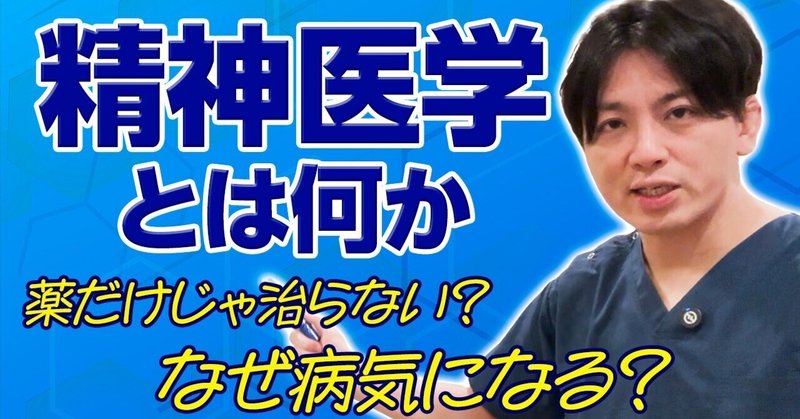
精神医学とは何か|精神医学が抱えている問題、構造、考え方
本日は、精神医学とは何か、精神医学が抱えている問題、構造、考え方をざっくりお話します。
うつ病は甘えだ、薬だけじゃ治らない、カウンセリングが大事だ、とよく言われますが、なぜ病気になるのか、どうしたら良いのか、何が今解明されてないのか、そういう話です。
そこを話そうと思うので、今回は「精神医学とは何だ?」という話をします。
精神医学とは何かというと、精神疾患を治すというマイナー科なんです。
医学の中ではマイナー科なんです。
メジャーとマイナーというのがまずあって、メジャー科というのは内科や外科です。
マイナー科というのは、皮膚科、眼科、精神科、耳鼻科など、これらが「マイナー科」と呼ばれます。
つまり人体の中の一部しか扱わない科のことです。
精神科は色々なものを扱っているような感じがするんだけど、あくまで脳の中のごく一部、しかも神経内科とは違って、目に見えないほどのごくわずかな変化しか起きてない、それを治療しようとしているので、精神科は医者の中からは「何なの?」と思われちゃうような科でもあるわけです。
そもそもそういうものなんです。
それが嫌だとかそういうわけじゃなくて、そもそもその程度のものしか頭の中で起きてないんだよ、ということを皆さんに知ってもらいたかったということです。
精神科は、今は生物心理社会モデルみたいな形で説明されることが多いんです。
発症のメカニズムは何かというと、その人が抱えている社会的な問題、家庭の問題、自分の健康の問題、家族の問題、友人・恋人の中で起きている問題、仕事の問題、勉強したいけどうまくできない学びの問題、趣味の問題、趣味でトラブル、趣味が上手くいかない、お金の悩み、そういう諸々の日常の悩みや問題があって、それがストレスになってる。
心身の疲労が起きる。
こういうものが溜まった結果、ポンッと症状が現れるというのが生物心理社会モデルです。
何か問題があって悩んでいるうちに、脳のどこかで炎症が起きたり、脳の中で変化が起きるんです。
これはかなり微小な変化なので、現代医学の中ではほとんどわかっていないです。
ほとんど何が起きているかわからないんです。
癌などはもう顕微鏡などを使えばほとんどわかるのに、脳の中のどういう変化が起きているのかがまだ現代ではわからないほど微小な変化が起きている。
それは何なんだろう?
大した変化は起きていないとも言えるし、すごい変化が起きているがまだ人類がわかってないだけとも言えるかもしれないですけど。
でも他の医学ではまだまだ科学は進んでいないにも関わらず、ここかなとわかるのにも関わらず、脳の問題だけはわかってない。
正常と異常の差がほとんどないということなので。
あるんだけど、すごく微小だし、あるんだけど、まだわからないぐらい。
それが精神科のマイナーたる所以です。
だから誰でもなるっていえば誰でもなるんですけど。
炎症があって症状が起きる。
症状の出方というのは人それぞれ違うよという形で、例えばポンと外れて再発が多いような病気になってしまう。
例えば統合失調症とか双極性障害とか、うつ病もそうです、古典的なうつ病ばそういう感じ。
良くなったなと思ってもまた悪化してしまうということもあれば、何となくずっと元気がないうつ病や不安のような問題もあるし。
身体の方に出てくるものもあるんです。
心はそんなに落ち込んでないんだけど、胃が痛い、便秘、下痢だとか肩こり、ヘルニアだとか。
痛みが強い線維筋痛症みたいな心身症のようなものもあるし。
依存症ですよね。
そこから逃れようとするがあまり、ストレスから逃れようとする上でお酒に逃げちゃう、ギャンブルに逃げちゃう、性行為に逃げちゃう、スマホに逃げちゃう。
そして一度逃げたらそれが快感なんです。
「ああ、助かった」と思って、苦しくなったらまたやりたくなってしまう。
その結果またやってしまうと楽になる。
だけど、どんどんやめられなくなってしまうとか。
あとはトラウマです。
記憶の障害として残って、忘れることができなくて苦しんでしまうPTSDみたいなものがあります。
色々ありますね。
これはざっくり適当に出しただけなのですが、色々なパターンがあります。
症状から、脳に何が起きているのかというのが一部わかってるところもあるので、こういう症状や病気から脳の中に何が起きてるかわかってることもあるので、それに合わせた薬を使ったり、まだ薬が開発されていないものもあったりしますよ、ということです。
精神科の治療とは何かというと、この症状、診断に対して、おそらくこの薬が効くんじゃないか、というものを使うということと、ここのストレスや心身の疲労が溜まってるので、ここは休息とか時間によって解決するというのと、あとここですよね、そもそもどんな問題があるの、と、この問題を解決してあげるというのが精神科の治療です。
これは本人が解決できるように、本人の解決能力を高める、考え方、受容する力を高めていくのも一つだし、本人ができないのであれば、家族や会社の人に医師がアドバイスすることで周りの人に助けてもらうこともあれば、社会制度を利用する、生活保護や障害年金を取るとか、そういう形でお金の問題を解決、悩みを解決することで問題を緩和させるなど色々なやり方がありますけど、それが精神医学ということです。
◾️人によってパラメーターが違う
じゃあ発達障害とは何なの?
パーソナリティ障害とか境界性パーソナリティ障害とか何なの?
HSPとは何なの?
ということになると思うんですよ。
まず基本はこうなんだけれども、この問題を起こしやすい人がいるよね、と。
何か変わってるとか、個性的であるとか、性格の問題、何かしらの問題があって、ここの構造自体に問題を起こしやすいものがあるよね、ということです。
それはその人の考え方の問題だったり、生まれつきの遺伝子的な問題でそういう風に考えるような脳みそになっていることもあるわけです。
不安を感じやすい脳みその人たちもいるし、不安を感じにくい挑戦的な人たちもいる、と。
色々な性格の人がいますから。
頭の良さにも上下があるように、運動神経にも上下があるように、全てのもの、人間のあらゆる知性というものはパラメーター的に違うんです。
今の民主主義や現代社会では、人間というのは努力をすればみんな何にでもなれるというか、才能やそういう遺伝的なものを、生まれつきの問題というのを、何となく隠蔽しているところがあるんですよ。
何となくみんな知ってるんだけど、どちらかというと白紙説というか、教育によって変化可能だみたいなことになってます、民主主義というのは。
資本主義、民主主義というのは。
だけど本当は違うんだけどね、ということです。
とにかくそういうパーソナリティー症や認知の歪みからくるもの、軽いものだとこういう歪みがあるよね、と言うし、重いものだとパーソナリティ障害や人格障害と言ったり、あとは変化の割合があまりに違うと、もう一個ある知的な問題と言えば、精神発達遅滞や発達障害、LD、そういうものもあります、ということです。
この発達障害を知的な問題に含めるのか、それとも知的な問題というよりは個性なんだというと、パーソナリティ障害の分類に入るのか、それともまた別のものなのかというのは、色々な議論の仕方がありますけど、基本的にちょっと今のところ益田独自のオリジナルの考えではないですからね。
発達障害をパーソナリティ障害という風に分類することはないです。
あくまで知的な問題、精神発達遅滞の仲間ないしそこの隣り、親戚みたいな扱いになってるのかなと思います。
今オンライン自助会をやっている上で困るパターンというか、困るパターンというのは発達障害傾向がある人。
発達障害と言っても、あるかないかやカテゴリーじゃなくてスペクトラムなんです。
数学がすごい得意とか漢字をいっぱいよく知っているとか。
だけど、ここからここはよく知ってて、ここからここはできないとかはないじゃないですか。
英語ができる/できない中で、英語ができる人、できない人と言いますが、英語もそこそこできる人もいれば、観光旅行くらいはできる人、ビジネスでもできる人、文学部のように細かいニュアンスでできる人、精神科医のようにもっと細かいニュアンスまで英語でできる人、様々なグラデーションに分かれるのと同じです。
発達障害というのもグラデーションに分かれます。
あとは繊細な人、HSPは医学用語じゃないですけど、よく使われてるんで使いますけど、社交不安の人、不安を感じやすい人で、不安を感じた後に回避的になってる人、逃げちゃう人もしくは依存的になってしまう人(いわゆる引きこもり的な人たち)というパターンもあるし。
あとは境界性パーソナリティ障害のように理想化とこきおろし。
記憶の中の人間と目の前の人間のイメージがグチャグチャになってしまって、この人は良い人なのか悪い人なのか、あるがままを見られなくて、自分の感情に合わせて良い人に見えたり、悪い人に見えてしまったりするというのがあります。
その中で妬みの問題もあったりしますけど。
この三つの傾向というのが、割と僕の中では最近自助会のメンバーたちに説明するときにも良い概念です。
色々な人がいるよということですけど、代表的なものを知ってもらえばなと思います。
でも結局人間をカテゴリーに分けていくことは本当は不可能なんです。
だけど僕らの認知は、脳みそというのは決して賢くないので、扱える情報量にも限界があります。
だからある程度カテゴライズしてあげたり分類してあげて、この人はこうなんだという風に考えないと難しいんですけど、本当のことを言うと、そんなカテゴリー分けができるもんじゃないんだけれども、厳密に言えば、哲学的に言えば、科学哲学的に言えばね。
ですが、僕らが脳みそを使って何かをしていくためには、そういう仮の足置き場みたいなものを作ってあげないといけないし、それを作ったことに弊害はあるんじゃないかと言われたら、もちろんあるんですけど、そういうのはあります。
ということです。
◾️問題を整理・明確化していく
だからどうしたら良いの?というと、こういうことを理解した上で問題を整理明確化していく。
自分が気づいていないものについては、ある意味無意識の領域にあるものは直面化していくということが必要になります。
そういうことをした上で解決を目指すのか、それとも諦めるのか、受容を目指すのかを一緒に考えていくということになります。
問題というのは整理明確化していけば解決できるものばかりではないんですよね。
トロッコ問題のようにA案とB案にまで整理されたけれども、A案にはこのマイナスポイントがある、B案にはこっちのマイナスポイントがある。
離婚したらいいのか離婚しない方が良いのか、究極的には答えは出ないわけですが、どちらもメリットとデメリットがあるから。
それをどう考えるのか。
あと、ループ構造のようなものがあります。
ひきこもりの人はひきこもりだから人間関係が下手になる、社会経験を積めない。
社会経験を積めないから自信がなくなる。
自信がなくなるから人が怖い。
人が怖いからまた引きこもる。
これはループ構造です。
こういうループ構造のこともあるし。
ジレンマ、自分が我慢すれば問題はなくなる。
だけど自分が調子悪くなる。
じゃあ相手が我慢してくれたらいいのに。
自分が我慢せずに相手が我慢してくれれば一番良いんだけれども、相手も我慢したくないから、腹の探り合いみたいな、どっちが我慢するねん、みたいな感じでこっちが先に我慢しちゃったらうまくいかない。
本当は互いに我慢しあわなければいけないんだけど、先に我慢した方が損をするから互いにやらないみたいなゲーム理論というかジレンマのような問題もあったりします。
そういう問題構造の中で、ある部分ジレンマの問題、トロッコ問題やループもそうだけど、ある段階では決断して「もういいや」と。
損して得を取れというか、肉を切って骨を断つみたいな、そういう決断や勇気というのが必要になってくるんですけど、そういうものが大事です。
ではこの問題は個人の問題なのかというと、そういうわけじゃなくて、やはり本人の責任じゃないんですね。
生まれつきの遺伝子の問題もあれば、環境の問題もあるし、運の要素もあるわけです、不運とか。
震災に遭うのは運じゃないですか、たまたまその地域に住んでいたからというのもあるので。
そういうものについては、もうちょっと全体的に治療していく必要がある。
個人だけじゃなくて、家族全体を治していく、会社全体に介入していく、社会システム全体に介入していく。
そもそも共働きはムリゲーじゃないか、共働きで子育てしてましてやその子どもがみんな優秀で聞き分けが良い子じゃなくて、発達障害のようなものがあったときに、それを全部親の責任だと言われたら無理でしょう、みたいなものもあるわけです。
そういうときには、やはり僕らが社会システムにどう声をかけていくのか。
どういう風に社会と一緒に僕らが無視されない精神科の患者さん、これらの問題が無視されない、あなたはたまたま良いんですよ、僕らはたまたま不幸な目に遭ってるんですよ、ということを共有していく、オープンにしていくことで社会を変えていくということも重要だったりしますけどね。
というのがあります。
こういう症状や診断に関して脳はどういうものなのかは類推可能なのか、こういうものがあるときにどういう性格の人が多いのかということは、類推可能なのかというと、可能な部分もあるし、100%一致はしないんです。
◾️どう変わっていけるのか
あとは、じゃあどういう風にしていけば変わっていけるんだろうか?
カウンセリングですか?と言うんですけど、カウンセリングも一つだし、コミュニティやメンターをきちんと作っていくのも大事だなと思って、僕はオンライン自助会や家族会というのをやっているわけです。
一人のカウンセラーとやっていくだけじゃなくて、人間の心の中は人間の集合体のようなもので出来上がってるんじゃないかという考え方もあるんです。
そういうモデルもあって、精神分析はそういう考え方をしますけど、人間とはやはりどこか陰謀論もそうですけど、未知なるものなどに対して人格を与えるということをよくします。
人間というのは目に見えないものに対して、人間として把握するみたいなところがあるんです。
それを過剰なエージェント説と言ったりするんですけど、僕も臨床で特にそう思います。
例えばこうしなければいけない「べき思考」のときに、そこを何とかすべきだというのは、社会のルールだったり常識だったり、精神分析では「超自我」と呼ばれるものなんですけど、この「べき思考」というのは人格の形をとることが多いです、父親だったり、上司だったり。
「べき思考」を治すのではなくて、その人の中にある父親像を変えていくことで治療が進んでいくんです。
心の中は、あの人が言ったな、あの人はこう言ったな、みたいな形で、人間というのは心を把握してたり、それを機能構造にしていることが多いので、つまり優しい人に囲まれていないと人は良くなっていかないんです。
お金がいくらあっても、いくら天才的な能力を手に入れても、やはり心の構成体としての人間像が優しい人たち、自分を愛してくれる人たち、自分を理解してくれる人たちで構成されないと、人間は絶対うつになるんです。
それは無人島で生きていて、無人島じゃなくてもいいですよね、惑星間の宇宙船でみんなが冬眠中に自分だけ起きてしまって、食料も豊富にあるし、ゲームもあるし、AIもいて、ロボットと会話できても気が狂いますよね、絶対。
人間とはそういうものなんです。
発達障害の人だとあまりそうならない人も一部いますけど、でもそれでもやっぱ変になってしまうんじゃないかなと思います。
永遠の孤独というか。
やはり人間というのは理解されたい、愛されたいというのがあるので、じゃあそういうためにはそのメンターやコミュニティをどうやって作るのかということを考えている。
これを地域社会がなくなって、今家庭と会社しかない中、利害関係、会社というような利害関係、家庭のような場所ではないところでやはり作っていく必要があるし、そういう中で、卒後教育じゃないですけど、ある程度大人になってからも心を学んでいったり、学校のような教育できるシステムがあった方が僕は良いと思っていて、そういうのを今考えています。
オンライン自助会もそうだし、月1のセミナーも今考え中です。
あとはこういう整理・明確化をしていく中で、それは人とやらないと本当にできないのかということなので、例えばやり方をワークブックや手帳やアプリという形に落とし込んだり、あとAIとのやり取り、AI家庭教師を作って、AI家庭教師で英語を学び合うようにAI家庭教師を通じて心の整理をしていく、学びをしていくということもいいんだろうなと思います。
もちろん生い立ちのことを整理するなど色々ありますけど。
これはプライバシー情報だから、自己責任でやらなければいけないし、本当はダメですからね。
ダメですけれども、将来的にはそういうこともあるんだろうなという風には思います。
プライバシー情報にやはり敏感な人は書くべきじゃないし、別にいいですよという人であっても、匿名性を担保しつつ書き込むことで整理できるかなと思います。
もっとクローズな場所でワークブックや手帳みたいな形でやった方が良いんでしょうけどね。
これも今の課題として、自分が今抱えていて、こういうことを未来に向けてやっていきたいなと思っているという感じです。
結局、薬だけじゃ治らないよと言ったらその通りで、こっちの問題を解決しなければいけないし、この認知の歪みというか、ここの緑枠のことも考えなければいけないし、かといって脳の炎症、脳の変化も起きてるわけだから、それに合わせた薬というのはやはり有効性もあるので、飲まなくてもいいこともありますけど、飲んだ方が良い場合もたくさんあるので、適宜利用していくということになるのかなと思います。
あとは社会制度をうまく利用してあげて、自分一人でこの問題を解決していこうというのは不可能なので、周りの人の協力を得たり、社会制度などをうまく利用するというのが大事ということになります。
ということで今回は、精神医学とは何か、というテーマでお話ししました。
◾️本日の宿題
今日の宿題はここにしましょうか。
心の構造が人の集合体なんだというその集合体、これまで出会った人や経験の中の人間によって心というのは構成されているということ、もしくは 、そのポジション、その椅子に誰かが座らされてるという感覚を言語化してもらって自分の中でコメントしてもらえると良い学びかなと思います。
▼オンライン自助会/家族会の入会方法はこちらhttps://www.notion.so/db1a847cd9da46759f3ee14c00d80995
▼iPhone(Safari)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/_49prDk9fQw?si=BMjBO1CyXlhq7BaI
▼iPhone(Google Chrome)からのメンバーシップ登録方法https://youtu.be/38zE3uwcPgg?si=XE2GJ8hWI-ATjjGe
▼オンライン自助会/家族会の公式LINE登録はこちらから
https://lin.ee/XegaAAT
ID:@321iwhpp
よくわからないこと、聞きたいことなどが
あれば、こちらにお問合せください。
運営スタッフより、返信いたします。
onlineselfhelpsociety@gmail.com
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
