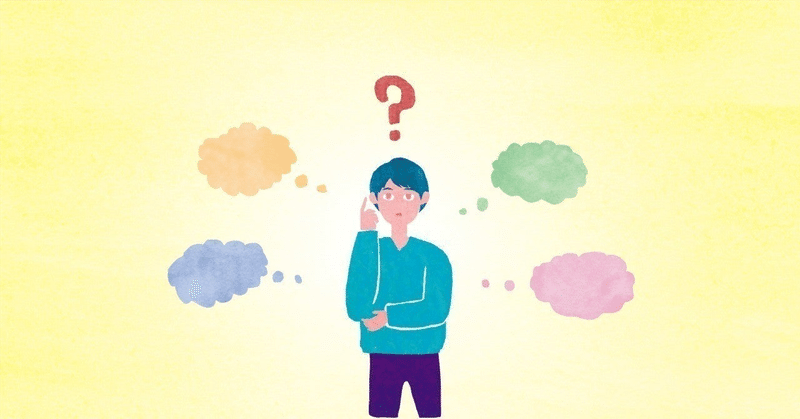
むずむずを大切に
わからないことがあると、私はむずむずする人間である。
中学くらいのころだったか、「駿台模試」というものがあった。
これが爆裂に難しくて、特に数学とかだと30点くらいしか取れないのだが、たびたびむずむずして集中力が途切れてしまうことがあった。
だからきまって、むずむずがあると点数が悪かった。
いまでも、このむずむずがある。
英語を読んでいたりして、分からない文章に出会ったときなんかは典型的だろう。
ちょうど、身体の中に虫がいる感じがするのだ。体のなかで、丁度カフカの「変身」みたいな芋虫がうねうねしている感じだ。
日本語でも岩波なんかが意味不明な文章の羅列をしたものとして有名だが、あのときも同じようなむずむずがある。
そういえば、三木清の「哲学入門」は入門でありながらまったく理解することが出来ずに人生で2度挫折した。
まあ、逆に挫折したから間違って哲学の道に足を踏み入れることなく、現世でなんとか生きることが出来ていている、という意味では日本の大哲学者の一人である三木清に感謝せねばならないところではある。
あのむずむずする感じというのは、ある意味で「わかりたい」という衝動に近いものだと思う。
もちろん世の中の全てがわかるというわけでもない。難しい物理や数学の話だとわからなくても「ああそうですか」という感じではあるのだが、なまじ自信のある領域になるといまでもあのむずむずがやってくる。
ひとがわかりたいと思うその根源的な欲求を知的好奇心とよぶのなら、そのむずむずは歓迎すべきモノなのかもしれない。結局むずむずするから、なんとか脱むずむずのために勉強していたのである。
むずむずに逃げずに立ち向かう、諦めずに脳みそを回そうとする根性みたいなモノって結構大事なのだろうと思う。
世の中を見ると結構「簡単」「わかりやすい」「お手軽」みたいなものが流行りやすい。もちろんわかりづらいことは誰のためにもならないが、わかりやすさが行きすぎてしまって陰謀論よろしく、事実と異なるものが生まれるということもしばしばだ。
一番恐ろしいのは、わかった気になって人生でむずむずすることを忘れてしまうことなのではないか。意味不明なものごとに対峙し、不快でも己の中にいる、わからずやな虫をうずかせることが求められている気がする。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
