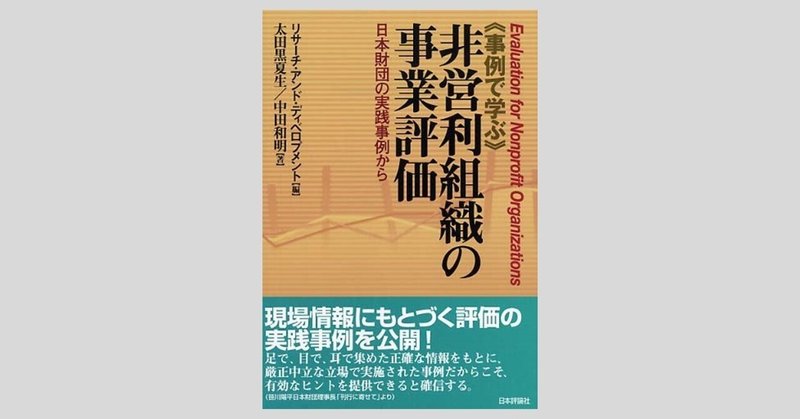
45歳・教員の「越境学習」 ~日本財団での1年間~(35)
「プロデューサー」としての助成事業(下)
私は2007年の3月末で日本財団における1年間の研修を終えた。そのため、自分が審査に関わった2007年度の事業について実際に進行管理をしたり、その成果を見届けたりすることはできなかった。
しかし、「プロデューサー」としての本当の役割は、審査が終わってからが本番なのである。事業の実施や予算の執行が円滑に行われるように助言をしたり、ときには軌道修正を図ったりする。そして、年度末に「その事業に助成をしたことにどのような価値があったのか」について評価をするところまでが仕事なのだ。
特に、最後の「事業評価」というのは曲者である。1年間、その団体の事業に寄り添い、お互いに「顔が見える」関係になると、どうしても情が移ってしまい、客観的な評価をすることが難しくなってしまうからだ。
また、自分が担当した事業について低い評価をすれば、審査や進行管理にあたった担当者自身の責任が問われることにもなりかねない。そのため、担当者と団体とが「共犯者」のような関係になり、評価が甘くなる惧れもあるのだ。
そのため日本財団では、一部の事業を抽出して監査グループによる評価を実施したり、事業評価自体を第三者であるコンサル会社に委託したりしている。
当時、この外部評価を請け負っていた「リサーチ・アンド・ディべロップメント」社は、当該事業の視察、各ステークホルダーへのインタビューやアンケート調査、成果の数値化などによって、多面的・多角的に事業を評価しようと試みていた。
そして、その成果の報告会は全職員が参加する研修というかたちで実施され、事業評価のあるべき姿について財団全体での共通理解が図られていたのだ。
同社による実践の一端については、『《事例で学ぶ》非営利組織の事業評価 日本財団の実践事例から』(日本評論社)として書籍化されている。

この本の冒頭には、日本財団の笹川陽平理事長(現・会長)による次のような言葉が載っている。
「評価を受けるということは、場合によっては自己否定につながる可能性もあります。人間は失敗もするし間違いもあります。失敗を失敗として認め、教訓として生かさなければ進歩はありません。評価を委託する側、とくに組織のトップは、あえて自己否定を受け止める勇気をもって事業評価に取り組んでいただきたいと思います。」
「刊行に寄せて」 日本財団理事長 笹川陽平
・・・「事業評価」を「学校評価」に置き換えても、そのまま通用しそうな言葉だといえるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
