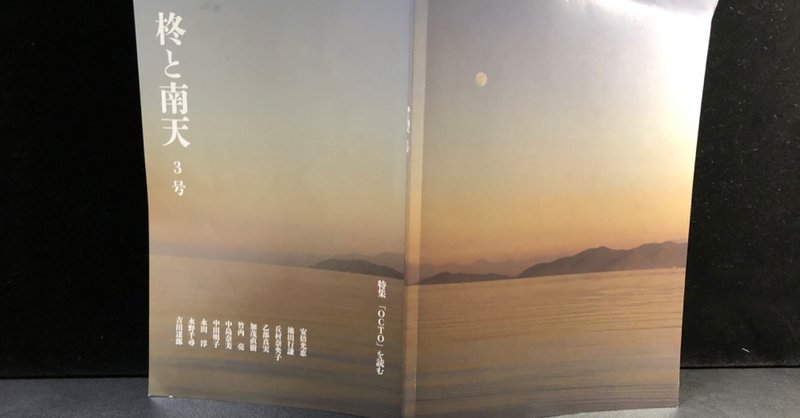
「柊と南天」一首評
1973年生まれの歌人11人による結社内同人誌「柊と南天」の3号が届きました。
同じ結社(塔)に11人も同級生がいるって、すごいことだと思うのです。まひる野には2人しかいない・・・。
しかも、1973年生まれって、第二次ベビーブーム(72年、73年、74年生まれ)の真ん中で人数が多い割には短歌をやってる人少ないよね、ひとつ集まってみませんか、という話の中から生まれて11人。永田淳さんの求心力のなせる業なのかな。
そうそう、「ひとつ集まってみませんか」という話はあったのです。でも、なんとなく実現しないままダラダラと時間が経っていったところ、「塔だけで結構いたからこちらはこちらでやります」「軌道に乗ったらいつかジョイントでも」と言いながら「柊と南天」が出てしまったので、慌てて「OCTO」を企画したのでした。
(ちなみに「OCTO」は1973年生まれの8人が73首ずつ載せた冊子です。わたしのところに在庫がたーんとありますが、日本の古本屋さんで「OCTO」、もしくは「OCTO 富田睦子」と入れて検索してもらったら古書いろどりさんのページから買えて、そちらの方が匿名性が保てると思います。)(わたしのとこに連絡もらえれば、送料こちらもちでお送りします。頒価税込み1000円です。)
なので、わたしの思い入れは一入。そして、それが片思いではない証明として(?)今回の特集は〈「OCTO」を読む〉なのです。ありがたやー。
この友情に感謝して、せめて一首評を書きたいと思います。後ろから行こうかなー。
乙部真美 「夜空」
木々の枝が切り絵のようだその昔ガス灯を点ける仕事をしたな
一連の最初の一首。「ようだ」「したな」という呟くような、ひとりごとのような言い方が生きていて、最近ダイアログとかモノローグとかナラティブとか、そういった切り口に興味が湧いているのでメモをしておきたい一首。
「ガス灯を点ける仕事」というのは不思議。よく考えればどこかの資料館のようなところや、もしくは観光用に設置されたガス灯を点ける仕事は今でもあるはずなのだけど、この歌では上の句で木の描写があって、それがガス灯と響き合って、結果、街路樹とそこに連なるガス灯を思わせてくる。
それがとても懐かしい(われわれ世代にガス灯がなつかしいはずはないのだけど)景色を思い起こさせて、街の過去と自分の過去が混ざり合って、じいんとしてくる一首だ。
永田淳 「檣に風を集めて」
「檣」は「ほばしら」。船に帆を張るための柱。この夏に刊行された『竜骨もて』の竜骨(キール)を思い出した。(ちなみに檣の歌は
この午後を降りやまぬあめ檣に風を集めて澪を曳きたし
これもいい歌。)
迫力が雨を降らせていることのわが暁の夢の破れ目
かっこいい。最近は口語ベースでさりげないところで微妙な感情の揺れを切り取る繊細というか小さい歌が多いけれど、私は自分が短歌をやっていて快感を感じるのは日常には使わない文語や、使わない用法の助詞や語順が一首のなかでバシッと決まって、その瞬間さあっと風が吹いてくるところなので、こういう作品を読むと快哉を叫びたくなる。
これこそ短歌の魅力じゃない?
「わが暁の夢の破れ目」は調べが良すぎて意味が流れるギリギリで持ち堪えていて、目を覚ます間際の崩壊する感覚が捉えられている。夢と現実がごちゃ混ぜになって、酷い雨が降っているその現実の音が夢の中のなにがしかの印象と重なってそこに畏怖するような迫力、大きな力を感じてさせる。こういう感じ、分かるなあと思うのは、やはり同じ40代後半を生きているからだろうか。なにか抗えない力ってあるんだよね。
永野千尋 「ちょっと月まで」
サッカーをドッチボールを中当てをかわして縄を垂直に跳ぶ
縄跳びを跳んでいる一連。私も小学生の頃は縄跳びをよくした。縄跳びとか、ゴム跳びとか、あの頃はよく跳ねたなあと思う。
一連は、おそらく子ども時代を思い返している歌だろう。
昼休みか、放課後か、校庭はサッカーをしているグループ、ドッチボールをしているグループ、中当てをしているグループなど賑わっている。何人かで集まって遊んでいる中、作者は黙々と一人で縄跳びをしている。「かわして」というのは空いている場所を探して、という意味と、「一緒にやろうよ」という声を断るという意味と両方があるのだろう。熱中する様子が伝わる。「垂直に跳ぶ」が、キラッと光る瞬間を捉えている。
加茂直樹 「風が鳴る」
三本の電線ゆつくり揺れてゐる小舟の底をなぞる形に
エッセイに引っ越しをしたとある。新しい部屋で窓の外を眺めているのだろう。一連、人の気配よりも風の存在感が大きい。防音が効いてもいるのだろうが、引っ越したばかりで周囲に不案内なことの心理的な不安や開放感が表れているのだろう。
電線の揺れる様子を「小舟の底をなぞる」と捉えたところが面白い。たわんで、左右に揺れているのだろう。同じような形をしていても小さな匙ではなく大きな艦でもなく、小舟。新たな生活への期待と今の不安定さがよく伝わる。
「三本の電線」は実景なのだろうけど、三本あると視覚的に面を感じることができて、ここもさりげないけれど緻密さがあって巧いなあと思った。
吉田達郎 「昭和」
ストリートヴューで見つけるスケバン刑事合流場所を 桑沢だったか
「昭和」という言葉はうまく意味を手渡すのが難しくて、第二次世界大戦があったのも東西冷戦の時代も昭和だし、高度成長期やバブル景気も昭和だ。そして私たち昭和48年生まれには昭和は子ども時代を過ごした時間だ。だから「昭和」と聞くとちょっと懐かしいような気分になる。人と人が今より密接で、人情などマンパワーが尊ばれていた時代。それはいい面も悪い面もあるけれど。
この一連では戦後すぐから「櫻の園」の映画までの移り変わりを詠んでいる。この「櫻の園」はチェーホフではなく吉田秋生だ。同年だからか、歴史的な事項よりこういう流行を抑えているところに面白みを感じて、掲出歌も面白かった。
スケバン、という言葉も過去のものになったが、斉藤由貴が、浅香唯が演じていた頃の「クラス全員が同じ番組を見ていた」頃を思い出すと懐かしい。
「桑沢」は、渋谷の桑沢デザイン研究所のことだろう。別々に知っていたものが繋がる瞬間の、腑に落ちる様子が捉えられている。
池田行謙 「夏の新宿 SHEENA RINGGO の」
鳥の声染みた材木 算盤の珠になり珠の打つ音になる
椎名林檎はわたし(たち)が20代の後半の、彼女がデビューしたての頃に多少聴いていたっきりなので「椎名林檎 夏の新宿」と検索してみたが、そのような曲はないようだった。だから「歌舞伎町の女王」のイメージで読んでいいのかな、と思う。タイトルには次の
朝焼けにあなたと染まる丸の内サディスティックな鳩の視線も
のほうが合うのだろう。ただ、椎名林檎の声を「鳥のよう」もっと嫌な言い方をすると「鶏の首を絞めたよう」だと表現することはまま聞くので、この歌も一連の中で機能している歌だと思う。
算盤は最近再びブームになっていて、「〇文や学〇に通わせるより感覚的に算数が身につくよ」と娘の教育に勧められたことがある。だから、この算盤は過去の記憶ではなく現在の光景だろう。野鳥のさえずりを聞いて育った健やかな木が材木になり、選ばれて算盤の珠になり、その音がいま都心でかちゃかちゃと鳴っている。その遠いはるかな道のり。
木が材木としてお金に変わることを「算盤をはじいて」いるとも取れるが結句「音になる」へ集約されていくから、声から音への変身と受け取りたい。
安部光恵 「君! 断罪せよ」
夕焼けが天まで高くゆらしているビルのあなたも見えていますか
素朴な感じの作風で、五七五七七の音に乗せることを楽しんでいるような一連だな、と思った。
夕焼け空をよく見ると、天頂のあたりは青空が暗くなって紺色に、地平近くになるにつれてグラデーションで赤味が増していく。この歌では地平近くの赤が天頂まで登っていくようにゆらめいて見えて、つまり見渡す視界が真っ赤なのであろう。素晴らしい夕焼けだ。
その視界にはビルが見える。自分にはビルで遮られて見えない部分も、そのビルにいる人には見えるはずだ。この素晴らしい夕焼けを、見知らぬあなたにも見ていてほしい。そんな気持ちなのだろう。
丘村奈央子 「アンダンテ」
風呂上り 扇風機には肩はないけれど摑んで礼を言いたい
一読して笑ってしまった。コミック的な表現のユーモラスな歌である。
風呂上りの熱い身体には、風が一番心地いい。扇風機があってよかったなあとの思いを、大げさな身振りで表している。
扇風機は頭部が大きく軸が細く、想像上の火星人に似ている。ガシッと肩をつかんで「ありがとう! 君がいて本当によかったよ!」と言いたいくらいだけど、肩がないね。
戯画化とオチ(ツッコミ)が同居していて、こういう表現がコミック育ち、アニメ育ちのわれわれの「笑い」なのだろう。
「肩はないけれど」の部分が一番の肝なのかな。単に戯画化するだけではない面白みが出ている。
竹内亮 『風切る音』
わたくしとルビを振るとき私の上下に入る白い隙間は
歌人協会の機関誌に著作権についての寄稿をされている作者。塔だったんだ! 詩歌で知財といえば中村稔さんだけど、デリカシーなく言えばもうほんとうにいいお年なので新しい方がいてくださるのありがたい・・・というのは置いておいて、この一首。
短歌において「余白」はとても重要なもので、今までも数多くの「余白」の歌が詠まれてきたけれど、これには唸った。
この余白は、意識的にせよ無意識にせよ必要で取られた余白ではなくて、「私」という一文字に「わたくし」という四文字のルビを振るときに、入りきらなくて少し空いてしまう文字間。余白は必要なものだけど、これは消したくても生まれてしまう隙間なのだ。
しかも、「私」の。すごい。
結句の「は」留めは評価の別れるところかもしれない。
「白い隙間は(一体何だろう)」という逡巡が込められているのだろうが、たとえば「真白き隙間」とポンと「隙間」を投げ出してみるとか、色々やり方はあるだろう。でも、その中で作者がこの表現を選んだのだから、その逡巡に歌の中心があるのかもしれない。
ともあれ、これから文字間の隙間をみるたびに思い出す一首になることは間違いない。
中島奈美 「欲張りの生命力」
はじめての息入りゆき音になり分娩室の声ひとつ増ゆ
作者は助産師さんということで、職場詠であるこの歌。生まれたみどりごが産声を上げる様子を描いてあざやかだ。
「息入りゆき」「音になり」がクールで痺れる。はじめは「声」ではないのだ。張り巡らされ研ぎ澄まされたプロの神経が見える。
それは一瞬で過ぎ去り、次の瞬間にはもう「声」になる。この永遠のような一瞬。せわしなく動きまわり短く指示を出し合う医師や看護師、助産師。ミッションコンプリートな充足感。
何度もお産をしている人でもきっと、自分が出産するときにはこんなに空間を把握しきれないだろう。出産をするのは母体だけど、こうやって冷静に見守ってくれる人がいてこそ安心して出産できるのだ。
「増ゆ」の結句がまた、この世を寿いでいるように感じさせる。
中田明子 「月と水母」
くらき海ほたる烏賊あふれ口数のすくなき街と遠くつりあう
言葉の選択と、接続の美しさが際立つ一連。
一読するときには言葉のつらなりの美しさにうっとりし、その後じわじわと描いている景が現れてくる。二度読んでもらえるかが勝負の分かれ目かもしれない。
韻律の特徴的なのは「ほたる烏賊あふれ」の8音で、8音というのは字余りだと気づかないくらいの歌も多いのだがここではかなり重く重要なアクセントになっている。韻律の上で一か所こうして引っかかりがあると(通常は四句が多いが)歌の姿がキリっとする。ほかの部分がきちっとはまっていることも重要だ。
景としてうかぶのは、まず夜の海。そして群れを成す生き物。はじめは「ほたる」がひらがなだから「烏賊」に目が行く。そして、街の灯りとそれに対応するホタルイカの光。そこでホタルイカの幻想的な様子が浮かんでくる。
「口数のすくなき街」は街の灯りの少なさを言っているのだろう。真夜中の、寝静まった様子。今年ホタルイカはは不漁だったと聞く。宵の口ならば街の灯のほうが明らかに多いのだろうが、今は「つりあ」っている。
もちろん「口数」には静かさもこもるだろうし、ふっと遠くに彼岸と此岸という感じもする。美しい一首だ。
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
「柊と南天」
