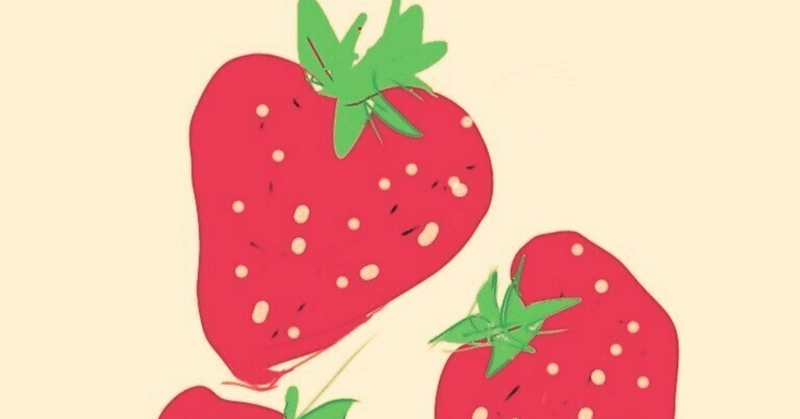
こちらは割と平和にやっておりますので
創作大賞の中間通った作品の元の作品をnoteでも公開をしておきます!
こちらの読み切り版の二人も個人的にはお気に入りです。
お楽しみいただければ幸いです。
第一話 安売りの山菜で
◇ 久留木舞
勝鬨橋を自転車で渡る。
築地市場から勝どきを繋ぐこの橋からの夜景は左右で色が異なる。上流側は低く平たい市場の光が等間隔に川に落ち、遠くに少し先の曲がった東京タワーが見える。どことなく工場地帯を彷彿とさせる夜景だ。一方で下流側はライトアップされた佃大橋や中央大橋、高くそびえ立つオフィスビル郡とわずかに東京スカイツリーを望める。眠ることのない都会らしい夜景はマンハッタンを彷彿とさせる。どちらにしても都内で有数の夜景スポット(しかも無料!)と言えるだろう。
しかしわざわざここに夜景を見に来る人は少ないしお勧めもしない。
この勝鬨橋は元々跳開橋であったため少し風が吹くだけでガタガタと揺れる。歩道もそれほど広くはないから長居はしにくい。夏は暑いし冬は寒い。禁止されているのにここから隅田川の花火大会を見ようとする人が毎年出るほどに素晴らしい立地ではあるけれど、正直なことを言えばテレビ中継でドローン撮影映像を観た方が見応えがある。多分ここからの夜景は写真で見るのが一番綺麗なのだ。
そんな身も蓋も敬意もないことを考えながら橋をのぼっていたら、お仕置きのように強い風が吹いた。暖かい春の強風。自転車も地面も大きく揺れる。ヤバイと思ったときには前輪が欄干に激突した。金属同士がぶつかって派手な音を立てたが、それに反応している余裕もなく、風に押され後輪も欄干に引き寄せられる。
「……」
両手でブレーキを握りしめ風がおさまるのを待つ。目も開けられない強い風だ。川に落とそうとでも言うのだろうか、ゴウゴウとうるさく、ガチャガチャと音をたてる橋は怖い。でも黙って耐える。
風がおさまると、スカーフはほどけ髪はばさばさになっていた。本当にひどい風だった。少し先をのぼっていた会社帰りのサラリーマンたちは欄干につかまって「ヤバイ風だったな」「ヅラ飛びそうだわ」などと楽しそうに話している。ひとりじゃないっていいなと羨ましがりつつ、私は自転車の前かごにスカーフをいれた。
一度止まってからのぼるのはしんどい。重たいペダルを立ちこぎで回し、サラリーマンたちを抜き、平坦なところにたどり着く頃には汗をかいていた。早く帰りたい。サドルに腰を下ろしゆるゆるとペダルを回す。夜景なんてやっぱり写真でいい。よそ見をせずに、ブレーキもかけずに、橋をくだった。
この勝どきに暮らしはじめてもう五年経つ。
住みやすい街だけどこんなに長く住むことになるとは思っていなかった。というよりも、ここで二十代を終えることになるとは思っていなかった。あっという間の五年で、あっという間のアラサーだ。
十八から雀荘に通いだし、毎晩やりこんでいる内に大会で優勝するほどになり、気が付いたらプロの雀士になっていた。覚悟を決めて二十四で家を出て以降、一度も家賃が払えなくなったこともないし、今じゃ麻雀映画や麻雀雑誌、誰かの麻雀動画や誰かの麻雀ブログなんかにも呼んでもらえるようになった。普通のOLよりも稼げている。ありがたいことだ。それでもさすがに死ぬまで今のライフスタイルを維持するつもりはない。
しかしいつ決断をするべきなのだろう。
最近はこのままずるずると生きていくような気もしてきている。いっそマンションを買ってしまおうかなんて悩み出しているあたり最早手遅れなのかもしれない。
「……まあいいか、生きてればそれだけで……」
アラサーとして危うい独り言を呟きながらマンションの駐輪場に自転車を止める。買ってきた食材の入ったエコバックを持つと肩が痛くなった。
「重いなぁ……」
お酒を買うのはやめておけばよかった。大人しく松下くんが車を出してくれる来週末を待つべきだった。しかし後悔は先に立たない。
重たい荷物を抱えてマンションに入り、郵便受けを確認する。チラシをゴミ箱に捨てて水道代の通知証をコートのポケットにいれる。
エレベーターを待ちながらスマホを見ると着信が二件と留守電が一件入っていた。
「あちゃー……」
松下くんからだった。
下りてきたエレベーターに乗り込み八階を押してから、留守電を再生する。
『久留木さん、もし買い物をしていなかったらでいいんですが……鰹節が残っていないので買っておいてくださると助かります』
「あっ鰹……そうだった、忘れてたー……やらかしたー……」
『でも忘れてても大丈夫ですよ。まだ2パックはありますし、……もし間に合えばなので。じゃあ夕飯には帰ります』
いつもの通り私の行動(買い物リストを忘れること、鰹節を忘れていること、買い物帰りに留守電を聞くこと、エトセトラ)を見越した留守電だった。松下くんは私の行動を全部読みきっている。いっそ雀士になればいいのに、なんて思いつつ部屋に向かう。
八〇一号室。
煩悩の数の部屋には鍵が三個もついている。松下くんは神経質な人なのだ。鍵をひとつひとつ開けて家に入る。
「ただいまー」
もちろん返事はない。
鍵を三個かけてから電気をつけた。
靴を脱いでシューズボックスにしまい、鍵と腕時計と鞄をシューズボックスの上に置く。トレンチコートとスカーフをコート掛けにかける。脱衣場で服をすべて脱ぎ、洗濯機を回す。シャワーで煙草の臭いを洗い落としてから部屋着に着替える。そしてコンタクトレンズをとり眼鏡をかけてエプロンをつければ、帰宅後のルーティーンは完了だ。
「重いー酒瓶が重いー……」
買ってきたブランデーは食器棚の一番下にしまい、あとの食材を作業台の上に並べた。
「……んー、じゃあやるかあ……」
今日の夕飯は天ぷらだ。
松下くんが帰ってくるまでに付け合わせを作り、天ぷらは準備だけしておけばいいだろう。
「下ごしらえ、下ごしらえ」
安く売られていたふきのとうを水洗いしてから、黒ずんだ根元に包丁をいれて皮を剥いていく。
「あー、春の匂いー」
水を張ったボールに剥いたものを入れながら、その個数を数える。
「二十八個も入って千円とかやばいな……たたき売りもいいところでしょうよ。ありがたい限りだけど儲けるつもりはあるのだろうか……」
ふきのとうと同様に安売りされていた他の山菜(うるい、たらの芽)も下処理をして水にさらしておく。こうしておけば松下くんが帰る頃にはエグミを抜けているだろう。
「筍は茹でて一晩放置して、と……明日は筍ご飯かな……」
他のてんぷらの具材として豚コマや茄子や竹輪や大葉も用意はしておく。私だけならこんなに要らないが、松下くんにはこのぐらい必要だろう。
「あとは新玉もあるし……」
松下くんが好きなかきあげも作ってあげよう。
新玉ねぎとにんじんを細切りに、絹さやを斜め切りにする。天ぷら粉を水で溶かし具材をまぜると赤が足りない気がしてきたので、桜えびも足しておく。
「まだ六時半か……」
新じゃがを水洗いし、器にいれてふわっとラップをかけて、レンジに入れる。五分ぐらいでいいかと動かし出してから1000wだったことに気がつき慌てて止める。600wでやり直し。
「さてと、次はふきのとうさんで……」
ふきのとうを二十個、水から取り出してみじん切りにする。火にかけたフライパンが温まってきたら胡麻油、すりおろし生姜を投入。それだけでもよい匂いなのだが、そこにみじん切りにしたふきのとうをいれるとたまらない匂いになる。
「味噌とー……砂糖とみりんでいいかなあ」
木ベラで炒めて、しんなりしてきたところで適当に調味料を加える。あとは弱火にして水気がなくなるまで炒めるだけ。蕗味噌の完成だ。
半分はタッパーにつめて、半分は皿に出す。(もちろん途中でレンジから新じゃがいもを取り出してバターをのせるのは忘れない。)
「さーて、……さてさて、一杯飲んじゃおう」
冷凍庫からキンキンに冷えたグラスとブランデーとかちわれ氷を取り出した。グラスに氷をいれてブランデーを注ぎ、冷蔵庫から取り出した炭酸水を静かに加える。
「んふふふ」
じゃがバターとまだあたたかい蕗味噌で一杯楽しみながら、松下くんを待つことにした。
「……東京都中央区で身元不明の……」
バックミュージックとしてテレビのニュース番組を流しながら、最近の楽しみであるラブコメ小説を読む。苦労人気質の竜神とおてんばな巫女が繰り広げる異世界ファンタジーだ。最初は笑いながら読んでいたのだが、三巻あたりから不穏な気配が漂い始め、いつの間にか戦争が始まっていた。今は七巻なのだが、正直竜神が水神と争いだしたあたりからついていけていない。しかしここまできたらふたりがハッピーになるのは見届けたいのだ。親戚のおばさんのような気持ちで頁をめくる。
「……明日の天気は……」
天気予報が始まったときに玄関の向こうからその足音が聞こえた。テレビを消すと鍵が開く音。
「ただいま、久留木さん」
松下くんの声。
「おかえりなさーい、今日は天ぷらだよー」
玄関の方に声をかけてから立ち上がり、天ぷらを揚げるためにキッチンに向かう。
山菜から揚げ始め、かき揚げを作り出したときに部屋着に着替えた松下くんがリビングにやってきた。この家ではどんなときも好青年な松下くんがにこりと笑う。
「ただいま」
「おかえり」
その笑顔にもう一度そう言った。
◆ 松下 白翔
「……後楽園、後楽園です……」
後楽園駅で南北線から都営大江戸線に乗り換える。
人の流れに沿って歩きながら研究を反芻する。教授とも話したが、もう新薬候補として発表できる段階に来ている。おかげですべきことは山積みだ。やりたいことは数えきれないほどあり、時間も体も足りない。
「……春日、春日です。お足元に……」
電車に乗り込みスマホを見ると、ニュース速報が入っていた。先週自殺させた女性のものだ。ニュースを読みながら『なんだ首吊りか、あんな派手な格好をしているのに地味な死に方するんだな』とがっかりする。
十八の頃から趣味は他人を自殺させることだ。何故そんなことをするのかと聞かれたら、楽しいからとしか答えようがない。
人間という生き物は無駄が多い。どれだけ時と費用をかけて能力を伸ばしても一度死んだら二度と起き上がらないあたり、本当に無駄だ。種としての成長が全くない。無駄な投資のかたまりだ。特にその無駄さを感じられるのが、自殺だ。無駄の極み。それを選択させるのが楽しくて、よくない趣味とは分かっているがやめられない。
それどころか趣味も高じればクオリティーが上がるようで、いつからか視線ひとつでできるようになってしまった。よくない。誠によくない。しかし楽しい。他の趣味ができない限りは続けてしまうだろう。
「……まもなく勝どき、勝ちどき……」
時間を確認すると七時過ぎ。予定通りの夕飯にちょうどいい時間だ。今日は久留木さんが夕飯を作ってくれている。なにを作ってくれるのだろう。楽しみで、つい、頬が緩む。
「……勝ちどき、勝ちどきです……」
電車の扉が開く。足早に家に向かった。
◆
「ただいま、久留木さん」
「おかえりなさーい、今日は天ぷらだよー」
久留木さん。
俺の彼女。
かわいい、かわいい、俺の彼女。
彼女とこの築八年2LDKの部屋に暮らしはじめて五年が経つ。そろそろ彼女を専業主婦にしたいのだが、彼女はまだ楽しそうに仕事をしている。だから今はその時ではないのだろう。どうせ死ぬまで側にいるのだ。焦る必要もない。
「……さてと、」
すべての鍵をかけてから、両手とドアノブと電気のスイッチ、鍵に至るまでアルコールで除菌した。彼女の鍵の隣に自分の鍵を置き、彼女の鞄の隣に自分の鞄を置く。
まず、彼女の鞄からハンカチと、ビニール袋や紙の切れ端といったゴミを取り出す。丸められたレシートを開く。……今日はサンドウィッチを食べたらしい……。ゴミはゴミ箱に捨てた。
彼女のコートをハンガー型の脱臭機にかけてコードレスアイロンでシワを伸ばす。自分のコートを脱ぎ、同じように手入れをする。
「……」
彼女のコートのポケットに入っていた名刺を記憶する。……また変な男に好かれたのだろうか。まったく仕方がなくて、かわいい彼女だ……。
彼女のSNSアカウントはすべて俺が操作できるし、彼女のまわりにいるくだらない人間たちの氏名、年齢、勤務先、家族構成、実家、預金口座、パスワード、SNSアカウント、なにもかもすべて把握している。だから彼女が傷つけられたとしても、……俺が必ず殺してあげられる……。
彼女のコートに名刺を戻してから脱衣所に向かう。
「……ふふ、ちゃんと洗濯していていい子だなあ……」
シャワーを浴びてから、浴室の上から下、隅から隅まで水滴をぬぐう。脱水まで終わった彼女の服を風呂場に干して浴室乾燥を動かす。自分の服を洗濯機に入れて回す。彼女と揃いの部屋着に着替えて、綺麗なハンカチを彼女の鞄に入れたら、帰宅後のルーティーンは完了だ。
リビングに向かう。
対面のキッチンのよいところはすぐにかわいい彼女の顔が見られるところ。
「ただいま」
「おかえり」
山菜の匂いがした。
◆
「山菜が安売りしてたんだー、筍も茹でといたから明日は筍ご飯だよ」
「それは楽しみですね」
「鰹節は忘れちゃったー」
「かなと思って帰りに買っておきましたよ」
「本当? ありがとう、松下くん」
「いえいえ」
揚げ物をしている彼女の横に立ち、買ってきた竹の子の水煮と鰹節のパックを取り出す。
「あ、水煮!」
「美味しそうでつい……生の筍があるならいらなかったですね」
「ううん、うれしいよー。炒め物作っちゃうね」
少し酔っているのだろう。彼女はいつもよりもゆっくりとした話し方をしている。それがまた愛らしい。
「俺が作りますよ?」
「てんぷら冷えちゃうよー」
「それなら天ぷら食べ終えてもまだお腹空いてたらツマミに作りますね」
「松下くん飲まないのに?」
「飲んでるあなたが好きなんです」
「また変なことを言うー」
水煮は冷蔵庫にしまい、鰹節は棚にしまった。彼女が大皿にてんぷらをのせていくのを見ながら、天つゆと大根おろしを作る。
「あ、天つゆ忘れてた。ありがとう」
「塩で食べるつもりでした?」
「楽だからねー」
「飲みすぎはダメですよ」
「嫌い?」
「まさか」
ごはんを茶碗に盛り、冷たい麦茶をグラスにいれて食卓に並べる。
「はい、できあがりー」
揚げたての山菜や野菜のてんぷらに、蕗味噌、作り置きの菜の花の漬け物とカボチャの煮物。新ジャガイモのじゃがバター。
「ごめんね、新ジャガで先に飲んじゃってたの」
「かわいいね、久留木さん」
「なにそれ! ほら、早く食べよう」
俺たちはいつも一緒に手を合わせる。
「「いただきます」」
声を合わせて、顔を合わせて、笑い合う。それから思い思いのものに箸を伸ばす。今日は俺はふきのとうのてんぷら、彼女は茄子のてんぷらだ。
揚げたてのてんぷらのさくっとした衣が歯に気持ちがよい。噛み締めるとじわりとほろ苦い春の味がこぼれ出す。熱い、と息を吐けば、鼻にも春の匂いが回る。
「あつつ……茄子、あつっ!」
ほふほふと久留木さんが熱そうに息をする。俺もそれを真似て、はふはふと息を吐く。そんな俺を見て彼女が楽しそうに笑う。それが可愛くて俺も笑う。
「美味しいですね、ふきのとう」
「お酒合いそうでしょ?」
「今日は飲みませんよ」
「ぬー」
「金曜に飲みますから」
「はーい。おばさんは学生さんに無理強いはしませんよ」
「また変な言い方して。そんなに年は変わらないでしょう……」
「だってー……」
今度は俺が茄子に箸を伸ばし、彼女はふきのとうを取る。塩で食べてみたり、つゆで食べてみたりしながら、互いにどうでもいい話をしたり、聞いたりする。机の下で足先の攻防を繰り広げたり、思わせ振りに視線を絡めたりしながら、春を食べる。彼女はフレンチハイボールをゆっくりと飲み、俺は麦茶をがぶがぶと飲む。
「ふふ」
「ん? どうしたの、松下くん」
「いえ……贅沢だなあと思って……」
「違うよ? 安かったんだよ、山菜。いつもの値段ならこんなにふきのとう買えないからね? 蕗味噌なんて無理なんだからね? 無駄遣いしてないんだからね?」
慌てたようにそんなこと言う彼女が可愛くて仕方がない。
彼女が毎月払ってくれている家賃は全部彼女名義で貯金している。ここは俺が買っている部屋だと言ったとき、彼女はどんな顔をするのだろう。まずきっと驚くだろう、それから怒るだろうか、笑うだろうか、怯えるだろうか。彼女の終の棲家は俺の隣と決まっていると言ったら泣くのだろうか。
ああ、楽しみだ。
「かわいい、久留木さん」
「もうちゃんと聞いてよ! お金は大事なんだよ?」
「分かってますよ。ただ俺は、あなたが手間のかかる料理を作ってくれて、そうして一緒に食べてくれる時間が贅沢だと言っただけです」
「……松下くんっておじいちゃんみたい……」
「嫌いですか?」
「誰も彼も松下くんみたいにすぐ好きとか愛してるとか言えないからね!」
「あ。ツンデレだ?」
「違うよ! もう!」
彼女が蕗味噌をぺろと嘗めてハイボールを飲む。
「それ合います?」
「試してみる?」
「だから飲みませんってば……」
「なーんでよー!」
「まだ水曜だからです」
彼女が目の前でわざとらしく拗ねる。それが可愛くて仕方がない。やっぱり早く閉じ込めてしまいたいと思いながら、彼女が作ってくれた料理を嚥下した。
第二話 貰いもののイチゴで
◇ 久留木 舞
「舞ちゃん、こっちでもやってよ」
「はいはーい、あとでねー」
常連に適当な返事をしてからリーチをかける。
「うわ、リーチ?」
「鳴いてもいいよー?」
「親リーチ相手に鳴きたくねえなあ……」
「そうー?」
今日は朝から体調はよくないが麻雀の調子はいい。お昼に松下くん特製の筍ご飯のおにぎりを食べていなかったら倒れてしまっていたかもしれないぐらいの体調の悪さだが、運は来てくれている。
「んー、と……」
取ったときに『勝った』と分かった。
「ごめんなさい。ツモです。リーチ一発ツモピンフ自風ドラドラ……あはっ、裏ドラついちゃいましたー」
「あはっじゃないよ、舞ちゃん!」
「7800オールでーす」
「おーい、まじかよ積み込みかよ!」
「自動卓でどうやって積み込むのよー? すーちゃんが箱飛びね。はい、おしまーい」
安い掛け金を回収して「また遊んでねー」と手を振って次の卓に座る。
「久しぶりじゃん、ミッチー! どこに浮気してたのよー?」
「してないよー舞ちゃんと会わなかっただけだよー。あ、紹介するな。こっちは俺の友達の今野だ」
「あ、よろしくお願いしますー久留木舞ですー」
「こいつイチゴ農家が親戚らしくてな、今日お土産持ってきたんだよな?」
「えー、やだーうれしいー!」
渡されたイチゴは木箱入りにできなかった廃棄ものらしい。でも十分に大粒で、つやつやと輝いていた。珍しく本当に嬉しいお土産だ。
「今野さんはどんなお仕事されてるんですかー?」
この仕事は水商売とアイドル業の間にある技術職だ。焼酎の水割りを作るのが好きな女はホステスに向いてるし、役を作るのが好きな女は雀士に向いている。そのぐらいの違いでしかない。(だから私は頭が動かなくなったら熟女バーに行こうと思っている。)
「舞ちゃん、今日は調子いいの?」
「うん、お腹一杯だからねー」
「またあれか? 彼氏さんのおにぎり?」
「そうなのー! やっぱり愛は強い!」
「舞ちゃんの彼氏一回連れてきなよー」
「絶対いやーこんな汚い親父に見せられないからー」
「ひっでえな舞ちゃん! さすが氷の女王!」
私の麻雀は愛想がない計算ずくの冷たい麻雀と言われている。それは仕方がない。私の思う麻雀の楽しさは勝負の楽しさだ。忖度なんてしない。それでここまでやってきた。
「じゃあよろしくお願いしますね」
「今日は勝つ!」
「んふふ、かかってきてー?」
天職だと思っている。
そのぐらいには私はこのゲームが好きなのだ。
◇
「おつかれさまでしたー」
「おつかれー、あ。この間のやつはどうするの? 出るの?」
この間のやつというのは、麻雀映画の仕事だ。役者として呼ばれるのだが、やることは胸の谷間を見せて「リーチ」と千点棒を投げるだけ。良くも悪くもそれだけだから、私が呼ばれるのだ。
「出ますー。スケジュールでたらシフト調整させてくださいー」
「了解ー売れっ子女優じゃん!」
「あははー」
オーナーに雑な返事をして雀荘を後にした。
フェミニズムはこの業界では損にしかならない。分かっていても疲れる日はある。いっそ女性専用の雀荘に移るか……などと血迷いそうになる。こんな日は早く帰るに限ると、タクシーを呼び止める。
「勝ちどき駅まで」
「駅でいいですか?」
「はい」
家の前まで送ってもらってもいいのだけど、なんとなくいつも駅までにしてもらっている。疑っているわけでも怖がっているわけでもなく、なんとなく、だ。
私の人生の大半がなんとなくなのかもしれない。窓に頭をつけて街を眺める。信号待ちしているサラリーマンとOLたち。似たようなスーツ、似たような靴、似たような髪型、コピー・アンド・ペーストされた数えきれない人々。どうして私はあの無数の型抜きクッキーに混じれなかったのだろう。
なりたかったわけではない。なのに今となって星みたいに遠いそれが、星ぐらいに輝いて見える。
「……」
雀荘からの帰り道はこんな風に『違う仕事を考えないとな』と考えることが多い。
けれど新しいことを覚えたいわけではない。ただ遊んで生きていけたらいいのに、そうもいかない人間社会。蝶よ花よじゃヤニ臭さに死んでしまう。でも私の女流雀士としての賞味期限が近づいてきている。いや、もう……私の賞味期限は過ぎているんじゃないだろうか……。
鞄の中からポーチを取り出し、ポーチの中から手鏡を取り出す。
目尻のにじんだアイシャドウを人差し指でぬぐい『五十で死にたいなあ』とぼんやり思う。それでもあと二十年もあることに吐きそうだ。
「もう着きますよ」
「あ、……勝鬨橋渡ったところで大丈夫です」
「分かりました」
煙草臭い。早くシャワーを浴びたかった。
◇
「おかえりなさい、久留木さん」
「ただいま、松下くん」
鍵を開けようとしたら中から扉が開き、松下くんが迎えてくれた。嬉しくて仕方ないけれど抱きつくことはできない。彼は煙草が苦手なのだ。
「シャワー浴びてくる! あ、これお土産だから冷蔵庫入れておいて!」
「はい、今日はお風呂沸かしてますからゆっくり入ってきてください」
「わーん、ありがとうー!」
私は早足で脱衣所に飛び込み、服を脱ぎ捨てた。
まず彼が好む匂いのボディソープとシャンプーとリンスとヘアトリートメントを使って、染み付いたおじさん臭さを洗い流した。
浴槽に入り、ゆっくりと体を伸ばす。足の指からストレッチを行っていく。体は女性らしいラインを保ってはいるけれど、痩せた膝あたりに年を感じる。
「ぬー」
アラウンド・サーティー。
目を逸らすことはできないほどはっきりと老いを感じる。肉が落ちていることにうんざりする日が来るとは思わなかった。やみくもに痩せても骨ばかりが目立つなんて知りたくなかった。
「……ぬー……」
嫌われたくないなあと思いながら風呂から上がる。
細くなってきた髪をドライヤーで乾かし、乾いた肌に化粧水とクリームで蓋をする。こんなことをしても若返るわけではないけれど気休めにはなる。
松下くんとお揃いのふわふわした部屋着は五年前は似合っていたけれど、今は厳しくなってきている。そろそろ違うデザインのものを選ばないと駄目だろう。
「……嫌われたくないなあ……」
私より三歳も年下の松下くん。
彼は格好よくて頭がいい優秀な大学院生だ。すでに私よりも稼いでいる学生実業家でもある。学校を卒業したら立派な社長さんになって、今よりもっと素敵な人になるだろう。だから捨てられる未来しかないことは分かっている。そのぐらい読めないと雀士なんてやってられない。それでも別れられない。そうじゃなきゃ学生と同棲なんてしてられない。
「……」
鏡に向かって笑ってみる。いくつか試してみると歯を見せて笑うのが一番若く見えた。(一番痛々しくも見えた。)
コンタクトレンズを外して眼鏡をかける。それからリビングの扉を開く。
「ただいま」
「おかえり」
もう一度その挨拶をして、キッチンに立つ彼のもとへ向かう。彼はにこにこと笑って私を迎えてくれる。その背中に抱きついてその肩に鼻を寄せても嫌がる様子はなく、むしろ嬉しそうに私の腕をつかんで自分の腰に導いてくれる。
優しい私の年下の恋人。
「夕飯食べられてないでしょう?」
「うん……お腹すいた。こんな遅いのにご飯作ってくれたの?」
「はい。待ってました」
「まだ食べてないの?」
「はい。久留木さんみたいにちゃんとしたご飯は作れないんですけど……」
「お味噌汁、すごくいい匂いがする。わざわざ出汁とってくれたの? ありがとう!」
「……味見してくれますか?」
「うん。一口ちょうだい?」
松下くんのつくるものは私のものよりも手が込んでいる。なのに彼は謙虚な態度で私に接してくれる。今日はそういうひとつひとつのことがありがたくて泣きたくなる。多分、生理前なのだ。
「はい、どうぞ」
彼が差し出した小皿に口をつける。澄みきった出汁の味がする。
「美味しい」
「よかった」
「仕上げに糸三つ葉入れるといいかも」
「いいですね、そうしましょう」
「……」
余計なことを言ってしまった。
美味しいありがとう嬉しい、だけ言えばいいのにどうしてこの口は……などと考えながら彼の腰に腕を回す。彼は嫌がる態度も見せずに「今日は大変だったんですか? 土曜日ですもんね。混んでましたか?」なんて言ってくれる。
「……松下くん」
「はい」
「お客様からイチゴもらったの、たくさん……」
「はい、さっき冷蔵庫に入れておきましたよ」
「それでケーキつくったら食べてくれる?」
「もちろんです。嬉しいです」
「……美味しくなくても?」
「久留木さんが作るものが美味しくなかったことはありませんよ」
「失敗するかも」
「それは楽しみです」
嘘ついてるのかなと松下くんの顔をのぞきこむと、キスされた。
「なんでキスしたの?」
「かわいいなと思って」
「なにそれ……」
本当に失敗しても彼はこの笑顔を見せてくれるのだろう。今のところは、きっと……。
「じゃあケーキ作ろうかな」
彼との未来は見えない。まだ見たくない。
「どんなケーキにするんですか?」
「頑張らないケーキ」
「頑張らないケーキ?」
「うん、冷やして固めるムースケーキにする」
「楽しみです」
松下くんの笑顔にキスをすると、彼は耳を赤くして「夕飯にしましょう」と私の頭を撫でてくれた。
◇
キノコの炊き込みご飯にナメコのお味噌汁、焼き鮭とホッケの開きに焼き海苔、オクラとミニトマトのもずく合わせ、キュウリの浅漬け。
松下くんは器も選んでくれるし盛り付けもこだわってくれるから、料亭のようだ。疲れた日にこんな夕飯を用意されたらせっかく練習した笑顔なんて出せない。頬の筋肉がふにゃふにゃになってしまう。こんな時間にこんなに食べたら太ってしまうけど、でも、食べてしまう。
「「いただきます」」
お味噌汁を一口飲む。
「あー、美味しいー……」
「よかった。久留木さんナメコ好きでしょう?」
「好き……松下くんが好き……」
「えー? ナメコで惚れ直してもらえるんですか?」
「うん……」
散らされた三つ葉がまた美味しい。炊きたてのご飯を頬張ると「んー」と呻いてしまった。美味しすぎる。
「どうしてこんなに完璧なのー?」
「俺ですか?」
「炊き込みご飯です!」
「なんだ、そっちか。残念」
「松下くんも完璧だけど!」
「あはは」
松下くんがガラスのチロリに冷酒をいれてきてくれた。
「最高!」
しかしうぐいす盃をふたつ持ってきておきながら、松下くんは盃を私に渡してくれなかった。見上げると、にこりと彼が笑う。
「このあとケーキ作るならやめておきますか?」
「もー、明日にするもん!」
「あはは、分かりました」
「もう明日休んじゃおうかなあ」
「そしたらデートしましょうか」
「やめてー惑わさないでー」
揃いのうぐいす盃に冷酒が注がれる。
「どこのだっけ?」
「新潟の春酒です」
「甘いかなあ。楽しみ」
「米どころですからね」
顔を合わせて、盃を持つ。ひゅーと音を立てながら、同時に酒を飲む。
「「あー……うまい……」」
ため息までハモってしまった。
◆ 松下 白翔
彼女の土日休みは月に一度あるかないかで、俺たちはその日を毎月の楽しみにしている。今月の場合は来週の土曜日だ。つまり今日は俺ひとりだ。
俺のひとりの土曜日は家中の掃除から始まる。寝室、風呂、キッチン、トイレ、玄関、目についたところから掃除をする。この作業をしながら昨日の実験を反芻する。どこが最適解か、どこが実現化できるか、どこが……そんなことを考えている内に掃除は終わる。
それが終わったら常備菜作りだ。
この同棲がうまくいっている理由はこの作り置きにある。これがあるからどんなに忙しくてもまともなものが食べられ、健康を維持できる。だから苛ついて喧嘩することもない。
「……苛つかせて仕事辞めさせてもいいか……」
少し考えたがリスクが多すぎる。おとなしく残っていた食材を冷蔵庫から出し、片端から料理に変えていくことにした。
豚肉ブロックと大根と卵を角煮に変え、山菜とにんじんをピクルスときんぴらに変え、小松菜と豆苗をナムルに変えておく。このぐらいあればいいだろう。
洗い物をしてから、彼女に渡された名刺の男を調べる。……おかしい、そんな会社はない……。……探偵か、警官か……わざわざ名刺を渡してきているのが気になる。……しかしこれ以上調べるならこの端末は使えない。あとは……別名義を経由してやることにしよう……。
時間を見るとまだ昼過ぎだ。
「……暇だな」
趣味に出掛けてもよかったが、先に仕事をすることにした。
俺の研究は技術を作ることで、仕事はそれを実用にすることだ。それらは全く別の思考を必要とする。研究者が貧乏なのは金を得るには別の思考が必要なことを分かっていないからだ。それはそのまま日本が貧乏な理由でもある。
まあ、……どうでもいいことだ。
「チッ……暇だな……」
ほんの二時間でためていた仕事が終わってしまった。仕方がない。俺は趣味のために出掛けることにした。
◆
繁華街のベンチに腰掛け、流れを読む。俺にとって、東京は畑だ。刈り取られるのを並んで待っている生首たち。俺が取ってやらなきゃそのまま腐り落ちるだけ。みんな死にたいのだ。だから趣味もはかどる。
目を合わせると、花こうに切れ目が入る。あとは時間が立てば実は落ちるのだが、たまにその場で落ちるものもある。それが、……楽しい。
目を合わせた男が道路に駆け出した。トラックがそれを轢く。人間の中身は色とりどりだ。心と同じぐらいには色がある。
「ふ、……」
気が済んだ。
踵を返し、家に帰ることにした。
◆
「イチゴのムースケーキをつくりまーす」
「久留木さん、酔っているのに大丈夫ですか?」
「うん!」
彼女がふにゃふにゃと笑う。かわいい。
「んと、まずクッキー生地を作るためにーバターをレンジでとかしてークッキーを潰しますー」
俺が皿を洗う隣で彼女はケーキを作り始めた。
彼女はバターをレンジに入れてから、袋に市販のクッキーを入れ綿棒で叩きだした。自分の手を打たないか心配だったが、酔っていてもさすがの料理好きだ、そんな失敗はせずにクッキーは粉々になった。そこに溶かしたバターを加えて揉みこんでいく。
「……ケーキの型ってあったけ?」
「しばらく見てませんね。多分土鍋の奥にあるかと思いますよ」
俺は手を拭いて洗い物を中断し、食器棚の奥を探す。やはり思ったところに丸いケーキ型があった。洗って水気をとってから彼女に差し出す。
「はい、どうぞ」
「ありがとうー」
彼女が笑う。笑顔がかわいいからキスをすると「料理中にちょっかいださないの」と叱られた。さっき俺が料理しているときは彼女からちょっかい出された気がするのだが、……まあいいだろう。
彼女はクッキングシートをケーキ型に敷き、クッキー生地を詰め込んだ。
「焼くんですか?」
「冷やしますー」
「冷やすんですか」
「うん、固まるまで放置」
彼女はケーキ型を冷蔵庫にしまい、それから洗い物をしている俺の背中に抱きついてきた。
「久留木さん、そんな可愛いことすると襲いますよ」
「作り置きたくさんあった……びっくりした……」
「惚れ直しましたか?」
「うん……ありがとうね」
「よかった。頑張った甲斐がありました」
彼女が俺の背中にぴたりと張り付いている。
「どうしたの、久留木さん」
久留木さんは「ぬー」と不満そうに唸った。最後の皿を水切りにのせて、手を拭く。首を捻って彼女を見る。
「久留木さん一回離れて」
「ぬー」
「ほら、来てください」
振り向いて正面から彼女を抱き直すと、彼女は俺の胸に顎をつけて俺を見上げた。そして眉を下げて困ったように笑う。
「松下くん格好いいなあ」
「顔ですか?」
「うん、顔も格好いい」
「冗談だったんですけど……」
今日の久留木さんはどこか疲れた顔をしている。
「仕事、なにかありましたか?」
しばらく言葉を待っていると久留木さんが「好きだよ」と問題の本質とかけ離れた事実を告げた。聞きたいのはそれではない。
「久留木さん、俺はエスパーじゃないですから説明してくれないと分かりませんよ」
「説明したら怒るもん」
「俺、怒ったことありましたっけ?」
「ないけど……」
「まだ高校生のときの元カレと同じと思われてます?」
「……」
どうやらそうらしい。
「久留木さん」
「イチゴのムースの準備しまーす」
「久留木さーん?」
「……あとで話します」
「約束ですよ」
俺の腕から抜け出した彼女が冷蔵庫からイチゴを取り出す。
その大粒のイチゴは、形こそ歪んではいるが傷もない上等なものだ。売り物にできるし、この量だと万は越える。こんな風に彼女の客は平気で十万単位のプレゼントを渡してくるし、誕生日になれば百万を越えるものを持ってくる。
「イチゴのヘタをとって、……んー……生クリームでいいかな……」
そんなもので彼女は買えないことは分かっている。彼女の心は俺にある。しかし、腹の底で嫉妬が燃える。
だから俺は棚からゼラチンを取り出し水でふやかす。
「あ、忘れてた。ありがとうね」
「手伝ってもいいですか?」
「うん!」
俺がほしいのは彼女のすべての時間だ。だからエスパーではないけれど彼女のすべての行動を読む必要がある。
彼女の横に立ってイチゴのヘタ取りを手伝いながら笑いかける。彼女が俺に笑ってくれる。
ヘタをとったイチゴを彼女がボールにいれる。そこに俺が砂糖を入れる。
「レンジ?」
「うん、三分ぐらいかな」
「分かりました」
俺がイチゴをレンジにかけると、彼女は冷蔵庫から生クリームを取り出していた。
「……なにか、俺は不安にさせるようなことをしましたか?」
「え? ……あ、違うよ。松下くんはなにも……」
「俺はあなたのためになにもできてないですか?」
「そういうことじゃなくて……」
「……」
「……」
今触ったら癇癪を起こす予感がした。彼女もそうなのだろう。俺たちは無言でレンジの秒数を眺める。リン、と軽い音が鳴り俺が器を取り出すと、彼女は「ありがとう」と言った。
彼女はハンドミキサーでイチゴを潰し始めた。それを見ながら、冷蔵庫に貼られたカレンダーを見る。それで気がつく。
彼女の耳に口を寄せる。
「すいません、生理前でしたね」
「……松下くんのそういうところどうかと思う……」
「漢方飲みました?」
「飲んでないけど……」
「俺は平和な心持ちのあなたが好きです」
「……」
漢方薬と水を用意すると、彼女はハンドミキサーを止めてちゃんと飲んでくれた。
「お酒もやめておいた方がよかったですか?」
「お酒はやめられない」
「ふふ、素直」
彼女が俺を見てへにゃと笑う。
「なんですか?」
「松下くん、酔ってるね」
「……俺が?」
「だからちょっと怒ってたんでしょ? なんでもないよ、余ってたイチゴもらっただけだよ」
彼女の人差し指が俺の眉間に触れる。
「……はあー……」
「なんのため息、それ?」
「なんでもないですよ」
「耳赤くなってるよー?」
「うるさいなー、もう……」
彼女がくすくす笑う。それがかわいかったのでデコピンをしておいた。
◆
クッキー生地の上にイチゴのムース生地を入れて冷やし、さらにイチゴのピューレを注ぎ、冷蔵庫にしまう。
「明日食べようね」
「そうですね……」
「どうしたの?」
「いいえ……薬が効いたようでなによりです」
「あ。えへへ」
「それでなにが不安だったんですか?」
「いや、あの、その、なんというか、将来みたいな、その……松下くんとずっと一緒にいたいなあ、別れたくないなあ、みたいな、その、なんというか……」
「二十九にもなって女子高生みたいなことを……」
「ごめんってば!」
「謝ってほしいわけじゃないですよ……」
もう来月からは生理止めてやろうかと思ったが、それは本当に嫌われるだろうからやめた。
第三話 休日のコンビニで
◇ 久留木 舞
「松下くん、小麦粉って残ってたっけ?」
「残ってますけど予備がないから来月まではもちませんよ。あと片栗粉と醤油と……」
「あ、待って、オリーブオイルがめちゃくちゃ安い……毒でも混ざっているのかな?」
「怖いこと言わないでください。買いますか?」
「んー……うーん……」
「買いますね」
「悩ませてよ!」
「俺は悩むの嫌いなんですよ」
私たちの休みが合うのは月に一度ぐらいしかない。だから食料品の買い出しはこのときにまとめて行っているのだが、松下くんはこの買い物の時はほとんど立ち止まってくれない。前に理由を聞いたら『買い物が早く終わったらその分長くデートができるから』と可愛いことを言われてしまったので、私も今はなるべく悩まないようにしている。
カート一杯の食料品を買いこみトランク積み込み、車に乗ってようやく一息つけた。
「松下くんってば足速くなってない?」
「成長期なんですよ」
「もうー……」
「それじゃあ、……今日はなにをしますか?」
「なにか提案があるの?」
「俺が用意してないと思います?」
「思わなーい」
運転席の松下くんが助手席の私に触れるだけのキスをした。
「でも疲れてるなら家で映画でも観ましょうか?」
「疲れてないよ……」
「去年の冬に観損ねたアクションのやつ、プライムに出てましたよ?」
「えっ! それは観たい!」
「じゃあ決まりです」
松下くんが私の髪を撫でながらキスをする。優しい。「帰りましょう」と松下くんが車を発進させた。本当に家に向かって車が進んでいく。
「……いいの? 色々考えてくれてたんじゃないの?」
「俺はあなたといられるならどこでもいいんです。ほら、そこ桜咲いてますよ? 見ましたね? お花見はおしまいです」
「……イケメーン……」
「好きでしょう?」
松下くんの横顔を見る。きれいな鼻だ。年々格好よくなっているのが本当に困る。多分そう見えるのは私の色眼鏡のせいで、つまり年々好きになっているということだから。
「ムカつく」
「なんでですか。惚れ直してくださいよ」
「なんかムカつくー! 二十六のくせにー!」
「それ関係あります? 去年の源泉徴収で喧嘩します?」
「それはほんとに腹立つ!」
「あはは」
私の年下の恋人。
かわいい彼氏。
多分、……私の最後の恋人。
「昨日ね雀荘に刑事さんが来たよ。前も来てくれてた人なんだけどね、実は刑事だったんだって」
「摘発ですか?」
「うちのレートでそんなことならないよー」
「……なにか事件があったんですか?」
「先週の土曜に新宿で事故があったんだってさ」
「それでどうして四谷の雀荘に話を聞きに来るんです?」
「現場の監視カメラに私の恋人が映ってたからだって」
「……あー、……なるほど」
松下くんは苦笑した。
「それで久留木さんはどうしたんですか?」
「面白い刑事さんだったよ。松下くんが目を合わせたから自殺したんじゃないかって……」
「久留木さんはどうしたんですか?」
松下くんは同じ質問を繰り返した。
彼はいつもの優しい笑顔で車を運転し続ける。だから私もいつもの通り彼の隣でのんびりと体を伸ばす。
「もしそうだったらなに? こちらは割と平和にやっておりますので、って言っておいた」
松下くんは横目で私を見て「ふふ」と笑った。その口の端だけ上げた笑みは皮肉っぽかった。ムカついたのでその頬をつつく。
「運転中にちょっかい出さないでください」
「刑事さん、美人だったよー?」
「あれ? 女……なんですか?」
「うん、女だよ。なんか男っぽい名前だったけど……しかも年下!」
「なんで俺に怒るんですか?」
「絶対あの女! 松下くんに気があんの! 腹立つ! だから私のとこに来たんだよ!」
「公務員がそんな公私混同しますかね?」
「公務員が一番そういうことするのー!」
松下くんの頬をつねると「痛いですよ」と彼が笑う。かわいい笑顔だ。だからつねるのをやめて、赤くなった頬にキスをする。
「やめてくださいってば……」
松下くんの耳が赤くなっている。本当にかわいい。
「……その刑事の名前と所属分かりますか?」
その顔もその声もいつも通りだ。
「……忘れちゃった」
「そうですか」
刑事が言っていたことを思い出す。『彼をおかしいと感じたことはありませんか?』『彼の周りはあまりにも死人が多すぎる』『おかしいと思ったことは本当に一度もありませんか?』あの女は確信を持っている顔をしていた。そして、同時に私のことを見下していた。だからイチゴ農家に知り合いがいるお客さん(警察署署長)に頼んで、彼女は飛ばしてもらうことにした。
でも、そのことは松下くんには教えてあげない。
「もうすぐ誕生日だね」
「誰のです?」
「松下くんのだよ!」
「あ、俺か。忘れてました」
「もうー」
だって彼はこういう展開を楽しむ人なのだ。だからこれは、ちょっと気の早いプレゼントだ。
◇
松下くんと初めて会ったのは雀荘からの帰りだった。
あの日はなにも頑張りたくない日だった。だから出来合いのものを買おうとコンビニに寄った。ついでにと雑誌を物色し、占い特集を買うか春服特集を買うかで迷っていると、妙な胸騒ぎがした。視線をあげると窓の向こう、コンビニの前に止まっていた車が不審な動きをした。
咄嗟だった。どうしてそうしたのかも分からない。私はそのとき、隣に立っていた男性の腕を引き寄せた。
破壊音の中で目を合った。
「……」
今まさに立っていた場所に車が突っ込んできたというのに、私が腕を引かなければ死んでいたというのに、まさに九死に一生を得たというのに、彼はとてもつまらなそうに私を見下ろしていた。
「……チッ」
その舌打ちは心底面倒くさそうだった。私が慌てて彼の腕を離すと、彼は私を抱き上げた。
「えっ?!」
「足、怪我しています」
心底どうでも良さそうな声色だった。
彼は私をガラスがないところまで運び、売り物のミネラルウォーターや消毒液、ガーゼや包帯を勝手に使って応急処置をしてくれた。ミニスカートから出ている私の脚には心底興味無さそうな手つきだった。
「ガラスは洗い流したと思いますが、念のため病院に行ってください。もしなにかあったら連絡ください」
彼は私に三万円と名刺を握らせて去っていった。救急車もパトカーも来る前の話だからほんの二分ぐらいの話だろう。それが私と松下くんの初対面だ。
あのときの松下くんの冷たい瞳を私はよく覚えている。そして松下くんはこの事を覚えていないことも、よく分かっている。
彼はおかしいのだ。始めから分かっている。それでも私は彼に連絡を取った。彼は私に会いに来てくれた。それから何度か食事をして、手を繋いで、そうして今がある。
私は彼が好きなのだ。今それ以上に大事なことはない。
◆ 松下 白翔
久留木さんが『コンビニ飯が食べたい』と言うなら近所のコンビニに寄ることにした。
「松下くん、ポテチ買ってもいい?」
「いいですよ?」
「太ってもいいの?」
「俺は太りませんから」
「なんでよー一緒に太ってよー」
「体質なんですよ……久留木さんはもう少し太った方がいいですよ」
「お仕事なくなっちゃうよー」
「そしたら俺が養うんですけど……そう言ったら機嫌悪くなるんですよね? 分かってますって、睨まないでくださいよ。ポテチ買いましょうね」
「一緒に食べてくれる?」
「当たり前でしょう。俺以外の誰と食べるつもりですか」
「知らなーい」
目についたポテトチップスをかごに入れていく。
「すっごいジャンクな気持ちなの。ピザも頼んでいい?」
「コーラも買いますか?」
「家にブランデーあるからなー」
「コーラとブランデーは違うでしょう?」
彼女がカップ麺をカゴに放り込んでくるので、俺は煮卵やサラダを入れておく。大きいバニラアイスと、四号瓶の日本酒と新発売のチューハイとかちわれ氷を入れたら四千円近くなった。
「買いすぎですね……」
「堕落した生活……」
「アイス溶ける前に帰りましょう」
「おうちデートだね」
そう言う彼女の笑顔がかわいすぎてキスをしたら「コンビニでなにするの!」とビンタされた。ここ数年で一番痛かった。
彼女以外にこんなことされたらきっと、その人間の身内を自殺させるだろう。でも、彼女だからそれもかわいい。
彼女に初めて出会ったときのことはよく覚えていない。恐らく他の人間とさして変わらず見えていたのだろう。ではいつから違うものに見え始めたのか、いつから特別なものに見え始めたのか、実はそれもよく覚えていない。
いつからか勝手に思考が彼女の行動を読むようになり、勝手に指先が彼女を誘い、勝手に足が彼女を迎えに行き、勝手に口が「付き合いましょうよ」と言っていた。
自分でも自分がどうしたのか分からない。だから多分、恋なのだと分かった。
それまでにない感情とそれまで想像もしていなかった景色はとても面白かった。そしてこうなっては最早手放せない。だから彼女にだけは優しくしている。
もしそれでも俺から逃げようとするなら、そのときは、……そのときだ。今のところは割と平和にやっているのだから、今考えることではない。
◆
彼女がピザを頼んでいる間に映画の準備をする。
「カニ……エビ……パリパリ……フワフワ……」
「なんでもいいですよ? カップ麺にしますか?」
「それはあと!」
「食べることは食べるつもりなんですね」
「今日は弾けるまで食べる!」
「はいはい、お付き合いしますよ」
コンビニで買ってきたサラダを皿に出して煮卵を割る。塩味のポテトチップスを器に出してソファーの前の机に置く。グラスに氷をいれてチューハイを注ぐ。
「久留木さん、先飲んじゃいますよ?」
「やっぱりマルゲリータにします! 注文! 三十分以内に来る!」
「ここだと十分もかからないでしょうね」
「そうなの?」
「駅前に新店舗ができたんですよ」
「そうなの! え、配達頼むの悪かったかなあ……」
「いいでしょう、別に……」
俺の隣に滑り込んできた久留木さんがグラスに手を伸ばし「乾杯しよ」と笑った。彼女のグラスに自分のグラスを軽く当てる。うすはりのグラスがチリと震える。
「割りそう」
「怪我しないように気を付けてくださいね」
「割る前提で話さないでよー」
顔を合わせて、くすくすと笑って、酒を飲む。
「あ、これ飲みやすいね」
「そうですね、変に甘くなくて……」
「そして度数も高くてよい!」
「呑兵衛め」
「嫌い?」
俺の彼女が笑う。
「……そうですね、嫌いです」
「えー!」
「嘘ですよ」
俺は人間として人間社会に生きていくのに向いていない趣味を持っている。この国の刑法では裁けなくとも問題がない訳じゃない。俺はおかしいのだ。なのに、どうしてだろう。彼女が笑うとそれ以外はどうでもよくなる。ただ彼女に喜んでほしくて、それだけになってしまう。
存外俺はつまらない人間だ。だから他の人間と同じように地味に死ぬのだろう。
「大好きです」
「ちゅーする?」
「うん」
そう返事して顔を寄せたら見計らったようにインターフォンが鳴った。彼女はゲラゲラと笑い、俺は大きくため息を吐いた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
