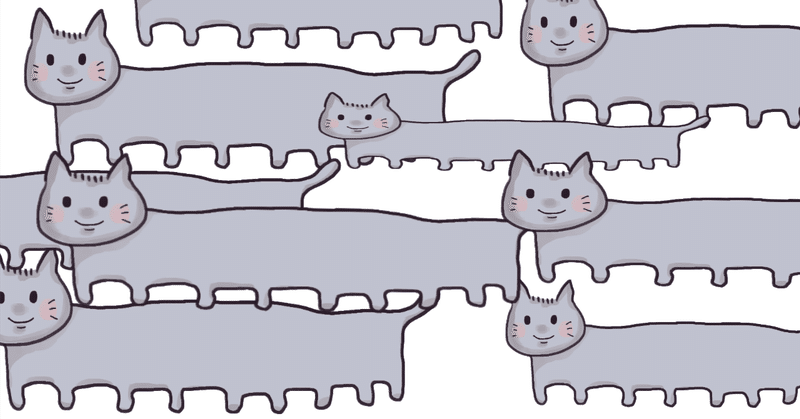
重度の吃音について
I think, therefore I am.
俺は……、だから、俺は……。
「我思う、ゆえに我在り」と言わざるをえない地点にまでデカルトを追い込んだのは「お前は何者だ」という問いでした。それは「私は何者か」という自問とは似て非なるものです。「私は何者か」という自問はモンテーニュの「我何をか知る」Que sais-je? の亜種(我に就きて我何をか知る)とならざるをえないのであって、「方法的懐疑」を繰り出してみたところで自問が自問である限りは『エセー』を一歩も出ることができません。コギト(自己意識)よりもむしろ、「お前は何者だ」と執拗に問いかけられること、強いられることがデカルトをデカルトたらしめるはずです。
そのことは暖炉の前で冬着を纏い、独り行われた『省察』をみる限りでは察しづらい側面です。その点で『省察』の再演とも見える遺稿が対話のスタイルで書かれていることは注目に値します。
ユードクスがポリアンドルにこう尋ねています。
さてもう一度、いままでの議論をくり返してみましょう。君は存在し、自分が存在することを知っており、しかもそのことを知っているのは、自分が疑っていることを知っているからです。しかしながら、このようにすべてを疑いながら、ただ自分自身だけは疑いえないところの、君とはいったい何であるのか。
ユードクスもあくまで影であって、本体として彼を突き止めることはできません。しかし、デカルトは確かに「お前は何者だ」という問いに苛まれ続けてきたはずで、それゆえに対話の形式が採られたわけです。
「お前は何者だ」、一切の与件としての問い。
「お前は何者だ」、そう問うお前は何者だ――こんな風に洒落て、問いを飲み込みコギトを導き出して事足れり(「お前」は私なのだ)、という手もあります。すなわち与件を「パラフィクション」(佐々木敦)として読むということですが、あまり面白くない。
誰が問うているのか。その空座を誰が占めるのか、あるいは占めているのか。おそらくこれは政治の問題圏にあります。「多数を相手にした為事」に従事する者は「お前は何者だ」と問うては回答を半ば強制して、落着させたがるからです。
さて、そんな問いがもし私に投げかけられたとすれば、I think (that)とI amの次の言葉が継げないデカルトのように、吃っているほかありません。
I think, therefore I am.
俺は……、だから、俺は……。
黙っているのとは違います。「多数」というのは、頭数が多いのとは全く違います。「……」が「多数」を抱えていてもよいわけですから。
…… think, therefore …… be.
…………、だから、…………。
山城むつみ氏の「コギトについて」という文章を参考にしました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
