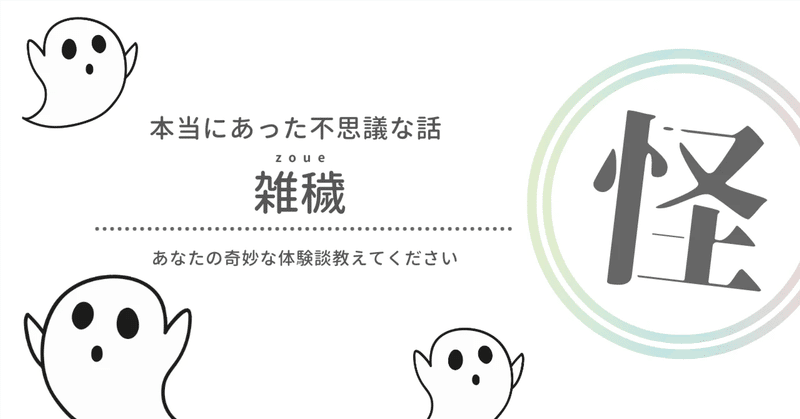
雑穢 #1027
義母の葬儀で帰省していた妻が、骨壷に入った遺骨を持ち帰ってきた。
葬儀は家族葬というよりもさらに小規模で、妻と義妹二人の三人のみで取り行ったようだ。妻は長女であり、喪主を務めることになったと聞いていた。
しかし、世は疫病の流行下で集会は憚られるとはいえ、たった三人の葬儀というのは少々異様にも思えた。ただ、それが故人の意思だというのだから従うばかりだ。
「あの人、昔から遺骨なんてそれこそゴミに出してくれれば良いのにとか、冗談とも本気ともつかないことを言っていたし、結局お父さんの遺骨も、愛子の家の仏壇に預けっぱなし。酷いったらないわ」
妻はため息を吐いた。愛子とは下の義妹の名である。
「お疲れ様。まぁ、今回で最後なんだから、そう言ってやるなよ」
結婚当初から、妻は義母の奔放なところにうんざりしていた。人生の長い期間を、母親に振り回されて生きてきたのだから、それは仕方のないところだろう。
だが、義母は奇矯な人だが悪い人ではなかったし、外から見る限りでは、娘のことは溺愛していた。ただ、その愛情の注ぎ方が、生真面目な妻には負担だったというだけの話なのだろう。何年も愚痴を聞いてきたが、妻も四角四面に過ぎるのだ。
「だって、化けて出ますから、なんて言われても困るでしょう」
ちゃめっ気が過ぎるな、などとその時は返事をした。
「お婿さんお婿さん」
その夜中、枕元に義母が出た。経帷子を着ているが、にこにこしていて、やけに血色がいい。ああこれは夢だと思って、はぁ、お義母さん、何かご用でしょうかなどと寝ぼけた返事をした途端、横で寝ていた妻が布団を跳ね除けて飛び上がった。それで夢ではないのだと理解した。妻の顔は今までに見たことがないほど目が吊り上がっていて、柔和な顔をしている義母とは対照的だった。
「あはは。綾ちゃん、そんなに怖い顔しないで。ほらちゃんと出たでしょう? それじゃ次はお骨を恵ちゃんに渡してね」
義母はそう言うと、パッと姿を消した。夫婦揃って夢じゃないよねと言い合って、朝まで起きていた。骨壷は居間のテーブルの上に置かれたままだったが、次は上の義妹に渡さねばならない。
「これだと愛子さんのところに骨壷が二つ行ってしまうなぁ」
二人で義妹の家に行く出しなにそう言うと、妻は「大丈夫」と答えた。
何でも二人分揃ってから散骨する約束になっているとのことだった。
妻はしばらく義母に腹を立てていたが、四十九日が過ぎる頃には落ち着いてくれた。
サポートよろしくお願いします。頂いたサポートは、怪談文化の発展のために大切に使わせて頂きます!
