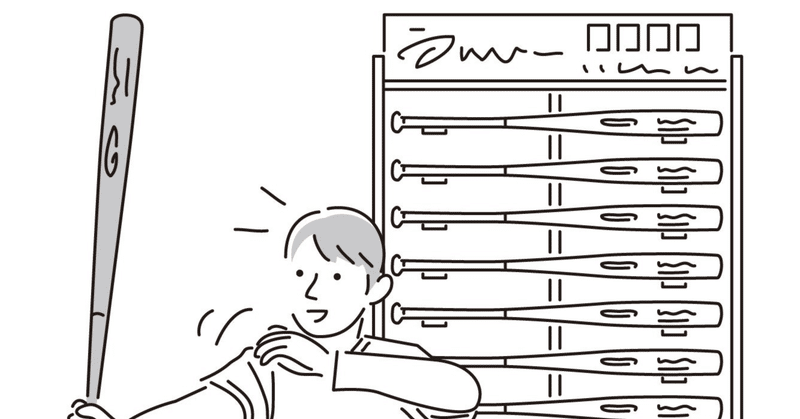
部活中止が残念じゃない中学生もいる、それが重要だ
「コロナ禍と児童生徒」に関する調査を紹介した記事で、興味深いものがあった。
簡単に言うと、「コロナで部活ができなくなって、中学生は悲しんだ。でも、それってみんながみんなそうなのかな?」というもの。
コロナ禍の3年間は遠足や修学旅行、学校祭などといった学校行事が中止や延期に追い込まれた。運動部、文化部問わず、さまざまな大会が軒並み中止となり、目標に向けて努力を続けてきた部員の無念の声は連日メディアに取り上げられた。
しかし、中村教授は「みんながみんな行事や部活動が中止になって残念かどうかは分からない。個人差がある。この辺りは多面的に見なければいけないという教訓が得られたと思う」と語る。それを裏付けるのが、21年12月に行った中学生を対象にした部活動に関する調査。部活動の縮小について「とても残念だった」「どちらかといえば残念だった」と答えた生徒は合わせて73.6%に上った。しかし、部活動に熱心に取り組んでいなかったと回答した生徒に限定すると、数字は48.0%と半分を下回る。研究チームは部活動の縮小や大会の中止が心理的に影響することを認めつつも、残念と思わない生徒も一定数おり、「児童生徒の置かれた状況によって反応は予想以上に多様だった」と分析した。
これを読んで、ふと、中学・高校生時代の部活に対する複雑な感情がよみがえってきた。
私はチームスポーツ系の部活に入っていた。レギュラーだった頃、部活が楽しくて仕方なかった。活動場所に行くのにスキップをしそうになるくらい楽しい時期もあった。上達すること、勝利すること、本当に楽しかった。
ところが、レギュラーから外れてからは、正直、部活が楽しくなくなってしまった。台風が来て休校になり部活もなくなると、正直嬉しかった。
ちなみに、この記事で出てくる調査はインターネット上で公開されており、読むことができる(【1~3】のファイルが該当箇所)。
この章を担当した山口先生は、章末の結論部分でこんなことを書いている。
こうした実態把握をおこなわなければ、現実を見誤ったままに政策決定がなされてしまう可能性があるだろう。全国一斉臨時休業から間もない 2020 年の 4 月から 5 月頃にかけて、9 月入学の導入の是非にかかわる議論が大々的におこなわれたが(中略)、そのきっかけのひとつとなったのが学校行事や部活動の中止・縮小を嘆く高校生の声であった。9 学入学に関する論争の是非を問うことは本稿の目的ではないが、少なくとも、適切なデータに基づく実態把握を経ることなく、ごく一部の事例をもとに早急な政策決定がなされることは避けなければならない。
「部活がなくなったのに大してダメージを受けていない中学生」像というのは、大人が好感を抱く中学生像ではないだろう。
だとしても、現実に、そういう中学生はいる。
どっちが良いとか悪いとかではなく、そういう中学生もいるのだ、ということが重要なのだと思う。
「適切なデータに基づく実態把握」の重要性を嚙み締めつつ、「部活なしラッキー♪」と思っていた自分も圧倒的マイノリティーというほどではなかったのだと、十数年越しに知ってちょっと安心した。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
