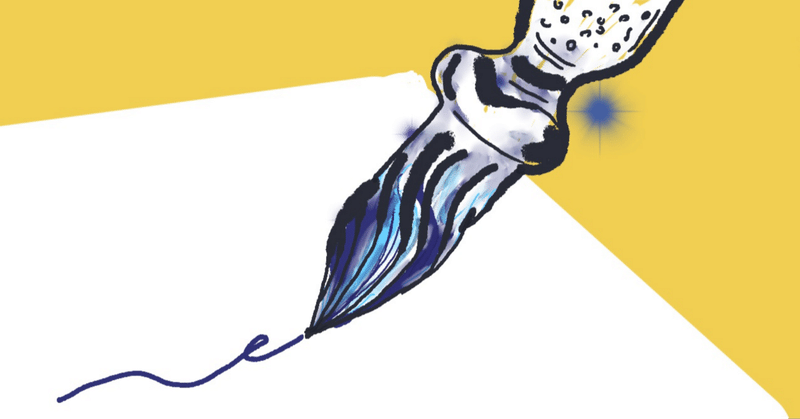
先生短歌、詠んでみた。
わたしがエッセイを投稿しているからか、noteで親しくさせてもらってる方々は、圧倒的にエッセイを書かれる方が多い。
そしてその中には、俳句や短歌を嗜む方もちらほら。
文学フリマでも、素敵な俳句集があったので思わず手に取ってしまった。
そんな方々にちょっぴり感化され、わたしもノートのすみっこに半年くらい前から短歌を書き連ねている。
5.7.5.7.7と制限があるからこそ、広がる世界。そこに情景を込め、心情を匂わせる。
ーなんて粋で風流な遊びなんだろう…!
三十一文字、「みそひともじ」って響きもなんだか粋じゃないですか。
というわけで、学校での光景を三十一文字で描いてみました。
解説を添えて、どうぞ。
「いい姿勢。」
褒めれば周りの
一斉に
伸びたる背中
こそりと笑う
クラスの中で何人もの子どもたちが、姿勢が悪いだとか、指示を聞いていないだとか、何か注意したいことがあるとき。
あえて今出来ている子を褒める、というのが先生になって身に付けた常套手段。
子どもたちの望ましい行動を引き出すために、注意だけじゃなくやっぱり温かい言葉の方が、聞いている方も心地良いし。
(もちろん内容によっては咄嗟に注意することもあるけれど)
誰かを褒めたらすっと条件反射的にそれに倣う子も多くて。特に低学年や中学年の子どもたちには結構、効果があるんです。
言った瞬間すっと周りの子たちの姿勢が良くなった姿見て、なんだか可愛いなあ、なんてと手に持っていた教科書の下、唇が弧を描いちゃう、みたいな。
いつの世も
変わらず励む
職人よ
どれだけ長い
消しゴムのかす
消しゴムで消すと、金魚のふんみたいに細〜くつながるけしゴムのかす。
ほら、アラサー世代の方々、子どもの頃「まとまるくん」とか使ってませんでした?
子どものとき、いろんな子たちが、どうやったら長い消しゴムのカスが出来るか試行錯誤していた気がする。
最初は普通に消していても、だんだん楽しくなっちゃってどれだけ長い消しかすを作れるか、のためだけに消している子どもたち。
ああ、もうほら無駄に机を消さないの。
というかあなた、休み時間ならともかく、今算数の時間なんだけどねえ。
「次回ってきたときも、まだしてたら取り上げるからね!!」
ってその子に声をかけたけれど、学習活動に必要なけしゴムを預かるわけにはいかないし。
けしかす、取り上げちゃう?
…いやあ、折角出来た長い長いそれ、ちぎっちゃったら嫌だしなあ。
「悔しい。」と
鉄棒睨む
その眼(まなこ)
我が遠くに
忘れしものよ
体育の授業では、器械運動の一つとして鉄棒を教える。
彼ら、前まわりはわりとすぐに出来るけれど、小学2.3年生の第一関門は、逆上がり。
鉄棒やマットなどの器械運動は、幼い頃から身に付いたの身体の使い方というか、運動神経というか…。
出来る子は練習せずとも、すっとできるし、出来ない何人かの子は、何度やっても出来ない。
そして、担任していたみきちゃん(仮名)は、後者の子。
ぜっんぜし脚が上がっていないし、お腹も鉄棒から遠いのよ。
周りの子がこともなさげに、くるくる回っていると、「自分もやりたい!」ってより思うんだろうね。
手にマメが出来ても、鉄棒を握り続けている。
歳を重ねるとさ、自分に向かないことって早々に諦めたり、合理化というのかな、出来ない言い訳、すぐ考えちゃうじゃないですか。
「それが出来なくったって、他があるし大丈夫。」って納得させてみたり、
「わたしはここまででいいや。」って自分でハードルを下げたりね。
まだ大人への階段を踏み出していない子どもたちの、出来ないとか出来るとかじゃない、「やりたいから、とりあえずやってみる」って純粋なガッツ、尊いよなあ。
ちなみに先のみきちゃん、2週間くらい練習して補助具を使ったら、ようやく一回だけ回れました。
良かった〜とわたしも胸を撫で下ろす。
単に逆上がりが出来た、だけじゃない。
「諦めなかったら、出来た」経験としてみきちゃんの記憶に残ると良いなあ、なんて思いながら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
