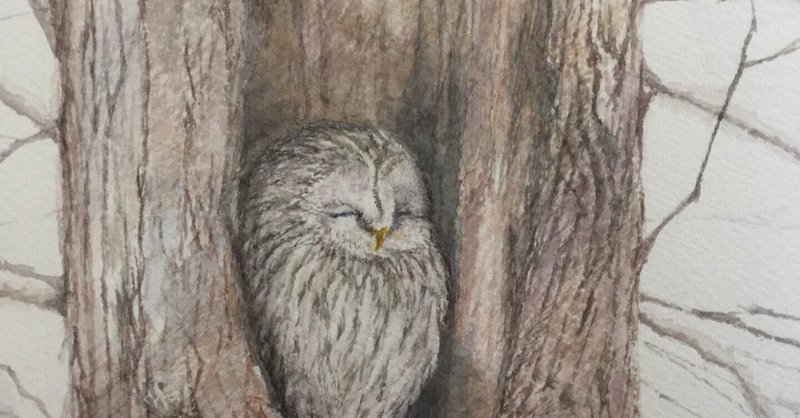
幸田露伴の随筆「折々草47」
四十七 散乱心
心が一点に注ぐことが出来ないで動揺して止まないのを散乱心と云う。例えば書物を読む時に一心が紙上に止まらないで、或いは鳥の声を耳にすると心が直ちに鳥の辺りに向って走り去り、或いは車が窓の前を通り過ぎると心は車を追って去るというようなことである。これを散乱心で事を為すと云うのである。昔の人はこの散乱心で事を為すのを甚だ嫌って、学問にしろ仕事にしろ為して成らないのは、大抵この散乱心で事に当たるからだと考えたようである。確かに散乱心で事を能く成すことは覚束ない。その実例が数学を学ぶときに誰もが知るところである。思考力が必要な数学の問題に対してモシ心がその問題に集中できていなくて、むやみに昨日見た演劇の光景を想い出したり、もしくは今夜某所で観る予定の映画を想像したり、もしくは自転車に乗って走る愉快などを想像したりすれば、思考の力は鈍って脳は混乱を惹き起こし、結局は茫然自失の状態となろう。であれば、数学の問題だけで無くどのような場合でも、散乱心では事を能く成せないことが分るのである。
世の中には抜群に聡明な人が居て、一時に多くの人が口々に訴えるのを聞くことが出来たり、手では書類を記しながら心では詩を作ることが出来る人も居て、このような人は歴史にも見え眼のあたりにも見ることがあるので、散乱心で事に当たっても差し支えないと思うかも知れないが、しかし八人芸のようなことが出来たからと云っても少しも尊敬できないのである。俗人は驚いて奇異だとしても、識者が何で価値を認めよう。時には左手で円を書き右手で四角を書くことを能くする人も無いことは無いが、たとえ実際にこれを能くしても価値の無いだけでなく、例外的なことなので常人が之を学んで遣るようなことではない。ニュートンは偉人であるが、人が「どうして君は引力についての大発見ができたのですか」と問うと、「私の不断心によってできました」と答えた。不断心は散乱心の反対である。龍樹菩薩は大賢人であるが、「散乱心は風の中の灯のようである。明るくても物を照らすことはできない」と説かれた。まことに風の中の灯とは巧みに形容されたものである。聡明な人が中年になると時に愚鈍の人に凌駕されることがあるのは、しばしば人の目にするところであるが、私の実験ではその原因の殆んどは、聡明な人が散乱心で事に当たることによって結局敗者の位置に立つようである。思うに聡明が過ぎると余裕が生まれ、心に余裕が生じれば勢い集中を欠き散乱動揺しようとする。聡明な青年が書物を読めば書物は甚だ読み易く、計算をすれば計算は甚だ為し易い。ここにおいて集中を欠き安易な心の馳せるのに任せ、一心は散乱し動揺し、日を重ね月を積むと終には頑固な習癖となる。散乱心で物事に当たるのが習慣となれば聡明な人も聡明で無くなり、風の中の灯火がチラチラと弱まるように、専心集中して物事に接する習慣を持つ愚鈍の人に勝てなくなるのは必定である。
天稟甚だ高い者も終(つい)には凡庸の人の下風に立つようになる。まことに惜しくも残念なことではないか。聡明な人の頼りないことを昔の人も多く云っている。散乱心を改めないことは驕慢心を改めないことよりもその影響は甚だしい。人の聡明は四十才五十才になると必ず衰えるものである。人々は聡明が未だ衰えないうちに、一心散乱の悪習を作ること無く、自身の為したいことを成すための地を作るべきである。
(明治二十三年十二月)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
