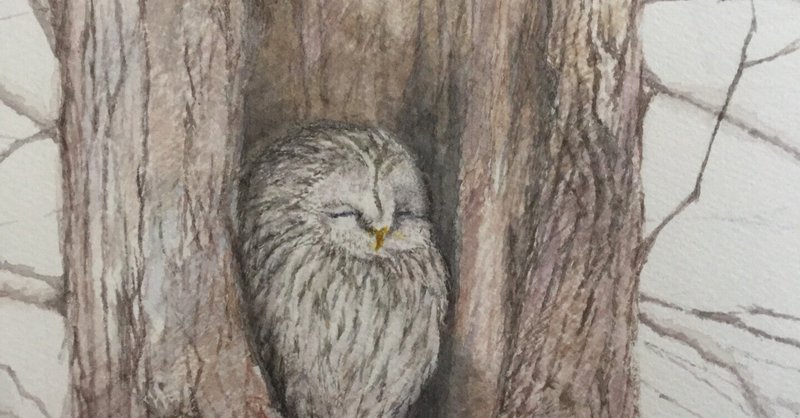
幸田露伴の随筆「無題」
無題(無題で出来ました。無題にして置いて下さい。)
〇
むかしは朱引きの内外(うちそと)と云った。今は市部と郡部とを分けて市中と郊外とに区別するが、江戸から東京になり、東京から大東京になって、住民は日々に多く、住居は月々に増えて、朱引きの区分はとっくにその実質を失い、市と郡の境界もすでに名だけのものとなった。昨日の柴垣は今日のなまこ塀に変わり、ハンノキに霞のかかる野原も煙突から黒煙を吐く処(ところ)となり、すべてが活動写真のように目まぐるしく移り変って、市内も郊外もただこれ夢の中に東西も分からず、春の日の雪の消えるしばしの間、南と北とを分けるに過ぎない。国が盛んになり都が栄えることであれば目出度いことこの上もないが、この十年の東京のさまは、一言で云えば住居の氾濫と云うだけである。
〇
小梅と云えば江戸の昔や明治の初めは寮の多い土地であった。寮とは今の別荘のようなものである。寮のほかには小農や植木師の侘しい小家が在るばかりで、稲田まじりに花畠や植え込みがつづき、寮の庭や四ツ目垣をくぐってはアオジやミソサザイが自由にゆきかい、茅葺屋根をかすめてはゴイサギやカッコウが声を落として行くところだと、古くは春水、近くは金鵞などの雑書を見ても知ることができる。小梅から東は請地・押上・柳島・亀井戸、北は柳ばたけ・須崎・寺島・隅田、皆同じおもむきで、いよいよ江戸を遠ざかるにつけて、いよいよ蕭散間曠(しゅうさんかんこう)の情が増してくるが、東京の民家が氾濫するようになって、小梅が先ず開けて、中の郷辺りは早くも家ごみになって、丹次郎蟄居のおもかげなども偲ぶことのできないところとなって、車はとどろき、人はわめき、夕焼け空に子供のざわめく好ましくない町に変わった。佐竹侯の広い庭がサッポロビールの工場となってからは、辺りの有様もいよいよ急激に変わったが、小梅橋を北に渡った水戸侯の邸(やしき)だけはさすがに人をのどかにして、三囲神社(みめぐりじんじゃ)前に少し遺(のこ)る蓮田(はすだ)と共に、なおも隅田川を西に隔てる郊外の風情を遺し、遠く望む浅草寺の甍や五重塔の白緑の屋根、待乳山(まつちやま)の堂や森、秋の暮れなどには、「そめいろの富士は浅葱に・・」の越人の句も思い出されて、そぞろ歩きの心もいささかこれに慰められる。であるのに、人情が先ず去って、天道もまた従い堕ちたものか、去年の火災で水戸邸も焼失し、鬱然と立っていた樹々も、今は焦げ残りの鬼々とした姿を見せるだけとなった、一望の焦土瓦礫の中に美しくない鉄道草の群がり立つのを見る。草の中でも冬草の幼く弱々しいものや、夏草がたくましく生え立っているのは何れも宜しくはないが、しかしなお思いようによっては観るべきところも無いではないが、鉄道草と云うのは明治以後に繁茂しだしたもので、今では上総や下総の海辺から上州や信州の山中までも蔓延(はびこ)っているもので、およそ雑草の数々ある中で最も忌まわしい嫌な草である。性質が強く他の草を押しのけ、丈も高く、やさしみが無く、牛や馬も好まず、和歌や俳句の題材としても廃墟・瘦せ地・荒村・貧居に取り合わせる他に用いるところのないものである。古(いにしえ)には麦の穂が生え出すのを見て悲しむ人もいた。今この名勝の地の鉅公の邸でこの悪草の我が世顔を見、川を隔てて待乳山のものがなしい景色を望む。人誰か暗然憮然としない者あろうか。
(大正十三年七月)
注解
・朱引きの内外:江戸幕府が定めて地図上に朱色の線を使って示した「大江戸」の範囲。
・活動写真:明治・大正時代の映画の呼称。
・小梅:江戸・明治前期の村名。隅田川を挟んだ浅草の対岸地域。向島1~3丁目・押上2・3丁目辺り。スカイツリーが建っている辺り。
・春水:為永春水。江戸時代後期の戯作者。作品は「吾嬬春雨」・「春色梅児誉美」など。
・金鵞:梅亭金鵞。江戸末期から明治中期の作家。作品は「春宵風見種」など。
・蕭散間曠:広漠と広がる閑散とした風景。
・丹次郎蟄居のおもかげ:為永春水の「春宵風見種」の中で描かれた、主人公の丹次郎の蟄居の様子。
・佐竹侯の広い庭園:浩養園(佐竹の庭として有名・明治二十三年から一般公開されて多くの人々の憩いの場ともなっていた。)。現在の墨田区吾妻橋1-23辺り。
・サッポロビールの工場:現在はアサヒ・スーパードライホールになっている。
・水戸侯の邸:水戸徳川家の下屋敷が在った所。現在の隅田公園の地。
・三囲神社:墨田区向島に在る神社。隅田公園に隣接している。
・浅草寺:いわゆる浅草観音。
・待乳山:隅田公園の対岸に在る小高い丘で待乳山聖天社となっている。古くから名所として文人墨客に愛され多くの絵画や歌の題材となった。
・越人の句:そめいろの富士は浅黄に秋の暮。
・鉄道草:ヒメムカシヨモギというキク科の植物の異名。草丈2mに達し大群落をつくることもある。
・鉅公の邸:水戸徳川家下屋敷の跡地。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
