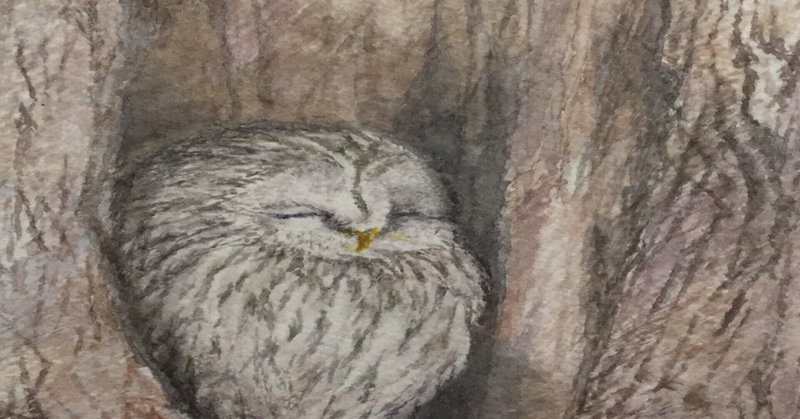
幸田露伴・明治の東京で「渡船」
渡船
八百八町に下駄の音の絶えるひま無く、二十四時間車の轟きの止む時も無ければ、十丈の紅塵は馬耳を没して、都は人の息つくところの無くなるところを、幸いに一条の流れが北から南へと注いで、新しきを入れ古きを吐き出す作用を為せば、江戸は辛くも隅田川に依って活きると云える。この流れの上だけが僅かに風清く塵も無い。であれば、朝三暮四の営みに心忙しく、僅かな利益に奔走する町の人も此の川面に出た時には、身を広々とした日の下に晒し、胸も商売のイザコザを忘れて、少時(しばし)は川面の光や雲の容(かたち)に目を洗い心を休めることであろう。そのような人々でなくとも渡船(わたし)を面白と云う人は多い。実に桜の花が空に懸る橋の上の眺めも悪くはないが、人も行けば我も行き袖も触れば肩も触る混雑に、猶いろいろの気づかいと煩わしさもあるだろう。渡船の中は、櫓に漲る水を受けて船頭の腕は頻りに疲れても、又は竿を中瀬の底に突っ張って船底の接触に悩むとも、乗客(のりて)は、人も休めば我も休み、腰も下ろせば荷物も下ろして、いわゆる同船客の心温かい話の遣り取り、煙草の烟(けむり)を長閑(のどか)に吹いて居られるならば、一入(ひとしお)気を休めて景色を賞することも出来よう。およそ隅田川の渡しは十数ケ所あって一長一短はあるが夫々に眺めが好い。最も川下のを勝鬨(かちどき)の渡しと云う。月島から築地への渡しである。海に近く眺望は広く、南風が颯(さっ)と来る夏の夕べの快さ、舷側に浪が飛沫(しぶき)を立てるのもおもしろい。その上の渡しを月島の渡しと云う。同じく月島から明石町への渡しであるが、此処のは竹竿と櫓櫂(ろかい)の昔ながらの式では無い市営無料の蒸気船なので、他所(よそ)とは趣が異なって、ただ単に速いことを特徴とする。風流とは云い難いことながら、川上おろしは氷より冷たく、霙ひとしきり黒雲の零れ落ちる日など、煙突は強い色を吐き機関はキビシイ音を立てるのも却って面白い。佃の渡しは自然と古びている。鉄砲洲の方から渡って行くと、何となく鄙びた里へさすらう様な心地がするのも私一人の思いではないだろう。愁雲天を閉ざして寒雨夕べに潅(そそ)ぐ秋の暮れなどに、一船が東に渡る、まことに心寂しいものがある。月の夜に親船の影黒く帆柱の高い姿を見るのも淋しい画である。勝鬨の渡しから佃の渡しまでの三ツの渡しは総て本澪(ほんみよ)を渡すのである。隅田川の下流とは云えども海が迫り潮が激しいので、海気があって野趣は無い。川の渡しと一口には云い難い。相川町の渡しは今は絶えて無い。蠣殻町から仙台堀へ渡る中州の渡しは、市中なので取り立てて云うことも無い。寒さがまだ残ると思っていた町の人が、たまたま此の渡しに乗って、川上や川下の打ち霞むのを見て密かに春の来たのを悟るのも此処の風情であろう。浜町から安宅への安宅の渡しと矢ノ倉の市場前から一つ目への千歳の渡しは、別に甲乙も無い風情であるが、時雨に渋い蛇の目笠や、春雨に花屋の荷など、この辺りは乗る人の様(さま)で見処もあろうが、船からの眺めは雪の日などにある。富士見の渡しは須賀町から横網へと行く、若葉時の夕陽やわらかな頃など、本所側は総て好い。振り返って見ると雲間に高く玲瓏と富士が聳えている、何とも云えず神々しく尊い。特に西風が吹き続いて世の中も次第に枯れ行く暮秋の夕べ、陽は既に沈み余光は猶天を焼く紅の空に、黒くして蒼く、蒼くして紫の、幽玄神秘の色に無言の威を包んで、超然としてその雄姿を厳かに示すのを仰げば、胸の冷えるような心地がしてこの上なく尊い。駒形の渡しは、水際に近い観音堂の小さな白壁造りの、形ばかりの宝珠を頂いた形も宜しく、雨の日にホトトギスの一ト声も聞きたい所であるが、今は絶えたのか久しく船の往来を見ない。「君は今・・」の句も渡しが無くなって、渡船場の在り場所も知れなくなっては、人も次第にその趣が解らなくなるだろう。浅草寺の裏門河岸から枕橋に渡る渡しは、東側から眺めて、春は山門や五重塔の霞むのを見る、秋冬は水上(みなかみ)遠く筑波を想いやる、皆好い。西側から夏の涼しい夜に酒亭(ちゃや)の灯を望むのを見、春の昼には長堤の桜が紅雲のように地に曳くのを見る、これも好い。竹屋の渡しは、未だ見ない人も絵や歌で知るが、西側から見た長堤一望の花の時期だけでなく、若葉が朝風にそよぎ烏が実桜に鳴く頃も面白く、葉が落ちて梢も透いて欠けた月が堤の陰から青み昇る秋も面白い。東側から見た待乳山の疎林と寺、山谷堀の斜水小橋、浅草寺の堂塔、富士の連山、春は紫に沈む筑波山、何れもおもしろい。特に冬から春にかけて沖に南風が荒く吹く時は、鴎が遠くこの辺りまで入って来て気ままに遊び浮かぶ、「胸に桜を分けて行く」と云う句も思い出されて、柳がけむり白魚が上る頃は特にめでたく長閑である。都鳥の名に由って業平が物思いをしたのは此処では無いが、吉原通いの猪牙船に英一蝶が浮かれたのは此処であろう。茂睡の歌の碑は遠望しても見えないが、其角の句のある神社の鳥居が顔を見せるのも面白い。竹屋の上流は寺島の渡し、寺島の上流は橋場の渡しである。野趣多く東岸の蘆荻にヨシキリの声もうるさく、上流はいよいよ開けて北方の水上に筑波山の姿が鮮やかなのは寺島渡しの勝れたところ、石浜の祠のほとりに老樹の鬱蒼と茂るのを見て、小松島の園地に水鳥がにわかに立つのを聞くのは橋場の渡しの風情、共に多く語ることも無い。汐入の渡しは、川が直角に曲がるところに当る。村は猶古朴な面影を残して、人は僅かに灰を造り地を耕すに過ぎなければ、茅葺屋根に竹垣の、船の着く辺りの状景は呉春などの画のようであったが、今は次第に変わりつつある。東岸の綾瀬や浮島の辺りは、川幅が広く開けて月を観賞するには極めて好い。汐入から上流には元木の渡しがあって元木から下尾久に渡る。そして小台の渡しがあって小台から上元木に渡る。その他、羅漢の渡し、矢新田の渡し、下村煉瓦屋の渡し、川口の渡し、皆多少の好処はあるが、市を離れて遠いので語らない。
(明治四十三年二月)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
