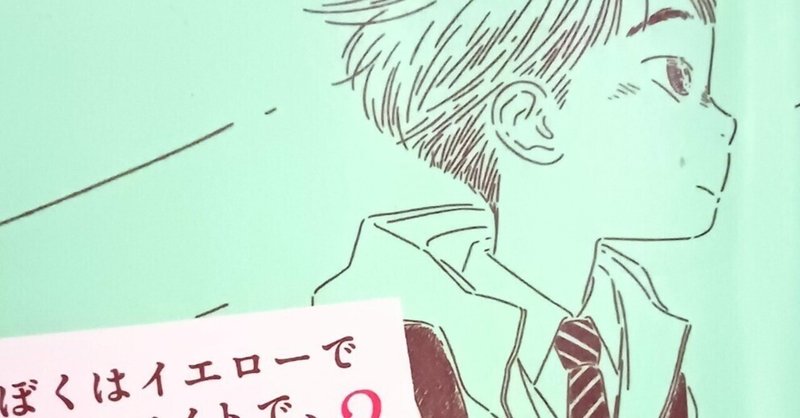
ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2
1は数年前に既読済で2も気になっていたのだがタイミングを逃し、やっと手に取ることができた。
イギリスのブライトンという街で暮らす著書の息子に起きる様々な出来事が話の中心。人種・階級社会・教育・ジェンダーなど多様な人々がいるイギリス社会を垣間見ることができる。
特に気になったのは教育制度について。
GCSEの試験科目の幅広さには驚いた。日本でおなじみの教科以外にシティズンシップや音楽・演劇・映像・宗教など実に多種である。
英国の知識人は、音楽とか芸術とか料理とかスポーツとか(中略)、いわゆる5教科以外の分野でもやたら博識というかいろんなことをよく知っている人が多いが、それはきっと中学生のときから受験科目として広範な分野を選び、それらの教養を身に付けなければならないからだろう。
著者もこう書いてあるが、自分の興味のある分野を自分で選んで様々学べるのはなんて豊かな環境なんだろうと思う。
日本の場合は絶対的5教科が優先でほかはオマケみたいな扱いで、たまに音楽やスポーツの優秀な人だけがその分野を選んでいける、公平ではない環境だと個人的には感じている。社会に出れば様々な分野の知識や経験をもっていることのほうが役立つことも多いし、この教育環境が日本の子供達にもあればいいのにと思う。
BTECの課題についても、日本なら大学生でやりそうな内容を中学生から与えるとは、ビジネスの実践的経験ができてとても良さそうだ。
それから選挙。
ちょうど12月の総選挙について触れているエピソードがいくつかあり、大人だけでなく息子くんたち中学生も選挙に注目しているのが単純にすごいなと感した。
親子で日常的に政治の話をしたり、学校の同級生同士で気候変動問題について論じ合ったり、テレビの党首討論を見ていたり、政治に対するフラットさというか身近さが日本とは全然違う。
日本では「若者の選挙離れ」と言われているが、そもそも成人になっていきなり選挙に行けと言われても、各党の動向の知り方も政策の読み方も教わってないのにどうすればいいんだという気持ちになることは想像できるだろう。基礎がないのだから。
この政治への関心の高さと身近さを日本でも実現できたら…。
「大人はちゃんとマニフェストを読んでないんじゃないの?」
息子くんのこの一言はなかなか出るものではないだろう。かっこいい。
好きなエピソードとして印象的だったのは、日本のじいちゃんとの別れの場面。感動するというより、ちょっと大人びた雰囲気で書かれている息子くんがちゃんと子供っぽく号泣してバイバイをしてるのに安心した。
日本とイギリス、こうしてみると結構違う。羨ましい部分もあればちょっと怖い部分もある。どこで暮らすかによって思考や人との接し方に差異が現れることを実感した。
自分は今のところはずっと日本にいるつもりだが、本から世界を知り、自分の知見と考え方を広げている。世界は広く、学ぶことは多い。
と、読み進めている時「この話の流れなんか知ってる...」と思い、図書館から借りた本だったので背表紙裏の貸出カードを見たらちょうど去年の同じ時期に借りていたことに気づいた。
2度目でも大変興味深い作品だった。
出典:『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー2』
ブレイディみかこ
新潮社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
