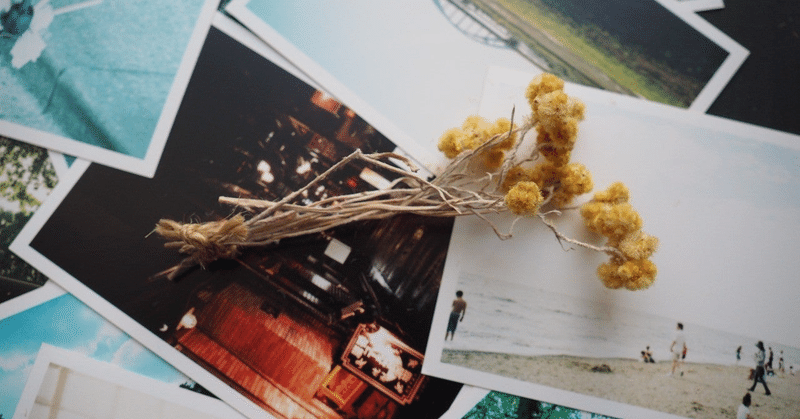
本当の共感は、マジョリティとマイノリティの枠を壊した先にある
最近、音声メディアにハマっている。聞いているチャンネルの一つが澤円さんのvoicyチャンネルだ。
先日、澤さんがADHDをテーマにお話をしていた。
「相手がADHDだと言っていても、私もADHDなんですと言わないようにしている」
私の周りにもADHDだということを伝えた上で普段の生活を送っている人がいる。だから、澤さんの言いたいことはなんとなく分かる気がした。
「自分が同じように言われて、傷ついたことがあるから」
澤さんは、理由をこう言っていた。
きっとこのエピソードは、ADHDに限った話ではない。共感というテーマで、誰にでもあてまはる話だ。
私だってと、言いたくなるとき
マジョリティとマイノリティという枠組みについて、知人と話すことがある。
「変わっているね、と言われることが多いから、そんな自分がコンプレックスで」
そう話す知人を見て、申し訳ないのだが、私はマイノリティだからどうこうの話じゃないのではと感じてしまう。
「あなたはどちらかと言うとマジョリティでしょう」
そう言われることもあるのだが、私はさらさらマジョリティだぞなんて胸を張ることはできない(というのが本音でも、たいていは相手が持っている基準において、私はマジョリティに分類されたことにして、何食わぬ顔で首を縦に振ってその場をやり過ごすのだが)
多数決の問題は、世界を二分すること
マジョリティとマイノリティという軸が生んでいる困難の一つは、共感できる人かという人間関係の課題だろう。
私はマジョリティだから、ちょっと変わり者なあの人はマイノリティで、私とは違う。
変わり者と言われる自分はマイノリティで、いい感じに環境へ溶け込めているこの人はマジョリティだから、自分とは違う。
この世界で地に足をつけて歩き回っている人間を、そう簡単に二分することはできるのだろうか。いや、できるかもしれないけれど、二分することって、本当に必要なことなのだろうか。二つなんて大雑把な分け方を、していいのだろうか。
多数決の良し悪しが議論される時にも、よくこの二分する怖さのようなものが取り立たされる。
数が多い方の選択を、全体の意志として結論づけていいのだろうか。マイノリティの声を聞かないことは、問題ではないだろうか。
ただ、この多数決におけるマジョリティ・マイノリティの決まり方は、単なる結論の違いの部分だろう。
結論が生まれる過程、つまりなぜその選択をしたかという部分には、マジョリティ・マイノリティ問わず、一人一人異なった意志が込められている。
A・Bどちらの選択肢が良いかという結論だけを見ると、数の多少でマジョリティ・マイノリティが生まれるのだけど、その手前に目を向けると、そんな二分できるほど単純な世界ではない。
だから、多数決の怖さはマイノリティの意思が反映されないシステムであること以上に、マジョリティ・マイノリティという軸で世の中を見てしまうことだと、私は思っている。
つまり、では表せない世界こそ、美しい
「つまり…」というフレーズが、私は苦手だ。
「私は〇〇だと思うので、方向性としてはAなのですが、Aだと全てを言い切れていない気もします」
という言葉に対して、
「でもつまり、Aだよね」
とまとめられてしまうと、うーんそうなんだけどそんな簡単に丸め込まないでくれと、フラストレーションが溜まってしまう。(本当に面倒な人だというのは重々承知なので、すんなり受け流してくれ自分と思う部分でもある)
話を前に進めるスキルとしては必要だ。特にチームとして目的にたどり着くためには、欠かせないキーワードだと思う。
けれど、私はそのつまりで言いくるめることができる細かい言葉の端々を、ちゃんと丸め込まずに生きていきたいのだ。
結論としてはAかもしれない。大雑把にはAだろう。
だけど、そのAという道に辿り着くまでに通った道やAという道の脇に細々とある小道の存在も、ちゃんと分かる努力をしたい。
もしかしたら、進もうと決めたAの道を世の中はマジョリティと噂するのかもしれない。でも、私はそんな聞こえのいいものじゃないぞと、世界はそんな簡単に二分できるものじゃないんだぞと、叫び続けていたい。
それはマジョリティじゃないと感じる人を傷つける可能性も大いにある。
そんなこと言ったって、あんたたちはマジョリティじゃないか、と。
澤さんが言うように、私たちも自分をマジョリティだとは思っていません、あなたと一緒ですと伝えることは、きっと誰も幸せにしない。その言葉はきっと、勘違いな共感だ。
だけど私は、マジョリティもマイノリティもこの世には存在しないんだと、信じてもらえるような言葉を、行動を紡いでいきたい。
本当の共感とは、言葉にしないことなのかもしれない。
言葉じゃなくて行動で伝えたり、少なくとも直接的に伝えるのではなく言葉の根っこにある心がつながることを願う姿勢が、本当の共感なのかもしれない。
マジョリティ・マイノリティという二分を超えて、本当の共感を手に入れることができたら、きっと私たちは今までよりもっとそのままの私たちで生きられるようになる。
そう信じ続けたらいつか、世界はもっと鮮やかで優しくなるだろうか。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
