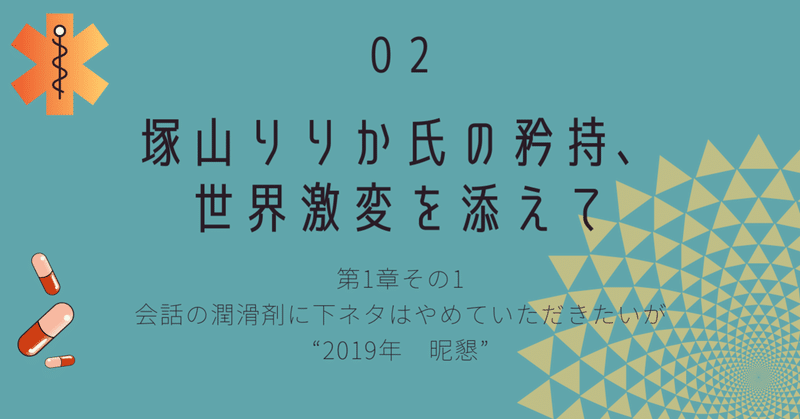
【小説】塚山りりか氏の矜持、世界激変を添えて:第1章その1「会話の潤滑剤に下ネタはやめていただきたいが」
“2019年 昵懇”
「おー、昨日はお疲れさーん。ちょうどつかやんが話題になってたとこだぜ」
翌日りりかが出勤すると、さっそく手術室の先輩である尾花静男が声をかけてきた。それともう1人、静男と一緒にいたのは昨日のあの修羅場で共闘したレジデントスタッフだ。名前を原久瑠偉と言うのだが、静男に色々とどんなに大変だったか話していたようだ。瑠偉は、りりかを認めるとまるで宴会場で会ったかのように声を上げた。
「つかやんお疲れー!いやー久々のでかい交通外傷で、アドレナリンびんびんになったねー!でも、俺たちならできるって信じてたぜ!」
と、なぜか最後の台詞は静男と瑠偉でハモりながらハイタッチをしてきたので、りりかも少し楽しくなってハイタッチを返した。それでさらに静男が盛り上がった。この男は手術室看護師いち声が大きいので、聞きつけた手術室の看護師たちが何事かとやって来た。するとまた昨日の緊急手術がいかにスリルに満ちたものだったか瑠偉が語り出すのであった。そしてりりかがまたハイタッチに応じると、
「おっぱい?ちんちん?」
そんな声が割り込んできた。しかもご丁寧にハイタッチに手を添えてきた。
「おー!下根先生!元気でしたか?」
静男が、この割り込んできた中年よりは若い、坊主頭の無精髭を生やしメガネをかけた、麻酔科医の下根太郎に歓迎の声を上げた。瑠偉、りりか、他の看護師も喜んでこれに加わった。下根は実にわざとらしく照れ笑いをして見せ、僕のおニューのパンツみる?と言ってズボンを下げ始めた。下根がとりあえずコミュニケーションを始める時の常套手段だった。いえ、結構です!という声と、派手なパンツだね!という声が混ざった。
さて、下根太郎はこの病院の手術室を鍛え上げた麻酔科医だ。この病院はグループ病院の中で、どちらかというと田舎に立地し、そこまで大規模でもなく、かといって小規模でもない、しかし急性期病院らしい忙しさはある。だが、それこそテレビで特集が組まれる様な最先端の治療などを提供できる人材が揃ってはいない病院だ。下根は、そんな場所でどうしてこんな一流の腕を持つ医者が働いているのだろうと思わされる実力の持ち主である。だが、彼の人となりを知れば納得もいく。この男はとにかく人が好きなのだ。誰よりも患者のことを思い、一緒に働くスタッフをチームとして盛り立てていく。それができるのも、ほどよい田舎の距離感だからなのだろう。
その実力がとかく発揮されるのが危機的状況においてだ。こんな事があった。ある時交通外傷で、正常だった位置が分からないほどの多発骨折、どこが出血しているのかも分からないほどの内臓損傷が疑われる患者が運び込まれてきた。当然、緊急手術となりこのような事態に対応するスタッフはたいてい慌て、どんどん興奮していく。
だが、その中で下根太郎は終始冷静に的確な指示を出していた。しかも患者の容態を鋭く先読みし、他のスタッフが患者の異変に気づく頃には必要な薬剤は全て揃えていて、そして投薬をすでに始めているのだ。
下根太郎が麻酔を担当するなら絶対に大丈夫だ。手術室看護師の誰もが口に出さずとも思っていた。だから、彼がこの病院を退職する時は誰もが引き止めたいと思ったが、家庭の事情であれば仕方がなかった。とはいえ、こうして月に一度は手伝いー応援ーに来てくれているのだからありがたい。
「先生、ズボン履いてパンツしまって!はい、どうも。ところでお子さんと奥さんは元気?」
最後にやってきたベテラン看護師で看護主任の熊田が声をかけた。下根は熊田さんじゃないですかーと言いながら彼女に抱きつき、熊田は応じつつセクハラだキャーと言うのがいつもの流れだ。
「元気ですよ、ええ」
「いくつになったの?」
「4歳です。最近は父親の真似をして、おっぱいとよく言うようになりました。我が子ながら立派にそだってます。そーいえば、春日はどうですか?」
「あー、斉藤先生は最近調子が良くないようで、先週から休みがちですね」
斉藤春日は下根がよく面倒をみていた麻酔科医で、以前からメンタルを病んでいた。
「んーなるほど…あいつに足りないのは、いいお尻ですね。ええ、間違いない」
つらつらと真面目そうに下根が話すので、その様子に、看護師たちは笑い合ってそれぞれにツッコミをいれ、それから思い出したように、手術の準備をするために散って行った。
昵懇…親しく交わること。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
