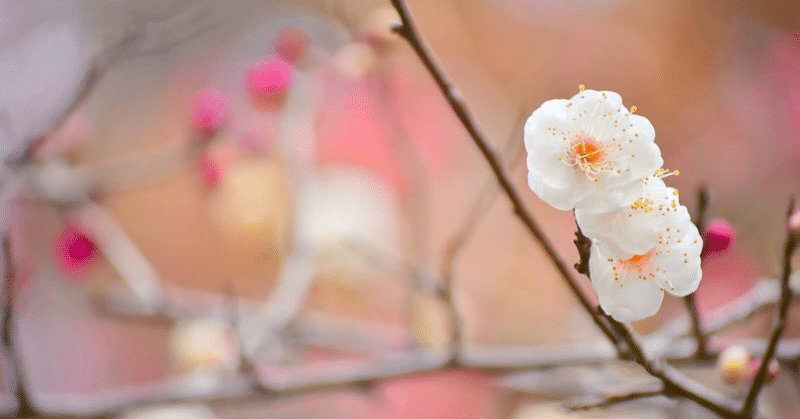
紀ノ川
有吉佐和子さんの小説「紀ノ川」を読了。
「小さな川の流れを呑みこんでしだいに大きくなっていく紀ノ川のように、男のいのちを吸収しながらたくましく生きる女たち。紀州和歌山の素封家を舞台に、明治・大正・昭和三代の女たちの系譜をたどった年代記的長編」という裏表紙の内容紹介に惹かれて。
女性の生き様や時代の流れを紀の川になぞらえる。
祖母の豊乃と嫁入りを控えた花がお寺の石段をのぼるところから物語は始まるが、頁をめくって早々に泣いてしまったのはこの小説がはじめてに思う。
豊乃が花に贈ることばが慈しみに満ちて美しく、胸が締め付けられるようで。
豊乃や花など登場人物の女性は、教養豊かで聡明で、つつましやか。決してやかましく物申すことはないのだが、周囲はその存在を目の前にすると息をのんでしまうほど。
なので、ここで描かれる女性像からしても小説全体を通して「強い」という印象も受けたけど、品のある紀州弁や着物の繊細な描写によって柔らかさも色濃く、読み進めながら何度も「麗しい」とうっとりした。
「お前はんのお母さんは、それやな。云うてみれば紀ノ川や。悠々と流れよって、見かけは静かで優しゅうて、色も青うて美しい。やけど、水流に添う弱い川は全部自分に包含する気や。そのかわり見込みのある強い川には、全体で流れこむ気魄がある。」
ここで男性や女性と一括りにするのはわたしの稚拙な考えだけど、実体験で、男性はしばしばわたしを搾取した気になっているのではと感じることがあった。
女性のしたたかさに気付かず、実は搾取されているのはそちらかもしれないのにね、と。
明治は10代も半ばを過ぎれば女性は嫁入りするのが当たり前。
令和の今は、わたしが大学生の頃にはなかなか耳にすることのなかったフリーランスという働き方もめずらしいものではなくなり、必ずしも決まったレールが用意されていないというのも自由の祝福だと思うが、わたしも明治に生まれて早々に嫁入りして家内として全うする人生だったらと考えたこともある。自由はときに人を苦しめる。しかし、聖徳太子が「世間虚仮」という言葉を残してこの世を去ったように、どの時代にも絶望があるということもわかっている。
紀の川を船で、駕籠にのって。
花の明治の嫁入り、優艶で素敵だったな。
カチャンという、望遠鏡のレンズの蓋が閉まる音で物語は終わる。
読み終えて、しばらく頭の中でカチャンという音が響き渡り離れなかった。
希望なのか絶望なのか、どちらでもあり、どちらでもない。
紀ノ川は昭和34年に発表された小説。
有吉佐和子さんは30歳を目前に紀ノ川を執筆されたということになる。
20代の若さで、老齢の心境をまざまざと描写する有吉佐和子さんの才能にただただ恐れ入るばかり。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
