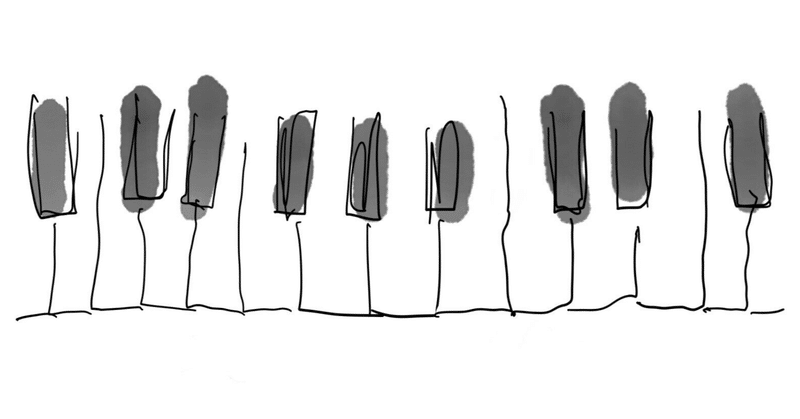
【短編小説】娘がピアノを辞めた日
「ごあいさつをします」
トイストーリーのエプロンを付けた芳香先生は、大げさに気を付けのポーズをとって背筋を伸ばした。
「みなさん、ごいっしょに、さようなら」
芳香先生の「さようなら」に合わせるように園児たちも「さよぉーなら」と、小さい頭を突き出すようにお辞儀をする。
化粧っけのない日焼けした芳香先生の顔にはニコニコという効果音がぴったりな笑顔が張り付けている。芳香先生は帰りの挨拶を終えるとバスに乗り込んだ。手を振る芳香先生を乗せたバスを見送って、私の右横に立っていた紗羽は公園のベンチに幼稚園カバンのリュックを置く。
「ママ、あそぶー」
紗羽は担いでいた自分のリュックを下すと、体が自由に開放されたのか公園の遊具に向かい軽やかに駆けていった。
ベンチに置かれた紗羽のリュックを開け、中身を確認する。幼稚園からのお便りは入っていない。漏らしたパンツやズボンも入っていないようだった。リュックには給食の時に使うフォークやスプーンを入れた巾着袋が入っている。
リュックの底に緑色の折り紙の端が見える。中敷きの下に挟まっている折り紙を引っ張ると、帰りのバスを待っている時間にでも作ったのか、無造作に折られた折り紙に大量のセロハンテープが張られた工作物だった。
工作物をしまい直し、リュックを閉め、紗羽の小さいリュックを自分の左肩に担いだ。パステルカラーの花柄の小さな水筒を左腕にぶらさげて腕を組み、滑り台にいる紗羽の方へ体を向ける。
今日は火曜日。
先週、先々週と莉菜ちゃんとかすみちゃんは火曜日がピアノのレッスンだった。私の予想通りなら、おそらく火曜日の今日も先週に引き続き莉菜ちゃんとかすみちゃんはピアノのレッスンのはずだ。
「りーなー。今日、ピアノ。帰るよー」
私が期待した側から莉菜ちゃんママが滑り台の近くにいる莉菜ちゃんに声をかけた。
「かすみもー。ピアノだから帰ろう」
莉菜ちゃんママのかけ声に続くように、かすみちゃんママもかすみちゃんに声をかける。
「じゃあねー。バイバーイ」
莉菜ちゃんとかすみちゃんが手を振る。莉菜ちゃんたちの近くにいる紗羽も手を振り返す。
「おつかれー。お先でーす」
莉菜ちゃんママとかすみちゃんママも母親の私たちに声をかけた。4人揃って公園の出口に向かう。
莉菜ちゃんたちの集団が帰ると、私はぐるりと首だけ180度動かすと、今日の公園に残っている母親たちを確認した。
紗羽と同じ年少組の康太くんのママは公園のベンチの近くに立っている。背中を丸め、スマホを見ている。きっとTwitterを見ているのだろう。康太くんママは帰りの幼稚園バスを待っている間も、ずっとTwitterをチェックしていた。華奢な体を猫背に丸め、公園のベンチの横でひたすらスマホをスクロールしている。
康太くんママには、紗羽と同じ年少の康太くんの上に小学2年生になったお姉ちゃんがいた。幼稚園が夏休みに入る前の今年の7月、康太くんママから、康太くんのお姉ちゃんの洋服や水着を紗羽にお下がりでもらうことになった。
「紗羽ちゃんママ。もしよかったら、洋服渡す日、うちでちょっとお茶しいひん?」
お下がりをもらうついでに康太くんママのお家にお邪魔した。康太くんママのお家でお呼ばれされた時、初めて康太くんママと【きちんと】話をした。
康太くんママのアクセントから康太くんママの出身は関西なのかと聞くと「そう。うちは兵庫、旦那は大阪」と康太くんママは答えた。康太くんママの出身地の話の流れから、旦那さんの転勤で2年前からこっちの東京に引っ越してきたのだと康太くんママは続けた。
「紗羽ちゃんママは? 元々、東京なん?」
「うん。私も旦那も出身がこっちで、私の実家は電車で15分くらいのところ」
「へぇ、そうなんや」と康太くんママは二回頷くと、「実家が近いの、ええなぁ」と大げさに肩を落とした。
「うち、【イエバ】のめっちゃファンやから実家近かったらライブ行きたい時とか、子どもら預けられるし、めっちゃ羨ましいわ」
ちょっと待ってな、と言うと康太くんママは立ち上がり、リビングの後ろの本棚から雑誌を数冊持ってきた。
韓国のアイドルグループ【イエローバック】が表紙を飾っている雑誌をペラペラとめくると、康太くんママは青髪の男の子を指差した。
「うちの推し、ケイ。むっちゃ、可愛くない?」
友達に彼氏の写真を見せられた時のような反射神経を使って、私は間髪入れずに「本当だー、かっこいい。イエバ、今すごい人気だよね」と、身を乗り出してみせた。
「うち、イエバがこんな人気になる前から知っててんで」
「すごーい。じゃぁ、古参ファンだ」
「そう。イエバ、古参やね」
私の反応に康太くんママは満足そうに頷きながら笑った。
見てもええよ、と康太くんママは自分が持っている雑誌を私に差し出す。
「見ていいの?」私は嬉しそうに見えるようにわざと一言断りを入れて、雑誌を受け取った。
ペラ、ペラと、ページをめくる。
イエバのメンバーがカメラ目線でポーズを決めてこっちを見ている。どれも全員同じ顔に見える。美容室でカットしてもらっている時、担当の美容師と会話をしないのも気まずいのでとりあえず目の前にあった雑誌を手に取った時のような感覚で私は康太くんママから差し出された雑誌を眺め続ける。
「イエバ古参」康太くんママの推し、青髪のケイと目を合わせながら、私は声に出さずに胸の中でそう呟く。
康太くんママの家にお呼ばれしたその日の夜、旦那の覚くんに康太くんママのことを話すと、私はごくごくナチュラルに康太くんママのことを【イエバ古参】というあだ名で呼んでいた。
幼稚園バスの停車場所が公園の前になってしまったことを嬉しく思わない保護者は、きっと私だけではないはずだ。私は子どもが遊んでいる様子をただ見守っているこの時間が子育ての中で一番苦痛だった。いや、見守る作業が苦痛ではないのかもしれない。子どもを見守る延長の先にある、母親同士の会話も立派な子育ての一環になっているのが嫌なんだ。嫌だけど、ものすごく嫌なんだけど、大人と無性に話したい日もあって、嫌な相手なのに会話を求めてしまう自分にも嫌気がさす。
康太くんが私の前を横切って、紗羽がいる滑り台に向かって走っていった。走った勢いを付けたまま、康太くんは滑り台を逆走するように登る。滑り台の下から登ってくる康太くんとちょうど上から滑ってきた紗羽が滑り台の真ん中でぶつかった。上から滑ってきた紗羽が康太くんを足で玉突きのように押し出すと、押し出された康太くんは豪快にバランスを崩して紗羽に覆いかぶさった拍子に滑り台に軽く頭をぶつけた。
「大丈夫?」滑り台の近くにいた私はとっさに二人に駆け寄る。
内心はいきなり康太くんに覆いかぶさられた紗羽を心配して駆け寄ったが、康太くんのことも気にかけているように、交互に二人の名前を呼んでケガがないか声をかけた。
何でもなかったかのように康太くんは滑り台から離れ、砂場の方へ行ってしまった。
駆けていく康太くんを目で追った後、私は【イエバ古参】に視線を向ける。イエバ古参はさっきと変わらない姿勢のままスマホを覗いている。情報収集のためSNSで推しの投稿やファン同士の情報を読み漁っているイエバ古参の姿は気軽に声を掛けられない雰囲気を漂わせていた。
紗羽も再び遊び始め、何事もなかったかのように滑り台の階段を登っている。
私も滑り台から離れ、さっき立っていた場所に戻った。戻る途中でちーちゃんママと目が合った。
「今日、寒いねぇ」
ちーちゃんママは肩をすくめる仕草をして、私に困ったような笑顔で話しかけた。
「ねぇ。今日、こんなに寒くなるならパーカー着てくればよかった」
私もちーちゃんママに同調して寒そうに両腕をさすってみせた。
ちーちゃんママはいつも笑顔を持ち合わせている人だった。笑わない人よりは笑っている人の方がいい。笑顔とは多い方がより良いと言われているけれど、ちーちゃんママの笑顔はどこか隙が無いようで却って人間らしくない。
「明日は、今日よりももっと気温が下がるみたいだよ」
ちーちゃんママは羽織っているカーディガンの前を抱きしめるように腕を組み直した。
「そうなの?」いかにも初耳でした、というようなニュアンスで私はちーちゃんママに顔を向けた。
「そう。さっきテレビで天気予報見たら言ってた」
「あ、そうなんだ。知らなかった」
終始、私は少し大げさに驚いたようなリアクションを取ってみせた。本当は明日から今週いっぱいまで気温が下がることを私は知っていたけれど、知らないふりをしてもしなくてもどっちでもいい会話の時はいつも知らない振りをする方が楽だった。
ちーちゃんママとの天気の話は、最近幼稚園で喉の風邪が流行っているんだとか何度話しただろう、そういう話に変わった。「季節の変わり目は体調崩すよね」いつも通りの天気の話の終わりに着地する。
天気の話が終わり、ちーちゃんママとの間に一瞬の沈黙が流れると私は口を開いた。
「ちーちゃんって、莉菜ちゃんとかすみちゃんと同じピアノ教室だよね? 莉菜ちゃんとかすみちゃんは同じ時間に一緒にレッスンしてるみたいだけど、ちーちゃんは莉菜ちゃんたちと同じ時間にレッスンはしないの?」
「千紘は姉の愛花(まなか)と一緒の時間にレッスンしてるんだ。だから莉菜ちゃんたちとはレッスン別なんだよね」
「へぇ。そうなんだ」
考えるように私は一拍置く。
「ちーちゃんたちが行ってるピアノ教室って、かすみちゃん家のマンションの向かいのお宅だよね?」
「そうそう。かすみちゃん家のね、お向かいさんの芦川ピアノ教室」
ちーちゃんママは、頷きながら斜め左後ろのかすみちゃん家のマンションの方角を指さした。
「紗羽ちゃんは、何か習い事してるんだっけ?」
ちーちゃんママに聞かれ、私は腕を組み直し少し悩むような顔を作った。
「習い事ねぇ。何かさせたいとは思っているんだけど、何にしようか悩み中なんだ」
「そうだよねー。悩むよねー」
わかる、わかる、とちーちゃんママは頷いて話を続ける。
「ピアノ、いいよー。指先使うし、リズム感も鍛えられるし、女の子にはピアノ習わせた方がいいよー」
いつもの張り付いた笑顔を崩さず、ちーちゃんママは自分で自分の言葉に頷く。
別に男の子がピアノ習ってもいいじゃん。ちくりと私は胸の中で毒付く。何かと性別で物事を判断する人の発言が引っかかる。引っかかるが、口にはしない。それがママ友の【ルール】だから。ちーちゃんママの笑顔は他者の反論を受け付けない拒否感が滲み出ている。
「私も小さい頃ピアノやってたんだ。紗羽も時々ピアノを弾く真似とかするし、ピアノ自体には興味あると思うんだけど」
ちーちゃんママの【女の子】の部分には触れず、けれど私はピアノという話題を逸らすことなく話を続けた。紗羽に視線を向けると、紗羽はいつの間にかちーちゃんと砂場で一緒に遊んでいる。年長組のちーちゃんは、年上のお姉さんらしく紗羽に優しく遊びを教えていた。ちーちゃんが時々母親の私たちをチラチラと確認しながら紗羽に優しく諭すように話す姿は、嫌な言い方をすれば「優しいお姉さん」を演じているようにも見える。
「バイバーイ」
康太くんの声がする。声の方に振り返ると、公園の出口で康太くんとイエバ古参が手を振っていた。康太くんたちに手を振り返す。康太くんたちが見えなくなると、私は首から下げていたスマホを手に取り時間を確認した。
※
「紗羽、今日ピアノ。今日は公園で遊ばないよ」
幼稚園バスから降りてきた紗羽に私は声をかけた。ピアノと聞いて、紗羽はリュックを下す手を止める。他の子に挨拶をして紗羽と私は一緒に公園を出た。
結局、紗羽が年中に上がるタイミングで、紗羽もちーちゃんや莉恵ちゃんたちが通うピアノ教室に習うことになった。紗羽が年中に上がると、莉恵ちゃんやかすみちゃん、ちーちゃんたちの年長組は卒園して小学校に上がった。ちーちゃんママから、かすみちゃん家のマンションの向かいの芦川ピアノ教室を紹介してもらった。体験レッスンを受け、その後ピアノも購入した。ピアノと言っても電子ピアノではあるが、キーボードのような簡易的な物ではなく、そこそこ値段が張る電子ピアノを購入した。
はじめ、紗羽にピアノを習わせるか夫の覚くんに相談した時、覚くんは渋い顔で「ピアノかー」と手の平で顎を擦っただけだった。
「紗羽、誕生日にアンパンマンのピアノのおもちゃ欲しいってねだったことあったじゃない? 幼稚園でも先生がピアノ弾いているのを見ているからか、よくピアノを弾く真似もしているし。それにピアノは脳科学的にも良いって聞いたよ」
説明や説得というより私は言い訳をしているように言葉を並べる。
「本人が、紗羽がやりたいならいいんじゃない」
覚くんはスマホを眺めながら答えた。スマホを見ている覚くんに私が不満な視線を送ると、「ピアノって結構高いんだな」とスマホの画面をこちらに見せてきた。
「遥の実家にまだ電子ピアノってあるんだっけ?」
「もうないよ。私が小さい頃使ってたピアノは壊れて、二年前実家がリフォームする時に処分したって」
「あー、そっか。もしまだ使えたら貰えたのにね。そういえば、遥も昔ピアノやってたんだよね」
「うん。小一から中一の途中まで」
「今も弾けるの?」
「全然」
ダメじゃんそれ、と覚くんはスマホでピアノを調べながら笑った。
ピアノをやっていた頃、私はほとんどピアノの練習をしない子だった。前の週にピアノのレッスンでピアノを触ってから、だいたい次にピアノを触るのは次のレッスンの時だった。ピアノをやっていて楽しいと思ったことはほとんどなかった。放課後は友達と缶蹴りや砂遊びをしている方が楽しかったけれど、二歳年上のお姉ちゃんもピアノを習っていたし、ピアノは何となくやるものだと小学生ながらに思っていた。
ピアノを習い始めて一年程経った。私は小学二年生になった。私が通うピアノ教室は子どもの足で15分くらいのお宅にあった。普段は自転車に乗ってレッスンに行くが、雨の日は自転車に乗ってはいけないとお母さんから言われていたので、その日私は自転車には乗らず歩いてピアノの先生の家へ向かった。
いつものようにろくに練習なんてしていない私は、途切れ途切れで曲にも聴こえないような下手くそな演奏をしてレッスンを受けていた。ピアノの鍵盤の上に置かれた自分の指先を見ると、さっきピアノに来る前に食べたお菓子のカールのカスが爪の間に詰まっている。指先からほのかにチーズの匂いがした。
レッスンの途中で後ろのドアが開く音がした。誰かが部屋に入ってくるのが分かった。「カンナちゃん、座って待ってて」
先生が私の背中で後ろに声をかける。思わず私も振り返ると、レッスンの部屋のソファーの横に幼稚園が一緒だったカンナちゃんが立っていた。
カンナちゃんとは幼稚園を卒業してから久しぶりの再会だった。カンナちゃんと私は幼稚園最後の年長のクラスが同じでよく一緒に遊んだ。卒園すると、カンナちゃんと私は別々の小学校になって疎遠になった。
雨だからかいつもより早めにレッスンに来たカンナちゃんは自分のレッスンが始まるまで三人掛けのソファーで待っていた。
「じゃぁ、遥ちゃんさっきの続きから」
先生に促され、レッスンが再開する。背中にカンナちゃんの気配を感じる。いつもレッスンは私と先生の二人きりだから、自分のレッスンを誰かに見られているのは変な緊張がした。私はさっきと変わらず途切れ途切れに演奏を弾く。テンポも遅い。楽譜も読めない。楽譜が読めないから途中で鍵盤から手を離し、楽譜の音符の「ファ」から順にソ、ラ、シと指でなぞって音符を読む。
「今日はここまで。よくがんばりました」
レッスンが終わり、私は小さい声で「ありがとうございました」と先生にお辞儀をした。ピアノの上の楽譜の教本を片付け、教本を椅子の横に置いたピアノのバッグに入れる。私と入れ替わるようにカンナちゃんがピアノの椅子に座った。
恥ずかしかった。私と同時期にピアノを習い始めたカンナちゃんに自分の下手くそな演奏を聴かれたのも、音符の「シ」すら、すんなり読めなくて、読める「ファ」から順にカールが詰まった指先で楽譜をなぞる姿を見られたのも、全部、恥ずかしかった。
「遥ちゃん、バイバイ」
ピアノの椅子に座ったカンナちゃんは振り返って私に小さく手を振った。私は先生とカンナちゃんに挨拶をして部屋を出た。ピアノの先生の家は一軒家で、レッスンの部屋は二階にあった。私はドアを閉め、玄関へ向かう。階段を降りる途中で、カンナちゃんの滑らかなピアノの音色が部屋から漏れる。私の知らない曲だった。カンナちゃんは今私がやっている教本なんて、とっくの前に終わっているのだと知った。
玄関で自分の靴を履く。玄関の上がり框に座り込み右足から片方ずつ靴を履くと、泥だらけの私のスニーカーの右横に黒のコーデュロイ素材の小さなショートブーツが並んでいた。今日カンナちゃんが着ていた、襟元にレースが付いたこげ茶色のワンピースによく似合いそうな可愛らしい黒のショートブーツだった。黒のコーデュロイのショートブーツの右横には傘の雫でできた小さな水溜まりがあった。カンナちゃんの上手なピアノの音色が玄関まで私の耳に届く。私は、まだ雨の雫が残る自分の傘を手に取った。手にした傘でそっとコーデュロイのショートブーツの右靴を小さな水溜まりの方へ倒す。ブーツの右側面が水溜まりに浸っていくのを見届ける。私は玄関のドアを勢いよく開け外へ出た。カンナちゃんのピアノの音はもう聞こえてこない。雨はもう上がっていた。
カンナちゃんのショートブーツを水溜まりに浸した日から私は劇的にピアノの練習に励むわけでもなかった。それでもピアノの発表会が近づけばそれなりに一生懸命練習をするようにはなった。
その後、私が小学4年生になると引っ越しをすることになり、カンナちゃんも通っていたピアノ教室を辞めることになった。お姉ちゃんは引っ越しのタイミングでピアノ自体を辞め、引っ越し先でレッスンに通うこともなくなった。私といえば、姉と一緒に私もピアノを辞めるとはなぜかならなくて、私はピアノを続けることになった。別に両親から強制的にピアノをやりなさいと圧力があった訳でもない。私にとってピアノは、絶対に辞めたい、とか、絶対に続けたい、とか、そういう強い思いを抱くものではなかった。
「て、ことは志田ちゃんに出会ったのは遥が転校した先の小学校だったの?」
覚くんはカンナちゃんの話を聞き終えると、整理するように私に聞き返した。
「そうだよ。志田ちゃんとは転校先の小学校で一緒だったんだよ」
「そうなんだ。俺、ずっと勘違いしてたわ。志田ちゃんって前の小学校が一緒の子だと思ってた」
覚くんは納得するように頷いて、話の続きを促した。
私が小学4年生の時に転校した小学校に、6年生の二学期に志田さんという女の子が転校してきた。夏休み開けの二学期。黒板の前で6年一組の担任の先生と並んで自己紹介をする転校生の志田さんはよく笑う子だった。
「志田ちゃん、ピアノ弾いて」
放課後、小学校から一旦家に帰り、私は志田ちゃんの家に遊びに行った。志田ちゃんの部屋に入るとアップライトピアノが置いてあった。
志田ちゃんもピアノを小一からやっていることは志田ちゃんが転校してきてすぐに知った。
志田ちゃんは私にピアノをせがまれ、重厚感のあるアップライトピアノの蓋を開けた。ピアノの椅子に浅く座り、鍵盤の上にふわりと手を置いた。さっきまでの笑顔が消え、スッと志田ちゃんの顔が引き締まる。志田ちゃんがピアノの椅子に座ってから鍵盤に手を置くまでの一連の動作は、まるで太極拳のような滑らかな所作だった。
志田ちゃんが弾いた曲は、モーツァルトのトルコ行進曲という曲だった。飛び跳ねているような指使いでアップテンポに曲が始まる。テンポはどんどん進んでいき、指を素早く細やかに動かしているかと思えば、5本の指を目一杯広げてお菓子のつかみ取りをするように力強く鍵盤を叩いたメロディーに変わる。曲のリズムはあれよ、あれよと目まぐるしく変わっていった。最後、この曲の一番の盛り上がりに達すると、曲が終わった。志田ちゃんの指がまたふわりと鍵盤から離れて膝の上に着地した。私はスタンディングオベーションをした。志田ちゃんのピアノの迫力に感動して、ぴょんぴょん飛び跳ねながら私は全力で拍手を送った。
「志田ちゃん、すっごい。マジで、そんけーする」
興奮して私は目を見開き、唾を飛ばしながら声に抑揚を付けて褒め言葉を繰り返した。志田ちゃんは私の褒め言葉を聞きながらいつもの笑顔を見せた。
小学生の頃、今まで友達を尊敬の対象として見たことがなかった。尊敬という言葉の意味もまだきちんと説明もできなかった頃、尊敬とはもっと仰々しいものだと思っていた。自分には到底できないことを成し遂げている誰かの姿は大きく心を動かされるのだと知った。大きく動かされた心は、シンプルに尊敬という言葉に変換された。
志田ちゃんにトルコ行進曲を弾いてもらった日から、私は何度も何度も志田ちゃんにピアノを弾いてもらった。志田ちゃんは私がいくらピアノの演奏をせがんでも、一度も嫌な顔を見せたことはなかった。私の知らない曲を志田ちゃんはたくさん弾いてくれた。反対に志田ちゃんが知らない曲でも、私の鼻歌を聴いて志田ちゃんはすぐに再現して弾いてくれた。志田ちゃんが私の家に遊びに来た時も必ずピアノを弾いてもらった。うちの電子ピアノには録音機能が付いていたので、志田ちゃんのトルコ行進曲を録音させてもらった。志田ちゃんが帰った後も、私は志田ちゃんのトルコ行進曲を聴いた。
志田ちゃんは息をするようにピアノを弾く人だった。バスケットボール選手がボールを扱う時にボールが自分の手に懐いているような仕草と同じく、志田ちゃんとピアノは一体だった。私は志田ちゃんが弾く、トルコ行進曲が好きだった。トルコ行進曲以外にもたくさんの曲を弾いてもらったけれど、初めて志田ちゃんにピアノを弾いてもらったトルコ行進曲は私にとって特別な曲だった。
志田ちゃんと私は小学校を卒業するまでの間に、今まで出会わなかった年月を埋め尽くすかのように急速に濃密に仲良くなった。毎日交換ノートを書いた。小学校を卒業するまでに書いた交換ノートの数は全部で10冊になった。志田ちゃんは、いつも私が書く交換ノートをおもしろいと言って褒めてくれた。
「遥が書く交換ノートを読むと本当に涙が出るくらい笑えておもしろい」
そう感想を教えてくれる時も、志田ちゃんは目尻を抑えながら笑ってくれた。志田ちゃんは私との交換ノートをおもしろいと言ってくれたけれど、私が書く文章に人を惹きつけるようなfunnyな表現がある訳でもなく、知的で雑学のような興味深さがあるわけでもなかった。いつも私の文章は誤字脱字だらけだったし、話があちこちに脱線しながら私の近況報告を、二人の交換ノートだけに登場してくる架空のキャラクターたちに喋らせているだけだった。私が作ったキャラたちは交換ノート内でずっと内容の無い話を喋り続けた。ミツバチの可愛らしいイラストの『ミツバチマーチのまー子』はとにかく毒舌口調でテレビドラマの感想をダラダラと話した。眼鏡におかっぱ頭の『ハナシ変わる君』が登場すると、脈略なく突然話が変わって『今日の名言』を唱えた。雑貨屋などで売られているような交換ノートではなく、ただの無地のノートを使って数ページに渡って私たちはただ自分の思うままに書き綴った。「私はこんなにおもしろいこと書けない」志田ちゃんは交換ノートの話になると必ずこう言って私を褒めてくれた。私にとってごく普通なことを書いているつもりでも、こんなに誰かが喜んでくれたのは初めてだった。
小学校生活が終わりに近づくと、小学校で最後の〇〇が怒涛に続いた。最後の体育、最後の図工、最後の給食。3月のはじめ、10冊目の交換ノートを休み時間に志田ちゃんから渡された。いつもなら家に帰ってから読むけれど、なぜかその日は掃除の時間に読んでしまった。交換ノートを読み進めると、志田ちゃんが4月に引っ越すことになり同じ中学校へは行けないことが綴られていた。私はすぐに志田ちゃんの掃除場所を確認した。志田ちゃんの4班は図工室が掃除当番だった。走ってはいけない廊下を全力で走った。心臓が波打つように全身に血が巡った。私は階段を下りて一階の図工室のドアを開けた。図工室に入ってきた私の顔を見て、志田ちゃんは持っていた長柄ほうきに掴まるように体を支えながらその場にしゃがみこんだ。
「なんで」
私の一言に、志田ちゃんは「ごめん」と潤んだ声で言った。
※
「志田ちゃんとは、期間で言えばトータル半年くらいしか一緒にいなかったんだよね。小6の二学期の九月から卒業の三月までしか一緒の学校じゃなかったから」
私は指を折って志田ちゃんとの学校生活の年月を数えた。前にも覚くんに志田ちゃんの話をしたことはあるけれど、こんなに詳しく思い出話をしたのは初めてかもしれない。
「志田ちゃん、私たちの結婚式にも来てくれたんだよね」
「ちょうどオーストラリアから帰って来てたんだっけ?」
「オーストラリアじゃない。オーストリアね」
覚くんの間違いを訂正して、私は正解を強調する。
「志田ちゃん、大学は日本の音大に入って、卒業してから一旦は就職したんだけど、やっぱりヨーロッパでピアノの勉強をしたいって言って、お金貯めてオーストリアに留学に行ったの。そこでハンガリー人の今の旦那さんと出会って2年前かな、結婚して。今はオーストリアでピアノの先生してるんだよ」
私の説明に「すごいね」と覚くんは頷いた。それなら、と覚くんは言葉を続ける。覚くんの表情は、揶揄する時のニタニタという笑顔に変わっていた。
「それなら、志田ちゃんは遥がヤンキーだった中学時代を知らないわけだ」
「待って。私はヤンキーじゃないから。私はただヤンキーの男の子と付き合ってただけだから」
覚くんのいつもの元ヤンいじりに飽きて私は小さく笑った。「明日早いからもう寝るね」時計を見ると11時を過ぎている。明日、紗羽のお弁当の日に合わせて私は早めにベッドに入った。ベッドの中で目をつぶると、さっき覚くんにいじられた中学時代を思い出す。紗羽のピアノの習い事なのに、思い出すのは私のピアノの思い出ばかりだ。
「ベートーヴェンのエリーゼのためにを弾けるようになったらピアノを辞めます」
次の四月で中学生になる小6の春休みに、私はピアノの先生にそう宣言した。
なんでベートーヴェンのエリーゼのためになの、と聞かれてもベートーヴェンにもエリーゼにも深い思い入れなんてなかったから何となくとしか言いようがなかったけれど、中学生になったらピアノは辞めようとは思っていた。辞めようとは思っていたけど、中学生になったからという理由だけで辞めるのはなんだか味気ない気もした。「けじめ」なんて言葉を使うと、それこそヤンキーみたいで嫌だけど、自分で決めた楽曲を弾けるようになったらピアノを辞めるというのは、私なりのピアノに対するけじめだった。
小6の春休みから中一の夏休み前までにエリーゼのためにを完全コンプリートして弾けるようになった。毎年大ホールでやる、夏の発表会には出なかったけれど、ピアノ教室の数人の生徒だけを集めた近所の文化センターで行われるお披露目演奏会で私はエリーゼのためにを演奏した。そして、私は晴れてピアノを辞めた。それから、ピアノを辞めた同時期くらいから私はテニス部で部活に励んでいった。
中二、中三になると私は少しずつヤンキーと呼ばれるような子たちとも仲良くなった。私は決してヤンキーではなかったが、他校の生徒と喧嘩した次の日に眼帯をしてくるような女の子たちとも友達だった。生徒会委員をやるような、成績が良くて真面目な子とも友達だったけれど、自分が好きな科目の英語しか勉強しなかった私は、成績で見るとヤンキーの子たちと同じ部類にされてしまったようだった。
中二の終わり頃、学年で目立つヤンキーの塚田くんとも付き合った。塚田くんと私は放課後になると川沿いの土手で一緒に時間を過ごした。私と一緒にいる放課後、よく塚田くんのガラケーには喧嘩の応戦の連絡が来ていた。私は塚田くんのことがちゃんと好きだった。だから、私と一緒にいる時は喧嘩に行かないで私と一緒にいてほしかった。
「やっさんが西中の奴らに喧嘩売られたって言うから今から西公園行ってくるわ」
パチンと派手に音を立て、塚田くんはガラケーを畳んだ。
「……喧嘩売っただの売られただの、ホントくだらない。話し合いで解決しないことは暴力ではもっと解決できないんだよ」
真っ当なようで綺麗ごとの理想論を振りかざし私は塚田くんを責め立てた。
話し合いで解決しないことを暴力で解決させる手段を選ぶのは、ヤンキーに限った話ではない。大の大人でも話し合いで解決できなくて戦争だって起きているのだから。中学生の私と塚田くんが今こうして土手で言い合っている間も、世界ではイラク戦争は起こっているし、東京の下町のヤンキーたちはガン飛ばされたなんだのとどっかの公園で喧嘩をしている。当時、中学生の私は好きな人に可愛く「行かないで」と素直な一言が言えなかった。
「学校の教科書で勉強しかしてない奴に俺たちのことなんてわかんねーんだよ」
塚田くんは吐き捨てるように言い、自転車の鍵をポケットから取り出した。塚田くんの言い分に私はなぜか頭にきて「教科書もろくに開いたことがない、勉強もできない奴に言われたくない」と私は反論した。塚田くんは怒ってそのまま自転車に乗って喧嘩に行ってしまった。塚田くんの後ろ姿を見送りながら、私だってまともに教科書を開いて勉強もしていないのに、さも勉強ができる体で話していた自分に少し笑えた。
英語の勉強しかしない中学生の私を見かねた両親は、都立の高校に受験しても見込みがないと判断したのか、両親は私にカナダの高校へ留学を勧めた。「なんか楽しそう」それだけの理由で私は高校の進路をカナダの高校に決めた。
志田ちゃんとは、中学生になっても交流は続いた。夏休みには一緒にディズニーランドにも行った。引っ越した志田ちゃんのお家にも遊びに行った。中学生になると私はもう志田ちゃんにピアノを弾いてとお願いすることはなくなった。中三の秋頃、高校はカナダの高校に行くと伝えると、「遥らしい」と志田ちゃんは変わらずよく笑って、エールを送ってくれた。
中学を卒業して、私はカナダ、ナナイモという都市へと渡った。ホームステイ先のお宅は音楽一家でグランドピアノやドラムが置いてある家だった。私より年下の中学生のホストブラザーはゆったりとした眠くなりそうな私の知らない曲をピアノで弾いてくれた。途中、彼は「遥も弾く?」と私にピアノの椅子を譲ってくれた。私が前にピアノをやっていたと話したことを彼は覚えていた。久しぶりにピアノに触れた。エリーゼのためにを弾こうと鍵盤に手を置くが、誰もが聴いたことがあるエリーゼのためにの始まりのサビのところが全然弾けなくなっていた。「忘れた」と笑って、私はまたホストブラザーに席を譲った。
「私の6年間はなんだったんだろう」
英語もまともに話せなくてコミュニケーションを図れないのだから、せめて言語がいらない音楽でホストブラザーと通じ合いたかったけれど、英語だけでなく音楽でも私は一方的に彼の眠たくなるピアノの演奏を聴くことしかできなかった。「志田ちゃんだったら」もし私が志田ちゃんみたいにピアノを演奏できたらと想像すると、私は言語を超える特技なんて持ち合わせていないことを突き付けられるだけだった。
カナダでピアノに触れてから、その後の人生で私がピアノと交わることはなかった。カナダの高校を卒業すると、大学は日本の私大に合格したので、日本に戻ってくることになった。実家には変わらず電子ピアノはあった。ピアノはあっても、私がピアノに触れることはなかった。
※
「紗羽、今日はプールだから寄り道しないで早く帰ってきてね」
自分で選んだアプリコットオレンジ色のランドセルを背負った後ろ姿に私は声をかけた。
「はーい。いってきまーす」
紗羽は柔らかい高い声で私に振り返り、手を振った。玄関で紗羽を見送り、リビングに戻ると時計はまだ8時を回っていなかった。キッチンに入り、朝食で使った食器を洗う。顔を洗っている途中で洗濯の終了のメロディーが鳴る。軽くメイクをしてから洗濯物を干した。
朝の一通りの家事を済ませると、リビングの時計は9時5分前だった。我が家のリビングルームは、昼間は電気の明かりがいらないくらい日当たりが良い。リビングのピアノの椅子に腰掛け、電子ピアノの蓋を開ける。電源を入れ、私はふわりと鍵盤に手を乗せた。
紗羽は今年、夏休み期間中の8月に二度目のピアノの発表会に参加した。幼稚園の年中からピアノを習い始め、はじめの頃は家でピアノを弾けるのが嬉しかったのか紗羽はピアノに触れることも多かった。年長に上がり、週一回のピアノのレッスンはさほど滞ることなく教室に通い続けた。
紗羽が通うピアノ教室の芦川先生に私が違和感を抱き始めたのは、割と序盤からだった。
ピアノのレッスンを始めたばかりで、まだ幼稚園生だった紗羽を送り迎えしていた頃、レッスンを終えた紗羽を迎えに行くと玄関先まで紗羽を見送る芦川先生と話す機会が度々あった。短い数分の会話ではあったが、紗羽のレッスンの様子以外にも芦川先生自身のことや、私が幼い頃ピアノを習っていたことなどを互いに簡単に話すことがあった。
「暗い曲、好きなんですね」
私の友達にオーストリアでピアノの先生になった同級生がいることを芦川先生に話した時、志田ちゃんとの思い出の曲、トルコ行進曲の思い出話をすると、芦川先生はトルコ行進曲を「暗い曲」と表現した。トルコ行進曲を初めて聴いた小6から今まで、トルコ行進曲を暗い曲だと感じたことが私には一度もなかった。私にとってトルコ行進曲は特別な曲だった。芦川先生は、思い入れのある曲だと話す相手に、その曲を「暗い」と言い切ってしまう先生だった。
芦川先生の言葉には含みがある訳でもなく、トルコ行進曲をなぜ暗いと表現するのか、音楽家としての解釈や説明がある訳でもなかった。芦川先生はただ言葉を不快な方に変換する人だった。
会話の中で相手に歩み寄るつもりで、相手の専門分野に触れることは良いことだと思っていた。歯医者さんで歯科助手として働いている友達に最近よく耳にするインプラントについて尋ねるように。専門的な事柄までいかなくても、その相手が興味を持っている分野に会話を振ったり、広げたりすることはよくあることだった。紗羽がまだ幼稚園に通っていた頃、私はたとえ興味無くても、【イエバ古参】に最近のイエローバックのライブはいつあるのかとわざわざ質問していたように。
芦川先生に志田ちゃんのことを話したのは、私なりの芦川先生への歩み寄りだった。芦川先生と同じくピアノを生業にしている人が私の友達にいるという話をしただけだった。
「ママ、プールやりたい」
紗羽は年長の途中からピアノに全く興味を持たなくなった。
幼稚園の年長の始め頃、紗羽はプールを習いたいと言い始めた。ピアノの次はプール、ピアノもろくに練習しないのにプールだってすぐ飽きられては困ると私は内心思った。季節はまだ肌寒い4月だったので、夏の時期になったら考えようと紗羽には伝えた。
「紗羽、ピアノの練習は?」
紗羽が小学生になり、学校がある平日は学校の宿題や公文の宿題で時間が取れないから、土日にピアノの練習はしようね、と約束した直後の日曜日だった。ピアノの練習を促された紗羽は眉間に皺を寄せ、口をへの字にして露骨に不服そうな顔を見せた。
「もうピアノ辞める?」
紗羽にこれまで何度言ってきたことだろう。別れるつもりはないのに、相手の気持ちを確かめるために「私たち、別れよう」を繰り返すカップルみたいに、私と紗羽も何度このやり取りを繰り返したことだろう。紗羽にピアノを頑張ってほしくて、辞めるという究極の切り札を何度も使ってきたけれど、切り札は使い込みすぎてもう威力を発揮していない。
嫌々、ピアノの椅子に座り、うんざりした顔で楽譜を見つめる紗羽の横顔を、私はソファーから見据えた。
急にスイッチが切れたように、表面張力ギリギリで保っていたコップの水が溢れ出るように、誰かが比喩で使ってきた数々の心の表現を体現するように、私は「もういいか」と肩の力が抜けた。
「紗羽。もう本当に辞めよう、ピアノ」
ママ、プールやりたい。昨日の夜も一緒にお風呂に入っていると紗羽はそう言って、鼻を摘まんで湯船に自分の顔を付けた。プハーっと息を吐いて顔を上げた。目をつぶったまま濡れた前髪を小さな手で掻き分ける。おでこを見せるように前髪を分けると、目を開け、紗羽は笑顔を見せた。
紗羽がプールをやりたいと言い出してから1年以上が経ってしまった。なかなか踏み出せなくて、ごめん。そう思えるようになったら、少しだけ気が楽になった。
ピアノを習わせようと決めたのは私だった。紗羽がピアノを習いたいと言い出したのではない。
「紗羽。来週、プールに見学に行こう」
ピアノの椅子に座った紗羽は顔を上げ、コクンと小さく頷いた。
紗羽のピアノレッスンが最後の日、芦川先生に、今までお世話になりました、と挨拶に行った。短い間ではあったが、紗羽もピアノのレッスンは楽しんでいた様子だったので、私も芦川先生にお礼を伝えた。
会話の流れで私がピアノをやっていた子供時代、私が最後ピアノを辞めた時の話になった。私はベートーヴェンのエリーゼのためにを弾けるようになってピアノを辞めた話をした。自分で決めた曲を弾けるようになって辞めるのは私にとって「けじめ」だったと話すと、芦川先生は「あぁ、なるほど」と含みを持たせてゆっくり二回頷いた。芦川先生の目は、まるで占い師が過去や未来を見透かすような目つきだった。
「それ、トラウマですよ」
そう断言する芦川先生の顔は、占い師そのものだった。
「トラウマなんですか?」
思わず私は聞き返した。えぇ、トラウマだと思いますよ、と芦川先生の断言は続いた。断言は続くが、なぜそれがトラウマなのかは言わない。これ以上、この人と話すことは何もないと思った。何の迷いもなく人の過去を簡単にトラウマと断言してしまう、あなたが私にとってトラウマになりそうだった。
紗羽がピアノを辞めた日の夜。私は志田ちゃんに電話をかけた。志田ちゃんとは私の結婚式以来会っていなくて、それこそ電話なんて中学生以来だった。オーストリアとの時差を確認すると、こっちの夜は、あっちは昼間だった。だからといって、学生時代の友達とは言え、前触れもなくいきなり電話をかけても平日の昼間はきっと仕事だろうし、電話に出られるとは限らない。それでもいいと思った。私の幼少期のピアノの習い事をトラウマなんて言葉で片付けてきた娘のピアノの先生のことをピアノの先生である志田ちゃんに話さずに誰に話すのか。こんなショッキングなことが無ければ、大人になって志田ちゃんにいきなり電話を掛けることもない。電話をかけたいと思っても、いつもならつい相手の都合を考えると踏み出せないが、芦川先生に腹が立った勢いで私は電話マークをタッチした。電話の呼び出し音に耳をすませる。
「もしもし? 遥?」
驚きが混ざった懐かしい志田ちゃんの声をした。
「なんでー」
志田ちゃんが電話に出たことが嬉しくて、逆に私が聞き返す。「今日、たまたま仕事休みだったの」と志田ちゃんは答えた。すり合わせたようなタイミングだった。
小学生の頃に戻ったようだった。最後に会った日から今日までを埋め尽くかのように私と志田ちゃんは、日本が深夜になるまで喋り続けた。
9月にピアノを辞めると、10月から紗羽は近所のスイミングスクールに通うようになった。スポーツクラブの25メートルプールを見た時、紗羽はガラス越しに声を弾ませた。
「こんな大きいプール、泳げるようになったら嬉しい」
ガラスに紗羽の顔が反射する。紗羽の吐息でガラスが曇った。
子育てに正解なんてものはなくて、正解が無いから私たちは色んな情報や人の意見に惑わされ、葛藤を繰り返す。子どもの習い事にも正解なんてない。ピアノよりプールの方が習い事として正解だったなんてことは言えない。けれど、ガラスにおでこを付けてプールを見つめる紗羽の横顔を目の当たりにすると、紗羽にはこれで良かったのだと今は思えた。
※
「紗羽ちゃんママ」
ファミレスのパートから帰ってくる途中、声のする方に振り返ると、ちーちゃんママとすれ違った。
「久しぶり」
幼稚園のバス停で一緒だった頃と変わらない、張り付いた笑顔でちーちゃんママは手を振りながら私の方に近寄ってきた。
「紗羽ちゃん、ピアノ辞めちゃったんだって?」
「そうなのー」
少し困った顔を作り、ちーちゃんママのように語尾を伸ばして私は頷いてみせた。
「練習も全然しないしさ、もうやりたくなさそうだから辞めたんだ」
ちーちゃんママに何か言われる前に、私は畳み掛けて話す。
「紗羽がピアノ辞めちゃって、家にピアノも残っちゃったもんだから、代わりに私が今ピアノ弾いてるんだ」
「へぇ」
「私、子どもの頃ピアノ習ってたしさ」
なんて反応すればいいか、ちーちゃんママはわからない顔をした。ちーちゃんママが口を開く前に私はまた畳みかける。
「私の友達で、オーストリアでピアノ先生やってる友達がいてね、その友達にピアノを教えてもらってるんだ。Zoomで」
へぇ、と頷くちーちゃんママの顔は笑っていたけれど、「今さらピアノ?」と顔が物語っている。
今さら私がピアノを弾けるようになったって、志田ちゃんのようになれるわけではない。フジコヘミングになれるはずもない。でも何かを始める時に、常にその世界で極めている人を羨んで自分の無力さに絶望するのはもううんざりだった。
「ピアノって、はじめはこんなの絶対両手で弾けないって思ってても、ゆっくり少しずつ練習するとだんだん弾けるようになるんだよ」
私はずっとピアノを習っていた6年間を無駄だと思っていた。
ちーちゃんママに隙を与えず、私は話す。
「弾けるようになりたい曲を弾けるようになるのって、実はすごいことなんだって気付いた」
無駄だと思っていたものでも、回りまわって自分に戻ってくる。
「今、何の曲、練習してると思う?」
ちーちゃんママは私の話なんて興味ないのは知っているから、私は自分から質問して、向こうが答える前に話す。別に答えてほしいわけじゃない。
「モーツァルトのトルコ行進曲」
分かっているのか、分かってないのかわからない顔でちーちゃんママは「あぁ」と、口角を上げた。【完】
最後までお読みいただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
