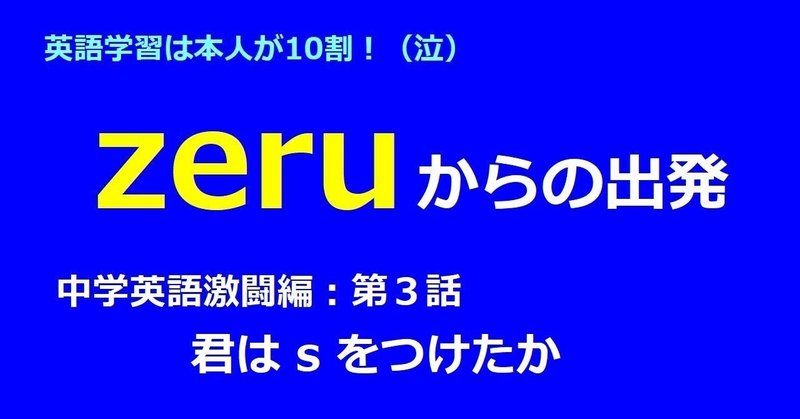
「中学英語激闘編」第3話 君は s をつけたか
夏休みの宿題に「むずい……むずい……」と頭を抱えるカイ。え?! それ全部1学期の復習ですけど……??
そして夏休みスペシャル、「刑事コロンボ」DVDへのカイの反応は?
3-1 中学最初の夏休み
中1の1学期を振り返ってみると、あの惨状の中、なぜ「塾に行かせる」という知恵が浮かばなかったのか、不思議ではある。
いくら英語のお助け人になってやりたくても、これは素人の手に負えるレベルじゃない。さっさと専門家の手に委ね、自分は執筆活動に精を出して、塾代をまかなえるようがんばったほうがものごとはよっぽどうまく回った気がする。
けれど、この時の私はまだ、いろいろな誤認や錯覚や固定観念にとらわれていた。
塾とは、学校よりも進んだ勉強をするところ。教科書の内容さえよくわからない者が行ってもしょうがない、とか。
塾とは、受験勉強のために行くところ。中高一貫校で高校受験のないカイは、今はまだ行く必要がない、とか。
塾とは、つまらない勉強をさせられるところ。中学入学早々、ちょっとばかりつまずいたからといって、さっそく送り込んだりしたら本当の英語嫌いになりかねない、などなど。
しかし最大の誤認は、
「そのうち何とかなるだろう」
であった。
自分の中学時代を思い出してみても、初めから何もかもわかったわけじゃない。むしろ、わからなかった。中1最初の英語の成績は、5段階評価で3だったと思う。「~があります」の there と、「かれらの」の their と、they are の短縮形 they’re はどう違うのか、みたいな、今から思えば信じられないようなことが理解できなかったのも前に述べたとおりだ。
少しずつ道が開けたのには、いろいろなきっかけがあった。それは必ずしも、塾とか参考書のような、勉強に直接関係あることではなかった。偶然目にしたもの、耳にしたこと、出会った人など、運やめぐり合わせによって、もっと英語がわかるようになりたい、やればできそうな気がする、と思い始めたことが大きい。
カイにもそういう時が来ると思っていた。
もうしばらくの間、授業にだけはついていけるよう手伝ってやれば、きっと来るはずだ。
この時は、まだ、本当に軽~い気持ちでそう信じていた。
なので、夏休みも、どこか夏期講習にでも通わせたほうがいいだろうか、などとは夢にも思いつかず、もっぱら宿題の手伝いに明け暮れていた。
3-2 あっと驚く三単現
夏休みの宿題で最大の分量を占めるのは、ワークブックであった。
内容は、ほぼ、1学期の復習。しかし未習の単語や表現もけっこう出てきて、応用力を問う部分が多い。それは、小テストも定期テストも教科書本文の反復練習だけでかろうじてクリアしてきたカイにとって、ものすごくハードルの高いものだった。
たとえばこういうことだ。
Jim plays the guitar.
Jim, play the guitar.
よく似た英文だが、ご明察のとおり、上は「ジムはギターをひきます」という三人称・単数・現在の文。下は「ジム、ギターをひきなさい」という命令文である。
賢い中1なら、1学期の学習内容を動員して、
1)Jim のあとにカンマがついているか、いないか。
2)play に s がついているか、いないか。
という点から2つの文の違いを見分けることができるだろう。
ところが、カイは、まずその着眼点を見出すことができない。「むずい……むずい……」とつぶやきながら、ひたすら「同じような2つの文」を打ち眺めるのみなのだ。
じゃあ「ケイコは寿司を食べます」だったら何て言う? 「寿司を食べなさい」だったら? 「ケイコ、寿司を食べなさい」だったら? などと、さまざまな例題で理解を促そうと試みるのだが、ますます混乱に陥るばかり。「だーかーらー、こっちの動詞には三単現の s がぁぁぁ」と、私の説明もついつい投げやりになってくる。
きわめて大ざっぱに言ってしまえば、中1英語って「いつ s をつけるか」がほぼすべてではないだろうか。すなわち「複数(名詞につける)」と「三単現(動詞につける)」。
1年生の終盤には動詞の過去形が出てくるが、それはもう主語が何でも同じなので世話なしだ。それだけ三単現はめんどくさい、というか、何で三単現だけこんなにめんどくさい仕様になっているのか泡を吹いて倒れそうなほどめんどくさいが、そこさえ体得できればそれ以上にめんどくさいことは当面あまりない。
何かもうちょっとましな教え方はなかったものか、今でも心残りだ。
だが、せっかくの夏休み。「むずい……むずい……」とうめきながら机にばかり向かっていても気が滅入る一方だ。
かねてから、私は、カイが中学生になったら一緒にやってみたいことがあった。
「刑事コロンボ」のDVD鑑賞である。
3-3 コロンボの声を聴け
「刑事コロンボ」は1970年代に一世を風靡したアメリカのミステリードラマだ。
旧シリーズ45作(1968~1978年)、新シリーズ24作(1989~2003年)、計69作。第1作から半世紀を経た今でもNHK BSで 4K版が放送されたり、新たな研究本が出版されたりと熱く語り継がれる歴史的名作である。
おもに中学から高校にかけて、夢中でこのドラマを見ていた私は、カイが保育園の頃、旧シリーズ45作のDVD-BOXが販売されていることを知り、迷わずポチった。いつの日か子育てから解放され、同じくコロンボファンである夫と2人で楽しめる日を夢見ていた。
しかし、カイが次第に成長し、大人向けのドラマも一緒に見られるようになってきて、気がついた。DVDは中高年が往年の名作を懐かしむためにあるんじゃない。次世代に伝えるためにこそあるのだ。カイに見せることは我々の使命といっていいのではないか。
最初に見せる1作は「死者の身代金」にした。なぜ「殺人処方箋」を避けたかについては、ややマニアックな話になるので触れない。
カイにとって、初のコロンボ体験は「長い」というのが偽らざる感想だったようだ。なにしろコロンボ1本の時間が「名探偵コナン」3本分なのだ。でも、一応「おもしろかった」とも言っていた。倒叙ものというスタイル、および、地位も名声もある頭脳的な犯人をコロンボが油断させておいて追いつめるというドラマの要諦も、この1作でほぼのみ込んだと思われる。
次いで「構想の死角」。次いで「指輪の爪あと」。次いで「もう一つの鍵」……
鑑賞を重ねるごとに、カイは犯人のミスを見破ろうとしたり、「もう1つだけ」とコロンボが戻ってくるタイミングを言い当てたりするまでに成長した。
夏休み中に見たのは「死者の身代金」+第1シーズン7作の計8作。カイが最も気に入ったのは「二枚のドガの絵」だそうだ。このあと最終的に足かけ5年で旧45作を完走するのだが、カイの好みは、情緒を排し動かぬ証拠で言い訳の余地のない決着をみるエピソードで一貫していた。
私はどちらかというと心理的綾のある作風、たとえていうなら「虚栄心ゆえに犯行に及んだ犯人が、虚栄心ゆえに馬脚を現す(それを狙ってコロンボが仕掛ける)」みたいなエピソードが好みで、親子といえどもコロンボ観は別という発見も楽しかった。
しかし、何という贅沢であろうか。
70年代にはまだ、テレビドラマなんて見るそばから消えていってしまうもので、どんなに好きな作品でも、再放送をしてもらえない限り二度と見られなかった。
一般家庭で録画をとるなどSF的空想でしかなく、放送時間にテレビの前に座っていることができなければ、一度見ることすらできなかったのだ。
生まれつき家にビデオデッキがあり、録画はもちろん、過去の戦隊シリーズや仮面ライダーやお笑い番組までもレンタルで借りてきて(あるいは、親に買わせて)いくらでも見られるのが当たり前だったカイには、これがいかなる奇跡かいまいち通じないのが歯がゆい。
歯がゆい点は、もう1つあった。
「刑事コロンボ」は、単にすぐれたミステリードラマというだけではない。
カイにとっては初めての、海外ドラマでもあったのだ。
興味ないですかねぇ? アメリカでは車は右側通行なのか、とか。アメリカの郵便ポストは青いのか、とか。チリってどんな食べ物なんだろう、とか。
そして、コロンボ始め登場人物たちは、実はみんな英語でしゃべっているのだ。DVDではそれが全部聴けるのだ。わからないまでも、どんな感じかちょっと聴いてみたい、とは思わないですかね? コロンボの本当の声、聴きたいと思わないですかねぇ??
3-4 興味がない!
今でこそ海外ドラマも洋画も二ヵ国語放送は当たり前だが、コロンボの日本上陸まもない頃は、吹き替えを聴くことしかできなかった。
小池朝雄さんの吹き替えももちろん楽しみだったけれど、楽しみであればあるほどそれと同じくらい、ピーター・フォークの演じるコロンボが「本当は」どんな声なのか、「本当は」どんなふうにしゃべっているのか聴いてみたくてたまらなかった。
その時点でまだ中学生だった私が、英語を聴いてわかると思っていたわけではない。
とにかくいっぺん聴いてみたかった、ただそれだけである。
同じように思っている人は、全国に大勢いたらしい。ある時、視聴者の要望に応えて、本編の放送後、コロンボの生の声をお聞かせしましょうというサービスタイムがあった。
どのエピソードのどの場面が使われたかは忘れてしまった。
小池さんのふわっとした声音とはまるで違った、ねちっこい声でびっくりしたことだけありありと覚えている。
いや、もう、ホントに「イヤな声」(苦笑)。こんな刑事に目をつけられてつきまとわれたらそりゃイヤだわ、と犯人の気持ちが一瞬にしてわかったようだった。
その声が「嫌いだ」と思ったわけではない。小池さんとの違いがすごかったというだけで。「びっくり」はしても「がっかり」はしなかった。しかし、ずいぶん違った。
二ヵ国語放送が一気に普及したのは70年代終盤、コロンボでいえば旧シリーズの最後の数作が放送された頃だったと思う。それも音声多重対応のテレビがなければ聴くことはできなかった。しかも、日本語字幕がつくわけでもなく、英語のまま丸投げされるだけ。もし初めからあったとしても、吹き替えで見ないことには一言もわからなかったであろう。
けれど、DVDは違う。音声は日本語・英語、字幕は日本語・英語・なし、全部で6通りの設定で見ることができるのだ。好きなエピソード、好きな場面を、好きな設定で、好きな時間に、何度でも何度でも見ることができるのだ。
わかるか。わかるかカイ、これがどんな奇跡か。
どうして君は何の興味も持たないんだーーー!!!
DVDだけではない。今は動画サイトで、いろいろな国のいろいろな映像を見ることができる。カイはお笑いの動画しか見ないけど、ほかにも未知の世界がいっぱい広がっている。
こんなことがあった。カイの英語の副教材に、「あれはバスですか」「いいえ、ちがいます。家です」という会話の穴埋め問題が出てきた。
「どんな見間違いだよ!」とツッコミを入れるカイに、私はYouTubeで「ロックフォードの事件メモ」の動画を探し出し、トレイラーハウスというものを見せてやった。
ジェームス・ガーナー主演「ロックフォードの事件メモ」(1974~1980年)。これも私の大好きだったドラマだ。
私立探偵ロックフォードは、マリブビーチに横たわる住居と事務所を兼ねたトレイラーハウスに住んでいる。ドラマもおもしろかったけど、トレイラーハウスというのがまたどういうものか興味津々で、いっぺん寝泊まりしてみたいという好奇心を抑えられなかった。
それが三十有余年後、こんな形で我が子の英語学習の一助となる日が来ようとは。これのことだよ、カイ。バスと見間違えるような家というのは。
だがカイは、「へー」とひとしきり珍しがりはしたものの、穴埋め問題の空欄を埋めたらそれっきりだった。
え……興味ない?
YouTubeにはお笑いの動画だけがあるんじゃないんだ! もっといろいろな動画で、知らない国の知らないものを見てみたい! という料簡はない??
それからも折に触れて、そう、たとえば授業で新しい表現を習った時、コロンボのDVDでまさにその同じ表現が使われている場面を「ね、言ってるでしょ、本当に言うんだよ英語の国の人は」と見せてやるなどしても、「へー」……終了……その繰り返しであった。
「わからない」ものはしょうがない。三単現の s でも何でも、わかるまでいっしょうけんめい説明してやるまでだ。
しかし「興味がない」は?
「興味がない」に打つ手はあるのか……??
(第4話 英検チャレンジ5級編 につづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
