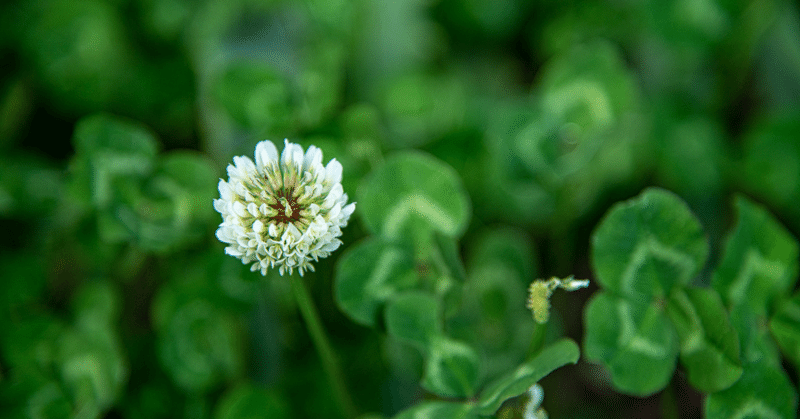
宗教はなぜ存在するんだろうか?
かつて問題視されたオウム真理教や今問題視されている旧統一教会等々、私たちは宗教に怪しさや不信感を抱きつつ暮らしている。新興宗教だけではなく、長い歴史を持つキリスト教、イスラム教、仏教も例外ではないように思う。でも、そう言いながらも、相変わらず、宗教は今も生き残り、我々はある程度嫌いながらも、一定程度距離を保ちながらも何となく心の支えとして生活している。
生きるためには食料が必要だ。我々人間はこの地球の自然環境をかなり把握理解している。食べられる動物や植物はどこにいるか。水はどこにあるか。そういったたくさんの実用的な知識。その他に必要となるのは、この生物の群れの掟や親子親戚関係、先祖についての知識だろう。やっていいこと、いけないこと。他の群れについての情報や、色々な言い伝えについても知っているに違いない。これだけのことを知っていればさしあたり生きていける。
けれども、不幸にも我々人間は生きるために必要なこと以外の余計なことも、きっと考えてしまうはずである。例えば、自分はやがて死ぬだろう。そしてこの世界からいなくなってしまうだろう。自分はどこから来たのか。そしてどこへ行くのか。自分はなんのために生まれてきたのか。この世界は、いったいどうして存在するようになったのか。などなど。
こうした疑問は、考えなくても生きて行ける。そして昼間、皆と一緒にいる間は忘れていられる。でも誰もが、ふとした折に、考えてしまう疑問である。余計な知性を持った人間という生物なら、きっとそうだろう。
それにはそれだけの理由がある。知性は生きている個々の個体の活動である。ところが個体は、必ず死んでしまう。これは多細胞動物の宿命である。大腸菌のような単細胞生物なら、分裂を繰り返して、同じ構造のものが永遠に生き続ける。細胞分裂と生殖の区別がない。多細胞生物は、生殖して子孫を残したあと、親の個体はやがて滅んでしまって、同じ構造(個性)のものは2度と現れない。知性も脳とともに滅んでしまうのだ。そして知性は、やがて滅んでしまう自分とはなんだろうと考えてしまう。
けれども、この問いには答えられない。死んでしまった知性に、死んだらどうなりましたかと聞くわけにはいかない。死んだ知性は、知性として既に存在しなくなっているからだ。死は知性にとって究極の、最後の、未知の世界である。自分の知ることのできないことを知ろうとすること。これが、人間が持つ不孝な知性の知性たるゆえんである。
人間は誰もが、自分は死ぬと知っている。知っていながら、それでも生きている。死は生きている人間には決して経験できないことだから不安である。これは知性をもつ生物なら、必ずそうあるあり方である。これは生きることだけを考える以外の知性という能力を持った人間の誇りでもある。しかし、同時に、このことが悩み苦しみの源泉でもある。
このことは、人間と人間のつながりにも反映する。人間はだれもが無力な幼児として生まれる。そのあと成長して、いったん自立しているようにみえる時期を過ごしたあと、最後は年老いて人の世話になりながら死んでいく。もしも人間が死なないで永遠に生き続けるのなら、他人にかまわず自分のことだけを考えるエゴイストになることもできるだろう。けれども人間は、やがては死ぬひ弱な存在である。互いをいたわり助け合うことなしに生きてはいけない。知性があるから人間はこのことをよく理解している。社会は、弱肉強食の自然状態ではない。人間が、互いに大事にしあう、秩序のある交流の空間である。
社会は、このように組織されるものなので、その内部は、価値(大事なこと)や意味(そのわけ)が満ちている。そうした価値や意味は、人々が共同で支えている。あなたが生まれる前から、そうした価値や意味は存在していた。そうした存在なしには、この世界も知性も成り立たなかった。そして、知性が滅んだあとでも、その舞台であるこの世界は続いていく。あなたは、有限でひ弱な小さな知性としてこの世界のまんなかにポツンと取り残されているように感じる。あなたは、あなたがこうしてポツンと存在することに、いったいどんな価値や意味があるのかと、なおも考えようとする。
社会を満たしている価値や意味は、私やあなたや個々の知性が自分で考え付いたものではない。あなたの知性が活動し考え始めたときには、もうそこにあった。なぜ、そこにあったのか。それは自分1人の知性の働きでは説明がつかない。それは、他にも知性がたくさん存在している(いた)ということもあるかもしれないが、その始まりまでは考えきれない。考えきれないことを、さらに考えようとする。それには工夫が必要である。
例えば、この世が、ある偉大な知性の手で設計され、製造されたと考えてみる。それなら、世界が価値にあふれ、意味に満たされているのは当然である。そして世界は製造されたのだから、始まりも終わりもない。この偉大な知性を神(God)とよぶことにする。するとユダヤ教やキリスト教、イスラム教の一神教である。人間は、神に製造された被造物である。人間は何の為に生まれたのか。人間は死んだらどうなるのか。そういったことを知りたければ、神が何を考えているかを知ればよい。神が何を考えているかは、神の声を聞いた人(預言者)の話を聞けばよい。預言者の話は旧約聖書や新約聖書やコーランに纏められているから、それを読むといい。
また例えば、この世界が、永劫の昔から究極の法則に従って運動していると考えてみる。すると、この世界には始まりも終わりもない、世界も人間も簡単にいうと変化しているように見えるが、実は変化していない。究極の法則は変化しないからである。変化していくものは、現象である。価値も意味も、人間の生命も変化していく。だから現象にすぎないのだ、と理解すべきである。この究極の法則を法(ダルマ)と呼んでみる。また最高の知性を、仏(ブッダ)と呼んでみる。すると仏教である。人間は誰でも知性をもっている。それを最高のあり方に導きさえすれば、誰でもが仏(ブッダ)になれる。究極の法(ダルマ)がどのようなものであるかは、仏(ブッダ)の言葉をまとめた経典やナーガルジュナの中論などの仏教哲学書を読めばよい。
また例えば、この世界は、過去を繰り返し、単に再生産しているのだと考えてみる。過去を忠実にたどることが、人間にとって最高のあり方である。知性は過去がどのようであったかを、よりよく理解しなければならない。この世界を成り立たせている価値も意味も、過去の世界によって支えられているからである。過去の世界の価値や意味は、過去の理想的な知性によって運用されていた。この知性を、聖人、とよんでいる。すると儒教である。聖人がどのように、この世界の価値や意味をそのまま次の世代に伝達することが人間の務めである。
いくつかの例を挙げた。これらは知性をもって生まれた人間が、考えられることの限界に挑戦する、いくつかの試みであり、工夫である。こうした工夫は、人々の共感をよび、人々に共有され、大きな運動となって拡がっていく。人類の歴史を紐解いてみると、知性が限界を超え、考えられないことを考えようと苦闘してきた歴史でもあることに気付く。そのような苦闘なしに、人間は、自分の存在理由を確かめることができなかった。しかし、結局、その苦闘を経ても、価値にあふれ、意味に満たされているこの世界がそのようであってよいのだという確信をもつことができなかった。誇りある知性として自分を肯定することができなかった。今もできていない。宗教とは、このような試みである。そして文明の原動力である。
宗教とは何か。その答えを、自信をもって回答するには時間がかかりそうだ。いや、永遠の時間がかかり、結局は永遠に結論が得られないだろう。何故なら、自分の知ることのできないことを知ろうとすること、それが宗教なのだから。
宗教とは知性という邪魔で余計な能力をもってしまったことにより、余計なことを考え、そのせいで必要ない余計な悩み苦しみを抱え込むことになったってしまった人間の知性が「苦しみを解決したい」という願望の下に、悩み解決のために試みた思索である。しかし、永遠に解決できないだろう。しかし、人間は、自分の知ることのできないことを知ろうとする不可能なテーマに今後も永遠と挑戦し続けることだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
