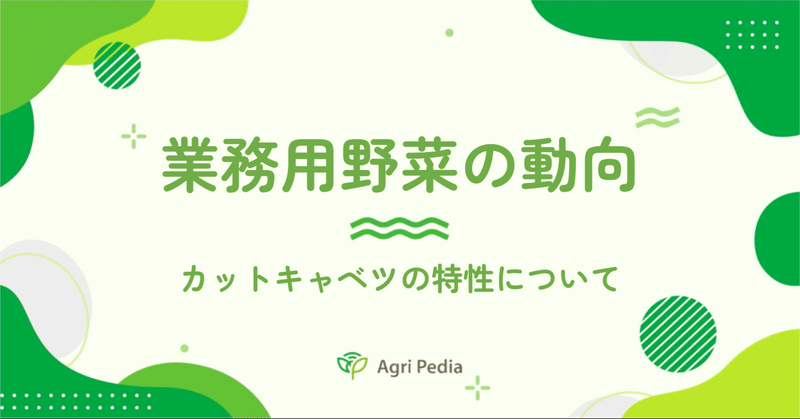
業務用野菜の現状~カットキャベツの特性について~
こんにちは。アグリペディアの村山です。
アグリペディア株式会社では、今後日本の農業を担っていく大・中規模農家にフォーカスした支援事業を行っています。
現在は「販売先のマッチング事業」を主に行っており、業務用野菜の生産者様の支援の一環として、本ブログを開設いたしました。
▼アグリペディアについてもっと詳しく知りたい方はこちら▼
今回も引き続き、カット野菜の動向について簡単ではありますが解説していきたいと思います。
▼前回の記事をご覧になっていない方はこちら▼
今回は、業務用野菜、主にカットキャベツの特性について説明します。
業務用野菜と生食用野菜の違いついて
本連載では業務用野菜について説明していますが、業務用野菜の明確な定義についてはこれまで触れていませんでした。
ということで今回は業務用野菜の特性について解説していきたいと思います。
業務用野菜には明確な定義がなく、何らかの手が加えられた野菜という概念的なものであり、キャベツを例に出すと、芯抜き処理をしたものから千切りにしたものまで、「業務用野菜」となるのです。
カット用、ホール用などそれぞれの用途によりある程度求められる品質は一定になります。
今回はアグリペディアで主に取り扱っている「カットキャベツ」を例に解説していきます。
一方、生食用野菜は購入者それぞれが異なる用途のために使用するものであり、求められる品質は多岐に渡ります。
下の表に生食用野菜と業務用野菜の特性の違いについてまとめました。

今回はこの表の「商品形態」と「栽培方法」について詳しく解説していきます。
商品形態
外見重視の生食用野菜と比較すると、業務用野菜は外見はあまり重視されず、「歩留り」が重視されます。
この歩留りとは、供給原料の量に対する製品量の比率のことであり、カットキャベツであれば原料キャベツより生食に適さない芯や汚れの付いた外葉などを取り除いたものが製品量になり、製品量の割合が高いほど良い原料キャベツということになります。

加工用野菜では、歩留りを良くするために大玉規格であることが一番に求められます。
大玉であれば歩留まりが良くなる傾向にあるほか、皮むきなどの1個当たりの作業時間は変わらないため、1個当たりの加工コストがかからない点も好まれます。
また、加工用野菜では水分量が少ないものが好まれます。
これは、カット野菜にする際に水分が多いと萎れてしまい食感が悪くなるほか、加熱調理をする際にはドリップ(食品から出る水分)が多くなり、味が薄くなる原因になるためです。
栽培方法
では、このような業務用向けのキャベツを栽培するためにはどうしたらよいのでしょうか。
大玉のキャベツを栽培するための工夫として、
・生育期間を生食用と比べて1週間から10日延ばす
・大玉収穫が可能な品種を選定する
・畝幅を広く定植する
などが挙げられます。
業務用出荷向けのキャベツ品種
キャベツには様々な品種がありますが業務用野菜の需要の増加に伴い、業務用の出荷に適した品種も育成されています。
先述した通り大玉規格が求められる他、業務用は計画出荷になるため、在圃性が高い品種が適しています。
品種選定には気候などが関係しますので、一概にはお勧めできませんが、業務用向けに育成された品種を3つご紹介します。
がいな(サカタのタネ)
方言で「大きい」という意味を持つ名前の通り、しっかりとした肉質、ずっしりと詰まった重量感のある大玉収穫が可能な品種です。
裂球が遅く、在圃期間が長いため、業務用で求められる2L~3Lサイズの大玉収穫できます。
中間地・暖地では夏秋どりが適しています。
おきなSP(タキイ種苗)
おきなを改良した品種。
L~2Lサイズの大玉収穫が可能であり、裂球が遅く、収穫期幅が広く業務用にも適しています。
中間地・暖地では秋どりが適しています。
夢いぶき(タキイ種苗)
12月下旬~1月に裂球の少ない品種として開発された夢いぶき。耐寒性・在圃性が高く、低温期の安定出荷に適しています。
また、短芯のため歩留りが良く、業務用にも適しています。
中間地・暖地では年内どりが適しています。
株間
業務用野菜の株間は生食用野菜の株間より広くとることで大型規格のものが収穫できるとされています。
実際に、業務用キャベツの株間についての研究例を紹介します。
大玉収穫のためには株間40cmで定植すると揃いが良く、1.7kg以上の大玉が9割程度収穫できる。また、10a当たり8tを上回る収量が得られるとともに、慣行株間の30cmと比較して定植苗数が25%削減できる。
「加工・業務用キャベツ栽培で大玉生産に適する栽植密度」より
こちらは寒冷地での実験となっていますが、多くの種苗メーカーでも業務用出荷のキャベツでは株間35~40cmが推奨されており、気候に関わらず株間を広くとることが推奨されていると言えます。
また、研究内容にもあるように株間を広くすることで定植苗数が削減できます。
業務用野菜は1玉あたりの単価ではなく、kg単価で取引されることが多いため、定植苗数を減らし大玉出荷することで収益向上を図れるのではないでしょうか。
栽培コスト
生食用の中から大玉のものを業務用に出荷するより、業務用の大型規格のものをはじめから栽培する方法が適しているとの報告もあります。
これは、業務用野菜は選別・出荷作業を簡略化できるため、選別・出荷作業が必要な生食用野菜と同一圃場で収穫すると、本来必要のない選別作業を行わなければならず、労働生産性が低下するためです。
また、業務用野菜の荷姿は鉄コンテナや折り畳みコンテナが主流のため、段ボール代などの梱包費もかからないため、経費削減に繋がります。
まとめ
今回紹介した商品形態、栽培方法について簡単にまとめていきます。
業務用野菜は歩留りが重視されており、大型規格が求められている
特にキャベツであれば、水分量が少なく締まりの良い寒玉系
キャベツであれば株間は40cm程度とし、大玉収穫を目指す
生食用キャベツと業務用キャベツは圃場を分けて栽培する
業務用野菜は苗費、梱包費などが生食用と比べて低い傾向にある
取引方法
今回説明しきれなかった業務用野菜の取引方法については次回のnoteで解説していきます。
次回の連載もお楽しみに!
アグリペディア公式LINEのご紹介
アグリペディアではカット野菜に関する情報の他、生産に役立つ情報を発信しています。無料セミナーなども随時開催していますので、是非公式LINEのご登録をお願いします!
また、業務用野菜のパートナー生産者様を募集しています!
他にも、業務用野菜を生産していてJGAPを取得したいという生産者
の皆様を支援しています!
既に業務用野菜を生産していて、販路拡大を検討している生産者の方、JGAPの取得を考えている方は公式LINEにて都道府県、作付け品目をご連絡ください。

参考文献
フードシステムの革新と業務・加工用野菜 坂知樹
加工・業務用野菜をめぐる現状 農林水産省
加工・業務用キャベツ栽培で大玉生産に適する栽植密度
野菜特集 2021春 サカタのタネ
タキイ最前線 2020秋 タキイ種苗
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
