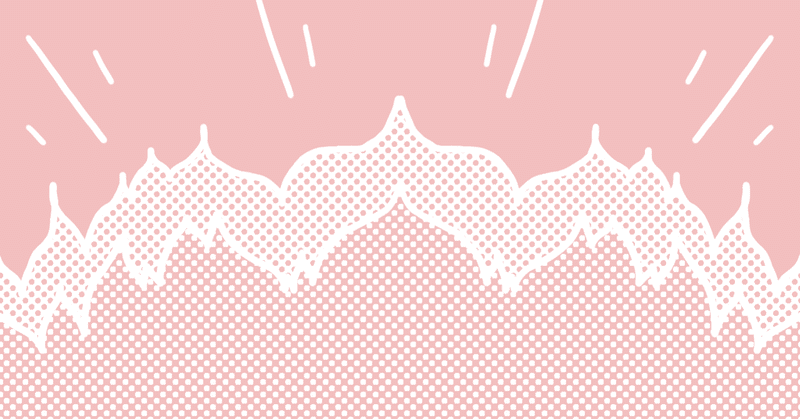
cakesの「ホームレス」記事に見る、編集部の層の薄さ
うーん、なんか例の件で編集部は再発対策案を出してたけど、全然効果なかったよって事で、これは手痛いんじゃないかな…。
※ご指摘があったので、よりわかりやすくなるように本文を変更しました。(11/20)
発端はcakesのホームレス記事
☑︎ cakesの連載コラム
☑︎ ホームレスを一種の異文化・ライフスタイルといった切り口で紹介している
☑︎ ホームレスへの先入観や偏見を丸出しにした記事と批判続出
無邪気な文面で「ホームレスの意外な生態」を紹介しちゃう記事です。
ツッコミどころ多くて、追いつかないですね。
(PV上げたくない方はアーカイブでどうぞ)
主な問題点は以下でしょうか。
☑︎ ホームレスといった属性に着目し、異文化扱いしている
☑︎「異世界性」などといった単語で、切り離しや分断をしている
☑︎ ホームレスをすべて「おじさん」「おじさんたち」と呼び、属性化させている
(仮にプライバシーに配慮するなら、記事では仮名でもいい訳ですから)
☑︎ 明るい面にのみ着目し、面白おかしく記事にして、問題点を無視している
☑︎「おじさんたちから得る刺激」と称して、他人をコンテンツ化して隠さない
☑︎ 文化人から非文化人を観察しに行くといった態度を隠さない
☑︎ メディアとしてホームレス問題をどうしたいのか、わからない
ホームレスは属性ではないので、いくら文化層が違うように見えたとしても「異文化」として語ってしまうのはダメなんですよね。
属性より「状態」と言った方がより近いですし、コロナ禍で若者もセーフティネットから滑り落ちてホームレスになってしまったりと、決して断絶された環境や文化ではありません。
紙一重の差でなってしまう事もあるし、地続きの生活と言った視点が欠けていると思います。
またカテゴリにライフスタイルってポジティブな単語を持ってきてしまうには、ちょっと問題がありすぎます。
心底好きでホームレスやってる人がいるかも知れない可能性は否定しませんが、風俗嬢同様に、その時の環境でやむを得ずそうなってしまった人を「自業自得」とか「自分で選んだ」とカウントしてしまうのは良くない事です。
ところで、ホームレスの方々に少なくない割合で知的障害者がいらっしゃるのはご存知でしょうか?
知的障害者や発達障害を抱えた方は、快適に生きる上で知識が必要であったり、適切なサポートが必要になります。
また、ネットの一部コミュニティでは、コミュニケーションに難がある、話が通じない方を「池沼」「アスペ」、仕事でミスが多い方を「発達」などと揶揄・侮辱する人がいます。
つまり、社会的に無能だと感じた人物に対して、勝手に病気だと判断する人々がいるという事です。
そこに昨今の実力・成果主義と自己責任論が合わさった結果、「知的障害者が多いから工夫する能力はない」とか「無能だからホームレスになった」みたいなストレートな偏見・発想が無意識に含まれているとしたら問題です。
例え今はホームレスであっても、その人その人に備わった技能や能力が消える訳ではありません。
しっかりとした専門知識・技能をお持ちの方から、専門的な支援が必要な方まで幅広い層がいるにも関わらず、ホームレスの中で自活能力や技能の高い上位層のみをチェリーピックし、一部の偏見を肯定し、「意外!ホームレスの人はこんな事も出来る!」などと面白おかしく吹聴してしまうのは、倫理的にどうかと思います。
(自分の中にある偏見に気づいたのはいいかもしれませんが、ホームレスの魅力と絡めて出すには無理がありませんか?)
そもそも、ホームレスだから…とかではなく、その人だからそういう事ができている訳で…。
3年も観察しているので、恐らく様々なエピソードはあると思いますけど、その中からひたすらポジティブな面だけを掬い取ってコラムの記事にしてしまうのが、バランス感がないというか、小学生の動物観察日記じゃないんですから…。
(別に個人ブログなら、単に個人の体験談だし良いと思うけど…)
さて、どうしてcakesにこのような記事が連載されるに至ったのでしょう。
作者はコンテストで優秀賞をとり、連載を開始
☑︎ 2020年note上で開催されたcakesクリエイターコンテストで優秀賞受賞
☑︎ cakes編集部のコメントは著者の内心を面白がっているもの
2020年2月6日から約2ヶ月の間、note上で記事を募集して行われたコンテスト。
その優秀賞7名の中に「河川敷グルメガイド 2020」と称した作品があります。
河川敷に住むホームレスのおじさん達が日頃どういう生活を送り、食材を確保して調理しているのか、さらに食材を差し入れて共に調理を行った内容などを、これまた無邪気に発表しています。
この記事につけられた編集部のコメント
河川敷で暮らすホームレスのおじさん達を取材して記事にしている、ばぃちぃさんご夫婦。独創的な切り口がおもしろいです。採れたての野菜で作ったお好み焼きや天ぷらがとてもおいしそう! noteのサポート代でおにぎりを作っておじさんたちに届けるというプロジェクトも魅力的。おじさんたちを取材する理由を、過酷な状況でも「前向き」な彼らに生き物としての強さを感じるためと綴っていて、ここも興味を惹かれます。(cakes編集部:井澤)
うーん、この記事を面白がって優秀賞に選ぶ時点で、編集部としてマズさ全開だと思います。
このコメントから透けて見えるのは、「『ホームレスを観察している変人』をさらに見世物にする編集部」と言った構造なので、割と酷い階層の再生産だと思います。
珍獣ハンターみたいに人間を吊るすの、良くないと思いますよ。
内心の自由があるので、他人をオモシロコンテンツとして見ちゃうのは否定しませんが、それを明け透けに出してしまうのと、正直者が良いって話は全然ベクトルが違います。
確かに河川敷では「健康・体力・資材力」みたいなある種の強さが必要だとは思いますが、「彼らの状況が過酷になればなるほどに目立つ「前向き」な側面に生き物としての根底的な強さ」とかにクローズして感動コンテンツ化してしまうのは、対人間に対してやっていいかというと…。
このコンテストは2020年6月に結果が発表されたものなので、既にこの時点で幡野さんのコラムで炎上する下地と素養はあった訳です。
何故、編集部は炎上を防げないのか
☑︎ 現在はウェブメディアが乱立し、編集者不足
☑︎ 転職や引き抜きなどで人材が流動化した結果、ノウハウが属人化
☑︎ 編集者として教養のある人物が少ない=層が薄い
前回の騒動で上げたcakes編集部の再発防止策です。
・編集部のチェック体制、掲載フローの見直し
・公式SNSの運用ガイドライン見直し
・客観的にご意見をいただくためのアドバイザリーの起用
・編集部および全社でのDVやハラスメント、差別などの問題に関する勉強会の実施
・専門家へのインタビュー記事の掲載
・DVやハラスメント、差別など、さまざまな問題を考えるコンテンツの掲載
アドバイザリーの起用ってありますけど、そもそも「今の編集部で適切なアドバイザリーを起用できるだけの知識があるのか」みたいな「適切な情報をググるための必要最低限の知識」な話があるんじゃないか…。
DVやハラスメントの講習や勉強会はやったみたいですけど、ホームレスって社会問題なはずなのに付いてるタグが「ライフスタイル」「ノンフィクション」ってそれで良いのか…。
2012年にリリースして以来、約8年間の中で編集部は何を蓄積してきたんでしょう。
「DVやハラスメント、差別など、さまざまな問題を考えるコンテンツの掲載」が今回の連載なら、せめて「専門家へのインタビュー記事の掲載」も同時にするべきでは?
こうなっている背景は、多分ウェブメディアが乱立してきて編集者が取り合いになっているから、人でも足りないし経験不足でもなれちゃうあたりにあると予想しています。
漫画業界では既に「漫画やネームを読める編集者」を取り合っているらしいですが、正直似たような状況が漫画だけでなく小説や記事分野でも起こっているのではないか…。
有能な人が転職や引き抜きにあってしまえば、その人のノウハウを会社で共有できていない場合、会社自体の知的資産というか技術資産みたいなものがごっそり抜けてしまうんですよね。
そうやって層が薄くなってしまうと、回復するのは中々難しいですし、結果何をチェックしたのかわからない素通り記事が出てしまったりするでしょう。
そして、cakes編集部は編集者として教養のある人材が獲得できてない、あるいは引き抜かれて層が薄くなっているのかも知れません。
となれば、何を専門家に相談して相談するべきでないか判断できない可能性もありますし、今後は暫くこのような騒動が続くのではないでしょうか。
まとめ
☑︎ 作者自身は(動機はどうあれ)リアルにホームレス支援活動をしている
☑︎ 作者に救われているホームレスがいるかもしれないことも否定しない
☑︎ ホームレスをオモシロコンテンツとして流しちゃう編集部はダメ
☑︎ 真っ当なメディアなら、せめて専門家の記事も貼って欲しい
☑︎ メディアとして最終的に伝えたい社会的にポジティブなメッセージがない
☑︎ cakesは決してホームレスにならない(と思っている)層のためのB級ウェブメディアとして認識されてもしょうがない
最初の動機や現在の内心がどうであれ、作者は実際にホームレス支援を行なっている訳ですから、そこは褒められて然るべきだと思います。
人の長話を聞くだけ聞いて、差し入れもしている訳ですから、この人に救われたかもしれない人がいることも否定はしません。
記事の感性(クックパッドとかもね)はどうであれ、実際にnoteの売り上げでホームレスの方々に食料支援をしていますし。
個人のブログとしてひっそりやっている分には構わないんじゃないでしょうか。
(そして、noteを買って支援するのも自由です)
しかし、赤の他人をそんなズケズケとオモシロコンテンツにしちゃう感性をそのまま連載にしてしまうcakes編集部には、批判が集まって当然でしょう。
(逆に可哀想な人々として被害者神格化みたいな事をするのも、また違うのですが)
ホームレスの方々も普通の人ですから、当然、接する際も普通の人間として尊重して接する必要があります。
ですが、ホームレスの方々の特殊性というのは、「お金がなく、保険証もなく、病院にかかることができない」「健康を維持するのが難しい」「災害が起きた場合に危険な場所で定住している」と、生活保護を受けて家を借り生活していれば助かるはずの場面で命を落としてしまう可能性が高い事です。
また、野宿しているという理由だけで理不尽に襲われ、怪我をされたり亡くなられる方もいます。
ですから、自然を愛した方があえて不便な環境で生活を行うような、単なる「田舎のスローライフ」とは全く訳が違うのです。
また、一度住所を失ってしまうと、安全な環境に再びアクセスする事の困難さや、貧困ビジネスに巻き込まれお金を奪われてしまったり、必要な支援がなく充分な人間関係が構築できずに仲間のいるホームレスとして再び生活が戻ってしまうなど、一朝一夕には解決できない問題が数多く横たわっています。
真っ当なメディアであれば、ホームレスになった時のための知見を面白おかしく発掘するんじゃなくて、ならないように行政知識を授けるとか、なった人がすぐに脱出できるように制度の整備を訴えるとかじゃないとやばい訳です。
しかも、今回のcakesの記事は、企業としてどうホームレス問題に向き合っていくのか見えませんし、一体どういう解決や未来を望んでいるのか全くわからないです。
ホームレスの生活を面白おかしく取り上げて「僕らも頑張ってるけど、彼らも賢く頑張ってるよね!」みたいなトーンであれば、上澄みの面白さだけを弱者から搾取していると思われてもしょうがないのでは?
そういう切り口や見方で困窮者をコンテンツ化するって一昔以上前の倫理観の持ち主か、アングラ系メディアじゃないとウケないですし、社会問題に対してポジティブなメッセージを記事として共有できないのであれば、cakesはアングラ系ウェブメディアとして認識されてもしょうがないです。
この前の炎上で意識高め層がごっそり退会しましたが、今回の騒ぎでもcakesとnoteの双方で退会される方が増えるんじゃないでしょうか。
編集部としては続ける気満々みたいですけど、今後はたして企業としてポジティブなメッセージや方向性を示していけるんでしょうかね?
とりあえず、手軽に支援をしたいならビッグイシューを買おう
11月30日まで、3300円でビッグイシューを3ヵ月分(6冊)が通販できるよ!
ここからは蛇足なんですけど。
「記事叩いてる奴らはどんだけホームレス支援してんの?w(意訳)」みたいなシニカル仕草も流行ってるみたいですが、ちょっと立ち止まってよく考えて欲しいんですけど、我々真面目に働いてる場合、ちゃんと税金を納めているんです。
それって働けるかとか、定住しているかに関わらず「国民」を支えるためのお金じゃないですか。
私たちの払った税金は、なんらかの事情で困った人を支援したり、病気や怪我をした時に治療ができるようにしたり、地味に生活が便利になるインフラだったり、様々な事に使われています。
そこで単に「ホームレスの方々や施設に直接支援しているか」「どれだけ支援しているか」でもってジャッジして、せせら笑う事って炎上に薪をくべる以上に、炎上に躍る人をエンタメ消費しているだけじゃない?
支援って方法は一種類じゃないし、なんなら直接金を注ぎ込んで支援するって方法じゃなくても、ホームレス支援策が充実するように議員に働きかけるとか、ホームレスになりそうな時に必要な情報にアクセス出来るようなアプリやサイトを作ったり、実際のところ出来ることはあるんだと思う。
真面目にいっぱい稼いで税金納めるとかでも、遠回りに貢献はしているわけで。
だから、働いてて税金払ってる人は全然支援してない訳じゃないし、むしろお金を払っているのに、なぜ届かないのか、なぜ受け取ってもらえていないのか、そういうところを一人一人が興味を持って調べて考えていくしかない。
もしホームレスになりそうな時、なった時、何が必要なの?どういった事に困るの?どういう支援があったら嬉しいのか?って、沢山の人が自分の立場に置き換えて、地道に考えたり整備していくしかないんだと思う。
さらにめっちゃ蛇足。
他人(特に弱者)をどうしてオモシロコンテンツ、あるいは悲劇的な側面だけ注目して感動モノにしてはいけないの?っていう事については、このTEDの記事を読んで欲しい。
このスピーチ読んで・聴いた上で、cakesというメディアひいてはnoteという会社として、どういうメッセージ性を世間に発表したのか、考えてみて欲しい。
参考資料
🌷使っていただいたお金は、本や、資材購入に当てられます🌹

