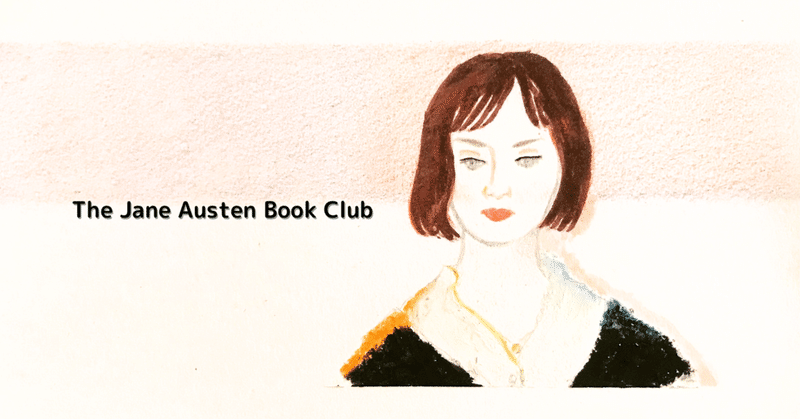
ジェイン・オースティンの読書会
『ジェイン・オースティンの読書会』(以後、本書)は、映画から入った。
プルーディー役の、エミリー・ブラントの熱演を見て以来、
原作を読みたいと思い続けてきたが、最初にそう思ってから、数年が経った。
その後、同じくアメリカのSF作家、テッド・チャンの作品を
(これまた『メッセージ』という映画で)知って、読み漁り、
彼が個人的に影響を受けたと感じる作家の一人に、
カレン・ジョイ・ファウラー(本書の著者)が、挙げられていることを
知ってなお、本書を手に取るまでには、さらに、数年かかった。
その理由のひとつは、おそらく、テッド・チャンも、
カレン・ジョイ・ファウラーも、SFの作家として知られているにも関わらず、
『ジェイン・オースティンの読書会』は、SFでなかったことにある。
SFの作家なら、まずは、SFの作品から読みたい。
しかし、いかんせん、邦訳がなかった。
ところで、これだけSFと連呼しておきながら、
実は、わたしは、正統派の作品をほとんど読んだことがない。
そもそもわたしが、テッド・チャンの作品に惹かれるのは、
彼の作品が、むしろ典型的なSFではないところに、あるかもしれない。
彼の作品は、人間を違う文脈においたらどうなるか、を問うというよりは、
そもそも人間を人間たらしめている文脈、そのものを、
問いの対象にしている気がするのである。
その問い自体は、SFに限定されない、より普遍的なもので、
彼の場合、問いかけの枠組みが、たまたまSF的だったのではないかと感じる。
(確か、テッド・チャン自身、自分の作品がSFなのかどうかはわからない、
という立場をとっていたように、記憶している。)
カレン・ジョイ・ファウラーは、
わたしにとって、そういう文脈のなかで現れた、
非SFも書くSF作家(しかも、SFに関しては情報が皆無)だったのだ。
なぜ、このようなことを長々と書くかというと、
こういう経緯が、いざ本を読むというときに、
なにか影響を与えることがなかっただろうかと、思ったからである。
さて、肝心の本書だが、タイトルの通り、(その大半が)
生粋のジェイン・オースティン好き、による読書会(※1)の面々を巡るお話である。
ジェイン・オースティンを読んでいれば、
より面白いのだろうが、読んでいなくても楽しめる。
本書巻末の、読者のためのガイドを読むと、どうやら、
ジェイン・オースティンは、評価が真っ二つに割れる作家のようである。
シェイクスピアと並べる人もいれば、「『自負と偏見』を読むたびに、
彼女の死体を掘り起こして…(中略)…頭蓋骨をひっぱたいてやりたくな」る
などと、こき下ろす人もいる。
(ちなみにこれを言ったのは、『トム・ソーヤーの冒険』の著者である。)
しかし、人によっては、ジェイン・オースティン前か、後か、
くらいの、インパクトを与える作家でもあるようだ。
全き前者であるわたしには、しかし、本書に、
ジェイン・オースティンの影響を読み取ることはできないので、
「①オースティンを読んだことがない人(※2)」として、
二、三、印象に残ったことについて書いてみたい。
ひとつめは、アレグラ(読書会を主催したジョスリンの親友、シルヴィアの娘で、レズビアン。母娘共に、読書会のメンバー。)の幼少期の話。
彼女は、四歳の頃、読んでいた雑誌の余白が気に入らず(「白は嫌い。つまんないんだもん」)、目につくすべての余白を、泣きながら塗りつぶしにかかったが、彼女が泣いていたのは、「けっして終わりがないことを知っていたから」だと言う。
「アレグラの人生は、このたったひとつの困った好みを満足させるために、永久に空しく費やされていくだろう。」
多くの人にとって、好みを満足させるのは、そう厄介なことではない。しかし、つまんない余白が嫌いなアレグラは、作中だけで二度、大怪我による入退院をした。
ふたつめは、メンバー中、唯一の男、しかもSFファンで、読書会以前には、ジェイン・オースティンを読んだことのなかったグリッグが、ホスト(読書会は、月毎に一冊本を選び、ホストになったメンバーの家に集まって行われた)を務めたときの断章である。
グリッグの家の「カウチの足元に敷いてあるラグは、ひとめ見てサンダンスの通販カタログで買ったものだとわかった。隅にポピーのついたタイプで、私たちもみんなほしいと思って見たことがあるからだ。」とある。
欧米の小説では、類型化された生活様式や行動パターンによって、ある人物の人となりを暗示するというやり方を、ちょくちょく見かけるように思う。この場合、誰もが見分けのつく特徴的なラグ、によって、グリッグの消費行動や嗜好までが垣間見えてしまうのである。
類型化はまた、物語において、物指しの役割を果たす。物指しがあることによって、そこからはみ出た、個性や非日常に、焦点を当てやすくなる。(ミス・マープルは、それを大いに活用して、事件の本質をいち早く見出す。)
もし、読書会のメンバーのうち、最も類型化と親和性の高い人物を挙げるとしたら、それは、アレグラの母、シルヴィアということになるだろうか。彼女は、慎重で、なかなか自分の感情を表さない。「家族と一緒にいても、どこか防備を固めているようなところがあった。」
しかし、その慎重さこそが、夫が年下の恋人をつくって家を出るという、彼女のおよそ望まないであろうドラマ(非日常)を、日常に引き込んだ大元だった。ちなみに、彼女はスペイン系の家系で、学生のころは毎日、英語のわからない祖母のために、「よくまあ事件の起こる」メロドラマの通訳をしていた。
と、ここまで来て、やはりSFとの決定的なつながりを見つけるのは、難しい。
本書は、あくまでも『ジェイン・オースティンの読書会』なのだ。
それでいて、何かしら、未知の広がりのようなものを感じさせるのは、
著者の筆力のなせる業だろうか。
余談だが、彼女は政治学を学んだのち、卒業と同時に結婚、
大学院では、日本と中国の研究をしていた。
子どもが生まれてからは、母親業に専念、
三十歳になってから、大学でクリエイティブ・ライティングのコースを取り、
作家になる決心をしたという。
クリエイティブ・ライティングを受講する前には、(プロになるつもりで)
ダンスにも挑戦していたというのだから、守備範囲がとにかく広い。
こんな経歴ひとつにも、感心してしまうのは、わたしだけだろうか。
いつか、SFの邦訳も読んでみたいものだ。
そのときには、また別の楽しみ(テッド・チャンが、彼女からどのように
影響を受けたのか、自分なりの仮説をたてる)が待っているだろう。
本は、一度読んだらそれで終わり、とならないところに、醍醐味がある。
『ジェイン・オースティンの読書会』
カレン・ジョイ・ファウラー著、矢倉尚子訳
(※1)(内容は「訳者あとがき」より抜粋)
読書会とは「欧米の場合は、むしろ社交サークルに近くて」「参加者は圧倒的に女性である。」「通常は毎回リーダーを決め、一回に一冊の本を取り上げてディスカッションする。」場所は、メンバーの家で「コーヒーとケーキをいただきながらというのが多いが」、図書館、書店などの場合もある。
(※2)(同上)
ファウラーは、小説を書くにあたって「①オースティンを読んだことがない人、②昔一度読んだだけの人、③毎年読み返す人、の三種類の読者を想定し、すべてを満足させられるように工夫をこらしたという。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
