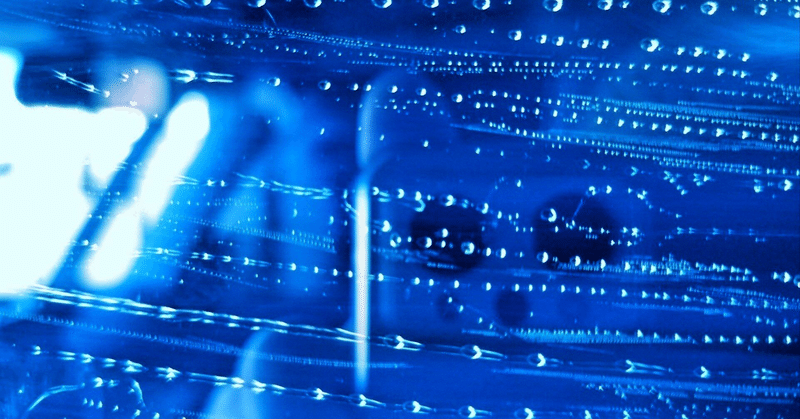
連載小説『エフェメラル』#3
第3話 宴のあと(前編)
「っていうか、ちょっと、酒、持ち込みすぎなんじゃねえか?」
エマは自分の船の中で開かれている宴会を、他人事のように眺めながら言った。再びエマの船に乗ることになったユーヒは、お酒が入ってご機嫌なジルと一緒になってお喋りをしてはゲラゲラと大声で笑っている。
月を出発したその日の夜、エマの船の新たな同乗者となったジルは、「せっかくだから、歓迎パーティーやろう!」と自ら言い出したのだ。
「エマ、別にいいじゃないの。これは私がみんなに飲んだり食べたりして欲しいと思って持ってきた、個人的な差し入れ。目的地までは三日間もかかるんだからさ。楽しもーよ!」
ジルはそう叫びながらソファに座っていたエマの隣に座り、腰に手を回す。二人の身長差のおかげで、傍から見れば仲の良い母娘のように見えなくもない。
「おい!くっ付いてくるんじゃんねえ!つーか、お前、急に慣れ慣れしくなったな。おいリン。この酔っ払いメガネ女をなんとかしろ。お前の姉ちゃんみたいなもんなんだろ?」
部屋の隅っこにある椅子でその大きな体を折りたたむようにして座ってたリンは、エマの問いかけを当然のようにスルーした。
「無視すんな!じゃあユーヒ、お前が相手してやれ」
「まあ、相手するのは全然良いんだけど、宴会が始まってから、私、ずっとジルと話してんだよ。ジルはさあ、エマとお話したいのよ。ジルの言動、見てりゃわかるでしょ?」
「そうよー。私はねえ、一目見たときからエマのことが気になってたのよー」
ジルにひっ付かれたままのエマは迷惑そうな顔をしながらも、ジルの手を振りほどくことなく、渋々その状況を受け入れていた。
ジルをエマに預けたところで、ユーヒはリンの元へ歩み寄る。
「リン。あなたもこっちに来て、一緒に飲もうよ。一人は寂しいよ?」
ユーヒの言葉を聞き、リンはユーヒの顔を一瞥するだけで返事はしない。
「話すのが苦手なのも、一人でいるのが苦でないことも分かってる。あなたはそれで良いかもしれないけど、私はそれじゃあ嫌。一緒にいるみんなで楽しみたい。私は欲張りだからさ。リン、私のわがままに付き合ってくれないかな?」
リンはしばらく考え込むように床を見つめていた。そして、ためらいがちにその口を開く。
「酒は飲めない」
「うーん。じゃあ、私と踊ろっか?」
「そんな訓練は受けていない」
「ふふ、ははは。訓練って、変な言い方だね。まあ、いいや、とにかくこっちに来て!」
ユーヒはリンの左手を掴んで椅子からグッと引っ張り、リビングの真ん中に連れてくる。
「エマ、曲をお願い!」
ユーヒに請われたエマは、ここぞとばかりにジルの腕を振りほどき、運転席まで速足で移動してラジオのスイッチを入れた。エマがいつも聴いているジャズ専門チャンネルから、ピアノトリオによるミドルテンポの曲が流れ出す。リンの手を取ったまま、ユーヒは音の波に乗るようにステップを踏む。リンはユーヒに操られる大きな人形のように揺れ動いていた。
「あら、なんと。リンが女の子と踊っている……」
ジルは二人の様子を見て、メガネの奥の目を真ん丸に見開き、珍獣に遭遇したかのような驚愕の表情を浮かべている。
「そんなに驚くことか?」
エマは運転席側からリビングを眺めながらつぶやく。
ユーヒとリンは踊り続ける。
ジルはそれを見守り続ける。
二人が踊り続けている間、リビングにはラジオが奏でる音楽と、四本の足が刻む足音だけが響いた。
踊る二人、そしてそれ見ながら微笑むジルを横目に、エマは一人、バスルームに通じる廊下に移動した。あたしはあの中には入れない。疎外感。それはエマの思い込みに過ぎないのだが、当の本人には、それが宇宙の真理であるように思えた。自分の船なのにな。エマは暗い廊下で一人きりになっている自分を嘲る。
「なあに?エマ、楽しい宴会抜け出して、一人で宇宙について考えでも巡らせてんの?」
廊下に来たのはジルだった。廊下の壁に寄りかかるエマの隣、同じように壁に寄りかかったジルは、胸元から煙草を取り出した。
「吸っても良い?」
「灰を落とさなければな」
ジルはライターで煙草に火を点け、一口、大きく煙を吸い込んで心と肺を満たす。
「エマ、あなた、元兵士でしょ?」
唐突な発言に身を硬直させるエマ。
「なぜそう思う?」
「そんなの、身のこなしを見れば分かる」
「そうか。っていうことは、お前もそうなんだろ?ただの医者じゃない。その制服だって、軍服そのものじゃねえか。医者っていうのもウソかもな」
エマの言葉を、ジルは否定しない。
「あなたが思っているとおり、兵士としての訓練も受けている。でも、医者なのは本当よ。兵士兼任の医師ってところね」
ジルは寄りかかった壁と反対側の壁に向けて口から煙を吐く。煙を吐いた肺に、今度は空気をしっかり吸込んでから、エマに自分の声がはっきりと聞こえるように言った。
「エマ……『エマヌエラ・コーディナル』。あなたのことを、私たちは知っている。たぶん、あなた以上にね……」
★
エマのトラックが目的地である人工惑星に向かっている頃、三台のトラックがエマのトラックと同じ場所を目指して暗い宇宙のハイウェイを進んでいた。
「今のうちに仕掛けたほうが良いんじゃないんですか?」
三台のトラックの中で一番後方に位置するトラック乗った少年が運転手に声をかける。
「ダメだ。マイルスの兵隊が目を光らせている。船の外からも、中からもな」
少年は本心からそんな質問をしたわけではないし、その答えを運転手から聞き出そうとしたわけでもない。これから始まる作戦に参加する自分の決心を確認するための自問だ。
「狙うのは、ターゲットが施設に入ってからだ。一番無防備な状況を狙う。それが今回の作戦の最も重要な点だ。あれだけシミュレーションを重ねたんだ。必ず成功する」
運転手は聞かれてもいないことまで少年に話した。バカじゃないんだ、そんなの分かっている。と、少年は心の中で言い返す。しかし、こいつが言っている『成功』ってなんなんだろうか。もちろん、ターゲットを殺すことが作戦の目的だから、どんな形であれ、人を一人、この世から葬り去れば作戦の目的は果たされたことになる。しかし、敵の懐に飛び込む形で行われるこの作戦で、生き残れる者が何人いるのだろうか?向かっている人工惑星が、医療研究のためだけに作られたものだとしても、施設を守るマイルスの兵士がかなりの数、常駐しているのだ。トラック三台に積んだ大量の武器があったとしても太刀打ちできるものではない。そんなことを考えている少年に、運転手がニヤニヤしながら話しかける。
「どうした小僧。ビビッて声も出ないか?」
少年は禿げ上がった小太りの運転手の言葉を無視する。今のうちほざいてろ。どうせお前も死ぬんだ。だが、おれは生きて帰る。おれには待っている人たちがいる。どんな形でもいい。絶対に帰る。
――ナンバー1から各艦へ。同胞からの伝達だ。事は予定通り進んでいる。このまま入港せよ、とのこと。各員は、目的地到着後の荷物の受け渡しを確実に実行すること。
先頭を行くトラックからの通信だ。目的地の入港ゲートには、数か月前から現地入りしている仲間が、入港ゲートの管理区域に潜入し、船を入港させるための準備を着々と進めていた。入港さえしてしまえば、あとはどうにかなる。しかし、入港の時刻だけは確実に守らなければならない。ターゲットが施設で最も長い検査に入るタイミングで作戦が決行される。そこから逆算して入港するのだ。これから行う作戦は、だれがどう見ても明らかなテロ行為であり、その理由がいかなるものであっても、法的にも倫理的にも正当性が認められる余地はない。少年はそう考えている。作戦司令部は『大義』という言葉を使ったが、それが単なる言葉遊びであることは、多感な年頃の少年には直観的に分かってしまう。それでも少年は作戦に参加する。なぜなら、それが彼の仕事だったからだ。生きるために、金のために、他者の命を奪う。
――ナンバー1から各艦へ。ターゲットが検査を開始した。これから入港する。作戦成功に向け、各自の幸運を祈る。以上!
いよいよ入港。少年は、胸の前で両手を組み、目を閉じて祈る。右手首に二重螺旋の腕輪が光る。
「『アオ』にまします光の女神よ。迷える我らに、永遠の安寧を与えたまえ……」
行動を起こす前のルーティン。少年の決心は固まった。
☆
ユーヒは毎年の健康診断で着るような、寝間着のような服を着させられて、ジルからこれから行われる検査についての説明を受けていた。
「はい、じゃあユーヒちゃん。生年月日を教えてくれるかな?」
「生年月日か。うーんと、AE453年の8月23日。でもさ、これ、『本当の』誕生日ではないんだけどいいかな?年はだいたい合ってると思うけど」
「別に良いよ。これは検査終了後、本人確認のための暗証番号みたいなもんだから。施設で育った子で、本当に自分の生まれた日を分かっている方が珍しいんじゃない?ちなみに、私も実際に生まれた日っていうのは知らない。でもこれまでの人生、それで困ったことなんて一つもない」
ジルは説明を続ける。
「検査はたくさんあるよ。身長体重、血液、内臓の検査。身体組織に関する検査だけじゃなく、あなたの精神世界についても、可能な限り調べさせてもらうわよ」
「精神世界って何よ?私の夢の世界にでも入り込むつもりなのかね?」
ユーヒはおどけた調子でジルに聞く。
「まあ、当たらずも遠からず。人が細胞レベルで記録しているデータにアクセスするのよ。地球に行く前と行った後で、その変化を調べたいから。ユーヒちゃんは、そのあたりは気にしなくていいよ。こっちの問題」
私の体なのに、こっちの問題とかあっちの問題とかってあるのかな。ユーヒは少し考え込んだが、考えてもきっと分からない、ということが分かったので、それ以上考えないことにした。身長伸びてるかな?体重……きっと増えてるだろうな。ユーヒはそんなことを思いながら、ジルに言われるがまま、次から次へと検査をこなしていった。
ユーヒが検査を受けている間、エマはジルから指定されたの部屋で検査の終了を待っていた。おそらく、施設で検査などを受ける家族の待合室のようなものだろう。リンは施設の知り合いに会いに行くのでしばらく別行動になる、とジルが言っていた。要するにエマは一人きり、置いてけぼりをくらっている。見知らぬ施設の中でエマができることと言えば、暇を持て余すことぐらいだ。
「まったく、なんて扱いだ。あたしの船でここまで連れてきたってのに『じゃあ、ここでゆっくりしててね!』とか言ってよー。完全に放置プレイじゃねえか。あのメガネ女が!」
エマは一人吠えてみたが、実際、そんなことぐらいしかすることがない。怒りのやり場もなければ、話し相手もいない。まあ、あのメガネ女と二人きりになるぐらいだったら、一人の方がマシだな、と自分を慰めてみたりもする。諦めてベットに横になっていたら急激に眠気に襲われ、エマは気を失ったように寝てしまった。
「おーい、エマー。寝てんの?」
声に気が付いて目を擦ったエマは、ぼやけた視界にジルの姿を認める。
「おお、メガネ女。ユーヒの検査は終わったのか?」
「メガネ女って言うな。ユーヒは最後の検査中よ」
エマは月を出発したその日の夜、ジルがエマを知っていると言ったことについて、まだその真相を聞き出せていなかった。そのときもジルは「ちょっとだけ、あなたのこと調べただけよ。トラック組合の事務所で初めて会った時から気になっちゃってたからね」といってはぐらかしていたが、ユーヒと行動を共にするエマのことを、この施設に来るにあたってかなり詳細に調べたに違いない。
「おい、メガネ。お前、あたしの過去について調べたんだろ?」
「んー、何、まだ気にしてんの?」
エマはこれ以上この話を長引かせるかどうか迷ったが、今後のこともある。はっきりさせようと思った。
「あたしは昔、お前の会社に世話になったことがある。正確には、お前んとこの会社の技術に、だけどな」
ジルはエマに背を向け、部屋の窓から人工の空を眺めたままエマの話を聞いている。
「だから、あたしの生体情報はお前の会社にあるってことだ」
窓に向けていた身体をくるっと回転させたジルは、少し間をおいて話し始める。
「そうね。そのとおりよ。マイルス商会は人体の再生医療で発展してきた企業だからね。再生した患者のデータは、その臨床試験におけるデータを含めて、全て管理している」
やっぱりそういうことだよな。エマは予想通りのジルの言葉を聞いて、むしろホッとしていた。それ以外の話のほうがエマを悩ませただろう。もう12年も前の話だ。
「ユーヒにそのことは言うなよ。まあ、別に言ったところで特に問題はないが、ユーヒには関係のない話だ」
「分かってるよ。一応、守秘義務っていう言葉の意味は理解してるつもりだから」
ジルはちょっと困ったような微笑みでエマを見つめる。あなたのこと、私はちゃんと理解している。とでも言いたいのか。その笑みに哀れみが込められているなら、見当違いも良いところだ。そうエマは思った。
「でも、お前が一方的にあたしのことを知っているのは不公平だよな」
「あら、あなたさえ良ければ、いくらでも私のことを教えてあげるわよ!」
ジルがそう言った直後だった。
ドドドドドッッ、、、ゴゴーーーーーーン
爆発音とともに、施設が大きく揺れた。
「なんだ??」
エマとジルは突然の轟音と振動に困惑した。しかし、その直後に施設内に非常事態を知らせる警報が鳴り響いたことで事の重大さを認識した。
「ユーヒがヤバい!」
ジルはそう叫ぶと同時に部屋を飛び出し、ユーヒが検査を受けている部屋に向かって走り出した。エマも反射的にジルの後を追った。
★
ユーヒは最後の検査中だった。直径3メートルはあると思われる球状の検査装置の中に入ってから、およそ30分が経過していた。装置の中に入っていたユーヒは、心地よい振動と、ボヤっとしたピンク色の光によって仮眠状態になっていた。ユーヒ本人が仮眠だと思ったのは、ぼやけた意識でも、自分が今何をされているか、どこにいるのかをはっきりと認識できたからだ。眠っていはいない。それは感覚的にも明白だった。やがて、そのピンクの光は徐々に白い光に変化し、その後は少しずつ青い光になっていった。
「なんだろう……とても落ち着く」
それは湖に浮いているかのような感覚だった。プカプカ浮かぶ体と、そこから見上げる空。ああ、ここは私の故郷、テティスなのだろうか……いや、違う。テティスの空は、もっと人工的というか、もう少しビビットな色だ。今見えている空は、テティスの空よりも淡い青。そこに、綿のような、白いものが浮かんで見える。たぶん、地球で見ることができるという『雲』なのではないか。そう思った瞬間、意識が遠のいた。時間が経過する感覚も失われていった。ただ、真っ青な空間に、その意識、存在だけが剥き出しで放り出されてしまったかのようだった。
――どうしたの?こんなところで……
ユーヒの意識に直接語りかける声。「あなたは、誰?」ユーヒは声にならない声を発する。
――私は、私。誰でもない。あなたがあなたであるのと一緒
ユーヒの意識は混濁している。もはや、その声と自分の声の区別がつかなくなっている。ぼんやりとした視界に、小さな影が近づく。それが影なのか、光なのか、ユーヒにはその判別もできない。ただ、それが人型のシルエットであることは分かった。
――早く、早く来て。わたし、待ってるから。会えるまで、待っているから……
ユーヒに語りかける影(もしくは光)が、どんどん遠ざかっていく。ひらひらと舞う、蝶のように。「待って、行かないで!」そう思った瞬間、爆発音とともに衝撃が襲った。球状の装置は、爆撃によって吹き飛ばされ、部屋の壁に衝突して大破した。ユーヒは装置の中から投げ出され、床にたたきつけられる。
「やあああああああ!」
痛みに叫ぶユーヒ。その声に反応して駆けつける人物が一人。宇宙での戦闘用に作られた装備をまとい、二重螺旋の腕輪をつけた右手にライフルを持った少年。呻くユーヒにその銃口を向けている。
「恨みはない。仕事なんだ」
誰に対して言っているのか、少年自身にも分からない。いよいよ少年が引き金を引こうとしたその直前、床で倒れていたユーヒが寝返りをうつように少年の方へ顔と体を向ける。うつろな目が、少年を見つめた。
「青い目……」
少年が動揺し、銃口をユーヒから外した瞬間だった。大きな爆音が響き、コンマ数秒後に爆風が少年を襲う。吹き飛ばされた少年は、ユーヒの背中側にある壁に叩きつけられ、気絶する。少年を吹き飛ばした爆発の方向から、リンが姿を現す。素早い動きでユーヒの元に駆け寄ると、割れ物を扱うかのようにユーヒを丁寧に抱きかかえ、爆発の影響のない出口へと向かう。そこに、ジルとエマが合流した。
「大丈夫か、ユーヒ!」
エマが大声で話しかけるが、ユーヒの反応は無い。エマは部屋の奥に、もう一人の人影を認める。
「あいつがやったのか!」
エマは胸元から銃を取り出し、部屋の奥で倒れている少年に向かって走り出した。至近距離に近づいてから、少年に銃口を向ける。
「だめ!エマ。殺さないで!」
ジルの叫びにエマは思いとどまる。
「リン、ユーヒは私が預かる。早くあいつを捕まえて!」
リンはジルの指示に迅速かつ正確に対応する。ユーヒをジルにゆっくりと手渡し、その後、倒れている少年を手際よく縛り上げた。施設はいまだに非常警報が鳴り響いてた。
「今はとにかくここを離れるの。まずは、エマの船に戻りましょう」
ジルの言葉に、エマとジルは無言で頷き、エマの船が停泊している入港ゲートに向けて走り出した。ジルとリンにそれぞれ抱えられた少女と少年は、身動き一つしていない。
「どうしてこんなことになったんだ」
なぜ、ユーヒがこんな目に遭わなければならないんだ……走りながら、エマは心の中で叫ぶ。ユーヒに対する心配、現状に対する不安は時間が経つにつれて強くなる。それはまるで得体の知れない黒い塊がエマの胸から腹のあたりで風船のように少しずつ大きく膨らんでいくようだった。エマの心はその黒い塊に圧迫されて、歪に変形していた。
つづく
