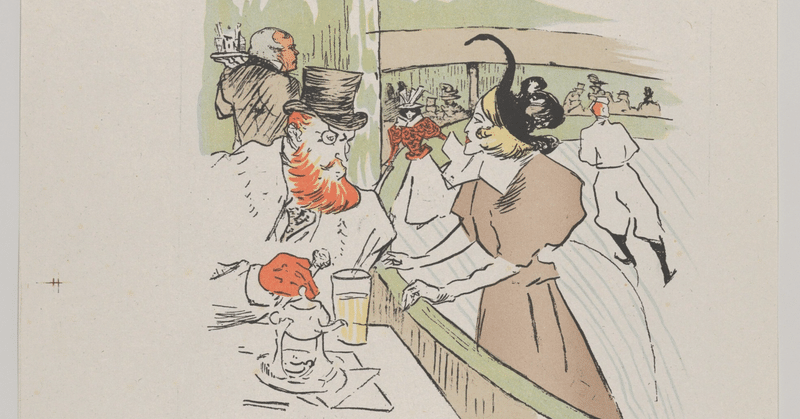
【side A】世界中のありったけのきれいな言葉を集めて
初めて自分に怒りを覚えた日を私は明確に覚えている。
その男の子は、大上くん、という名前だった。
小学校の入学式当日。南の窓から差し込む日差しで埃が舞うさまが見える教室で、私は初めて出会う人種に会った。浅黒い肌、こぼれ落ちそうにおおきな瞳。くっきりとした輪郭を持つ唇や、小さな鼻ですらどこか他の子とは違った。
私の隣にいた彼は、肩をすぼめ、けして誰とも目を合わせないように机に目を落としていた。周囲の子ども達は配られた教科書を騒ぎながら読み上げたり、真新しいノートや鉛筆を誇らしげに見せびらかしている。だが、彼は喧噪の中で、これから起こるできごとに怯えているように見えた。
教科書に自分の名前を書けという教師の声に従い、筆箱から油性ペンを取り出した。名前を書き終えて息をつくと、隣の机の上にある小さなこぶしが、ぎゅっと握りこまれているのが見えた。
浅黒い手の甲の肌にピンク色の爪が食い込んでいる。俯いていた顔はいよいよ机にのめり込みそうなほどに下を向き、けれど、彼は目を見開いていた。瞳に、まるく液体の膜が張っていた。
既にその時から、気づいていたのだ。誰も彼に助けの手を差し伸べようとしないこと、そして、彼が何も口に出さないならばそれが彼の日常であることを。けれど、私は口を開いた。
「ペン、持ってないの?」
薄く涙の膜が張った瞳が、噛み締められていた唇が同時に開いた。信じられないものを見た、というような顔をしていた。私は、油性ペンを彼の机に押しやった。
「ありがとう」
教科書に私のペンで書かれた名前で、彼が、大上くん、であることを知った。
大上くんは、忘れ物が多かった。赤ペンから始まり、教科書、定規、漢字ドリル、体操着、給食袋、時には上履きまで。私が、教科書やペンを貸すのは日常となった。けれど、彼は、一度も、私に「貸して」とは言わなかった。
いや、それは欺瞞だ。私は、当時からわかっていたはずだ。
言わなかったわけじゃない。言えなかったのだ、彼は。
入学して一ヶ月ほど経った休み時間に、廊下で同じクラスの女生徒に声をかけられた。彼女は、苛立ちをにじませながら言った。
「ねえ、三谷さん、どうして大上と話すの?」
背の高い彼女を見上げた。吊り上がった細い目の上の眉が大人のようにひそめられていた。
「あいつ、気持ち悪いでしょ。幼稚園の時からそう言われてた」
ざわめいていた廊下が、幕を引くように静けさを増した。彼女は、続けた。
「あいつと話しちゃだめだよ。じゃないと危ないよ。大丈夫。話さなければこっちに入れてあげるから」
翌日から、私は学校に行けなくなった。
周囲を人間だと信じていたが、実は全員アンドロイドか宇宙人だった。
映画や小説でよくある設定だが、当時の私の視界はまさにそれだった。本当に、彼女の言葉を聞いた瞬間に廊下を行き交う人々全員が、緑色のどろどろした粘液状の得体のしれない何かに見えたのだ。世界と人に対しての認識は、同じ土台の上で動いているという基礎があってだ。だが、世界は私が当たり前に信じていた土台とは全く異なるルールで動いていたのだ。
世界は、いきなり、異界になった。
親も、教師も、生徒も心配した。なぜ学校に行けなくなったのか、当時の私に筋道立てて説明する力はなかった。全員が宇宙人に見えたから、なんて、今の年齢になっても言えるわけがない。だが、本当にそう見えたのだ。気持ち悪い。「気持ち悪いでしょ」というあなた達が私にはどうしても気持ち悪い。
学校に行けなくなった間、教師や生徒から届く「あきこちゃん早く学校に来てね」という手紙や連絡を見て、そして、学校にもう一度行き始めた時の腫れ物に触るような周囲の振る舞いを見て、私は太宰治の言うところの『道化』の気持ちを理解したような気がする。
“つまり、自分は、いつのまにやら、一言も本当の事を言わない子になっていたのです”
それからも、私は忘れ物をする大上くんにものを貸し続けた。その行動が、周囲から「三谷さんは優しいから可哀想に」と思われていることを私は自覚し始めていた。そうなの、本当は嫌なんだけど仕方なく。ペンを貸す時の表情から、教科書を二人で見るために机を寄せる時の一瞬のためらいから、私は、その気持ちを周囲に見せるように心がけた。
大上くんは、その時、私の心境に気づいていたと思う。けれど、何も言わなかった。
ごめんなさい、と思う気持ちを持つことも許されないと思った。哀れまれるべきは自分だった。だって、大上くんの方がずっときれいだから。結局、緑色の粘液にまみれた私よりずっと。
そして、一学期の終業式がやってきた。
終業式のあと、教師が、二学期に、隣の席になりたい人を紙に書いて先生に渡してください、と言った。今の時代ではそうそうありえないことだが、当時、こういったことはごく普通に行われていたのだろう。
教室内はざわめき、浮足立っていた。一人を除いて。
すさんだり、自暴自棄になっていたり、どこかおかしくなった人間は、大人になってから何度か見てきている。だが、絶望に叩き落された瞬間の人間を見たのはあの時、一度きりだ。教室の中、机の前にいるしかない、まっ暗な、本当にまっ黒の、顔。
大上くんが、こちらを見た。
あの、まるくて大きな瞳で。
黒目に、本当にきれいな黒目に、私が映っていた。
生徒から紙を集めたあと、教師が私にそっと皆が帰ったあとに残るよう囁いた。教師が使うスチールの机の前、西日が差し込む角度、消したばかりの黒板のチョークの粉っぽさ、すべてを鮮明に覚えている。
「三谷さんは来学期、前川くんの隣になりたいって書いていたけど……」
そこで口ごもり、教師は続けた。
「お願いがあるの。二学期も、大上くんの隣になってもらえないかな」
その時の私は、どんな顔をしていたのだろう。自分の表情はわからない。ただ、体の側面に落とした手の、こぶしが、震えているのはありありと思い出せる。
知っていたなら、わかっていたなら、なんで。
そして、なんで、私も、ほかの子の名前を書いたの。
そう、これも刻銘に覚えている。もう、仕方なくやっている、というポーズは限界に近い、と私は気付いていた。二学期も大上くんの隣になったら、私も学校の中で「気持ち悪く」なるだろうと。
希望者を書く紙を前にして、私は人を裁き、選んだ。
それなりに学校でうまくやっていて、粗野でも乱暴でもなくて、人気のあるグループにいるわりにはそこまで目立たず、要は楽で、無難な男子を。
本当は誰よりも、大上くんの隣にいたいと思っていたのに。
「わかりました」
そう答えた私の震えるこぶしと唇を、教師は、きっと大上くんの隣になることがいやだからだと受け取っただろう。
違う。
私は、自分を恥じていた。自分に、怒り狂っていた。
嘘つき。気持ち悪い。嘘つき。
帰り道、あの緑色の粘液はもう吐いても吐いても取返しのつかないところに吸収されてしまったのだと思った。
二学期に、大上くんの姿は教室になかった。教師は、転校をしたと言った。小学校の一学期で転校をせざるを得なかったほどの状況だったのだろうと、私は思った。いや、違う。私は、知っていた。最初から。私だけじゃない、生徒も、もちろん、教師も。
今、振り返れば、大上くんは東南アジア系のハーフだったのかもしれないと思う。彼の浅黒い肌や大きな瞳は、日本人離れしていた。あの、小学校の一学期のみで転校せざるを得ない状況も、彼の出自から来ていたとしたら。そう思うと、ますます口の中が苦くなる。
言えばよかった。
私はあなたが好きだ、と。
気持ち悪いのは周りで、あなたは全然きれいで、私もそう在りたかった、あなたと一緒にいたかった、と。
私は今、緑色の粘液を飲んでいる?
時々、私は自分にそう問いかける。
一見きれいなグラスに入った緑色の液体は大人になった今も時折、目の前に差し出される。
そんな時、私は大上くんの話をする。
彼の瞳はきれいなままだろうか。私の中にはまだ緑色の粘液が残っているだろうか。
もしも、彼に会えたなら、私は言いたい。
世界中のありったけのきれいな言葉を集めて、あなたはきれい、本当にきれいだと。
作家/『ILAND identity』プロデューサー。2013年より奄美群島・加計呂麻島に在住。著書に『ろくでなし6TEEN』(小学館)、『腹黒い11人の女』(yours-store)。Web小説『こうげ帖』、『海の上に浮かぶ森のような島は』。
