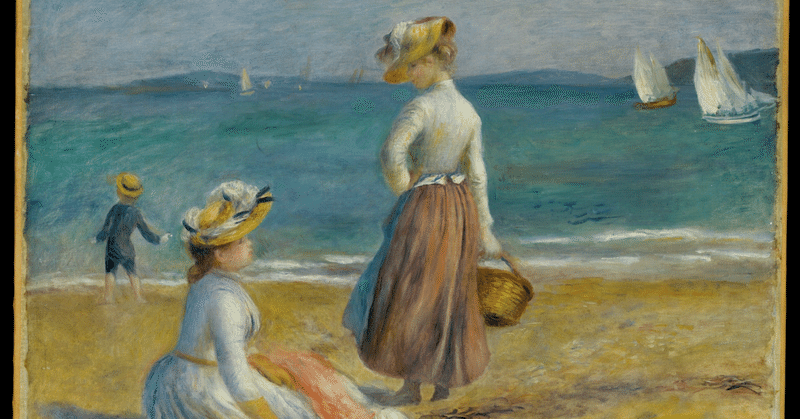
【side B】菓子パンとフライドポテトしか食べられない女の子は
真夜中のファミリーレストランで、山盛りのフライドポテトを前にして彼女は言った。
「怖いんです。食べることが」
日焼けした肌、全く肉感のないまっすぐな脚。腰と胸のボリュームが控えめなバービー人形のような体型をしていた彼女は、私が当時勤めていたキャバクラの同僚だった。年齢は19歳。いかにも若くていかにもギャル風の見た目をした彼女の太ももの隙間から見える景色は、羨ましいというよりも逆立ちしてもなれないスタイルというものがあるな、と知るに足るものだった。
私の勤めていたキャバクラに当時は10代の女の子はいなくて、その頃、古株になっていた私は彼女と何となく話すようになった。彼女は大学生で、家の近くのファミリーレストランでもバイトをしていて、何かの拍子に店のボーイと二人で彼女のアルバイト先を冷やかしに行った。
話の成り行きはキャバクラのお客さんから同伴を望まれている、というところからだったと思う。
「いいじゃん、同伴だと同伴料ついて成績上がるし。あのお客さんは美味しいもの食べさせてくれるよ」
私はそんな風に答えて、そうしたら彼女は言ったのだ。
菓子パンとフライドポテトしか食べることができない、と。
「そんなカロリーの高いもの食べても細いなんて羨ましい、やっぱり若さかな」
そんな風に言ったら、彼女は違うんです、と答えた。
彼女の家は母子家庭で、母親は遅くまで働いていて、夕飯はいつもテーブルの上に置いてあった菓子パンだったという。もしくは、学校帰りに友達と寄るファストフード店で、友達から分けてもらうフライドポテト。
「ずっとその暮らしだったから、今でも他のものが食べられないんです。何だか怖くて」
そう言いながら、冷めかけたフライドポテトを氷の解けたコーラで彼女は流し込んだ。
「お客にそのことを言うと偏食だ、どうだってうるさいから、適当にごまかしてつまむ程度にしといたら? もしくはお店の前はお腹が出るからあんまり食べないようにしてるって言うとか」
同伴を乗り切るテクニックとして私はそう答えた。それ以上、何かを言うつもりはなかった。
そんな食生活してたら体に悪いよ、世の中には美味しいものがいっぱいあるよ、食わず嫌いはよくないよ。
そんな正論は、本人だってわかっていて、既にそれを受け入れられない自分をさんざん責めているはずだ。だから、私は、何も、言わない。
と、その頃の私は思っていたのだが、今はまた感じ方が変わってきている。
別に、健康でも不健康でもいいじゃない。みんな、好きなように生きている。
過去の私は、どこかに正しい生き方があって、どこかに幸せの定型があって、それに沿うように暮らすことが人の本来で、けれど、それができない人もいる、という風に考えていたのだと思う。
そう、みんなが「幸せ」になりたいはずだ、と。
しかし、その考えは、どのコースとルートと状態が「幸せ」かと自らが幸せを定義している状態である。自分の分の幸せを定義するのは、自分の裁量において好きにすればいいが、他人の幸せを勝手に定義するのは、全く、おこがましいことだな、と今なら思う。
自分が感じる幸せを、相手も感じてくれたらうれしい。
その気持ちは今も私にあり、だから、加計呂麻島に来てくれた友達が楽しそうだと本当に嬉しいけれど、同時に私が、それ完全に破滅だし地獄だよね、と思うルートが幸せな人も世の中にいて、一言で言えば、好きに生きることが出来てよかったね、という話なのだ。
どっちが闇でどっちが光かなんて、もう考えるのも面倒くさい。
あの彼女が今もフライドポテトと菓子パンだけで生きているなら、それはそれでいいし、どこかで思い切り方向転換してマクロビオティックやヴィーガンに目覚めているのも、まあ、よくある話である。
それもすべて物語という名のライフストーリー。
陳腐さを嫌う自らの陳腐さなど、もう、どうでもいい話。
作家/『ILAND identity』プロデューサー。2013年より奄美群島・加計呂麻島に在住。著書に『ろくでなし6TEEN』(小学館)、『腹黒い11人の女』(yours-store)。Web小説『こうげ帖』、『海の上に浮かぶ森のような島は』。
