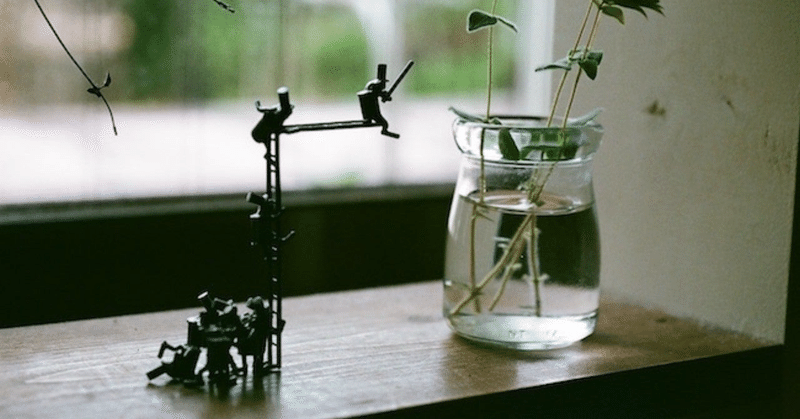
家族の自宅介護と住宅環境のはなし①
自宅で10年にわたる介護を経験し、建築家として感じたことを自宅介護リフォームに応用しています。
1.元気だった母が突然倒れた
母が52歳、私が29歳の時に、母が突然倒れました。
ある日、普段は風邪ひとつ引かない、健康な母が倒れ、脳腫瘍と診断されました。職場で意識を失い、けいれんを起こし、救急車で市立病院に運ばれ、すぐに検査入院になりました。
意識はわりとすぐに戻りましたが、右半身の麻痺とけいれんが不定期的に起こるという後遺症が残りました。
その後、大学病院の脳外科に紹介していただき、さらにそこで検査を続け、脳腫瘍の摘出手術を受けました。
手術は無事に終わり、ほっと胸をなでおろしたのもつかの間。。。
手術後は半身の麻痺だけでなく、脳にも後遺症が残りました。
意識はあるんですが、人間らしさがないというか、理性がなくなったというか、わかりやすく子供返りしているような状況でした。
文字を読むのも書くのも好きだった母が、文字を書けなくなり、入院してからずっと書いていた日記も、術後は書かなくなってしまいました。
失語症に近いのか、言葉も上手に出なくなり、会話も以前のようにはできなくなりました。のちに知ったのですが、これはけいれんを押さえる薬の影響も大きかったようです。
リハビリに同行してびっくりしたのは、ものさしを見て、「これはものさしです」ってわかるんですが、その「ものさし」をどうやって使うかはわからないようで、口をつぐんで首をかしげていました。
歯ブラシを見ても、同様の反応でした。
脳腫瘍ってこんな風に後遺症が残るのかと驚いたんですが、これからもっと大変になることを、私は全く予測できていませんでした。
2.子供と違って、大人は退化していく
子供は毎日が成長期で、背が伸び、体重が重くなり、言葉を覚え、出来ることがどんどん増えていきます。
しかし、大人は逆です。
今日、当たり前にできていることが、いつか当たりまえにはできなくなるんです。
物忘れや体力の衰えから始まり、病気や老化による退化で、出来ないことが増えていきます。
当たり前に生活していた自宅ですら、転んだり躓いたりするようになります。
階段の上り下りがおっくうになって来たり、ちょっとした段差が気になり始めます。
玄関での靴のぬぎはきもおぼつかなくなりますし、浴室にも危険がいっぱいあります。
術後の母は、後遺症が残って、生活は一変しました。
でもこのときの私は、手術が成功したのだから、これから回復に向かっていくと思っていたし、まだ52歳で若く、また社会復帰もできると考えていたんです。
しかし、これが激甘でした😅
脳腫瘍を摘出した人がみんなそうではないそうですが、うちの母の場合は年々、後遺症がひどくなるタイプの病状だったんです。
3.病気の種類や病状、進行具合によって快適な住まいの形が変わる
退院して自宅療養になってから、半身麻痺の母が少しでも自立した生活が送れるよう、少しづつリフォームを繰り返しました。
その時すでに私は福祉住環境コーディネーター2級の資格を持っており、福祉や介護の面からの家づくりの必要性や、有効なリフォームについて、知識はありました。しかし、それは机上のものでしかなかったと思います。
実際に、後遺症を抱えてどんどん自立が困難になっていく母を間近に見ながら、、自宅で10年にもわたる介護を経験し、必要なリフォームが変わっていくと気が付きました。
たとえば、手すりひとつとっても、病状によって手すりが必要な位置や、高さや、向きが、変わることを知りました。
この経験は、福祉リフォーム、介護リフォームに対する考え方を大きく変えてくれ、建築士としての私のマインドに大きな影響を与えてくれた出来事です。
4.QOL(生活の質)を出来る限り保つためのリフォーム
QOLってご存知ですか?
クオリティーオブライフの略で、「生活の質」という意味です。
福祉住環境コーディネーターの資格を取るときに学んだことばです。
それぞれがそれぞれの尊厳を保ちながら生活をすることが出来るようにサポートすることが、介護にとっては重要になるということで、このQOLを保つためにどんなリフォームが必要になるのかを、建築士目線で考えることがわたしの仕事です。
たとえば、ベッド上で1日を過ごすより、出来る限り家族とソファーに座って過ごせるように安全な動線を確保することや、おむつに頼らず、出来るかぎりトイレに行って、健康な人と同じように用を足せる状況を保つことで、本人の人間としての尊厳を保つことになり、生活の質を保てると考えられています。
なので、たとえば、自力でベッドからトイレまで安全に移動するには、どういうリフォームが必要か、半身に麻痺があっても安全に入浴するためにはどういう工夫が必要か、など考えました。
そして、母の脳腫瘍は、年を追うごとに後遺症が出てくるタイプの病気だったので、どう頑張っても、年々麻痺がひどくなり、筋肉が衰え、自立した生活を保つことがついに困難な状況になってしまう日が来ました。
そうなると、今度はまたその状況に合わせてリフォームが必要になりました。ベッドから車いすに移乗しやすいように工夫をしたり、車いすでトイレに連れていったときに車いすから便座に移乗しやすくするにはどうするべきか、また考える必要がありました。
そして、母のQOLだけではなく、介護する人のQOLにも配慮する必要があると、またこの頃に知ることになったんです。
いわば、介護人のQOLのための介護リフォームです。
5.まとめ
自宅で親の介護をする時代はもう終わっているのかもしれません。
しかし、他人ごとではなく、自分事として考えたらどうでしょう?
自分が今より衰えてきたときに、率先して施設に入りたいと思うでしょうか?
これまで見てきたお客様で、そんないさぎの良い人は一人もいませんでした。
みなさん、出来る限り自宅ですごしたい、でも出来る限り家族の手を煩わせたくない、そしてできるかぎり人間としての尊厳を保って生きたい、そうおっしゃいます。
そうおもったときに、この、QOLを保つための福祉リフォーム、介護リフォームが誰にも必要になると感じています。
ちょっと長くなってしまったので、続きは次回・・・
次は介護人のQOLのための介護リフォームについてまとめたいと思います。
建築士の目線で
宅建士の目線で
賃貸不動産経営管理士の目線で
既存住宅状況調査技術者の目線で
古家を愛するファンとして
女性ならではの細やかな心遣いで
そして、
自宅介護経験者の目線で👀
患者と介護人双方にとって必要な、介護リフォームのご提案を行っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
