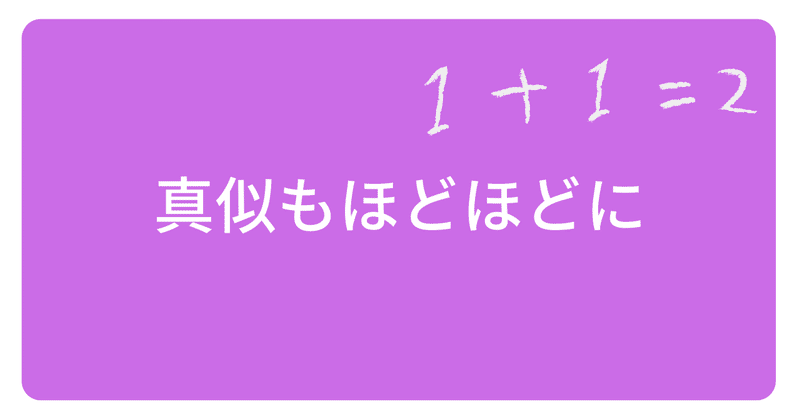
真似をするのはいいことだ。大いに真似しよう。という風潮が今の世の中少なからずあると思う。このことについて、僕は少し立ち止まって考えたい。
例えば、何かを新しいことに挑戦しようとするとき、失敗したくないと思う。その心から、ロールモデルを見つけ出し、それを真似する。これが一つの正攻法だと思われている。
しかし、自分でやる前から真似ることはそんなに正しいことだろうか?
真似ることは、確かに先人たちが悩んできたことをショートカットできる。ショートカットした時間を使って、さらに深い悩みに切り込める。とても効率的だ。
だけど、答えがあると思い込んだ真似の連続は、自分で考える力を養わない。むしろ、一種の思考停止であり、衰えさせているのではないかとさえ思う。
学校での勉強は、真似の連続である。
答えを用意した問題に対して、回答を作らせる。速く答えに辿り着くことが、評価の基準となる。
学校でいい評価を得ようと思うと、問題に対する解答を暗記して回答を作るのが、効率的で理にかなっているとされる勉強方法だといえる。つまり、解答をそっくりそのまま真似するのがいい勉強法となる。
こうした教育によって、僕たちはすっかり答えのある問題に慣れきってしまった。
ここで、問題となるのは、世の中のほとんどのことには答えがないことである。答えがないなら、もちろん先人たちの知恵は借りるとしても、自分オリジナルの答えを自分の頭で生み出すしかない。
しかし、真似の連続によって自分の頭で問題にぶつかることを省略してきたå僕たちは、インターネットや本、あるいは歴史に答えがあると思い込み、自分の頭で考えるよりも、探す方に時間を費やす。
そろそろ、世の中には答えのある問題なんてほとんどないことを自分で体感しなければならない。そして、知恵は借りても真似を捨てて、自分オリジナルの答えを自分の頭から創造しようとする。その姿勢を意識しなければならない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
