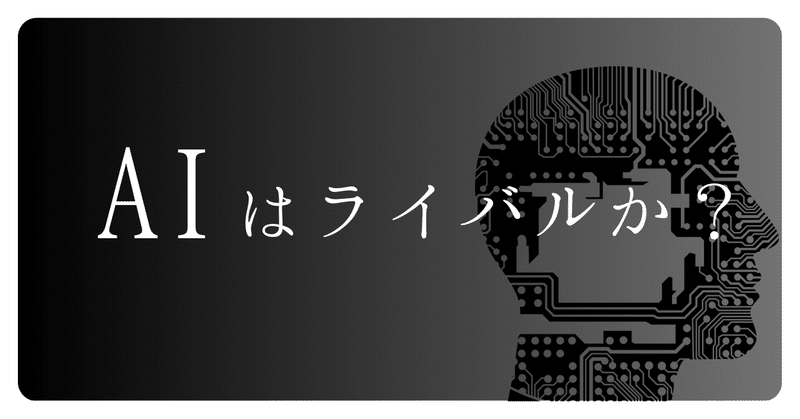
AIはライバルか?
今、ChatGPTなどのAI(人工知能)が凄まじい勢いで人々の生活に浸透してきている。聞いた話では、2045年にシンギュラリティ(技術的特異点)が起きると予測した研究者たちの予想を遥かに上回るスピードでAIの性能があがっているという。
AIによって、いまある多くの仕事が代替される時代はもうすぐそこだ。
そうした危機感から、リスキリングという言葉が注目され初めた。
リスキリングとは、新しい分野で仕事をするために必要な知識やスキルを身につけるために学び直しをはかることだ。
こうしたリスキリングが流行したのには、メリトクラシーという考え方が社会で採用されているからだ。
メリトクラシーとは、能力によって人の地位が決まることを良しとする考え方だ。現代ではこのメリトクラシーの考えに則って、学校や会社など組織での評価の仕方が決まっている。
したがって、新しい能力を身に着けようとすることは、メリトクラシー型の現代社会をサバイブしようとする上で、ごく自然なことだといえる。
そして、リスキリングをはかることで、AIに対抗しようと考えるのもまた自然な流れだと言える。
しかし、リスキングをしたとしてもAIにはたちうちできない。と、冒険の書〜AI時代のアンラーニング〜の著者である孫泰蔵さん(実業家、孫正義さんの実弟)は言う。
なぜなら、AIには学習機能が備わっているからだ。これはAIがAIである所以でもあるけれども、自分で自分をアップデートできてしまうのだ。しかも、そのスピードは加速度的に上がっていくので、人間は抜かされたと思ったらあっという間に突き放されてしまう。
だから、AIに対してリスキングという手法で勝負を挑むことは、負け戦をすることに等しいことなのだ。
じゃあどうするか?
孫泰蔵さんはこういっている。
自ら「優秀な機械になろう」とする人間は、遅かれ早かれ「メリトクラシーの最終兵器」である人工知能にとってかわられる。
しかし、そのことを恐れるよりも、人工知能は人間を機械として働くことを解放してくれる「メリトクラシーの解放者」だととらえればいい。
AI時代のアンラーニング
つまり、AIによって機械的な仕事を奪われることをポジティブに考えようということだ。
ただ、これはメリトクラシー型の社会にどっぷり浸かってきた人々にとってなかなか難しい。
そこで必要になるのが、アンラーニングだと孫さんは続ける。
これまでに学んできた価値観や行動様式、思い込みなどを捨て去り、そのうえで新たなものを再学習する姿勢、アンラーニング。
これを生涯続け、世界に新しい意味を見出し、成長し続けること。それこそが人間らしい生き方だと考えている
AI時代のアンラーニング
アンラーニングをし続け、メリトクラシー的な考え方から抜け出す。AIを「メリトクラシーの解放者である」とポジティブに捉えるところから、人間らしい生き方とはなにかを模索していく。
じゃあ、そのアンラーニングはどうやってしていけばよいのか?
僕はその問いの答えのひとつとなるのが『哲学対話』なのではないか、と思っている。
という話はまた今度。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
