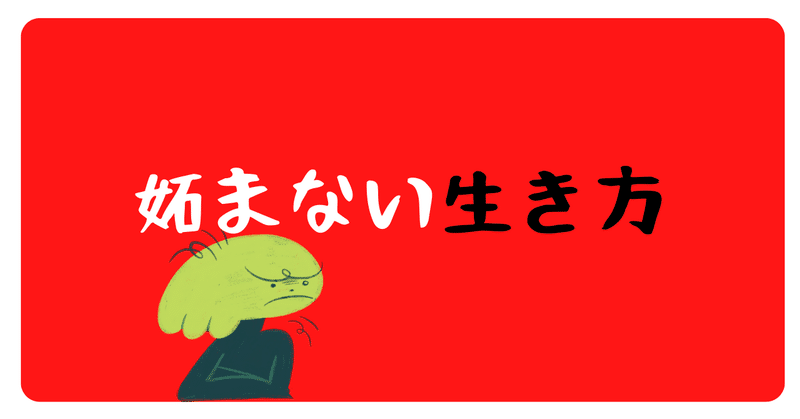
SNSを見ていると、人の人生を垣間見た気になる。大半の人は、自分の生活の見てほしい部分をSNSに投稿するので、そうした投稿を見ると、羨ましく感じたりする。
素直に羨ましがるだけならまだいいかもしれないけれど、それが妬ましく思うようなものであると、自分の中にある劣等感に気づき、突如として嫌悪感に襲われる。
人のことを妬む感情は、自然発生的なもので対処法がないように思える。
僕自身そう思っていた。が、ついにその対処法を見つけた。それは、生き方の多様性を知ることだ。
それは、いろんなところに自分の足で行き、そこで出会う人々の生き方に触れるということだ。
朝、大阪の事務所まで電車通勤すると、本当にたくさんの人たちとすれ違う。すれ違う彼らにも、自分と同じようにそれぞれ自分の生活がある。
さらに、東京ではもっとたくさんの人々が蠢いていて、生活している。これを世界にまで広げて考えると、想像もつかないほど無数の人たちが、ひとりひとり人生のいろいろなステージにたちながら生きている。
自分の知っているつもりになっている世界は、本当に一欠片なのだ。
僕はこの前、ブッダが悟りを開いたと言われるブッダガヤに行ってきた。そこで、40歳前半のインド人の男と仲良くなった。彼は、フリーランスで日本人を相手に観光案内の仕事をしていたけれど、コロナで仕事がなくなって暇を持て余していると言っていた。二人の子供がいて、どちらも私立の学校に通わせているので学費を工面しないといけないけれど、仕事がない。でも、そんな状況にありながら、彼からは少しも悲壮感を感じなかった。毎日、バイクで行きつけのチャイ屋に行って、そこにいる仲間と談笑したり、スマホで動画をみて暇を潰しているらしかった。
僕は、彼のそんな楽天的な性格を羨ましく思った。もし自分が同じ状況なら、もっと落ち込んでいて、禍々しい負のオーラで周囲の人を卒倒させているかもしれない。
こんな生き方もあるのだと、自分の脳みそにきつく締められたネジが少し緩んだ気がした。
人の生き方は自分の想像がつかないほど無数にあるのだと感じることができた。
それまで、本や映像では自分と違う環境に住む人々のことを知ったつもりになっていたけれど、実際に自分の肌で触れて感じることとは天と地ほどの差がある。
「人というのは、つま先から頭までの全てがその人の物語なのだ」と京大元総長の山極さんがいうように、実際に足を運んで会って会話しないとわからないことがある。
そうして、無数の生き方があることがわかると、自分が妬ましく思う人も無数にある生き方のひとつに過ぎないと思える。
またさらに一歩引いてみると、羨んだり、妬んだりしている自分もその無数の中のひとつだといえる。
そう思うと、妬ましく感じるような人も、妬ましく思っている自分も何だか肯定できる気がしないだろうか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
