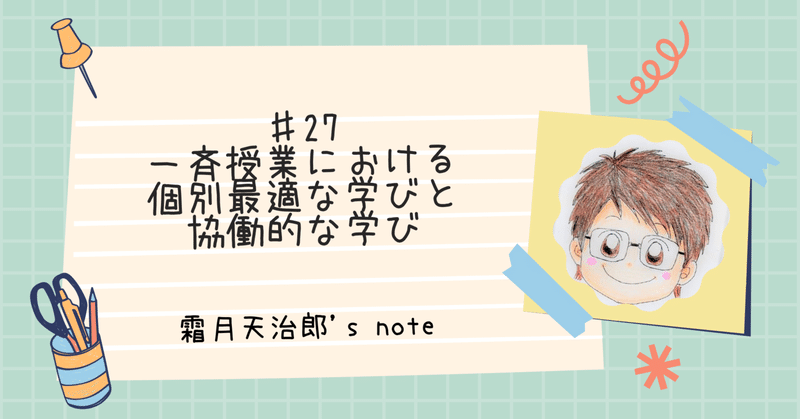
#27 一斉授業における個別最適な学びと協働的な学び
27回目の投稿となりました、天治郎です。今回のテーマは、最近の私の研究テーマである「一斉授業における個別最適な学びと協働的な学び」です。2年生の「ひき算の筆算」で実践しました。
1 単元の概要
本単元では、ひき算の筆算(2位数)を扱う。2位数の加法と減法では、各位の計算を、位を揃えてかけば、2位数の計算が各位の数の計算に帰着され、1位数の加法及びその逆の減法などの計算で処理できることになる。これを形式的に処理しやすくしたものが筆算形式である。なお、この計算方法は十進位取り記数法に基づく計算であり、以降の乗法や除法の計算の原理にもなる。そして、これらの計算の指導に当たっては、具体物や図などを用いることが肝要である。今後取り扱う3位数や4位数についての加法及び減法の計算の仕方を考える際に有効に働くことになる。
2 研究テーマについて
中央教育審議会(2021)「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して~全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現~(答申)」では、「個別最適な学び」と「協働的な学び」とを一体的に充実することを目指すとしている。そして、「教科等固有の見方・考え方を働かせて自分の頭で考えて表現する力」、「対話や協働を通じて知識やアイディアを共有し新しい解や納得解を生み出す力」等の資質・能力を子供たちに育むために重要なことが、「個別最適な学び」と「協働的な学び」であり、2つの学びは「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善を行うための手段であることも述べられている。
他方、加固(2023)は、中央教育審議会(2021)を基に、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の目的を
資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に(アクティブ)に学び続けるような人に育てること(p.17)
とまとめている。また、
『答えが出たら終わり』とするのではなく、知識が使える根拠や背景を考え、他の知識と結び付けながら知識を構造化させていくような『学び方』を学ぶことが大切なのです。(p.20)
とも述べている。さらに、一斉授業と個別学習を取り入れた単元構成の実際を提案している。
近年、賛否はあるものの、算数でも「個別最適な学び」という声の元、「自由進度学習」の実践が行われている。しかしながら、公立小学校においては、まだまだ一斉授業が主流である。そこで本単元では、加固(2023)の立場に立ち、「一斉授業における個別最適な学びと協働的な学び」を研究主題として設定することとした。
3 本時の主張
本単元では、以下の指導計画に基づき、授業を行っていく。
【第1時・第2時】2位数の減法計算の仕方と筆算の仕方を考える。(一斉授業)
【第3時】繰り下がりのない様々な減法の筆算の仕方を考える。(個別学習)
【第4時】繰り下がりのある2位数-2位数の筆算の仕方を考える。(本時:一斉授業)
【第5時・第6時】繰り下がりのある様々な減法の筆算の仕方を考える。(個別学習)
【第7時】ひき算のきまりについて考える。(一斉授業)
【第8時】学習内容の定着を確認する。(けテぶれ:個別学習)
①授業の前半
授業の導入では、「天治郎は、34円もっています。1⊡円のチョコレートを買います。のこりはいくらですか。」と少しずつ板書する。児童の質問に答えながら、問題の意味が理解できたところで立式させる。「34-1⊡」という結果を得るが、「⊡に数字を入れないと答えが出ない。」という声が挙がるだろう。そこで、「どんな数だったら簡単?」と問い返せば、「0~4」の数を答えるであろう。それらの数を入れた計算(の筆算)は既習事項であるからだ。「0~4」の数を当てはめて筆算をすることを通して、簡単だと考えた理由(繰り下がりがない)を明らかにする。尚、⊡に当てはめる数は、1人ひとりの意思により選ばせるようにする。「自分で決めること」が、個別最適な学びの第一歩だと考えるからである。
②授業の後半
一方で、「どんな数だったら難しい?」と問えば、「5~9」を挙げるであろう。それらの数を入れた計算(の筆算)は、繰り下がりが発生し、未習事項となるからである。ここでの子どもの問いは、「一の位が引けない場合の筆算はどうするの?」であろう。しかしながら、前単元「たし算のひっ算」や本単元第1・2時の学びを通して、繰り下がりのある筆算の計算の仕方やその難しさを、具体物や図等を用いて式や筆算と関連付けて説明する姿も期待できる。

この際には、「通称『さんぽ』」を行う児童もいるであろう。子ども自身の「話したい」という想いに基づく児童主体の交流は、協働的な学びの第一歩だと考える。
全体で話し合う際に、「どうしてそうしようと思ったの?」と発想の源を問うことで、児童が働かせた数学的な見方・考え方を言語化・顕在化し、全体で共有できるようにする。
授業前半と同様に、⊡に当てはめる数を「自分で決めさせること」で、今後の個別学習における学び方に生かせるようにする。また、ひく数が少し変化したいくつかの筆算を比べること(Teamsと黒板の併用)を通して、繰り下がりのある筆算の仕方を一般化できるようにする。これは、これまでの問題解決型の一斉授業ではなかなか実現しなかったことである。数を自分で決め、様々な筆算が生まれるからこそ、互いの考えを比較し合う意味が出てくる、つまり、協働的な学びを行う価値が出てくると考える。
最後に、「まとめの視点」をもとに、本時の自らの学びを意識的にまとめることができるようにする。尚、筆者は、二宮(2006)の立場に立ち、「振り返りは『随時行われる児童の診断的評価活動』であり、まとめは『学習の総括活動』である」と捉えている。
4 本時の実際
以下が本時の実際の板書である。結論から言えば、算数の本質としての課題が見られた。一方で、学び方を学び、自立した学び手になっていくという態度の高まりは見られた。

5 さいごに
最後までお読みいただき、ありがとうございます。授業の実際については、需要があればまたどこかでお話できればと思います。御意見等お待ちしております。
【主要引用・参考文献】
加固希支男(2023).小学校算数 「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実.明治図書.
盛山隆雄他(2021).学びに向かう力を育てる!算数教科書アレンジ.明治図書.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
