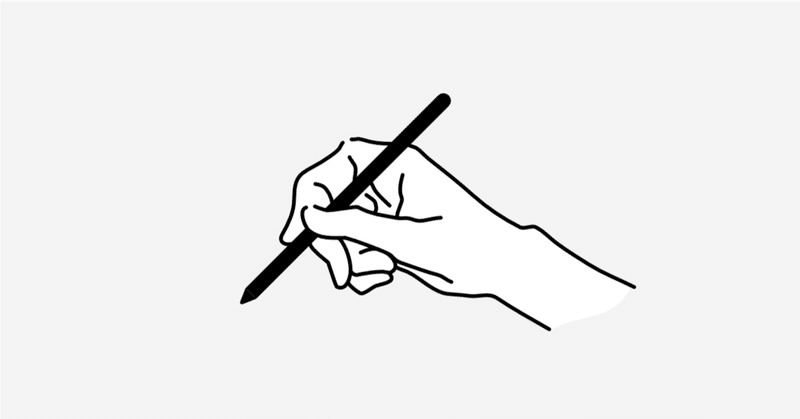
名前のないライターたち。キャリア形成の格差とWebのトレンド
文章を書くということは、いささか安く見積もられすぎやしないか。最近ずっとそんなことを考えている。
基本的に書くことはクオリティやインパクト、専門性を度外視すれば誰にでもできることだ。このnoteというプラットフォームがまさにそれを体現しているように。それ自体は全く自然なことだが、大変悲しいことに、この社会において「誰にでもできること」には価値が見いだされにくい。
それで割りを食うのは誰か。われわれライターと呼ばれる存在だ。
名前のあるライターと、名無しのライター
ものを書く職業はさまざまあるが、ここではあくまでライター(Webライター)と分類されるものについて言及したい。
非常に雑な分類にはなるが、この社会には大きく2種類のライターがいる。名前のあるライターと、名無しのライター。具体的に言うと、執筆者として記事に名前が乗っている人とそうでない人だ。
僕が今何者かと言えば、「名無し」と「名前のある」ライターの狭間にいる存在だ。
二者の間には大きな隔たりがある。記名記事を持っているライターは、それ自体が名刺として機能し、次の仕事につながっていく。一方、名前のないライターはわかりやすい実績を示すことが難しい。
名前のあるライターは記事単価数万円の取材記事を書くチャンスを得ながら、必ずしも順調ではないかもしれないけれど、たしかにキャリアを積み上げていく。
名無しのライターは文字単価1円未満〜数円の記事を書きながら、「今月は何文字書いた、何記事書いた」という勘定を続けていくことを強いられる。
つまり何が問題なのかというと、記名か無記名かによってライターとしてのキャリア形成に大きな格差が生まれるということだ。そしてその格差を埋めることが当人の自助努力だけでは非常に困難なのだ。
ライターが名前を手に入れるためには、企画力を養い、良きタイミングで編集者と巡り合うしかない。自助努力では困難といった数行前と矛盾するようだが、「上」に行く方法を、少なくとも僕はほかに知らない。つまりライターが上にあがっていける構造なんてものは、実のところ存在しない。
Webメディアのトレンドに翻弄されてきた「名前のない」ライターたち
ライターは記事を載せる媒体があってこそライターたりうる。だからライター、特にWebライターを語る上でWebメディアの歴史を避けて通ることはできない。
2000年代中盤、当時のSEO対策はとにかく多くのリンク(被リンク)を自分のサイトに貼ることが良しとされた。そんなトレンドのなかでSEO対策サービスを行う会社の中には、中身の薄いサイトを大量に作成し、それらを使ってクライアントの被リンクを稼ぐという方法をおこなうところもあった。このコンテンツ作成を担わされていたのが、後にクラウドソーシングと呼ばれるプラットフォームを通じて仕事を取っていたライターたちだった。もちろんすべてがそうだったわけではない。だが事実としてそうした事例はある。
中身のクオリティは問われず、とにかく粗製乱造がかなえばそれでよかった時代。ライターに正当な対価が支払われる土壌は存在しなかった。
そしてWebライターとクラウドソーシング、そしてWebメディアの交差点となったのが、2010年代中盤以降のキュレーションメディアブームだ。
自社でメディアを持ち、情報資産を蓄積し、ドメインパワーを高めていく。この時代は検索エンジンのアルゴリズムも大きく変わり、それに応じて企業のWeb戦略も変化していくこととなる。
そしてこの頃、クラウドソーシングサービスは広く一般に知れ渡り、誰もが「ライター」を名乗れるようになった。「ライターになりたい人」と「コンテンツを欲する企業」の需供は見事に合致し、このポイントで多数の「Webライター」が生まれていった。
だが、「文字コンテンツをつくる」ことの価値はこの段階でも正当に評価されることはなく、企業は「安く良いもの」を求め、ライターたちは文字単価いくらの案件を大量にこなさなければままならなかった。
とはいえ、この頃の「コンテンツ」が良質なものとは到底言い難かったのもまた事実で、基本的な日本語力・文章力の欠如は珍しくなく、コピペや著作権法違反も横行した。
他方でそのチェックを担う編集者も、その実マーケティング畑の人間がほとんどで、彼ら彼女らも記事のクオリティを担保するスキルは持っていなかった。その悪循環は温存され、キュレーションメディアの記事の質は地に落ちていった。
その果てで起きたのがかの有名な「welq事件」だ。医療系キュレーションメディアを標榜していたにもかかわらず、専門家の監修はなく、なかばオカルトじみた内容の記事を掲載し、「死にたい」といったキーワードでSEO対策をおこなっていたことも露呈した。
これを期にキュレーションメディアは(未だ運営しているものはあるが)徐々に鳴りを潜め、トレンドは「オウンドメディア」に移っていく。
ここでの「オウンドメディア」は、報道・出版業界以外の企業が運営する自社メディアとしておく。(たとえばIT企業の運営するメディアなど)
こちらはキュレーションメディアと異なり、記事作成のプロセスに取材・監修が入ることも多く、記事としての質は圧倒的に高い。対価もはじめの頃はひどいものだったが(それでもキュレーションメディアとは比べ物にならない)、最近は改善されてきているという。
ここで問題になってくるのが、冒頭の「名前」の話だ。
Webメディアの記事末尾に○○編集部のような記載があるのを見たことがあるはずだ。反面、しっかりと執筆者の名前が記名されているメディアも見たことがあるはずだ。
企業のスタンスとして、「自社」が出したコンテンツとするのはまったくもって道理だが、ライターの存在をあまりにも透明化してはいないか。もっといえばライターを「飼い殺して」いないか。
存在を透明化された「名無しのライター」は、記名記事という名刺代わりになるものを得ることができず、企業のオーダーに従い続けることを強いられる。そのキャリアに先の見通しなどありはしない。
ライターはマーケティングの道具ではない。ライターは各々が名前と信念を持った執筆者だ。そのことを一体いつになったら学ぶのだろうか。
平然とライターの仕事を文字単価・時間単価に単純化しようとするマーケティング担当者に問いたい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
