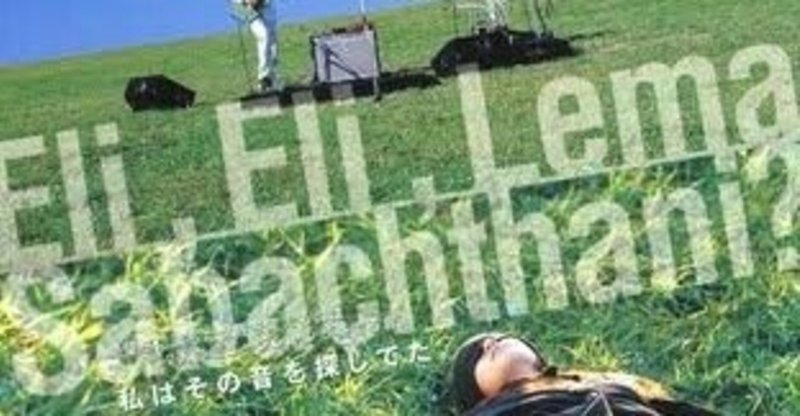
エリエリレマサバクタニ
ノイズ音楽に傾倒したのは高校2年生の秋だった。
当時の彼女の勧めで、恵比寿のとある映像展にひとりで向かった。
入場無料であったのは高校生の身分に嬉しく、しかし、初めて行く恵比寿ガーデンプレイスの、あまりに整然とした大きなイルミネーションと、街を歩く綺麗な格好をした男女の大人たちは、着ていた制服の下にある肌をむず痒くさせた。
映像展入り口では、受付員に笑顔を見せることで入場できた。
奇抜な格好をしている人、相対して、あまりにシンプルな格好をしている人、などが複数ある映像作品を凝視していた。
その後ろ姿は、当時の自分の目にはどれもお洒落な人たちであるように見えた。
32分割された一枚のスクリーンの各コマには1人ないし2人の男が映っており、テニスボールを地面に弾ませたり、やがてバウンドが終わったテニスボールを拾いあげたかと思えば、こねくりまわし、再び自然落下させている。
その映像の周期が各コマで少しずつずれており、コマの壁を挟んで互いに干渉する瞬間があるように見えたりした。
いわゆる、前衛的手法の映像であった。
自分は、それらの映像に脳が焼かれた。
理解は難しかったが、心の奥で確信めいたものが芽生えたのを感じた。
前衛芸術の目覚めである。
映像展を出ると、夜の初秋の風はまだ暖かく、ワイシャツの間から胸に当たる空気が心地良かった。
そのまま恵比寿ガーデンプレイスの人工的な光の中を散歩した。
お洒落な雰囲気に萎縮する必要は無かった。
映像展を見るまでとは、まるで別人のようで、足取りが軽く、自信に満ち溢れていた。
自分の表現は音楽であった。
これは偶然ともとれるし必然でもある。
家にギターあったこと。ピアノを習わなかったこと。
音楽が好きだったこと。
表現について考えていると、柔らかい涙が出そうになった。
帰り道は、悲しくなるほど自由で、恐ろしいほどに広い宇宙だった。
高校を卒業した直後、知り合いに誘われた花見の会でかわいゆーさくと出会う。
彼は自分に色々な映画や音楽を教えてくれた。
そのどれもが刺激的で、ユーモアに富んだものだった。
ほとんど毎日遊んでいるような時期もあった。
(今でもよく遊ぶし、初恋のアーティスト写真を撮ってくれたりしている)
自分のする前衛的アプローチを伴った表現や、奇抜な考えを、面白いと言ってくれる友人だ。
ある時、「エリエリレマサバクタニ」という映画をゆーさくに教えてもらった。
青山真治監督作、浅野忠信、宮崎あおい、そして中原昌也などが出演していた。
DVDで観賞したが、出演者をみて少し驚いたのを覚えている。
中原昌也といえば、Hair Staylisticks や 暴力温泉芸者などの、ハウスやノイズ音楽を手掛けている人物だ。
「レミング病」
この世界では希死念慮が強まり自殺してしまう病気が流行している
浅野忠信と中原昌也は、その脳の病気の治療となる音楽を作っていた。
それは、いわゆるノイズ音楽であった。
全編を通して、荒廃した世界を映し出しており、またそれは精神の荒廃を表しているともとれる。
ワンカットが異常な長さで撮影されており、車が丘を越えるシーンだけで約3分使われている。
このような殺伐とした3分は、とてつもない長さに感じる。
音楽家はさまざまな音を集め、音楽に変える。
火葬で人と木とが燃える音をマイクで拾う。
鉄の弦を一本だけ張った板にギター用のピックを携えたものが劇中に出ていた。
それは楽器というにはあまりにも大雑把な作りだ。
ここにエフェクターを繋ぎ、弦を弾いたり、擦ったり、叩いたりして奇妙な音を作り出す。
ラストシーンについてはあえて言及しないが、ノイズ音楽に傾倒していた自分にとっては、あまりに厳荘で、悠久で、美しく、涙が止まらなかった。
音楽は、精神に対してさまざまな効用をもたらす。
同じ音楽でも、聴取者の精神状態や、過去の出来事によって千差万別の効用がある。
では、ノイズミュージックではどうか。
その、不規則に並べられた音階のない音塊(おんかい)の波は、心にどのようなことを訴えるのか。
作中ではこれが、レミング病の症状を一時的に緩和させるものであると言及されている。
ただし、あくまで緩和であり「治療」はできないのである。
音楽には絶大な力がある。
ただし、それは全て直接的に作用するものではないのである。
音楽を聞くことによって得た高揚や安らぎは、精神疾患の症状を緩和することはあれど、治療はできないのである。
音楽によって何かを救うことはできない。
自分を救えるのはその人自身であるからだ。
ノイズミュージックという一般的な市場から外れた音楽種は、その奇怪さからか、通常は聞く人を選んでしまうが、この映画の中では多くの人が聞くものとなっている。
その光景はいびつであるし、少し滑稽でさえある。
しかし、音楽に正解はない。
西洋音楽によって音階という単位が確立され、和音の拡張により音楽が劇的な進化を遂げた時代。それよりも前に回帰する。
世界中にあった民族音楽は、ノイズ音楽の側面を持っていることが多い。
インドネシアのガムラン、日本の雅楽などは、とりわけアンビエントととれるノイズ音楽に包括されるような要素がある。
我々が一般的に聞いている音楽に、れっきとしたメロディやリズムやハーモニーがあるのは、実は偶然の積み重ねでしかない。
とはいうものの、ノイズ音楽が世の中に広く知れ渡ることはおそらくないだろう。
この映画がSFというジャンルに括られているのを見たとき、皮肉めいていて笑ってしまった。
ノイズ音楽がポップスのような聞かれ方をするのはもはや「ファンタジー」なのである。
ノイズというもの自体は、音楽を素直に人に伝えるのには不必要であることが多い。
それ故の「ノイズ」であるし、本来淘汰されるべきものだ。
ただ、好きなものが淘汰されたり、認められなかったりするのは辛い。
絶望してしまうことだってある。
しかし、この映画をはじめてみたとき、ノイズ音楽を愛している自分を肯定してくれているような気がした。
それは、ファンタジーだからこそ良いのである。
音楽は自由である。
空想を描ける芸術であるから、ファンタジーなのだ。
だから、このままでも大丈夫だと、気づかせてくれた作品だった。
この度の青山真治さんの訃報を受けて、私の大好きな作品の思い出を書かせていただきました。
青山真治監督の作品は、エリエリレマサバクタニを皮切りに色々と見ているのですが、自分の心に圧倒的に深く刻まれているのはやはりこの作品です。
素晴らしい作品をありがとうございました。
ご冥福をお祈り申し上げます。
カニユウヤ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
