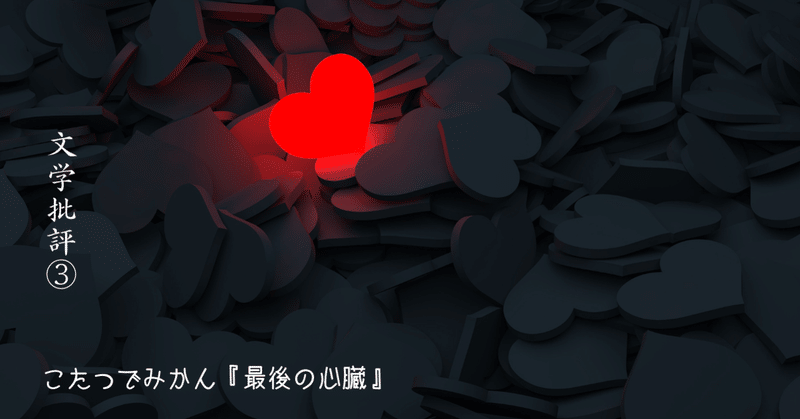
こたつでみかん 『最後の心臓』 批評
こたつでみかん『最後の心臓』
https://ncode.syosetu.com/n1089gx/
山口静花 評
夢中になって読みました。ぐんぐんと引き込まれる軽やかな文体、および会話の群れ、時折挟まれる情景描写に、熱に浮かされるようにして読み進めていました。最後まで、スッと一本の筋が入っているように軸を持っている印象を受け、きちんと読み通せる流れはできているな、と感じます。
今作品で、わたしが特に魅力を感じたのはキャラクター性、特に主人公である魔女の心理描写や人間らしさを帯びた描写の数々です。ララもとい人形とくっきりと違いのある、まさに光と影のような2人の存在感はこの小説の大きな魅力と言えるでしょう。
魔女は不幸を好みながら、その心理の裏には誰よりも自分が幸せになりたいという思いがあるように見受けられ、しかし顔にある傷のせいでそう思うことを許せない葛藤が、物語の裏でほのかに香っている、そういう想像の余地を持たせた描き方がされており、印象深かったです。
また、ラストシーン、2度あることは3度ある、と、物語が終わった後にも想像を及ばせるような仕掛けが施されており、読後感にも気を配っているように感じられました。
少しもったいないと感じた点を挙げさせていただくとすれば、読みやすいが故に読み応えに欠けている、ということでしょうか。無難、と言ってしまえばそれだけで済んでしまうような、ライトな感触、ライトすぎる雰囲気になってしまっているように感じます。
するすると流れるような文章の中で、凹凸を感じられるような冴えた一文や、特別力を込めた描写、があるとよりメリハリがついて読者を飽きさせないのではないかと考えました。物語の流れ、プロットを着実に踏み締めていくような印象で、読者がハラハラしたりドキドキするという装置が、今作品からは感じられませんでした。現在の文章だと読み手の印象に残りづらい小説に仕上がっているように思います。よりキャラクターの魅力を際立たせるためにも、文章単体の面白さ、グッと深みにハマらせる一場面といった側面を、もう少し追求しても良いと感じました。
加えて、森から街へ拠点を移すわけですが、その展開がやや急に感じられました。魔女にとっては、ララとの幸せな日々の延長線上にそれがあり、森を出ることはもはや些細な出来事だったのかもしれません。ですが、頑なに森に閉じこもろうとしていた月日のこと、バックグラウンドを考慮すると、あまりに呆気ない展開だったように思われます。もう少し字数や説明を割いても違和感はなさそうです。そう感じるのは、最初、ララの死体を発見した時、ていねいに描写が連なっていたせいかもしれません。生きていたララとの回想を含めたワンシーンは特に映像的で、字数が割かれているように思います。それに比べると、中盤から終盤の展開は、大きな出来事が起こっていながらそれほどこだわりなく過ぎ去っていってしまったように感じられるのです。その点がすごく惜しいと感じました。序盤に込めていたパワーを引き継ぎながら、物語を書くことができると、より読者にとっても面白みのある作品になるのではないか、という可能性を感じさせます。
とはいえ夢中で読んだ読者の1人として、今作品はぐんと引き込まれてしまう魅力のある作品であると言えるでしょう。些細でありながらきらめいている日々の美しさを、存分に楽しむことのできる作品でした。
すてきな作品を読ませていただきありがとうございました。
山口静花でした。
齋藤圭介 評
言葉と料理は魔法だと思う。
普段、生活していて、そう思うことがある。ばらばらになっているものから、あるいは、ばらばらにしたうえで、そこから何かそれ以上のものを生み出す。
それらはもちろん基本的には調和のとれたものを目指そうとするので、日常を脅かすものではない。むしろ日常を日常らしくしていくための隠された魔法のようなもので、繰り返されたところで、まさかそれが規範にふれるなんてことはない。
しかし、そこに何かのたましいが強く働くと、様相は変わってくると思う。科学における倫理の問題が、まずは顔を出す。社会における信仰が揺さぶりをかける。民衆の集団心理も巻き込まれる。そうして誰かの日常が異端として指さされるときに、血が流れる。あるいは血の流れない、迫害がある。
この小説は魔女狩りというものがひとつのテーマとして根底に流れているけれども、この主人公は、自分のつくったものに、最終的には日常を脅かされる。しかし、それは単なる順序ではないところに、このものがたりの眼目があると思う。その感情はやさしくひねくれている。この魔法は、考えてみるとむずかしい魔法であるとも思う。
胸のあたりがふわふわと温かくなるような心地だった。人形が喜ぶと、なぜだか自分もいい気分になるのだ。自然と私は、人形が喜ぶようなふるまいをするようになってしまっていた。気が付いたら、私たちは森を出て、とある都市の街角で薬屋を営むようになっていた。
自分の作り出したものに自分の身を脅かされ、また自分が慰められるとは、皮肉なことにも思えるが、例えば創作者という魔女見習いにとっては、あるいは、創作者が生み出す言葉とは、まったくそれに近いものがあると思う。
もちろん、人目にさらされなくとも良いのである。この小説のように、人里離れた森の小屋の中で育まれる、そういうささいな営みで良いのである。
われわれは、他者や外部のイメージの断片から、それらがもし憎まれるものでも、時として何かを生み出す。そして徐々に、継ぎはぎの傷も消えてくる頃に、それに対して、ある種の情や思い入れが芽生えることもあるだろう。あるいはそれが変容して、手が生え、足が生え、心臓の脈が打ちはじめ、まるで人間のようなかたちにすらなって、生き物のようになってわれながら愛しいものになることもあるだろう。
そうなったときに、その生命体を、どうしようかと考える行為が、言葉における魔法が解かれるのか否か、もっというと、その魔法を信じてみるのか、信じていてもよいのか、そういう問題を呼び覚ましてくると思う。なぜならば「都市」とは、自らが密かに愛しんできたものの表皮が剥がされ、時としてその生命さえも奪われる場所なのだから。
そういう残酷さを、このものがたりは伝えると思う。
そうなるならば――誰しもがそう思う。そうなるならば、出過ぎたことはしない方が良い。またひどい目に会うだけである。自らのためだけに、日常の炊爨(すいさん)をしていた方が楽であるし、安心である。わかっている――けれども、われわれは心のどこかで、また不器用な失敗を繰り返すのではないかと思っている。脅かされない日常は、気付くことの出来ない日常なのだから。
あるいは二つめ以上の心臓はものがたりの中でのみ許されたものであって、最初の心臓こそ最後の心臓であるということを、心底知っているので。
誰かのために炊事をすることにも、誰かのために言葉を探ることにも、ほんとうは日常を脅かす可能性があるのかもしれない。
――――――――――――――――――――――――――――――
批評は以上となります。
この記事を読んで、自分の作品の批評の依頼をしたい!と思った方は以下記事に応募フォームがございますので、そちらからご応募くださいませ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
