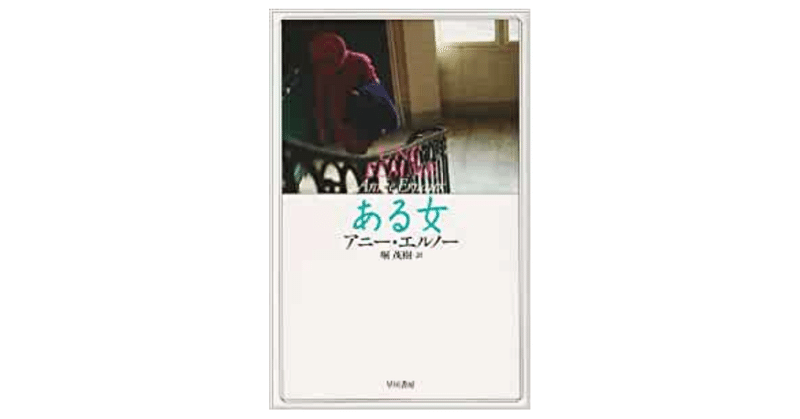
「ある女」と袂別すべき母親がいた
『ある女』アニー エルノー,(翻訳) 堀 茂樹 (Hayakawa Novel)
母が死んだ。
十二歳で学校を辞めて工場で働き、父と結婚した後は、共に店を切り盛りしていた母の人生。自分の子供に少しでも良い教育をと子どもの数は一人にし、教育にお金をかけてくれた母。そんな母の誇りは、一人娘が教員免許をとり、知識階級の仲間入りを果たしたことだった。やがて忍び寄る病魔の影。母はアルツハイマー病になっていた。母を引き取り介護に明け暮れるが、自分一人では母の面倒を見切れず、養老院に預けることに――。
フランス人女性として初めてノーベル文学賞を受賞した著者が、自らの母親の人生と、母が娘に託したものを綴る、自伝的小説。
アニー・エルノー二冊目。最初に読んだのは父の人生について書いた『場所』だった。次の作品は父の人生よりも、作者と母の関わりの部分が『場所』よりも大きいかもしれないと思った。そう、『場所』のほうは下層階級という社会的な出自を明らかにした本であるならば、ここでの母とは共犯関係的な、何に対してのだろうか?文学の共犯関係だ。それだけ私小説に近いのかもしれない。
最初の書き出しが「母が死んだ」は、カミュ『異邦人』の「今日ママンが死んだ」を想起させるがアニー・エルノーは「ママン」という甘える言葉ではなく「母」という客観的な言葉を使っただろうと思えるのだ。それだけカミュの一人称は母語的な表出を感じるのだが、エルノーの文章には母国語的な階級差がある世界を振り返る文体が、そこに身を寄せるというよりは袂別していくような硬質な厳しさがある。
ただその中にエルノーの叫びがあるのだ。母の死を語るこの作品を語りながらそこに母の姿を見出し、作品が完成するときは母の死によって作品を手放すというメタ・フィクション的構造を持っている。それは母をまるで著者の子供を産み出すようなものだとも言っている。それ以前は、著者は母の子供だったのだ。この逆転していく関係が強く出てくるのは、まだ著者がいる上流階級に母を奪われたくないという気持ちだろうか?しかし、その国のシステムは母を母ではなく「ある女」という痴呆症患者に落とし込む。
母に対する愛憎半場する感情を客観的に筆記していくという作業が一つの喪に服す儀式であるかのように。
母が次第に痴呆症を患いかつて凛として立っていた母ではない姿を見る時、彼女は何を感じていたのだろうか。その部分はかなり辛い筆記になっただろうと想像出来るのは、私の母も痴呆症になったからかもしれない。妹がその変化した母について嫌なことと思いながら聞いていた。そしてそれを確かめられた時の哀しい感情はいまでも忘れられない。それから暫くはコロナ禍でホームでの面会もままならぬ、結局最後にあったのは玄関越しに看護師に連れてこられた車椅子の母の姿だけであった。
その空白の部分を埋めるように読んでいた。
関連書籍
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
