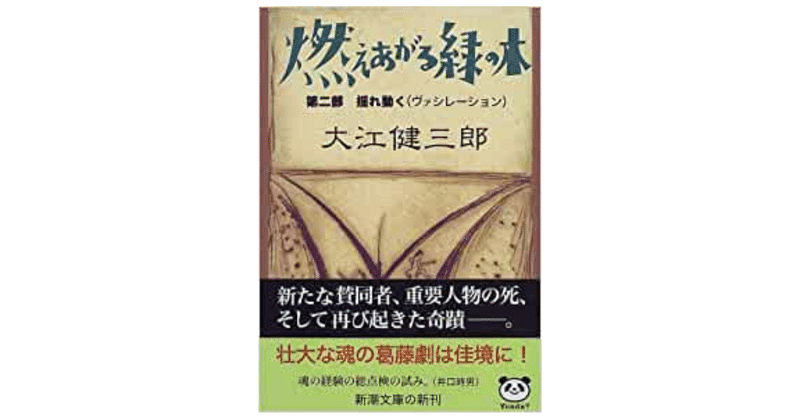
イェーツの詩を読み解きながら「燃あがる緑の木」
『燃えあがる緑の木〈第2部〉揺れ動く(ヴァシレーション)』大江健三郎 (新潮文庫)
百年近く生きたお祖母ちゃん(オーバー)の死とともに、その魂を受け継ぎ、「救い主」とみなされた新しいギー兄さんは、森に残る伝承の世界を次々と蘇らせた。だが彼の癒しの業は村人達から偽物と糾弾される。女性へと「転換」した両性具有の私は彼を支え、その一部始終を書き綴っていく……。常に現代文学の最前線を拓く作者が、故郷四国の村を舞台に魂救済の根本問題を描き尽くした長編。
第二部のタイトル「揺れ動く(ヴァシレーション)」イェーツの詩「Vacillation」から来ている。二部全体がイェーツの詩の解釈に占められているように感じるのは、ギー兄さんの父である元総領事のレイト・ワーク(晩年)の仕事というべき「魂」の探索がイェーツの詩を読むことであったからだ。
それがギー兄さんの教会建設の柱となる。大江健三郎の文学の過去の文学からの解釈はバトンのように次世代(新しい人)に渡されていく。
大江健三郎の一つの読み方として文学を読むというのがある。それは普通に読んではなかなか理解出来ない詩や文学を一つの言葉の意味と解釈を通じて、大江健三郎の物語(小説)の中で読むというものだ。それは文学作品を個々の感性で読むのではなく、大江健三郎という眼鏡を通して見る世界だ。イェーツやブレイクの英詩をそのまま読める人はいいが、一般の日本人は翻訳というステップを踏んで読むことになる。その中で翻訳者の解説やら文学の解説本で理解するということがあるのだがなかなか理解出来ない。大江健三郎の文学はそれを小説の中でやっていて、一つの理解の助けになるのだ。
ドゥルーズの「文学の言葉(書物)は世界を見るための眼鏡である(正確な引用ではないが)」という。まさに大江健三郎の小説は一つの世界を理解するための書物であるといえるかもしれない。その構造こそが大江健三郎の小説のメタ・フィクション的面白さなのだ。そのもっとも有名な作品が『新しい人よ目覚めよ』のウィリアム・ブレイクの解釈だろう。
例えば岩波文庫の『イェイツ詩集(対訳) 』(訳)高松雄一
(岩波文庫)では以下のような翻訳である。
人は二つの極のあいだにいて
おのれの道を走る。
炬火(たいまつ)が、火を吐く息が
現れて、昼と夜の
あの背反を
ことごとく抹殺する。
肉体はこれを死と呼び、
心はこれを悔恨と言う。
だがそれが正しければ
歓びとは何だ?
二つの極のあいだというのは、二分法の対立構造で例えばギー兄さんの魂の救済には、支持者と反対派がいる。これを書いているサッチャンも男と女の性の中で両性具有という道を探している。「燃あがる緑の木」自体たが燃える木と緑を茂らす木の融合されたイメージで、その間で揺れ動く生と死の間で生命(魂)が喜びをもたらすというこの物語の主題ともなっている。それは元総領事のレイト・ワーク(晩年の仕事)でもあり、ギー兄さんの教会作りでもあり、サッチャンの生き方でもある物語を含んでいる。
中でも元総領事は癌であることを知っていて、その余命の中で魂の救済という永遠性を求めようとしているのだ。それがイェーツを詩を読むことで、その瞬間が永遠と感じられるような出来事に出会うのだ。
例えばK伯父さんが川の濠で水死しそうになったときに川魚が群れをなして一方向に泳いで静止したのを見て永遠性を感じるのだ。それは死の手前の永遠性のように言っているのだが、我々もそんなシーンに出会うのではないか。
花見で桜の散る一枚の花びらのスローモーションに永遠性を感じたりすること、それは俳句とか短歌とかの歌の世界、いうなれば詩の世界と共通しているのではないか。あるいは聖書の福音書を読んだときに感じる喜びというものはそういうものではないのか?
ギー兄さんの教会では聖書的なものは無かったのだが有志がそういう言葉を集めて、例えばイェーツの詩の一節にそれを見出す。
“Rejoice!”という言葉は、伊能三兄弟(愛・育・英)とその妻たちが、まず愛が──What matter?と発話する。続いて育が──Out of cavern comes a voiceと応じる。さらに英が──And all it knows is that one wordと大声で、そして三人の娘たちが声を揃えて“Rejoice!”と喜びを伝える。この呼びかけがいつしか祈りの言葉になっていくのだった。
大江健三郎はこのやり取りの中に黒人教会のゴスペルのコール&レスポンスを見出すのだ。そういえば黒人霊歌に多大なる影響を受けながらもフリー・ジャズという新しい試みをしたジャズマンにアルバート・アイラーがいるが、彼のアルバム『Spirits Rejoice 』を連想したのだ。
アルバート・アイラーは中上健次が『破壊せよ、とアイラーは言った』という本を出しているように「壊す人」のように思われていたが、本当は黒人霊歌のようなゴスペルに深く根ざしたブラックミュージックを演る人でもあるのだ。
大江健三郎の趣味はジャズよりもクラシック的な傾向が強いのだがワーグナーの『トリスタンとイゾルデ』の歌詞の引用とかヨーロッパ文化のキリスト教的教養も伺える。その中に日本の伝承の辺境という四国の山奥の民話を繋いでいくのだ。それはイェーツがアイルランドのケルト神話の物語と自らの詩を繋いでいく共通項があるように思える。イェーツがアイルランド独立(復興)運動に関わっていくことを日本の60年代の安保闘争やその後の学生運動に関わりをも見出していくのだ。
そしてこの宗教小説はどこか過去の文学、イェーツの詩からダンテ『神曲』やドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』に繋がっていく。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
