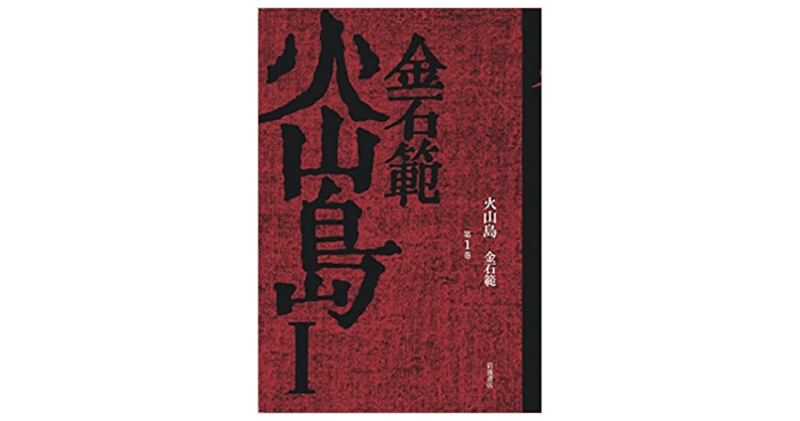
済州島の『戦争と平和』は、日本統治時代から。
金石範『火山島1』
日本の植民地支配から解放後の朝鮮・済州島。青年たちは、民族と正義への熱情に駆られ、淡い恋愛感情に心乱れながらも、まっすぐに生きようとする。その彼らを待っていたものは。「四・三事件」を描き切った、大佛次郎賞・毎日芸術賞受賞の雄編。
日本の長編小説だと思うのだが在日作家が書いたから日本の小説だとはあまり認知されてないようだ。内容が韓国のことだからだろうか?この1巻を読む限りにおいては日本の帝国主義・統治時代からの負の遺産が韓国社会に与えた影響が語られる。それはアメリカのレッドバージの影響下でソ連を後ろ盾とする北朝鮮との分断国家争い、アメリカ軍の傀儡政権との主権争い。初代大統領・李承晩はかつての日本傀儡政権の置き土産とした軍部や警察、右翼組織など済州島の民主化運動を弾圧するのである(島民の1/3が犠牲になったと言われる)。
長編小説ということだがプルースト『失われた時を求めて』よりはトルストイ『戦争と平和』パターン。
第1巻は、在日韓国人である南承之(ナム・スンジ)が共産党の密使(スパイ)として祖国である済州島にやってくる。1章が100p.前後でまとめられおり、全4章。
第2章からは、地元の有力者の息子・李芳根(イ・ハンバン)の視点に変わる。イ・ハンバンがナム・スンジに興味を示して再開する(かつて日本で二人は出会っていた)のだが、その妹・有媛(ユウオン)を引き合わせて関係していくようなストーリー。まだ四・三事件にはならずにその前章という感じなので、ちょっと退屈な読書となってしまった。
それは韓国名が漢字では読めず、覚えられない苛立たしさにあるような。登場人物が途中で変わるのも、感情移入を許さない。それは全体小説の群像劇であるからなのだろうが、人物名で苦労する。この場合、漢字表記でなくカタカナ表記でいいと思うのだが。漢字で登場人物のキャラをある程度表しているのだろうとは思うけど、読めないのだから。そういえば、金石範も読みがわからなくて本を探すのに検索できないということがあった。もう読みでカタカナにしたほうがいいと思うのだ。新聞でもカタカナ表記が増えているような気がする。
一章はそんなわけで、済州島と社会情勢の紹介程度と思っていたほうがいいのかも。その中で特に注目したのが、豚の胎児の料理だった。韓国文学は料理がよく出てくるというが豚の胎児の料理は驚いた。実際に韓国の伝説料理「セキフェ」というネット検索で出てきた。こういう伝統は都市部よりも島のような閉鎖された地域に残るというから、もともとは高貴な伝統料理だったのかもしれない。酒に酔った後の酔い冷ましを兼ねた精力料理ということだった。
その前に人の排便を豚の餌にすることで美味しい肉になるという話。自然のサイクルということなのだろう。
それと儒教的なものがより強く残っているのだ。先祖や両親を敬う社会であること。母親の法事が盛大に行われる。法事のために家が傾くということもあるという。見栄もあるのだが、それが喪主の権威となるのだ。
イ・ハンバンが島の有力者の息子でありながら反権力的なのは小学生時代の天皇崇拝にあった。天皇に頭を下げて敬うのがおかしいと思い、その御影にしょんべんをかけたという。第4章の実母の法事がクライマックスとしてのドタバタ劇で、なるほどそれが社交界での済州島の人間関係(対立項)を表しているのだ。その中でイ・ハンバンの家は経済的なものを求めて政治と繋がっていく。その犠牲になるのが、妹・ユウオンなのだろう。
そして韓国社会の家父長制的な影響の中にいながら民主化運動の波に飲まれていくイ・ハンバンなのだ。そのキー・ポイントとなるのが、作者の分身であるナム・スンジのような気がする。歴史的物語の他に愛の物語があるとすれば、その辺りか?
まあ、人間関係が複雑になりそうだ。イ・ハンバンが根っからの反体制ではなく、坊っちゃん的なキャラだから、素直にナム・スンジと共通するわけではないような気がする。あと、法事に来ていた乞食坊主の存在。日本で言えば隠者のような趣だが気になる人物も出てきた。
島全体が少しづつ極右勢力である西北(ソブク・自警団のような極右組織)に支配されようとしている。それがイ・ハンバンの飲み屋の女を巡る喧嘩から法事への参加という緊張感を含むシーンでのドタバタ劇(イ・ハンバンの少年時代の武勇伝と日本への島流しの過去)は読み応えがあった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
