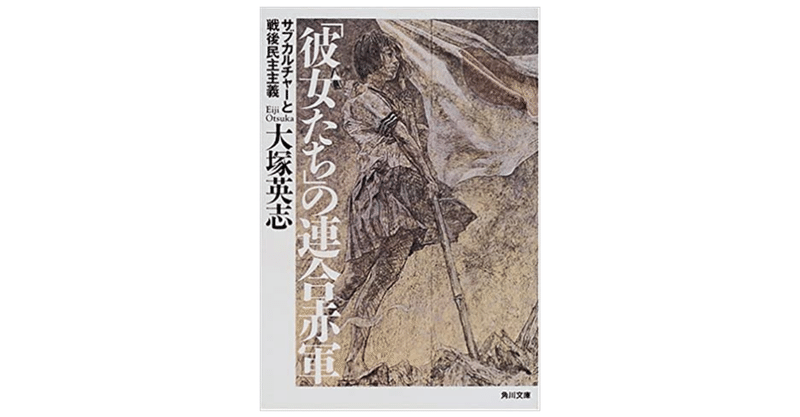
イグアナ娘と付き合う方法?
『「彼女たち」の連合赤軍 サブカルチャーと戦後民主主義』大塚 英志 (角川文庫)
獄中で乙女ちっくな絵を描いた永田洋子、森恒夫の顔を「かわいい」と言ったため殺された女性兵士。連合赤軍の悲劇をサブカルチャー論の第一人者が大胆に論じた画期的な評論集! 新たに重信房子論も掲載。
前回の読書でヤンキーにならずにすんだ私を顧みたのだが、さりとてヲタク(オタクを使わずヲタクにするのは狭い意味でのヲタク性なのか?)にもならなかったのだが、この本を読むとその部分も垣間見れるような気がする。
全体的にはフェミニズムの取りこぼしてきたきた消費される女性を語りながら、江藤淳『成熟と喪失』問題があるのだと思う。子供を産まない母親問題にどう男たちは対処していくのか?
「彼女たち」の連合赤軍 サブカルチャーと戦後民主主義
まず永田洋子が「乙女チック」だという著者の言い分にはあまり説得力がないように思える。ただ文章の中に絵を入れただけで、それもキャラ化した絵だから「乙女チック」となるのか?そこが疑問だ。「乙女チック」も厳密な言葉ではなく、感情論である。そういう風に見えたというその判断は、果たして一般的なものなのか?
その疑問は、ここに絵が出てこない。それでネット検索してみるも、なんか私の「乙女チック」とはイメージが違うのだ。「乙女チック」は著者が永田洋子を可愛い女に仕立て上げた言葉だと思う。それは上野千鶴子というフェミニズムに対置させるための言葉だった。
永田洋子は手記のなかでボーボワールの第二の性に触れて、それに気を止めながらもマルクス・レーニン主義の方向へ踏み出すのだ。それは、彼らの同志としての、つまりボーボワールの言う女性性を排除したところにある。そのリーダーシップが男性原理と重なり、連合赤軍の中の女性性を否定していく。それは連合赤軍の成り立ちの仕方。赤軍派幹部である森恒夫は赤軍とあるように軍隊組織であるわけだった。一方京浜安保共闘革命左派である永田洋子は、赤軍と対抗するためによりリーダー的な振る舞いをしなければならなかったのだ。それは山本直樹の漫画『レッド』に描かれていた。
森恒夫は軍隊オタク的なヤンキーだったのだと思う。その部分をサブカル・オタクの心情と重ねているのだが、よく分かりにくい。森恒夫の見栄と弱さを監獄の中での総括(反省)の手紙で説明する。彼の人称の問題で公的な手紙では「私」を使い、個人的な心情発露には「僕」を使う。
上野千鶴子らフェミニストらの批判で、70年代の小説で男性作家の「ぼく」の使用があった。庄司薫『赤頭巾ちゃん気をつけて』から三田誠広『僕って何』を経て村上春樹の「ぼく」だ。男が公的な場所では「私」を使用し個人的発露で「ぼく」で甘えてしまう。庄司薫は、大江健三郎と同じ年で、パロディとして偽名で小説を書いたのが、一般的になったのだという。
大江健三郎や上野千鶴子の「ぼく」の批判。そして、ややこしいのだが加藤典洋の「ぼく」は公に発言しているからいいのだという。「ぼく」っていうのは甘えの構造なのかな?そんなニュアンスだけど。そこに、森田童子「僕たちの失敗」を重ねるから、ますますなんだか分かりにくい。
要は森恒夫の個人的な弱さを去勢された男として、女性性の拒否としてみるのだ。ここで森恒夫に対する過剰とも思える説明はなんなんだろう?ただの軍隊好きなヤンキーなやつでいいと思うのだが、オタク性と女性性の拒否と。そこに永田洋子の女性性拒否が合体するという話なのだ。
話を戻すと上野千鶴子のフェミニズムが取りこぼしてきた女性が、連合赤軍の女性メンバーだった。永田洋子は女性性を拒絶することで連合赤軍を支配していく。その永田洋子のもう一つの一面が「乙女チック」ということであり、それは70年代の消費される女性性だった。永田洋子らが連合赤軍に加わらないで生き続けたらボディコンでパラパラとかやっているというような。それはどうかなとは思う(永田洋子の容姿について語られているからだ)。
ただ面白いのは永田洋子と漫画家の萩尾望都をつなげている点だ。萩尾望都世代が後の同性愛的(異性愛の性的欲求を拒絶するような)な漫画を描いていく。あまり詳しくはないのだが話題になった萩尾望都『一度きりの大泉の話』は何かそういう連合赤軍的なものを感じさせた(この本を読んでから)
(上野千鶴子)フェミニズムが取りこぼしてきた女性はオウムの女性信者までつながっていく。オタク性(森恒夫)と女性性(永田洋子)の連合赤軍ということなのか?森恒夫の話が半分ぐらいある。
「彼女たち」の日本国憲法
江藤淳のサブ・カル批判は、丸谷才一に向かっているが、それは丸谷才一が評価した村上春樹批判なんだと思う。江藤淳が古い体質の批評家(小林秀雄タイプ。そういえば小林秀雄もヤンキーだと斎藤環が書いていたのは納得してしまった)で村上春樹を読めなかった。サブ・カルの作家の流行だと思っていた。
そういう保守主義の日本国憲法批判があるのだが、現実にアメリカの属国なような憲法上で生きているのがけしからんというわけだった。そこで戦後の日本国憲法の成り立ちから50年以上受け入れてきたのだから、もはや自分たちの憲法だろうという論理。まあ、江藤淳のような保守主義の難癖はずいぶん聞かれそれで憲法改正に持っていこうとする。それは戦前の保守主義の回帰なのだ。
そして現憲法の中でもっともラディカルなのが男女平等思想で、それはアメリカ以上なのだとする。第十四条。
「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係に おいて、差別されない」
さらに、より急進的な第二十四条。
①婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
その憲法制定に関わったユダヤ系女性ベアテ・シロタ・ゴードンの存在。彼女はGHQの中では「女子供」として扱われたが、彼女はアメリカの憲法に不満でありそれを変えたいと思っていた。それはベテアの家政婦だった少女・小柴美代の口減らしの為に売られていく少女の境遇を聞かされて、「女性の権利」を織り込んで行った。
しかしベテアの草稿は、日本側に拒否されていく。そして、ベテアの手を離れていくが、平塚らいてうの拒否に出会う。それはらいてうの女性参加は自己の鍛錬としてのものであって、モダンガール的に消費される女性は描いていなかった。
連合赤軍事件が起きた1972年は、日本は消費社会に足を踏み入れた時期であり、吉本隆明の「転向」問題が出てくる。共産党の「転向」問題ではなく(それも関係しているのかもしれない)「マス・イメージ論」が出てくる。ここで吉本は高橋源一郎の文学を取り上げてサブカル全盛期になっていく。江藤淳の奇妙な捻れは、高橋源一郎を認めてしまう。
吉本隆明の中流幻想実態論は、マルクスの商品価値を引用して、水が商品として売られてしまったことを持って、日本では総中流となってしまった。それは実態である。
埴谷雄高とのコム・デ・ギャルソン論争。アジアの搾取(収奪)される民衆の上に成り立つ中流意識。しかし、埴谷雄高は日本の民衆を見れない。
吉本ばななの存在。吉本ばななの好意的な文壇は、吉本隆明の立場をより強固なものとする。戦後の「かわいい」文化が花開いていく。
少女漫画「花の24年組」の登場。身体性が後退し内面性が表に出てくる。女性性への対峙の仕方が男性視線から離れていく。そして、よりポップな岡崎京子の登場。
肉体の無頓着な解放がブルセラ文化を生んでいく。萩尾望都『イグアナの娘』産む性としての母性から乖離。出生率の低下。その反動としての出産本の氾濫。無批判な母性イメージの増大。
江藤淳『成熟と喪失』で描かれた母なるものの喪失。母なるものは、国である。それは、男たちにおたく化を促進させ、女たちは「ヴァーチャルな身体」として化していく。それがサブカル化された日本の姿になった。
しかし、それは反動として母=国家としての回帰を呼び覚ましていく。サブカルが右傾化するのと関係があるのか?「彼女」たちは反憲論者になっていくのか?
終章 〈ぼく〉と国家とねじまき鳥の呪い
「正史」というものが果たしてあるのか疑問なのだが、誰のための「正史」かで変わってくるのだろうし、「自虐史観」であれ「自国史観」であれ、「正史」をほんとうに語り得るのか?それを村上春樹は、陰謀論めいた闇の正史がはびこる、歴史修正主義なのだろうか?そうしたものに対峙する力として〈ぼく〉が語る物語はファンタジーとして機能していくのではないか?ということなのか。
ファンタンジーが闇の陰謀論と対置するものとしての文学、それを江藤淳の『成熟と喪失』をサブテキストにして、第三の新人を読むことによって、接続していく物語という。それはオリジナルではなくコピーとしてなんだが、むしろ村上春樹がアメリカ文学をコピーさせたやり方に似ているのかもしれない。それはまったく無国籍性のような、村上春樹が日本だけで読まれる文学ではない可能性。それは色が希薄なだけに、どこでも存在する若者の共感を得ているのかな。
著者が江藤淳にこだわるのは、『成熟と喪失』を読まなければよくわからん。母というのがポイントだと思うのだが、母の喪失という。母の崩壊とあるな。それは萩尾望都『イグアナの娘』で具現化したことなので、それを引き受けるのがお前だぞということなのか?つまり村上春樹的なベッドトーク(ファンタジー)で女たちをひきつけろとか言っているのか?
主体という幻想──『光の雨』と融解する自他境界
立松和平の小説『光の雨』は、連合赤軍の死刑囚坂口弘の手記を元に自分語りをしているとして、批評する。もっともだと思うのは、坂口弘が盗作されたとして訴えたて一度は中断されたが、そんな経緯もあって問題作なのだが、ここに登場する人物が語り手の爺の精神と融解してしまい一つの革命思想の敗北として語られている。それは、死者たちの声がすべて彼の精神に一体化する気持ち悪さ。
それを聞いている少女もそれを受け入れてしまうのだ。例えば総括の女性から子供を取り上げて革命戦士の子供として育てていく話は、実際にあったことだが誰もが納得いく話でもなくそれを受け入れてしまうことの気持ち悪さが語られる。エヴァでシンジ君がアスカに合一しようとするときにアスカが思わず吐き出す言葉として、気持ち悪いがあるのだ。
そうしたことは死刑囚の心情として、作家が描き出すことに反発する例として永山則夫が、寺山修司の記事に反論したことを上げている。それとは反対に宮崎勤のどんな評論をも自分のものだと受け入れる乖離性を描き出す。何を書かれても頓着しないらしい。
カメラ目線の重信房子
宮崎勤と同じように語られるのが重信房子であるが、彼女はアイドルのように写真で撮られること。それが例えば逮捕される時でも笑いながらピースサインなど出してしまう。それが普通のおばさんになれなかった彼女の悲しみとして、宮崎勤と並べられる。まあ、そうなのかな。左翼の松田聖子という感じなのか?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
