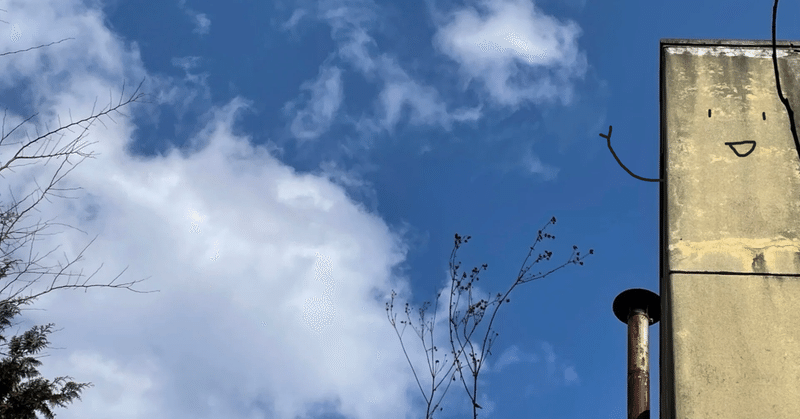
「生きる」を観て。
昨日、勢いでなんか、口の悪いことを書いた記憶があります。
すみませぬ<( _ _ )>
あの後『「生きる」大川小学校津波裁判を闘った人たち』
という映画を観てきて、さっきたこ焼きで軽く食あたりし
私という不肖ただの人間、生意気なことを言ってはいかんな……と大いに反省した次第です。
生きるっていうのは、みんなすごいんだと…たこ焼きと名がつけば何でも全部美味しいと思うなと…
買ったからには全部食べるのが美徳と思うなと…(途中不安はあった)
この勢いで何かを書くと、ぐちぐちぶちぶち自分の反省点を書きそうなので、そんなことはせず…
「生きる」の方の話を書き留めておきたいと思いマスク。
東日本大震災に対しては、いろいろ…記憶とか感情が絡まっていて、今でもあまりうまく触れないでいることの一つです。
なので、この映画も…うまくは触れられないのですが、なんというか…自分がこの映画に感動したとか、ドヤァって人にすすめるのも違うというか…
そういう思いって「観てほしい」としか、言えないことがあり…
でも、「観てほしい」って言ってみんな観てくれるなら、宣伝広報の人だれも苦労しねぇだろ、と言われると…その通りでして( ';' )←どういう感情やねんの顔文字。
でも、このところの、自分の…すぐ変わるわけじゃないものと向き合ってるときの…徒労感みたいな…無力感みたいなものを掬い上げてもらったところがあります。
それは、私じゃない人が、私の目指すところを生きて見せてくださった感覚といいますか…
映画のハラスメント問題に関しても、自分の職場のことに関しても、知っても、一人で空回りしても、なんか、何をしてんのかな、と思うことは多々あるのです。内側から変えるなんて微塵も簡単じゃないし、独善的なだけかもと自問しますし、冷笑、嘲笑、陰口一発ですぐ怯むし、簡単に落ち込みますし。ヘタレがすぎる。
かといって、昨日みたいにイキったこと書けば何かやってる気になれるかというと、それも本当に一時的で(お恥ずかしい)。
でも、この映画の中でも、大切な人、大事な命に何が起こったのかを知りたい方達がいて、その鬼気迫る勢いに怯む人がいて、大人たちの狡さがあって、部外者の思い込みがあって。それが人を傷つけて、傷つけようとする何かがあって、傷ついてきた人たちがいて、でもどうにか立っていて。
生きていて。生きることを選んでいて。
そういう人を置いていく社会があって。
私はこの映画を観なければ、その置いていく流れの一滴でしかなくて。
第三者委員会的なもの、の、難しさもまざまざと見せつけられたといいますか。公平って、人間が、しかも法の外でそんな簡単に出来るわけない…。だから司法の場に持っていくしかなくても、その司法も公平を体現するにはあまりに不確かで…でも、勝ち敗けで。命に値段もつけなきゃならなくて。
そういうのを色々、なぁなぁに、やってるふりでやり過ごす術だけが、日本社会は突出してしまったのかなと、我がことながら色々反省しました。
あの説明会などの空気。黙ってるだけの、何か考えてるかのようなフリをしている立派げな大人、俯いて黙ってやり過ごす、資料をめくってみたり、なにかを書いてみたり…でも、そこに誠実はない。決めつけるわけじゃないけれども、結果として誠実なんてない。
そういうものと対峙していると、あれ?私って人間だよな…みたいなところから揺らぐ感覚になるといいますか。
誠実に接する価値のない人間、ていうのを体現されてしまうと、ちょっと途方に暮れるといいますか…個人の経験上ですけれども。
そういう「あちら」と「こちら」を行ったり来たりする…記録でした。
社会は簡単に「心理的安全性」とか、「対話が大事」と言いますけども。
なんか…なんか…つかれちゃったナ―…(と言って離脱できる人はいいよね、までが世間知のセット…揶揄じゃないけど…これも途方に暮れる)。
離脱っていうのも、どこまで離れたら離脱できているのか、よくわからないです。生きていれば、何かしらつながって、関わって、過ぎたと思ったら戻って来て、向かったと思ったら離れて、離れたと思ったのに降ってきて。
しかし、それはそれとして、ドキュメンタリー映画の上映機会も、もっと増えたらいいなぁ。観たい。
ドキュメンタリーといえば森達也監督(私のような素人的にはそう見えた)、みたいな頃と、今もまた、世相が変わってきていると思うので、なんというかその辺りも、人間を観る機会のひとつひとつとして、育ってほしい。
人は生きて、そこに在って、そうである以上、生きるという文脈や感情という原理があり、関わりというエネルギーが存在したりする。
不調もある。機嫌もある。毛穴もある。トイレもいく。親がいたりいなかったりする。見えない涙も、見える笑顔もある。虚無もある。願いもある。
そういうものを可視化する視点は、本来誰にでもあるものだと思うのですが、意地わるく切り取ることもできるし、自分に偏りがあればそれもそのまま映り込む。手ブレもある。録音技師さんのやり方もある。いない現場もある…?
少しずつ、そういう視点も増えてきました。映画。
そういう話に持っていくと、震災にまつわる…エモーショナルなものとは違ってきてしまうのですが。
あえて、その距離はとっておきたい自分もいます。逃げはしない、けど、まだ覗き込むのはこわい。感情は人と人をつないでしまう。
日本て、そういう意味で、昏い穴がたくさん、大小さまざま、そこらじゅうにある国だと思うのですけども。あまりそこは描かないというか。
それっぽく、やってる感、や、すり替え、流すこと、が、うまくなってしまっているというか。
そう見える私が、まさにそういう人間であるというだけかもしれないですけども。
それの何が悪いのかというと、たぶん、信用や信頼を築けない。国内外問わず。人と人。
誠実じゃない姿勢って、そういうことなのだろうと思います。
映画のなかで「あなたたちを信じていいんですか?」という(ような感じの…うろ覚え)質問があって、それに対し、ごにゃごにゃぐにゃぐにゃ応えていた、言質を取らせないようなあれは、私の逃げスタイルそのままで。見たくない…(´-ω-`)
そして、そういう態度を取られたこともたくさんある。
人は、何かを信じないと生きられないと思う。
でも、自分自身の事すら、信じるのはとても難しい。
ここでまた「世界の終わりから」に話をつなげるのは、ズルいですかね。
なぞの宣伝スタイル。
いや、でも、私自身、誰かに信じてもらうに値する人間ではなく、というか、一方的に信じられるとこわいというか。
簡単に信じた者勝ちな社会も…けっこう嫌でして。だって、それなら後からなんとでも言えてしまう…
私は、ミスもするし、狡さもあるし、セコさもあるし、毛穴もあるし、虫を殺めることもあれば、道路でお亡くなりになった狸を見て見ぬふりすることもあるし、自衛と称してスルーすることなんて腐る程ある。
言うだけでやれてないことも宇宙規模である。
でも、そういう日常のどうしようもなさに対して、舞台を変えて、主人公を自分ではない誰かが生きてくれて、そこから浮かび上がってくる自分みたいなものもあるといいますか。
そういうのは、やっぱり、ドキュメンタリーよりは創作の方にやってほしいと思ってしまうところがあります。
なぜかといえば、辛いこと、苦しいこと、痛いこと、逃れようのないこと、それがフィクションであってくれることで救われるものがあるから。
現実と非現実の間に、ちゃんと境界線ができるから。
だから…えーと、映画って言ってしまうと、枠はものすごく大きいんですけど…「生きる」鑑賞をごちそうする会は開こうとしないくせに、「世界の終わりから」鑑賞をごちそうする会を開こうとするのは、そういうところかもしれません。
「生きる」は、他者の中に希望を見る…見せてもらえた感覚で(それもなんか軽率で失礼な感想のような気もするのですが…)
「世界の終わりから」は、うーん、転じて、自分の中に希望が生まれるというか…そんな感じです。
あ。タイムリーに記事が。
「大川小悲劇繰り返さないで」 娘亡くした父ら訴え 札幌で映画上映 | 毎日新聞 (mainichi.jp)
というわけで、しつこいですけども「世界の終わりから」上映ごちそう会、ご応募待ってます。
上映時間が発表されないことには何とも…なんとも、あれですが!
しかし…宣伝とか広報の方も、たいへんだなと最近つくづく思います。
難しい。人の気持ちを動かすとか、それによって行動を促すとか、引き出すとか。難しいっす。おつかれさまっす(だれ)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
