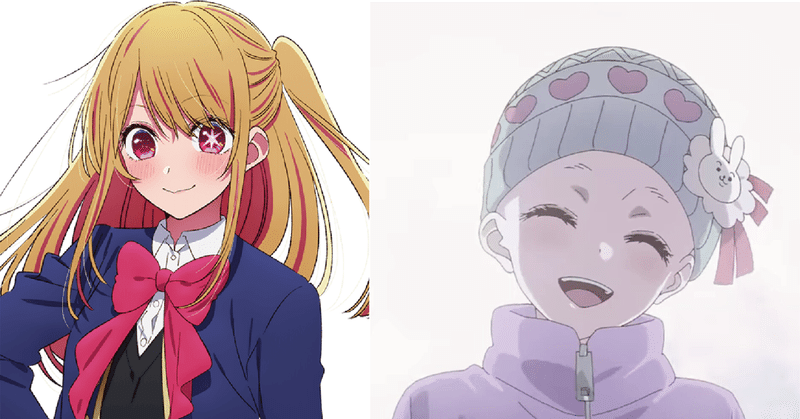
11.さりな&ルビーの心理社会的発達段階
今回は、7.有馬かなと心理社会的発達段階(前編)や8.有馬かなと心理社会的発達段階(後編) でも触れた 心理学における心理社会的発達段階(エリク・エリクソン)という考え方を元に、「天童寺さりな(以下、さりな)と星野ルビー(以下、ルビー)の精神的発達」に関して書いていきたいと思います。
心理社会的発達段階(復習)
上記2つの記事でも触れたように、精神分析家エリク・エリクソンは、生涯発達における発達課題を示した段階(理論)として心理社会的発達理論というものを提唱しました。年代で8段階に分けられており、それぞれの時期(発達段階)に獲得すべき発達課題を設定し、それを乗り越えながら人は生涯にわたって成長していくと考えました。
心理社会的発達段階
乳児期(0歳〜1歳半頃):基本的信頼 対 不信
幼児期前期(1歳半頃〜3歳頃):自律性 対 恥・疑惑
幼児期後期(3歳頃〜5,6歳頃):積極性 対 罪悪感
学童期(5,6歳頃〜12,13歳頃):勤勉性 対 劣等感
青年期(12,13歳頃〜20,21歳頃):(自我)同一性の達成 対 拡散
成人初期(20,21歳頃〜40歳頃):親密性 対 孤立
壮年期(40歳頃〜65歳頃):生殖性 対 停滞
老年期(65歳頃〜):統合 対 絶望
さりなとルビーの発達段階
さりなは、退形成性星細胞腫(脳の星細胞から発生する腫瘍)によって、12歳の若さで亡くなってしまいました。その後、さりなはアイの双子の子どもの一人として転生し、星野ルビー(本名:星野瑠美衣)と名付けられました。ルビーは、アニメ第1期では15〜16歳、原作の15年の嘘の収録時点では、17〜18歳(高3)です。
上記表の心理社会的発達段階では、さりな登場時は「学童期(5,6歳頃〜12,13歳頃):勤勉性 対 劣等感」、ルビーは幼少期(0歳〜5歳頃)を除くと「青年期(12,13歳頃〜20,21歳頃):(自我)同一性の達成 対 拡散」にあたるといえるでしょう。
さりな(12歳)の発達段階「学童期:勤勉性 対 劣等感」
以下は、原作121話からの引用です(括弧内は加筆)。
母親は娘(さりな)に愛情を注いでいましたが、少女は4歳の頃に重い病気が見つかりました。10年生きられる可能性は1割にも満たないと知り、母親の心は壊れてしまいました。
父親は娘と母親を引き離し、母親の心の回復し努めました。その一家は、地元の名家の生まれだったので、地元で一番立派な病院に娘を預けました。両親は悲しみを誤魔化す様に仕事に没頭し、現実から目を逸らす様になりました。そして、いずれ娘からも目を逸らす様になりました。
(中略)
少女の容態は悪くなる一方でした。慢性的な頭痛や吐き気、バランス感覚を失い歩く事もままならず、記憶や認識にも影響が出ていました。苦しい日々を支えたのは一人の少女でした。彼女は焦がれる程に憧れます。
症状が末期に近づくにつれて、母親はついに姿を見せなくなりました。苦しむ娘の姿を見るのが嫌だったのでしょう。それでも少女は、健気に母が訪れるのを待ち続けました。母は自分を愛していると信じ続け待ち続けました。
(中略)
少女はその短い生涯を狭い部屋の中で生き、苦しみに耐え、願いは叶わず、それでも毎日毎日母を待ち続けました。愛されていると信じて。
原作のとおりに考えると、さりなは4歳に病気が見つかるまでは、愛情を注がれて生きてきました。乳児期の基本的信頼感と幼児期前期における自律性は獲得してきたのかもしれません。幼児期後期の発達段階「積極性対罪悪感」においては、さりなが懸命に積極的に人生を生きようとし続けているのに対して、父親は母親と娘を引き離し、病院に預け、仕事に没頭することで現実から目を逸らすようになっていきました。
幼少期においては、子どもとの関係性は親(大人)側の責任であり、自分が悪くないにもかかわらず、「自分が悪い子だから、親に愛してもらえない」と自分を責めてしまいがちです。そんな抱く必要のない罪悪感を抱きながら、また勤勉でいようとしても病気によって多くのことができない劣等感を抱きながら、アイの推しであることや、ゴローの存在に支えられてきたのでしょう。
ルビー(15〜18歳頃)の発達段階「青年期:(自我)同一性の達成 対 拡散」
ルビーは、さりなの生まれ変わりとして、アイのもとに生まれました。アイが、アクアやルビーのことをちゃんと「愛している」かに自信を持っていなかった(原作10話)ものの、またアイが死んでしまうまでの短い間だったとはいえ、ルビーはアイや周りの人からの愛情を受けて育ってきました。
ルビーが芸能科のある陽東高校に入るころより前に、アイの葬儀が行われた後の会話(原作10話)で「ママ言ってた。私がアイドルになるんじゃないかって。アクアは私なんかでもなれると思う?」とアクアに尋ねています。この時点からルビーのアイドルになることを具体的に考えており、非常に早い段階から、自分の将来について強い思いを持つようになりました。これはマーシャがいうところの早期達成にあたるといえます。
マーシャによるアイデンティティ・ステイタス(同一性の地位・状態)
エリク・エリクソンの理論を発展させ、アイデンティティ・ステイタスという概念を確立したマーシャによると、アイデンティティ(自分が何者で、今後どういう風に生きていくか)については、
1.これまでに危機を達成しているかどうか。
つまり、「自分が何者でどういう人間としてこれから生きていくか」という自分という存在に対する悩む機会の有無。
2.現在、傾倒(コミット)している対象があるか
つまり、いま一生懸命取り組む対象(仕事や趣味、生きがいなど)があるかというコミットメント対象の有無
によって、大きく4つに分けられるとされています。
同一性達成:自分が何者か?ということを考える危機(クライシス)を経験しており、現在自分がコミットする(取り組む)対象がある状態
同一性拡散:危機を経験しておらず、現在自分がコミットする(取り組む)対象がなく「自分が何者か?」が拡散している状態
早期完了:危機を経験していないが、現在自分がコミットする(取り組む)対象があり、「自分が何者か?」を早くに持っている状態
モラトリアム:危機を経験しており、現在自分がコミットする(取り組む)対象を模索している状態
厳密には、早期に(アイの死の際に)アイデンティティの危機を体験しているとも考えられますが、この4つの中では早期完了にあたるといえるでしょう。
さりな12歳→ルビー0歳へと転生・成長した場合の発達段階をどう捉えるか
最後に、さりなからルビーへと転生したことについて考えてみましょう。さりなは12歳で生涯を閉じ、ルビーとしてまた0歳から生きてきました。最初の「天童寺さりなとしての12年間」と「星野ルビーとしての(アイが死ぬまでの)4〜5年間」を合わせると16~17年間ということになります。この16~17年間という期間を、あらためてエリク・エリクソンの心理社会的発達段階に照らし合わせてみると、「(自我)同一性の達成 対 拡散」の時期にあたります。
ルビーは、アクアから「…にしても、あいつよくあんな本気で遊具で遊べるな…」と言われていましたが(原作7話)、こうやって見てみると、ルビーも天童寺さりなとしての生きてきた期間の分、発達段階を経てきているのかもしれませんね。
…となると17~18歳段階では、12歳(さりなの生きた期間)+17~18歳=29~30歳くらい?とも考えられますが、そのあたりは周りの環境との相互作用もあるので、単純に足し算はできないのでしょう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
