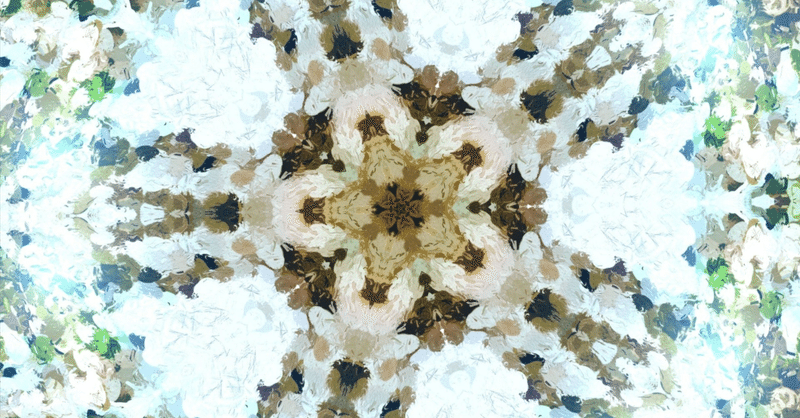
ダジャレ銀行
悠斗は、焦っていた。会社の借金返済の期日はあした。大阪の街は大晦日の雑踏でごった返している。あの銀行はコンピュータ営業のため、年中無休である。運命の日があすだと思うと、胃が痛くなってくる。
それにしても、なぜ返済日を元旦にしたのだろう。父の意図がわからない。
「神よ、みこころならば、わたしにダジャレを授けたまえ」
神が返答をするとは思えなかった。あまりにも身勝手なお願いだと自分でもわかっていた。神は都合のいい魔法使いではないのだ。しかし祈らずにはいられない。
悠斗がタクシーを降りたとき、通りの向こうからでっぷりした伯母が歩いてくるのが見えた。目がギラギラしていて、舌なめずりしている。着ている服は、こういうときに限って清潔感がただよっていた。焦りの代わりに嫌悪感がふつふつとわいてきて、そんな自分が恥ずかしくなった。
「あら、悠斗ちゃん」
伯母は、異様なまでのなれなれしさで、悠斗に近づき、その腕を取った。
「久しぶりやねえ、浩志のお葬式以来やないの。ここへは何しに来たん?」
答えはわかりきっているのだが、敢えて聞くところが伯母なのである。嫌悪感がいや増してきた。伯母はそれを見て、しめたという顔になった。
「ははあ、ダジャレ銀行へ行くんやね。ほな、いっしょに行かせてもらいまひょ」
「神は理不尽だ」
思わずホンネがポロリと出てしまった。
「ダジャレ銀行には、弟の遺産がぎょうさん詰まっとるんやろ? どのくらいあるん? うちにもちょっと、見せて欲しいわあ」
「悪いけど、少々、ご遠慮ください」
「さよか。考えてもみて。あたしも浩志の会社の役員なんよ。経営は傾きかけとるんやろ、浩志から聞いて知っとるんやで。うちに任せてくれたら、悪いようにはせんよ」
「ムリです。あんたに社員の気持ちがわかるはずがない」
「あらあ、社員はあたしの所有物よ? どう扱おうと勝手やんか」
「ひとでなし」
「そんなこと言ってええのん? 澄ましたクリスチャンの闇の部分がボロ見えやん?」
伯母さんは、どんどん悠斗をダジャレ銀行に連れて行く。
「やっぱり悠斗は、会社経営には向いとらん。たった三十一歳やし。ならば当然、あたしが社長になるべきや。会社はもっと成長する。社員には、びしばし働いてもらわなにゃなあ」
「会社というものは、社会には貢献し、社員には優しくあるべきです。イエスは弱い者の味方だった」
「あのなぁ、会社は慈善事業やないし、理想論ではやってけんのよ。この不景気で、どこもさっぱりワヤやねんから」
ダジャレ銀行の扉が開いた。AI行員が無表情でこちらを見つめている。その奥には観葉植物。玄関付近にはATMがずらりと並んでいた。その前で人々が、思い思いのダジャレをテキストで投入している。
オレオレ詐欺の教訓から、大きなおカネを引き出すときは、ダジャレをAI行員に言わねばならない。通帳や印鑑の代わりに肉声やテキストでダジャレを言い、それがAIの記録と合致していれば、おカネが引き出される。別人がなりすます可能性は低い。声紋により判別されるからだ。
悠斗は父浩志の血を引いているので、声紋が似ている。それに、銀行の要求する書類(遺言状)も持っている。悠斗以外のだれも、ダジャレ銀行からおカネを引き出せない。出せないはずだ。
問題は、亡き父の残した銀行合言葉のダジャレがわからないということだけだった。
「イラッシャイマセ」
AI行員は、機械的にしゃべった。
「さすが最新鋭の技術をあつめた銀行やね、ロボットが行員やなんて」
伯母が感心するので、悠斗は目を細めた。
「伯母さん、ここが初めてなんですか?」
「え? そんなわけないやん。久しぶりに来たでな、こんなんやったかなぁって思ただけや」
やけにオタオタしている。どうせ遺産目当でついてきたんだ。伯母は父にうまいこと言って遺言状を作らせた。バカヤロウの親父は死の直前に書き直したが、新しい遺言状にダジャレを書かなかった。終活のときだけマジメだなんて、らしくないぜ。
「35番の方、受付へどうぞ」
呼ばれてAI行員のところへ行くと、行員は立ち上がってお辞儀をした。
「西村さま、お久しぶりデス。ナニかお飲み物でも」
「紅茶が、こーっちゃった」
伯母が口走った。悠斗は寒くなったが、AI行員も伯母もガン無視している。
「遺言状はお持ちでショウか」
「おもちゃの遺言状を欲しいって、おもっちゃったよ?」
伯母は自分の遺言状をかざした。AI行員は、それを受け取るとじっくり検分した。
「声紋チェックは合格デスが、遺言状が古いままデス。フシギですネ、シバラク見ぬまにズイブン変わられたヨウで」
「あの頃は映画用の特殊メイクしとったんや。わからんかいな」
「――そうなんデスか?」
疑うようなAI行員。
「ええから、おカネを引き出してちょうだい」
伯母はじれている。
「申し訳ありまセン。上得意サマの場合には、通常の手続きを踏まないのデス。コチラへ」
AI行員が先に立って、奥の階段へと歩きはじめた。
伯母が、軽い足取りでついていく。悠斗もついていった。
「伯母さん、あなたは血族じゃない。遺産を受け取る資格なんかないんだ」
悠斗が言うと、
「なに言うとるん、長年功績のあったもんは、どこの世界でも褒美があってしかるべきやろ。うちは小さい会社かもしれんけど、若造の社長なんぞ、問題にもならんわ。今は亡き浩志は一代で会社を育て上げた立派な社長やったし、うちはその姉やで? ああ、待ち遠しいわあ、社長になったらしっかり遺産を使わせてもらうで……! 借金なんか踏み倒せばええんやし、あんたはクビや、クビ!」
「理不尽な!」悠斗は叫んだ。「そんな話があるものか、一から十まででたらめだ!」
「ええのか? 激怒するクリスチャンなんて、ありえへんで?」
悠斗は、怒髪天を衝いていた。
「いいかげんにしろ! おまえにカネはやるもんか! 行員さん、この人をやっつけてください!」
「済みまセン、ロボット三原則ニヨリ、出来まセン」
「ろぼっと三原則ぅ?」
「第一条。ロボットは、人間に危害を加えられナイ、デス」
「こ、こ、こんなヤツを、に、に、人間と認めるのか!」
「こんなヤツってなんやねん、この薄汚い甘ったれ! 男には職場に七人、女には職場に九人の敵がおるんやで!」
「まあマアまあマア、二人トモ、落ち着いてクダサイ。もうじき金庫デス」
そうだった。会社が今にもつぶれそうなのに、内輪もめしている場合じゃない。
悠斗は、深呼吸した。落ち着け。このままではアチラの思う壺だ。
「雷は、もうたくサンダー」
伯母は、階段を降りるAI行員にすがりついている。おれの激怒を雷だと思ったらしい。
両親が亡くなったのをいいことに、伯母はもう自分が社長になったつもりだ。なるほど、伯母には経営の才があるのだろう。しかし、理想と現実の間で、一歩一歩、社会に夢を与えていくのが企業ではないのか。経験値が低いのが悔しい……! ロボット三原則ってなんだ。人間の条件ってなんだ。おれが雷なら、伯母は……?。
言葉より行動だ。おれには伯母にはない理想がある。それがどこまで世間に通用するかは判らないが、負けてなるものか。
とたん、一番下の段差で転んでしまった。
「あ、テントウムシ!」
伯母のギャグに、ほとほと愛想が尽きた。
「ダイジョウブですか」
「ああ」
階段を降りきったAI行員は、ふたりをいざなうと巨大な金庫の前に通した。
「コチラにダジャレを言ってクダサイ」
悠斗は、その金庫に大きな耳がついているのに気づいた。どうやら、この耳へダジャレを言うらしい。
いっそう伯母が張り切りだした。いきなり、悠斗の持っている新しい方の遺言状を奪い取ると、
「やったるで!」
思いつく限りのダジャレを言い始めた。
「高級家具のにおいをかぐ」「欲ばりな忍者は何にんじゃ」「月曜日が、はじまんでー」「フレンチはソースが命? そーすね!」
父もそうだったがよくもまあ、これだけの滑るダジャレを思いつけるものだ。ヘタな鉄砲も数撃ちゃ当たる。もし万一、ダジャレが合致したら……。冷汗がどっと出て、身体の芯が冷たくなる。
しかし、どのダジャレも通用しない。
新年のカウントダウンがはじまった。伯母は髪の毛を振り乱している。
「おかしい。声紋チェックはOKやし、遺言状だってバッチリなんやけど」
地団駄を踏んでくやしがった。
「あなたは遺産相続人ではナイ。ご退場ねがいマス」
AI行員が、伯母の腕を取ってその場を引きずり出していく。
「待って! もうちょい待ちーや!」
伯母の声は、消えていった。ハゲタカがいなくなった! 悠斗の心臓が踊る。
「邪魔者はいなくなった、リラックスして思いつくことを言えばいいんだ」
悠斗がそうつぶやくと同時に、新年を祝う鐘と音楽が鳴り渡った。
「父さんがよく言ってたなあ。『大阪で新年を迎えられてうれしんねん』って」
カチリ。
ぎい。
金庫がしずしずとあいた。
茫然と中を見つめる悠斗。
「悠斗、ご苦労やった。すぐにホテル『ニューヨーク』ヘ行け」
目が金色だが父の姿だ。
「父さん!? いやよく見るとロボットか。なるほどなぁ。だがなんでここにはおカネがないんだ」
「わかっとるやろ。ええか、そこにいる幼なじみの頭取には話を通してある」
「『ホテル・ニューヨークで入浴』とか?」
「アホォ」
「そいつ、信用できるのか?」
「幼なじみや、信じられるヤツやで。とにかく聞け、ほんまの合言葉や」
金庫の奥で、ロボットはそっくり返った。
「福沢諭吉がゆーとった。“おカネはおっかねー。野口英世のグチ、ひっでーよ!” Byダジャレ銀行」(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
