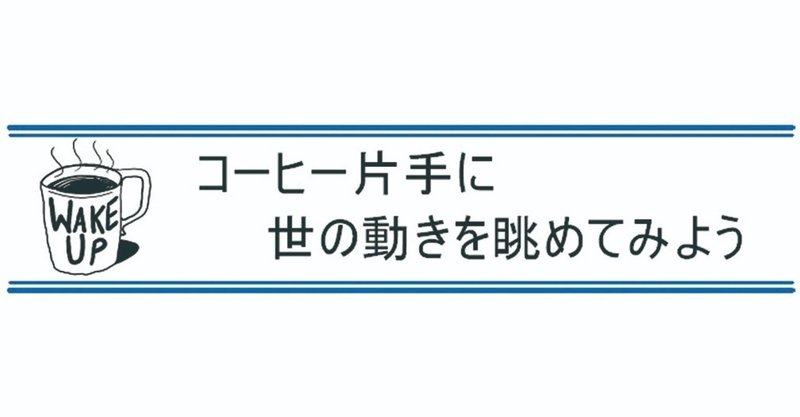
コロナ・ウイルス禍の下で広がる労働市場の明暗(3) =落ち込んだ「就業者」はどこに行ったか=
これまで見てきたようにコロナ・ウイルス禍で就業者の減少が継続しているが、一体その人達はどこに行ったのか。ここでは労働統計からお示ししたい。
〇 労働市場の仕組み
最初に労働市場の仕組みを表1にお示しする。表1は以下の定義に基づいて、男女別に作成したもので、数値は前年比増減(万人)である。
就業者 = 雇用者(正規+非正規) + 事業者(家族従業員を含む)
労働力人口 = 就業者 + 失業者
経済的人口 = 労働力人口 + 非労働力人口
表1. 労働市場の推移(前年比増減、万人)
![経済的人口[2489]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36869040/picture_pc_df1a7c77580cd7a2cef378223deb39a9.png?width=800)
日本の労働統計では16歳以上の人口を対象としている。「非労働力人口」とは通常、学生、(主婦など)家事を担う人、そして高齢者などをいい、労働市場で「働く意思のない人」と定義されている。
労働市場で「働く意思のある人」を「労働力人口」と呼び、この「労働力人口」に「非労働力人口」を加えたものを「経済的人口」と呼ぶ。
例えば、正規、非正規を問わず職を離れて大学院などに進学した人は「非労働力人口」に含まれる。また、「働く意思がある人」が職を離れた場合、失業者登録をされない場合も「非労働力人口」に組み入れられる。すなわち、「働く意思がある人」でも「非労働力人口」として振り分けられる場合があるということである。
〇 減少した「就業者」は「失業者」として労働市場に止まり、その他の多くは「非労働人口」として労働市場を離れる。一部の外国人は海外へ
それでは上記の労働市場の仕組みを踏まえて、現実の労働市場を眺めてみよう。図1は表1の男女合計を示した図である。
![(図)経済的人口[2490]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36870486/picture_pc_6d97d2f40cb0e8005d1231e5c663710f.png?width=800)
図1. 労働市場の推移(男女計、前年比増減、万人)
(1) 「就業者」について眺めると、今年1-3月期前年より36万人増と昨年10-12月期までの65万人程度の増加から鈍化、続く4-6月期は同78万人減へと一挙に大幅な減少を示した。
(2) これに対応する形で、「失業者」は今年1-3月期前年より1万人の減少と前期10-12月期の同10万人減から減少幅を縮小している。続く4-6月期には同26万人増となった。
(3) 次に「就業者」と「失業者」を合わせた「労働力人口」を眺めると、今年1-3月期前年より35万人の増加であったが、4-6月期には同52万人の減少に落ち込んでいる。すでにお分かりだと思うが、4-6月期の「就業者」の減少は78万人減で、「就業者」の減少分のうち26万人が「失業者」として増加したということである。
(4) 今年4-6月期について再確認すれば、「就業者」の減少のうち26万人が失業者として増加しており、これらを合わせた「労働力人口」は52万人減少しているということである。
(5)「働く意思がある人」とされる「労働力人口」は52万人の減少で、「就業者」の減少78万人を全て吸収できず、「労働力人口」で吸収できない分は「働く意思のない人」として「非労働人口」に計上される。4-6月期の「非労働力人口」はそれまでの減少から一転して44万人の増加となっている。
この間正規雇用が増加しており、このことを考慮すると「非労働力人口」44万人の大半は非正規雇用者と考えることができる。学生、主婦、老齢者、さらには働き盛りの人達も含め「働く意思がある人」であっても、「失業者」として登録されず労働市場から退出させられたということである。
(6)「労働力人口」(52万人減)と「非労働力人口」(44万人増)を合わせたものが「経済的人口」(8万人減)となる。「経済的人口」自体は16歳以上の人口総計で中長期的なトレンドで推移するものであり、景気などの短期循環に左右されるものではない。
但し、16歳人口には日本に居住する外国人が含まれているため、現状のコロナ・ウイルス禍の下で海外からの実習生なども含め海外に出た外国人がいることも想定される。これらを含めて4-6月期の「経済的人口」が8万人減少し、日本の労働市場が定義の中で成立している。
これらの動きを示したのが図1である。今年4-6月期の動きを要約すれば、78万人前年に比べ減少した「就業者」は、26万人が「失業者」として、44万人が労働市場を離れて「非労働力人口」に、そして海外に出た外国人を含めた「経済的人口」が8万人減少したということである。
〇 男性は「失業者」として労働市場に止まり、女性は依然として労働市場から離れる姿が継続
同じ定義で男性、女性別に労働市場での動きを眺めてみよう。図2は男性、図3は女性の動きである。
![(図)経済的人口.(男性)[2491]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36844619/picture_pc_1b4ea4f9fe2cebf5fa1902ff3901dd36.png?width=800)
図2. 労働市場の推移(男性、前年比増減、万人)
![(図)経済的人口.(女性) - コピー[2492]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36844684/picture_pc_a49e7f7618c0673385202e3da23fada3.png?width=800)
図3. 労働市場の推移(女性、前年比増減、万人)
四捨五入により男女合計値と異なる点があるが、表1で示したように、今年4-6月期の「就業者」は前年より78万人減少したが、そのうち男性が同37万人、女性が同40万人で、女性の減少幅が大きい。
これを労働市場で受ける形で「失業者」は同26万人前年より増加しているが、そのうち男性は同20万人増、女性は同7万人増である。「就業者」減少幅の違いから見ても女性の「失業者」の増加幅は非常に小さい。
この違いは「非労働力人口」に表れている。3-6月期の「非労働力人口」は前年より44万人増加しているが、男性は同16万人増、女性は同27万人増である。
すなわち、減少した「就業者」のうち、男性は女性と比べて「失業者」として労働市場に止まる方が多く、女性は労働市場から離れて「非労働力人口」になるのが多いという実態が見えている。
この4-6月期で観察された男女間の違いは、7月以降、より鮮明なものとなっている。
男性は減少した「就業者」とほぼ同程度が「失業者」として労働市場に止まる一方、「非労働力人口」は前年より減少に転じている。
女性は、減少した「就業者」のうち「失業者」として労働市場に止まる人達が増える形で推移してきているが、8月時点でも依然として労働市場から離れる「非労働力人口」の増加が継続している。
〇 リーマン・ショック時と比べ、今回は女性雇用者の減少が大きい
図4は雇用者の前年比増減を男女別に示したものである。これまでお示ししてきたように、雇用者は今年4-6月期急激に減少、7月、8月の平均(Q3)では前年より86万人低い状態まで落ち込んでいる。この落ち込みはリーマン・ショック時の2009年4-6月期に記録した最大の落ち込みと同じである。
![雇用者(男女)[2493]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36844797/picture_pc_550429ba475d925d84c8d3e3259de365.png?width=800)
図4. 雇用者の推移(男女、前年比増減、万人)
現状の雇用者の落ち込みを男女に分けて眺めると、男性より女性の雇用者減少幅が大きい。これを同程度の大きな落ち込みを示したリーマン・ショック時と比べると、リーマン・ショック時の落ち込みは男性が大半であったということで、現状の雇用者の落ち込みは女性雇用者の落ち込みと言っても過言ではない。
〇 雇用拡大を支えた女性に大きな圧力が
リーマン・ショック時と明確に異なる背景には2013年末から動き出した女性の社会進出、労働市場への急激な参入がある。
図5、図6は労働参加率と失業率を合わせた図で、それぞれ男女別に示したものである。労働参加率とは、「経済的人口」のうち「労働力人口」としてどの程度労働市場に参入しているかを割合で示したものである。
![労働参加率(男性)[2485]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36845332/picture_pc_40082470de9f9101ed2b9abf0a36f226.png?width=800)
図5. 労働参加率と失業率(男性、季節調整済、%)
![労働参加率(女性)[2486]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36845411/picture_pc_d1fac7a508354da4ab57e1b424fb12ff.png?width=800)
図6. 労働参加率と失業率(女性、季節調整済、%)
男性の労働参加率は長期間低下を続け、2015年前半に70%を少し上回る水準で下げ止まり、その後上昇に転じ、今年1-3月期には71.7%となっている。上昇幅は2%ポイントに満たないものである。
他方、女性の労働参加率は、2002年から2012年後半まで48%台で推移、その後急速な上昇基調に転じ、昨年末には53.8%に達している。上げ幅は5%近くと男性の2.5倍以上の上昇幅を記録している。
図4でも明らかなように、2013年から始まった雇用者増加の背景には女性の急激な労働市場への参入がある。現状の男性を上回る女性の雇用減は、大きく膨れ上がった女性雇用者の下で起こっているということである。対して、リーマン・ショック時に女性雇用者の減少が僅かであった背景は、その時期女性の労働参加率が低位で変化していなかったためである。
女性の労働参加率が上昇することを眺めて一般的には女性の社会進出と呼ぶが、女性の労働参加率上昇の背景には、家計所得の鈍化の下で、年金、介護保険、消費税率引き上げなどの負担増があり、加えて団塊の世代が定年を迎えていくという流れがある。それを裏付けるように高年齢の女性から労働市場に参入してきたという現実がある。また雇用する側でも非正規雇用として労働コストを抑制できるというメリットもあり、双方が噛み合って女性の労働参加が加速されたのである。
女性雇用者の大幅減少と労働市場からの退出というコロナ・ウイルス禍での現状を深く配慮しなくてはならない。今回の雇用悪化は製造業だけでなく、女性が参入し易い宿泊・飲食サービス業や卸・小売業などサービス業で大きくなっており、それが女性の雇用悪化を拡大させている。
雇用拡大を景気拡大の旗印としてきた政府は、女性の労働市場への参入理由、雇用環境の悪化を認識し、通来の不況対策ではなく、「選択と集中」による迅速で、継続的な支援をする必要がある。
〇 現状、事業者は増加を示すが、海外経済の弱さが不安視される
最後に雇用者と並んで「就業者」に組み入れられる「事業者(家族従業員を含む)」について図7を基に男女別に眺めてみよう。
![事業者(男女)[2487]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36845983/picture_pc_7b9879327f383cc943ea7e14507f4bd6.png?width=800)
図7. 事業者(含む家族従業員)の推移(男女、前年比増減、万人)
「事業者(家族従業員を含む)」の推移を眺めると、2008年からのリーマン・ショック時、そして2015年、2016年の中国経済及び新興国経済の鈍化時に大きく減少している。
どちらの落ち込みも男女とも大きな影響を受けており、その背景には海外経済の鈍化が大きく影響している。
現状を眺めてみると、これまでお示ししてきたように「事業者(家族従業員を含む)」は過去2回と比べて大きな落ち込みを示しておらず、男性事業者については第3四半期(7、8月平均)は前年より増加している。
但し、過去の落ち込み時に海外経済の鈍化が深く関わっていたことを考慮すると、先行きには不透明感が漂う。
IMFは今月10月の「世界経済見通し」で世界の経済見通しを6月に公表した見通しより0.8%ポイント上向き修正した。6月時点より中国経済の回復が急速であるというのが上向き修正の背景であるという。
但し、それでも今年の世界の実質経済成長率はマイナス4.4%に止まる。
今年プラス成長を示すのが中国のみでプラス1.9%。米国はマイナス4.3%。ASEAN5か国マイナス3.4%、ユーロ圏マイナス8.3%、そして日本はマイナス5.3%である。
来年の世界経済見通しはプラス5.2%とされるが、2019年末の経済水準に来年戻ると予測されるのは中国のみで、他の国々は2022年まで待たなくてはならいという予測である。
このような世界経済の下で中国経済に期待をするが、中国はリーマン・ショック時4兆元という巨額の景気刺激策を実施、2015年、2016年にその後遺症に悩まされた経験を持っており、今次は抑制的であろう。
世界経済は今年7-9月期から回復に入っているとされるが、パンデミック化したコロナ・ウイルス感染は欧米で再び拡大の情報もあり、海外環境は先行きも含め不透明であることに変わりがない。
〇 「街」が消える・市町村レベルでも中長期的な視点での財政支援を
図8は事業者所得(農家所得などを含む)である。出所は内閣府で、昨年から参考系列として公表を始めたものである。
![営業余剰[2497]](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/36846111/picture_pc_2e497c040bdb2a7cdc77a3df40c4f13d.png?width=800)
図8. 営業余剰・混合所得の推移(暦年,1995年=100,前年比,%)
暦年ベースで事業者所得の推移を眺めると、リーマン・ショック以降大きく低下、2011年に底を打ったが、2014年の消費税率引き上げを受け回復力が低下、昨年では1995年に比べ20%程度低い水準にある。
現在事業継続給付金などもあり「事業者」が増加しているが、増加が継続するか不透明である。昨年消費税っ率が10%に引き上げられ、海外経済の回復力が弱いなかで、事業継続給付金の浸透が遅れており、さらに年末で終了するといわれている。
とくにコロナ・ウイルス拡大は消費市場を直撃している。とくに消費市場を担っている事業所は女性を中心とした非正規雇用者で成り立っている。この雇用基盤が危機にさらされていることは、雇用の減少だけでなく、地域、とくに「街」レベルでの事業消滅を引き起こす。「街」が消えていく危機にあるとの目線で、政府はもちろん、市町村レベルで必要な独自の行政支援が必須である。
国や各行政体は財政赤字で施策実行に二の足を踏む状況であるが、生産、商業基盤の消失は所得発生基盤の消失を意味し、少子・高齢化が進展する中、先行き地域経済の疲弊を加速する。
この状況を抜け出すには金融政策だけでなく財政政策が急務である。単年度の財政バランスに縛られる状況ではない。中長期的な視点での産業政策を含めた施策が急務である。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
