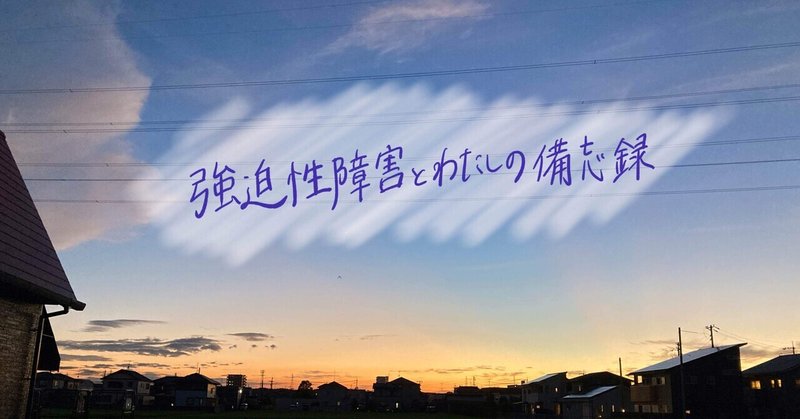
再発
12月と1月上旬、卒論の執筆に追われていました。
しかし、卒論を提出し終えてから、自分の中で歯車が大きく狂い始めました。感情のコントロールが効かなくなってしまいました。
タイトルの通り、強迫性障害の症状が強く出て、薬が必要になり、再発しました。
12月末、卒論提出2週間前を切ったあたり、試行錯誤を繰り返し、毎日朝4〜5時まで取り組んでは寝て、9時に起きて執筆作業を再開するといった生活を、学生最後の年末年始に送っていました。
こういう生活をしていたら、普段だったら私の性質的に、精神的に落ち込みやすくなります。しかし今回は、落ち込むどころか、出来るだけこだわって書き切りたいという気持ちで、寧ろ不安なんて感じないような、不思議な状態でした。
卒論提出3日前、最後の誤字脱字などの確認作業をしていたとき、自分が何か重大なミスや罪を犯しているような気がする不安が浮かんでは、頭の中で消そうとする、という思考を繰り返していました。
思えば、これが最初の前兆でした。
提出後のゼミでは、3週間後の口述試問に関する説明がありました。
そのゼミ終了後の私は、同級生と普段ではありえないほどの量を喋っていました。それも自分で自分を制御できていないほど、関係ない内容まで喋りすぎてしまっていました。そのうえ、「なんであんなに話したんだろう」「うざくなかったかな」などと、喋りすぎた自分を責め、ひとり反省会を繰り返していました。
それから3日後、朝起きようと思うと、身体が鉛のように重くて起床にものすごく時間がかかりました。3週間くらい、ずっと全力疾走だったから疲れたのだろうと思っていて、2、3日経てば落ち着くかなと思いました。
しかし、何日経っても起床が辛く、その辛さは日に日に増していました。
身体の重さが続くと、次は食欲が湧かなくなりました。とりあえず食べるといった形で、お腹も空かず、機械的に食事をしていました。
そんな日々が続く中、次は寝つきが悪くなりました。眠たくて眠るというよりは、頭の思考が突然プツンと切れて眠るような、気絶みたいな睡眠。
ただ2、3時間経てば、眠ることができたので、以前程、深刻な精神状態ではないだろうと思っていました。どちらかというと、個人的には、一時的な疲れだと思っていました。
しかし、ついに何もない時に頭が真っ白になり、涙が止まらなくなり、頭の中で色々なことが反芻し、それに対して確認が止まらなくなりました。
したくもない、意味もないと思っている自己否定が、なぜか止まらなくなりました。
おかしいなと思っていた私は、とりあえず、2021年の発症で学んだ、自分に合っていると思っていた、以下の3つの対処法を試してみることに。
①手を動かす作業をする
卒論の口述試問前だったので、とりあえず口述試問対策用に、自分の卒論に付箋を貼ったりしようと思いました。しかし、口述試問対策用の卒論のファイルを手に取った途端、両手が震え、動悸が激しくなり、全身から冷や汗が出てきました。今までにはなかった、おかしな感覚が襲いました。
②本を読む
大好きなエッセイを読もうとしたものの、文字が頭に入らず、「本が読めない」という感覚が私を襲いました。何気なく読めた本が、それが絵本であっても読めなくなりました。
③散歩する
散歩に出かけてみると、ものの数分くらいの一時的に、思考の一部分だけは軽くなりました。少し気が楽になって、大丈夫かな?と思うものの、自分の全身から出てくるサインは一向に改善せず。
そして当時の私は、どの対処法も「上手くいかない!!!」とパニックになっていて、対処の仕方も、どう日常を過ごしていいかも分からなくなって、混乱していました。
少し冷静になれた時に、ふと今までと違うことを考えてみると、「卒論の口述試問」に関するものを見たとき(友達のSNSや自宅の本棚の関連資料が並んでいたりするところ)、また頭の中でふわっと口述試問に関する考え事が浮かんだ時に、身体からのサインや、自己否定、頭の中の確認、涙や全てが、通常より激しく反応していたことに気づきました。
「あ、、3週間後の口述試問に私は不安や恐怖を感じているんだ」と原因が見えてきた瞬間でした。
ストレスの原因から距離を置く、離れる。
原因があればこの対処が、身体のサインを落ち着ける最善でした。でも、今年大学を卒業したいと思う私には、口述試問を乗り越える必要がありました。
ストレスの原因から離れたいけど、離れたくない、そんな葛藤が続いて、自分の中では抱えきれなくなり、一向に改善しない身体のサインも続いていた時。
大学のカウンセリングに行くか、もしくは精神科を再受診するか、、そんな選択肢も浮かんではいたものの、判断しようとしても、思考と判断が自分が思ったようにできなくなっていました。どうやって判断したらいいのかわからなくなったような感覚でした。
それでも、どうしても自己否定と頭の中の確認作業がとまらなくなって、私はとりあえず、大学のカウンセリング室に駆け込みました。頭の中はきちんと判断ができているのか、いないのかは、まだわからないままでした。
そこで、口述試問までの時間をどうやって対処するか、どうやったら自分をリラックスできそうか、カウンセラーさんと一緒に話しながら、ゆっくり、ぐちゃぐちゃになった思考や感情を整理しました。
そんな中、カウンセラーさんが2つ提案をしてくださりました。
1つ目。日頃集中できる場所(私にとっては自宅)とは真逆の、日頃は全く集中できない場所(私にとっては、カフェなどの人の声がする場所)で、卒論のファイルにまず触れること、ページを適当にめくること、などの小さなステップを1つずつ試してみること。
2つ目。投薬が必要かどうかはカウンセラーさんは判断できないので、精神科の先生に相談してみて、投薬が必要なら薬物療法を試してみること。
以上の2つをとりあえず試してみることに。
まず翌週、約半年ぶりに精神科を再受診しました。
そこで口述試問に対する不適応と、それと同時に強迫性障害が再発したことがわかりました。そして口述試問までの間、抗不安薬(一般的な呼称は精神安定剤)を飲もうという、投薬の判断が出ました。
そして精神科受診後、カフェで少し卒論のファイルをめくってみることにしました。最初は動悸や冷や汗、手の震えは止まらなかったり、周りの小さな音にも過敏に反応し、脳がずっと何かに反応して恐怖や不安を感じ取っている状態でした。しかし、それも1時間半以上経過した頃くらいからは少し落ち着くようになりました。
カフェでの口述試問対策を重ねるうちに、少しずつ冷や汗や動悸が、前よりも収まっていきましたが、当日は何が起こるか分からないと思い、予防として前日にカウンセリングを再受診したりしてなんとかその日々を過ごしました。
そして迎えた口述試問当日。
口述試問前に、とりあえず抗不安薬を飲んでも、手の震えはおさまらず。手は冷えて、呂律はまわらず、頭も真っ白で、自分で何を言っているのか途中でわからなくなる瞬間が沢山ありましたが、なんとかその時間を終えました。
終わってみると、びっくりするくらい呆気なく、口述試問前の不安が、ものすごく不思議なものに感じました。
今回再発して、最初はとても動揺しましたし、落ち込みました。せっかく落ち着いたはずなのに、あの苦しい日々に戻ってしまう、と乗り越えた壁がリセットされて、再び振り出しに戻ったような感覚に襲われ、落ち込みました。
半年程かけて寛解したはずの症状のほとんどが、1ヶ月間くらいにぐっと凝縮して溢れた時、どうして良いか分からなくなる絶望感に襲われました。一時的なものだと、主治医からも伝えられ、大丈夫だと心で何度も言い聞かせても不安は溢れてきました。これが正直な気持ちでした。
そして今は、少し落ち着き、ようやくこうやって整理ができるようになり、波はあるものの薬は飲まずに過ごせています。
無事、大学の卒業も確定。
周りのたくさんの方々のサポートがあって、今回も症状と向き合うことができたので、周りへの感謝は忘れずに、それでも、まず、一生懸命向き合った自分に「おつかれさま」と労いの言葉をかけようと思います。
ZINEの制作費や、表現を続けるためのお金として使わせて頂きます🌱
