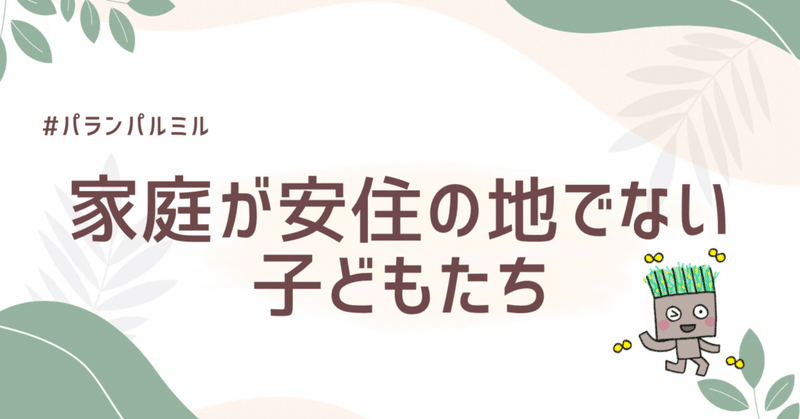
家庭が安住の地でない子どもたち
2024年のゴールデンウィークが終わりますね。
私はというと、体調を崩していて散々でした(笑)
息子をどこに連れて行ってやることもできず(基本的には、混んでいるときは基本どこも行かず、空いているときに行こうねというスタンスでは常にあるのですが)、
明日からの学校で『GWどこいった』トークに寂しい思いをするんじゃないかという、もっともらしいけどあんまり重要じゃない心配をして(笑)、とりあえず焼き肉を食べに行きました。
「鉄板で自分で焼くって、特別だよねっ!」という親のおべんちゃらを受けて、キャッキャと楽しんでくれる息子に感謝です。
私は中高生の頃、友達から「GWに外国行った~」「GWはおじいちゃん・おばあちゃんのところにいって~」とか聞くのが本当につらかったんですよね。
ほんと、家族でどこかいくとか、家族でなにかするとか、そういうのって絶対ないといけないものではないんです。だから、別に重要ではないのだけれども、それらが「普通」と捉えられがちな期間においては、どうしても普通から外れてしまった時のしんどさがあります。
親が離婚してそんな余裕はないし、おじいちゃんおばあちゃんはおろか親族もいないし、私には無縁の世界。
世界が違うんだと思っても、どうしても比べてしまってさみしかったのです。
だから、息子にも上記のような心配をしてしまうのは、一種のスキーマのなごりなのかもしれないなあと思ったりもします。
ウィーズにもこの期間、いろんな相談が寄せられて、いろんな子どもたち、かつての子どもたちとのかかわりがありました。
ウィーズに来てくれる『家にいるのがしんどい』『家族といるのが辛い』という子どもたちは、物理的に「ひとりである」という状態でなくても精神的に「ひとりだと感じる」という子が多いです。
逆に家庭というもっとも身近で、もっとも小さくて、もっとも長く所属している組織が心から安心できる場所であれば、たとえ物理的に「ひとりでいる」という状況があったとしても、孤独を感じづらいのです。
家庭や親はルーツだからこそ、そこが安定していなければ、すべての基盤が揺らいでしまうんですよね。
ゆえに、オンライン上からゆるくつながる私たちに対しては、その「孤独」「おさまらない揺らぎ」からくる不安や恐怖が、落ち込みや怒りといった表現であらわされることがとっても多くあります。
しかもたいていの場合、それらの表現はとても大きな表現です。
はじめましてな子どもがこちらに刃を向けて「どうせここも私の話なんて聞いてくれないでしょ!私の対応めんどうなんでしょ!」と言ってくることもあれば、「消えたい!」「クソ!!!」と叫ばれたり。
そんなときに、同じレベルで同じ感情・同じ行動を返さないことはとっても大事だなと思っています。
ただ黙って話を聞き、ひとつひとつ対話しながら聞いていくこと。
『その時どんなことがあった?』
『その時どんな気持ちだった?』
『その時どうだったらよかったなと思う?』
本人にまず冷静に考えてもらわないと、本当になんとかしたいポイントや、本人の本当の思いにまでたどり着かないからです。ここまでにも相当な時間がかかることも多いです。
『なんでそんなこというの!』
『なんでそんな態度なの!』
というのは、最初の表現への対応に過ぎなくて、それで手を放されてしまったら、傷が広がるだけなのです。
体調が悪くなるのには理由があるのと同じように負の感情の表出にも理由があります。
そして、人は基本的に、その時選べるその人にとっての最善の選択をして生きています。
今はその表現を選択するのがベストであるとこの人が感じる理由があるんだ、と思いながら向き合っていかないといけないんですよね。
その先に、無条件の愛が伝わる時が来るのだと思います。
パランパルミルは、1:1での向き合いを大切にするからこそ、それを加速させる可能性を秘めているはず。
負の感情の表現が大きくなる前の発散の機会も生めるはず。
来年のGWには少しずつ、リアルなその場が生まれていますように。
がんばるぞー。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
