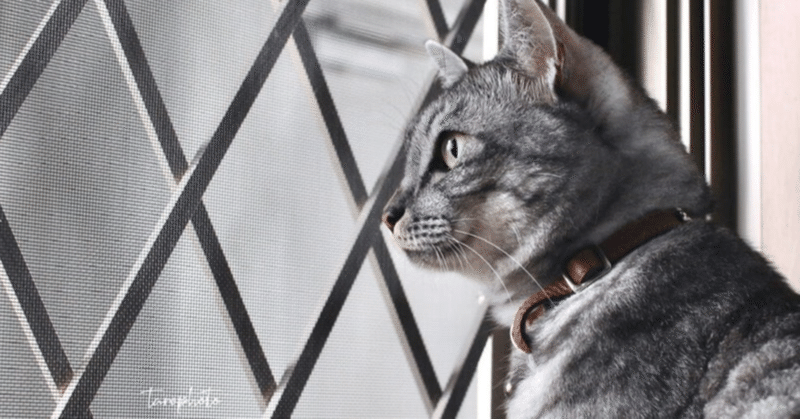
【評論】‘‘文学的論考’’-安部公房『赤い繭』論について-
【序論】[-文学を読む上で、‘‘文学的論考’’を深めるために-]
対象物として、文学というものは何かということ。あるいは文学作品が持つ、広範な特性や世界についてのことを考える上で、論考する際はとても難しく感じることがあります。
具体的に、文学について考える時、私たちはテキストを読み、そこから解釈を加えていくことで論考が深まっていく。
文学の特性について、文学の持つ力、役割というもを考える上では、やはり作品を取り上げて様々な解釈を加え、論理的に考えを展開していかなければいけないと思います。
作品を一つ取り上げて、そこから思いや考えを交錯し合う中で、文学を知るきっかけになった安部公房の『赤い繭』に衝撃を受けたことは未だに記憶しており、ぜひとも取り上げて作品の理解はもちろんのこと、考察を深め‘‘文学的論考’’として記してみたいと思いました。
【本論】[『赤い繭』にみる、‘‘おれ’’についての内省について]
まずは、本作の全体像として、『赤い繭』はおれという一人の人間が自分の帰る家を探して、最終的には足から絹糸が伸びていき、自分という存在がこの世から消滅して、赤い繭の家が完成する話であり、彼という人間に拾われ、彼の息子のおもちゃ箱に入れられるという奇妙な物語であります。
この話を初めに読んだ時は、正直に言って最初はわけがわからなく、しばらく本を置いてそのままにしていたことがありました。
ですが、ある時、あの時に読んだモヤモヤ感が忘れられず、もう一度再読してかつ、精読することを心掛けてみることにしました。
すると、明らかに、わたしが初めに受けた印象が変わっていたことに気付かされました。
すなわち、私はこの再読の瞬間に、安部公房がこの『赤い繭』という作品で、何を伝えたかったのかという意図が少しでも感じられたからなのではないかと思います。
物語性を軸として、一見すると、論理性が欠けた非文学的な作品だと思われがちですが、いたって『赤い繭』という作品は論理的な作品であるということが考えられることに気付かされました。
それは、どういうことか?
主人公のおれは家を見つけることができた。
だが、その代わりにおれという存在を失ってしまった。
何かを手に入れれば、何かを失ってしまうというメタファー。
『赤い繭』は、現代社会が抱える問題点に、直接的な関わりがあると考えると、作品を読み解くヒントが眠っていると考えられます。
そこで、安部公房の『赤い繭』を考察するにあたり、物語の前半部分における『赤い繭』の中で、私自身が特に気になった箇所があったので引用したいと思います。↓
夜は毎日やってくる。
夜が来れば休まなければならない。
休むために家がいる。
そんならおれの家がないわけがないじゃないか。
ふと思いつく。
もしかするとおれは何か重大な思いちがいをしているのかもしれない。
家がないのではなく、単に忘れてしまっただけなのかもしれない。
そうだ、ありうることだ。
(『壁』安部公房 新潮文庫 「赤い繭」p220より引用)
引用された本文の箇所に注目すると、おれに関しての思想を考察する上で、夜というものは毎日やってくる当たり前な日常生活の一部だということが理解できます。
休むために家がいるという必要性を主張しているところに視点を変えれば、休むという意味は眠るという言葉に類語・関連語・連想語として、置き換えることができるのではないでしょうか。
夜が来れば休まなければいけないというおれ自身の感情が、休むための場所としての家を探す目的性を駆り立ているということが理解できます。
さらに、おれは重大な思いちがいをしていることに気付かされます。
おれの家が見つからない原因は、単におれが忘れてしまったからだと続けさまに「そうだ、ありうることだ。」と自己決定することで、おれ自身を納得させていることにわたしは疑問を感じます。
おれの言動を冷静になって考えてみれば、自分の家を突然忘れてしまうということはおれの身に記憶喪失という現象が起きてしまっているという可能性があります。
なぜ、おれは記憶喪失を引き起こしているのか、その原因を追求する為には記憶喪失というものについて、視点を捉える必要があると考えてみました。
記憶喪失について、おれにかんする記憶というものは、記銘、保持、再認のいずれか、またすべてが正常に働いていない状態になっているということが理解出来ます。
『赤い繭』の本文を引用した箇所で、「家がないのではなく、単に忘れてしまっただけなのかもしれない。そうだ、ありうることだ。」とおれは発しています。それによって、この一文から考えられることは、おれは深刻なまでの記憶喪失に陥っているということが裏付けられるのではないだろうか。
記憶喪失の原因として、詳しく明示するにあたり、おれという人物は『赤い繭』で描かれる以前から、頭部外傷、もしくは直接的な脳に関しての障害、もしくは激しい感情体験によって引き起こされた病によるものを患っているのではないかと作中から考えられます。
しかし、ここで疑問なのが、『赤い繭』ではおれに関しての手掛かりとなる過去については、一切描かれていないところであります。
では、過去以外におれに関する人間像、もしくは内面性をより深く、考察するものが必要になってくることが考えられます。
その後の物語では、おれは偶然通りかかった一軒の前に足を止める。
そして、もしかするとおれの家なのではないかと期待して家のドアを叩いてみる。
すると、半開きの窓から覗いて現れた一人の女の笑顔でありました。
私は、ここまでの一連の物語に何故か興奮を覚えました。
それは、私がかつて、出会ったことがなかった異様な感覚に近いものだったからだと思います。
行間を読むことで、ここにはない世界に連れていかれてしまうのではないかという期待と不安が入り交じった瞬間に、確かに私の中で何かが大きく変化する感覚を覚えました。
話を戻すと、おれと女との会話のやりとりの中で、おれという人間は何者なのかということ探究する必要がある為、もう一度気になる箇所があるので、本文の一部を引用したいと思います。
「一寸うかがいたいのですが、ここは私の家ではなかったでしょうか?」
女の顔が急にこわばる。
「あら、どなたでしょう?」
おれは説明しようとして、はたと行き詰る。
なんと説明すべきかわからなくなる。
おれが誰であるのか、そんなことはこの際問題ではないのだということを、彼女にどうやって納得させたらいいだろう?
おれは少しやけ気味になって、
「ともかく、こちらが私の家でないとお考えなら、それを証明していただきたいのです。」
「まあ……」と女の顔がおびえる。それがおれの癪にさわる。
「証拠がないなら、私の家だと考えてもいいわけですね。」
「でも、ここは私の家ですわ。」
「それがなんだっていうんです?あなたの家だからって、私の家でないとは限らない。そうでしょう。」返事の代わりに、女の顔が壁に変って、窓をふさいだ。
ああ、これが女の笑顔というやつの正体である。誰かのものであるということが、おれのものでない理由だという、訳の分からぬ論理を正体づけるのが、いつものこの変貌である。
だが、何故……何故すべてが誰かのものであり、おれのものではないのだろうか?
いや、おれのものではないまでも、せめて誰のものでもないものが一つくらいあってもいいではないか。
時たまおれは錯覚した。
工事場や材料置場のヒューム管がおれの家だと。
しかしそれらはすでに誰かのものになるために、おれの意志や関心とは無関係にそこから消えてしまった。あるいは、明らかにおれの家ではないものに変形してしまった。
(『壁』安部公房 新潮文庫 「赤い繭」p221~p222より引用)
次の文章はおれと女による会話文であります。おれという人物は自分の家に関しての記憶、それと自分という人間は本来何者なのかということまでの記憶までもが消失してしまっているということが理解出来ます。
誰しもが、自分はどこから生まれて、両親は誰だったか、自分の名前は何という名前だったのかということが突然、記憶から抜け落ちてしまえば、帰る家を見つけることという発想を思い浮かぶということは考えられないのではないかと思われます。
ですが、おれという人物はおれが何者なのかということを問題ではないという意思があります。
それどころか、帰るべき家を見つける為に、どうやってでも女の家が自分の家であるかのように説明して納得させようとしているところが実に奇妙であると感じられます。
そこまでして、おれが家にこだわる理由というのは何なのでしょうか。
このおれにとっての家という存在はどれほどの価値があるものなのでしょうか。
女との会話のやりとりの中でおれは、奇妙な言葉を女に投げかけるシーンがあります。
「あなたの家だからって、私の家でないとは限らない。そうでしょう。」という女に対しての発言であります。
たまたま、見つけたある家の中に初めからいた住居者であり、かつお互いが初対面であるということが作中において考えられます。
なぜなら、たとえおれが以前から女にとって面識がある知人、または兄妹、親戚、恋人だという事実なのにも関わらず、女のことを知らないのであれば、記憶喪失が原因だということになります。
しかし、一方の女の方はと言うと、おれが第一声を発してから、顔をこわばらせて「あら、どなたでしょう?」と対応を示していることに注目したい。さらに、おれが女に自分の家でないということを証明してくれるように追及すれば、女の顔がおびえる描写から、見ず知らずの人間が自分に、わけのわからないことを喋りかけて、恐怖心を抱いてるところから、おれと女との間に接点はないということが裏付けられるのではないでしょうか。
だが、一番の問題は住居者であるのにも関わらず、そこにある家が自分の家ではないかと考えているおれの思想そのものであります。
自分の考えを女に主張した後に、女は返事の代わりに壁に変わって窓をふさいでしまい、おれを完全に拒絶する姿勢をとっている。
そういった態度をとられたおれは、これが女の笑顔という正体だということを突き付けられることになる。
つまり、作者の安部公房は『赤い繭』の中の女の笑顔というものの正体というのは、おれに対して向けられた拒絶によるものだということが考えられます。
つまり、女の顔が壁に変わり窓をふさぐことで、外界にいるおれとのコミュニケーションを断絶させたこと、コミュニケーションをとる前に見せた女の笑顔によるものの正体をおれは初めから知っていたのではないかと思えます。
ここで描かれている女の存在というのは、おれに対しての拒絶のメタファーだということが理解出来るのではないかと思います。
さらには、「誰かのものであるということが、おれのものでない理由だという、訳の分からぬ論理を正体づけるのが、いつものこの変貌である」というような考えを持つ、おれというのはかなり俗離れした人物像だということが考えられる。
自分とはかけ離れた論理を正体づけるものが、いつものこの変貌だと理解しているのなら、おれに関する記憶というものは全てが、欠落しているとは限らないということになる。
すなわち、以前からおれは誰かに拒絶されていたような人間だったというような性格が浮き彫りになるのではないかと考えられます。
対人関係から起きる拒絶によるものは、こちらから、何かを他者に向けて発信しても、見えない壁のようなものに拒絶され、いつまでもコミュニケーションが取れず、挙げ句の果てに孤独になってしまうという現代人の問題点を暗示しているように思えます。
もしかすると、自分の発した言葉によるものは、他者にとってみれば理解出来ない言語表現として、そういったことが何度も生じてしまう度に、拒絶されるようになってしまったのではないかと考えたりもしました。
拒絶する為に変貌する。
引用箇所において、「何故すべてが誰かのものであり、おれのものではないのだろうか? いや、おれのものではないまでも、せめて誰のものでもないものが一つくらいあってもいいではないか。」という点で、この世界で描かれているもの全てがおれという存在を拒絶しているのではないかと考えられます。
女以外のものもおれを拒絶するかのように、意志や関心とは無関係にそこから消えてしまう方法を取ったり、明らかに家ではないものに変形したりと、拒絶による行為そのものがエスカレートしているのではないかと思えます。
おれ自体の存在をこの世界から抹消させたいかと思わせるほどの拒絶反応というものは、おれにとってみれば重大なことのように考えられます。
誰もが自分のことを拒絶するような態度を毎日取られていれば、精神的に異常をきたしてしまってもおかしくはないと思います。
変貌という現象が拒絶としてのメタファーであるとすれば、女という生物、工事場という土地、材料置き場のヒューム管という物質、そういった万物が変貌し、おれを拒絶するのであれば、万物そのものは『赤い繭』においてのおれが記憶喪失を引き起こしたと思われるトラウマとして抱えるおれ自身の過去、すなわち「誰かのものであるということが、おれのものでない理由だという、訳の分からぬ論理を正体づけるのが、いつものこの変貌である」と描かれている過去を示す表現として「いつものこの変貌である」というところの「いつも」という箇所にあります。よって、いつもという言葉にはそれ以前の過去のことを暗示しているのであって、引用した表現の意図としては「過去にこの《変貌=拒絶》によって、過去に受けた心の傷というものは今でもおれの心は記憶していて、おれだったはずの記憶というものはこの変貌によって、おれとは別のおれに変貌してしまったのではないかと考えられるのではないでしょうか。
女とは完全に拒絶されたおれは公園のベンチにたどり着く。
この場所が、おれの家であるのではないかということに少しでも希望があるように思えたのだが、棍棒を持った一人の警官によってそれは違うことに気付かされることとなる。
公園というのは公共施設である為、自分一人に所有権があるということではなく、あくまでもみんなのものだということと、もう一方では誰のものでもないという論理が正しいということをおれに主張する。
このことから正当性のある論理によって、おれ自身による論理というものは不当だということが決定されることになる。
確かに、家というものには競合性と排除性を有している私的財に当てはめることができ、対照的な公園というものは非競合性、または非排除性の両方かどちらの一方を有する公共財に当てはまることから、ここでのおれの論理が通用しないということはいたって合理的だということが理解出来ます。
仮にも、おれが警官に向かって自身の論理を主張すれば、警官によっては逮捕されてしまう可能性もあるのではないかと考えられます。
非日常的な描写では決してなく、論理によって構築されているこの世界だからこそ、いつおれの身に何かが起こったとしても、物事一つ一つをとって疑念を抱くということは論理からかけ離れた危険性があるのではないでしょうか。
警官がおれに対して発した言葉の意味合いというものを探ることでよりおれの内面に近付くことが出来ると思われます。
警官の発言と、それに対してのおれが受けた感情を本文から引用したいと思います。
だが彼は言う。
「こら、起きろ。ここはみんなのもので、誰のものでもない。ましてやおまえのものであろうはずがない。さあ、とっとと歩くんだ。それが嫌なら法律の門から地下室に来てもらう。それ以外のところで足をとめれば、それがどこであろうとそれだけでおまえは罪を犯したことになるのだ。」
さまよえるユダヤ人とは、すると、おれのことであったのか?
(『壁』安部公房 新潮文庫 「赤い繭」p222より引用。)
引用した文章では、警官がおれに対して前述の通り正当性を主張する。
その後に、警官はちぐはぐな言葉を発します。
それを受けておれは、さまよえるユダヤ人ということを自分のことだと当てはめて表現しています。
つまり、その後に発せられたちぐはぐな言葉というのは、さまよえるユダヤ人だと意味されるということであります。
では、さまよえるユダヤ人とはどういう意味なのかということを提示する必要があるので説明したいと思います。↓
【さまよえるユダヤ人】
① さまよえるユダヤじん【さまよえるユダヤ人】(the wandering jew)……刑場に引かれて行くイエスを侮辱した罪で、世の終わりまで世界を放浪することになったというユダヤ人伝説。(『広辞苑 第六版』 岩波書店 2012)
② さまよえるユダヤ人(wandering jew)……最後の審判の日まで放浪を続ける運命を負わされた伝説のユダヤ人。彼は十字架を背負って刑場へ引かれていくイエスを嘲笑して、「とっとと行け」といったのに対して、イエスは「私は行くが、お前は私が帰ってくるまで待っていなけばならない」と答えたといわれる。そのユダヤ人が実在しているという話が残っている。それは靴屋のアハスエルスといい、1542年ハンブルクで彼に出会ったというドイツの司教は、彼がイエスの罰を受けた「永生の」人間であるというのを聞いたと伝えている。この話を記したパンフレットが当時広く行き渡った。イギリスの年代記作者ロジャー・オブ・ウェンドーバーはもっと古い伝説を伝えている。1228年イギリスに来たアルメニアの大司教が、イエスを嘲笑したユダヤ人に会ったが、その男はピラトの召使カルタピルスで、のちに改宗して洗礼を受けヨセフと名を改めたと語ったという。同種の伝説は他にも記録されている。永遠の罰を受けて、休みなく放浪を続ける人間という伝説は、ヨーロッパ各国で多くの作家の興味を喚起したが、特にレーナウ、シャミッソー、A, w,シュレーゲルなどドイツ・ロマン派の詩人が好んで題材とした。ゲーテもその一人であった。(『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタニカ・ジャパン 2012)
提示されたさまよえるユダヤ人の概要は以下の通りであります。①での項目では、主に簡潔にまとめられた意味として書かれており、②での項目目では①項目と同様である簡潔な意味と、その後に続く内容ではさまよえるユダヤ人に関しての語源について詳しく掲載されています。
おれはどうして、自分の家をいつまでも探し出すことができないのか。
このような不幸な現実をおれは世の終わりまで、世界を放浪することになったユダヤ人伝説を置き換えているということが分かります。
拒絶され続け、永遠におれは苦しめられることになる。
だが、おれがさまよえるユダヤ人を置き換えるという思考があるとすれば、ユダヤ人伝説に記された刑場に引かれて行くイエスを侮辱した罪が原因とされる場合、おれは過去に何かしらの原因で、拒絶されるようになってしまった理由があるということになります。
拒絶されるということを考えると、おれ個人による外面性や内面性などの両方によるもの、また一方だけによるものが原因なのではないかと思われます。警官に言われた後に、おれは「さまよえるユダヤ人とは、すると、おれのことであったのか?」と言葉の意図を理解した後に、過去性が含まれる思考が働いている。
つまり、おれは警官に直接言われる前までは、どうして拒絶され続けているのかということをはっきり理解していなかったということが理解出来ます。
現実として、拒絶されるということ以外でも他者が自分に対しての悪い態度や言動というものはやはり、本人と同じ気持ちになってみなければ、本当のところは分からないものであると思います。
原因を迅速に解明しなければ、永遠に他者との距離は近づいても遠くに離れて行ってしまう恐れがあります。
ここまでの過程として、おれは「何故すべてが誰かのものであり、おれのものではないのだろうか?」と固執した論理を持っていたはずだが、疑いを持つ対照的だと思われる論理へと変化していることが分かります。
このことから、おれにとっての論理の変化というものは現在のおれから、過去の本当のおれである再生の可能性を意味しているのではないでしょうか。
そして、警官と別れてから、おれは自分の家を見つける為に、ただひたすら歩き続けることになる。
作中では、おれは家がない理由を吞み込めないようである。
では、本来のおれにとっての家という存在は何を表しているのだろうか。
神は、おれを永遠に家まで辿り着かせないように仕掛けているのであれば、おれが過去に犯した罪というものは、それほどの重罪だったのかと考えさせられてしまいます。
作者の安部公房は『赤い繭』でのおれを通して、現代社会に蔓延る因果応報の教えに近いものを作品に反映させたのではないかと私自身は感じました。《ユダヤ人=おれ》というような関係はフィクションとしての表現にも大きく働きつつ、決しておれのような境遇に陥ってしまわないように、作者自身が読者であるわたしたちに直接、訴えかけてくるような感覚を覚えました。
ただ、運命に従い歩き続けるおれに突然、奇妙なことが起こります。
おれの身に起きた変化について、また本文の一部を引用し考察したいと思います。
おや、誰だ、おれの足にまとわりつくのは?
首つりの縄なら、そうあわてるなよ、そうせかすなよ、いや、そうじゃない。
これはねばりけのある絹糸だ。
つまんで、引っ張ると、その端は靴の破目の中にあって、いくらでもずるずるのびてくる。
こいつは妙だ。と好奇心にかられてたぐりつづけると、更に妙なことが起った。
次第に体が傾き、地面と直角に体を支えていられなくなった。
地軸が傾き、引力の方向が変わったのであろうか?
コトンと靴が、足から離れて地面に落ち、おれは事態を理解した。
地軸がゆがんだのではなく、おれの片足が短くなっているのだった。
糸をたぐるにつれて、おれの足がどんどん短くなっていた。
すり切れたジャケツの肘がほころびるように、おれの足がほぐれているのだった。
その糸は、糸瓜のせんいのように分解したおれの足であったのだ。
もうこれ以上、一歩も歩けない。
途方にくれて立ちつくすと、同じく途方にくれた手の中で、絹糸に変形した足が独りでに動きはじめていた。
するすると這い出し、それから先は全くおれの手をかりずに、自分でほぐれて蛇のように身にまきつきはじめた。
左足が全部ほぐれてしまうと、糸は自然に右足に移った。
糸はやがておれの全身を袋のように包み込んだが、それでもほぐれるのをやめず、胴から胸へ、胸から肩へ次々にほどけ、ほどけては袋を内側から固めた。
そして、ついにおれは消滅した。
後に大きな空っぽの繭が残った。
ああ、これでやっと休めるのだ。
夕日が赤々と繭を染めていた。
これだけは確実に誰からも妨げられないおれの家だ。
だが、家が出来ても、今度は帰ってゆくおれがいない。
(『壁』安部公房 新潮文庫 「赤い繭」p223~p224より引用。)
本文中では、おれの体は突然異常をきたし、徐々に足がほぐれていくところから始まっていく。
おれの身に何が起きたのか。
どうして、ほぐれていくことになってしまったのか。
論理的に考えても、わたしたちがおれのような状況下に置かれることは、まずないと断言してもいいと思われます。
だとすれば、『赤い繭』においての安部公房が描くおれという存在は、人間としての生態系上の役割として重要なことであるならば認めざるを得ないということが分かります。
おれの姿がどんどん変化していく過程で、ほぐれた糸がおれの意志とは関係なしに全身を袋のような姿にする上で、内側から固めていく行為というのは外部との接触をこちらから遮断して、拒絶される苦しみを防衛する為のおれ自身による自己防衛の表れのようなものではないかと考えられます。
引用文に注目すると、おれという存在は完全になくなってしまった代わりに《繭=家》を手に入れたことと、誰からも妨げられないということで、思わず安堵したんだと理解でき、作中で見事に表現されています。
だが、その後すぐに自分が消滅してしまったことに後悔するような対照的な言葉として、こちらも表現されていることが理解出来ます。
では、作者の安部公房は『赤い繭』でのおれが消滅した代わりに、家を手に入れることになったおれを描いて何を伝えたかったのでしょうか。
そのことが分かる引用された文章に続くところこそが、『赤い繭』での全ての主題なのではないかと思います。
繭の中で時がとだえた。
外は暗くなったが、繭の中はいつまでの夕暮で、内側から照らす夕焼の色に赤く光っていた。
この目立つ特徴が、彼の眼にとまらぬはずがなかった。
彼は繭になったおれを、汽車の踏切とレールの間で見つけた。
最初腹をたてたが、すぐに珍しい拾いものをしたと思いなおして、ポケットに入れた。
しばらくその中をごろごろした後で、彼の息子の玩具箱に移された。
(『壁』安部公房 新潮文庫 「赤い繭」p224より引用。)
こちらの引用箇所については、安部公房は「繭の中で時がとだえた」と表現しています。
繭の中にいる状態というのは、外部での情報が一切ないということであり、内部により頑丈な壁をつくることで、おれは拒絶に対して対抗しているのではないかと考えられます。
繭という壁を作ることで、おれがいる場所が汽車の踏切とレールの間で彼によって見つけられたということがようやくこの瞬間に気付くこととなります。最後に、引用箇所を踏まえて《繭=家》というのは前述の通り自己防衛、すなわち《繭=家=壁》という形で表すことが出来るのではないでしょうか。
壁で守られているおれは、彼の息子の玩具箱という大きな壁によって、絶対的な防壁を手に入れることとなります。
そして、おれは自己肯定感を高めれば高めるほど一生、繭のままであり、おれはこの先繭からもう一度、おれに戻れる可能性はないだろうと思われます。
【結論】[『赤い繭』における‘‘文学的論考’’を終えて]
安部公房の『赤い繭』を論じるにあたり、人生において生きる上で、楽に人生を送ることは非常に困難であります。
自分自身に置き換えてみると、私自身もおれと同様に《繭=壁》を作りできるだけ、関わりというものを避けることで、自分を守ってきたことがあったと振り返ってみるとそう思えてくることがあります。『赤い繭』の最後に、人格者としてのおれは意識に食われ、本来のおれに戻ったのではないだろうかと感じます。
本来のおれの姿が赤い繭にあの瞬間、変わったということはおれ自身の本当の記憶をおれは少しでも、思い出したのではないかと思えます。
『赤い繭』において、作品としてのテーマ性、作中人物における象徴、作者と作品による関係性、会話表現における意図、私がこちらの作品で構築させた文学観によるもの。
そういったことを全て含めることで、安部公房の『赤い繭』に関わる新しいアプローチを記すことが出来ました。
過ぎ去った過去を思い出すことで、人によっては楽しかったことや悲しかったことで感情の受け止め方により、突然昨日の自分とはまるで違う人間として生まれ変わることがあります。
『赤い繭』に出会えたことで、私は文学を読む楽しさと面白さを手に入れることが出来ました。
そして、私なりの‘‘文学的論考’’という考え方をまとめ記すことが出来たことは大きな学びであると実感しています。
【参考文献】
『壁』安部公房 (新潮文庫)
よろしければ、サポートお願い致します。 頂きましたサポート資金は、クリエイターとしての活動資金として使わさせて頂きます。これからも、宜しくお願い致します。
