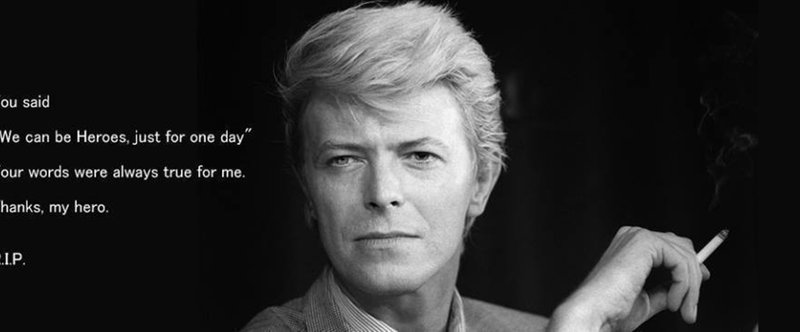
【デヴィッド・ボウイ、星になる】
出来事としては、2016年01月10日。数字がシンメトリーになる神妙な1日。
そんな日に、永遠のマイ・ヒーロー、デヴィッド・ボウイが亡くなった。
僕がデヴィッド・ボウイを知ったのは、高校生の頃。今から20年以上も前のことだ。
当時は「伝説」と言われるバンド、BOOWYが解散してまだ間もない頃で、僕はBUCK-TICKの大ファンだった。それまで音楽なんてむしろ軽蔑していた「いい子ちゃん」の自分であったが、友人が編集してくれたカセット・テープが僕の人生を変えた。
僕の「音楽の扉」を開いたテープに収録されていたいくつかのバンドのうち、僕はZIGGYをまず好きになり、BUCK-TICKのファンになっていった。
ほどなくして「ZIGGY」というバンド名が「ZIGGY STARDUST」から抜粋されて命名された名前ということを知り、BUCK-TICKの音楽性にデヴィッド・ボウイが大きく影響を与えていたことを知った。初めて好きになった洋楽であるニルヴァーナも、ボウイからの影響を明らかにしていた。
その流れで、僕はデヴィッド・ボウイを2枚組の『シングル・コレクション』から聴くようになった。
最初の印象は、あまりよくなかった。90年代最先端の音楽に較べ、70年代の音はどうしてもソフィスティケイトされていない、粗野なものに感じる。80年代の音は軽薄な機械が鳴らしているようだった。ボウイの声も、実は好きではなかった。
しかしさまざまな音楽を聴いていくうちに、多くのミュージシャンやバンドがボウイの影響を明らかにしていた。その趣味嗜好はさまざまで、鳴らす音もさまざまだった。
今にして思えば、それは影響もとのボウイ自身が「多面的な音楽性を持っていることのあらわれ」だった。
しだいに僕は、ボウイを違和感なく聴くようになっていった。そうして音楽の幅が広がり、さまざまな音楽を許容できるようになった。
いつしか、僕はボウイの大ファンになっていた。
きっとそれは、容姿ありきだったに違いない。だって当時のボウイ最新作と言えば、復活作と大々的にアナウンスされながらも、セールス・内容ともに地味だった『ブラック・タイ・ホワイト・ノイズ』だったのだから。
初めて買った現在進行形のボウイの新作であるそれに、僕は「なんでこんな人がみんなに愛されるんだろう」と思った。
しかしその疑問を凌駕するほど、ボウイの持つヴィジュアル力は圧倒的だった。
そうしていつの間にか、僕は「スタイルとしてのボウイ」を尊敬するようになった。
アルバムの中でもメロウな「ドント・レット・ミー・ダウン・アンド・ダウン」を聴きながら、カッコ気にしいになっていた僕は「こんなカッコイイ大人になれればなあ」と思うようになっていた。
でも、ギターはうまく弾けなかった。
それでも想いが募り、仲間内のライヴであがったステージでは、ボウイになりきって「スターマン」を熱唱した。客席が最後のコーラスを復唱してくれたとき、自分が「ジギー」になった自分だった。
その後も、僕はボウイを聴き続けた。
やがてボウイの新作は「2年か3年に1枚、ドロップされる『元気だよ』と知らせてくれる手紙」のようになっていた。
キラキラ光る傑作『リアリティ』でパワフルなヴォーカルを聴かせてくれたときなど、その「変わらなさ加減」に嫉妬さえおぼえたほどだ。
人生が流れていき、いろいろがうまくいかなかった。
でも、またうまくいくようになった。
その間、ボウイは静かに、終幕に向けて歩いていた。
そんなことなど、気づくはずもなかった。
いつでも存在し、いつまでも存在する、永遠の存在のように思っていた。
新作『★(ブラックスター)』の発売がアナウンスされ、今回は何と発売前にYouTubeで全曲を公開するという、類を見ないセールスをやってのけた。
それでもCDが売れる自信があるんだな、まったく大した歌舞伎者だぜ……などと考えていた矢先。
ボウイは、人知れず、星になっていた。
黒く塗りつぶされた星は、かつてスーパー・スターだった自分の現在を描いた意味深なタイトルかと思っていたら、ひょっとしたら「病魔に侵された自分の象徴」だったのかもしれない。
2016年01月10日。
日付がシンメトリーになることさえも計算されていたかのような「自らの死さえプロモーションにフル活用する」とんでもないことを、ボウイは最後にやってのけた。
アルバムは「ステイション・トゥ・ステイション」を思わせる意味深な構成と長さの表題曲より始まり、死にまとわれた男が復活する内容の「ラザルス」があり、最後には「僕にはすべてを与えることはできない」と宣言して去っていく「アイ・キャント・ギヴ・エニシング・アウェイ」が配置されていた。
……まるで遺書のような歌詞と内容!
しかし音楽性は、見事なまでに「現在のボウイ」だった。懐かしい歌で終幕を告げるわけでもなく、きちんと「今、ボウイがやりたい音楽」で満ちていた。
だからこそ、死なんて、唐突に訪れるなんて思いもしなかった。
ところがそれさえも、ボウイの計算とプロモーションの一環だった。
とんだ「偉大なる歌舞伎者」だ!
ボウイ逝去を知ったとき、僕はひとりで業務をおこなう店で働いていた。
ネットのニュースで拡散が始まり、事実と想像のないまぜが不安感を襲った。しかし営業中、ひとりで運営している以上、涙など流せるわけがなかった。
閉店時間となり、シャッターを下ろして、
誰にも見られない独りになった瞬間、僕は、肩が引きつるほど、泣き崩れた。
運転しながら、『アースリング』収録の「リトル・ワンダー」を聴く。
哀しい曲ではないはずなのに、歌っていても、歌えなくなるほどに、想いがあふれていた。
帰宅すると、妻に「いつもはTVを見ているけど、今日は音楽を聴かせてくれないか」と頼んだ。
妻は言葉少なに「いいよ」と言ってくれた。
「こんなに哀しんでもらえるなんて、デヴィッド・ボウイさんは、幸せだね。世界中でこんなふうに、哀しんでもらえているんだね。たくさんの人に愛されていたんだね。幸せだったんだね」
どうしても泣き崩れてしまう僕の耳もとで、妻が囁いた。
その言葉は嬉しいものの、どうしても、
哀しかった。
結婚を機に、CDをほぼ実家に置いてきてしまっていた僕は、手もとに残すぐらい愛聴していた『ジギー・スターダスト』を聴いた。
妻が初めて「スターマン」を耳にして、すぐさま「虹の彼方に(Over The Rainbow)」をもとにしていることがわかっていた。ちなみに、妻は音楽に通じている人間ではない、ごくごくの一般人だ。そんなふうに、ボウイの曲は「自然と、その人に入っていく」ことを実感した。
しかし一方で、ピアノのみで弾き語りされる「レディ・スターダスト」のデモにはどうしても、胸が詰まった。
星になった姿でも拝んでやろう、と思って煙草を持って外に出ると、夜でもわかるほどの曇天だった。
「野郎、最後の姿まで見せないのか! どこまでカッコつけるんだよ!」
ボウイの完全なる去りざまに、僕は、哀しみとは違う質の涙を流した。
こんな完璧な人に、敵いっこないや。
そうつぶやいて、乾いた涙の痕を残し、僕は妻のもとに戻った。
ボウイの死後数時間で、あらゆる作品が一気に売り切れになっていた。
大してボウイを好きでもなかった人がひどく残念がったり、ボウイを知りもしない記者が勝手な記事を捏造したりしていた。
だが、ボウイ自身が仕掛けた「死を賭したプロモーション」の前では、何の効力もない。死期を悟りながら健在に見える写真を発表したり、意味深な行動すべてを1枚のアルバムのために昇華させていた。
ボウイの核を成す音楽、それを紡ぎ出してきた「デヴィッド・ボウイという存在」の前では、すべてのニュースは空虚だった。事実も嘘も、幻想さえも。
こんな想いは、いつ以来だろう?
ジョージ・ハリスンが亡くなったとき。あれ以来だ。
しかしボウイは、いくらか自然と死に向かう姿を見せていたジョージと違って「実は死んだなんて嘘で、またひょっこり現れるんじゃないか?」とさえ思わせる、見事な去り方をしてみせた。
だからこそ、僕は、心の底からは信じていない。
デヴィッド・ボウイというスーパー・スターが、この世からいなくなったことを。
だってここには、音楽があるじゃないか! 彼が録音した色褪せることのない音楽は、いつだって僕をわくわくさせる。しかも「次の作品ではどんなことをしてくれるのだろう」という夢想さえ、掻き立ててくれる。
それらの音楽を共有できる限り、ボウイは、この世の中に存在する。
記憶から消える(=完全なる死)なんてことは、ボウイにはあり得ない。
いつまでも、スーパー・スターとして、いや、目を凝らせば見える、暗闇に光る「★(ブラックスター)」として存在するんだ!
だから僕は、いつまでも、デヴィッド・ボウイを自分のヒーローとして崇めていくだろう。
死んだなんて言わせない。
あなたは、生きている。
いつまでも、いついつまでも。
だけど最後に。
「僕の人生を素敵な色に染めてくれて、ありがとう」
これだけは、言っておこうじゃないか。
次の世界で活躍するまで、しばらく、安らかに。
デヴィッド・ボウイ。いつまでも、ありがとう。
(了)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
